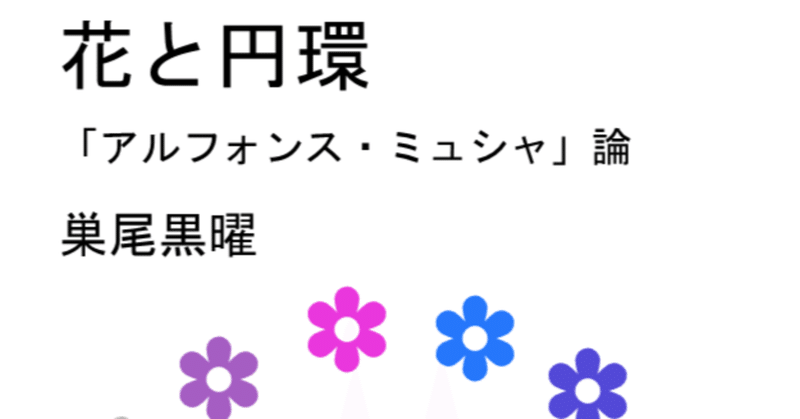
『花と円環 「アルフォンス・ミュシャ」論』試し読み
本稿は諸事論考 第2巻としてこの度発売した『花と円環 「アルフォンス・ミュシャ」論』の試し読みである。
ここに第1章全文を公開する。
興味のある方は是非、文章の最後に貼り付けてあるURLから、Kindleにてご一読されたい。
*
1,ミュシャと私
アルフォンス・ミュシャ。1860年にチェコで生を受け、ベル・エポックのパリを華々しく彩らしめた稀代の画家。彼は2023年の今となっても、現代芸術に深甚な影響を及ぼしているのだという。私が彼を知ったのは、何ということもない、ただの偶然からだった。私は往時、医学部志望の浪人生で、その浪二つになろうかという時に、新幹線に乗っていた。これも何ということはない、通学のためだ。私から見ても実に豪奢な生活で、こんな生活を送らせてくれた両親には、大変感謝している。私は新幹線で予備校に通っていた。それも、二年。一年目に滑り止めを受けずに国公立医学部のみを受験し、あと一歩の所で敢なく不合格。面接点が30点という稀に見る低得点で、成る程、他府県の医学部というものはこうも県外出身者に厳しいのかと、現実の無情を味わった頃のことであったろうか。通学中に単語帳を捲るのにも飽き飽きして、目を上げた。……まあ、それから虚空を呆けて眺めて、二分。呆けて、どうせ今年も落ちるのだろうと、考えていたのかも知れない、そんな二分。……私はそこに豊かで、豊穣で、一際目の引く色彩を、それも極彩色の色彩を、見出した。それは広告であった。どうやら美術館で、件の極彩色を描いた画家の絵を展示するらしい。美術館と言えば、元々、小林秀雄は良く読んでいた。センター試験――今では共通テストと呼ぶらしい――2010年代の現代文、小林秀雄の『鐔』。忘れもしない。高校三年生時にセンターの問題を初めて解いた時、その難解と、言い知れぬ興奮に、当時、衝撃を受けたものだ。私は彼の文章が好きだった。その美文、その思想、何よりその修辞。私は彼に一時期、魅せられていた。その小林秀雄は、美術館というものを、美というものに触れるには全く不健全で、居た堪れない様な場だと、確か、『骨董』という文章だったか、それに書いていた様に思う。故に、私は刹那、懊悩した。美術館に行くべきか、行くべからざるか。その何方が精神にとってより高貴であるか。それが問題だ。結局、展示会の最終日に丁度予備校の面談があったこともあり、私は両親と美術館へ赴くこととなった。
ただし、正確には、展示会に辿り着いたのは、私一人であった。予備校に着く以前に、軽微な自動車事故で両親が負傷し、来られなくなったのだ。私も軽いむちうち症の様な状態になったため、両親と同じくして、同日医師の診察を受けるべきであったと思う。しかし、何が私を突き動かしていたのだろうか。それは予備校で待っている面接員への申し訳の無さからであったのかも知れないし、何か得体の知れない義務感からだったのかも知れない。だが、何れにせよ、最も大きかったのは、恐らく「ミュシャの絵が見たい」という、熱狂にも似た渇望だった。結局、面接自体は、一浪目の経験が生きてか第一回模試の偏差値が70超えだったこともあり(その後偏差値は奈落に落ちていくのだが)三十分以内に恙無く終わった。その後新幹線で美術館に一人赴いた。時は、盛夏である。その暑熱に魘されながらも、私は辿り着いた。美術館。そもそも、私は絵を見に美術館へ行く、ということについて最も縁遠い人間であったし、また、美術館へ行こうとも、ミュシャの広告を見るまでは思わなかった。何より、外に出るのが億劫だったのだ。私が美術館へ行ったのは、ミュシャの美に魅せられたからだったのであろうか、或いは、単に興味本位であったからだろうか。その何方でも、恐らく、無い。単純に、私は彼の絵を綺麗だと思った。そして、綺麗な絵を見に行こうと思った。たったそれだけのことなのだった。
そして、結局、着いた。忘れられない、「ミュシャ展 運命の女たち」。私の思想を拡張した展示会、アルフォンス・ミュシャと出会った場、そして、私に絵の見方を教えた恩人……或いは、悪人。
これが、私とミュシャとの、出会いだった。
出会いが最悪であると、その後に良い関係が築かれるのはトレンディドラマの鉄則である。
私とミュシャの出会いも、最悪であった。
二浪生の私は、当時、絵についてはとんと全く分からなかったのであるが、その代わりに、資金と時間を犠牲にして得た少々の思想や哲学に関する知識があった。先に述べた通り、一時期小林秀雄に執心していたこともあったため、批評というものについての興味もあった。また、高校三年生時に筒井康隆の『文学部唯野教授』を読んでいたため、そこから所謂文学理論、別称批評理論に関する知識も、少しはあった。以上から、私は展覧会会場に於いて、一つのことを企んでいたのである。それというのは、曰く
「アルフォンス・ミュシャの絵を批評してみる」
と、いうことであった。しかし、素人が徒手空拳で何かを述べられる程、絵画というものは甘くはない。それも、人でごった返した展覧会の黒海の中で、である。一枚の絵にかけられる時間というのも数秒から、まあ数分有れば良い程だ。そんな短時間で絵を批評するのは、土台無理な話である。私も、そのご多分に漏れず、会場に於いては人の熱に浮かされた様に、その面を紅に染め、必死で何かを見ようとして……そして何も得られずに、絵の前から立ち去った。つまりは、夏の真っ只中に人が密集すれば、当然暑くなる。暑くなれば人間の顔というのは、赤くなる。更には意識も朦朧としてくる。謂わば一種の「熱中症」である。私は会場でその様になっていた。後になって思い返してみれば、成る程、絵が綺麗だったという印象があっても、個々の絵がどうであったかという具体的な分析は、何をも思考には残されていなかった。……確かに私はあの会場に在って、何かを考え、それについて批評しようと、考えていた筈なのだが。美術館で購入した展覧会の画集を幾ら眺めて見たところで、そこには光の反射の整然とした集合があるのみで、時を経る毎に、様々な雑事と些事とむちうちに疲弊させられ、私はミュシャについての批評を忘れ去った。
だが、私の記憶が確かであれば、同じ年の同じ夏である。別の美術館でミュシャに関する展示会が開かれているとの情報があったため、あの熱に浮かされた会場に在った「何か」を取り戻しに行くべく、私はそれへと向かった。そこには、先の展覧会と変わらずミュシャが在った。私はそれを見た。観客が余り多くはなかったため、今度は、じっくりと、眺め入った。すると、ミュシャの、あのアール・ヌーヴォーの、あの豊穣で絢爛な色彩を眺めている内に、私は失った何事かを思い出した。
そうだ。「花と円環」なのだ。ミュシャは。
私は、本批評の主題である二つの象徴「花」と「円環」そしてそれらと「人間」との関係を、再び己の思惟に招き入れることに、成功したのである。これらに関する記述は後の章でするため、ここに於いては述べない。しかし、兎も角、どの批評家も(とはいえ、ミュシャについての批評など、私は一度も読んだことは無いのだが)これら三つの関係に関しては、述べていない様な気がする。その意味では、本稿は世界で初めて、ミュシャを、ある意味では「思想家」として、評価した批評であるのかも……と、いうのは、後の章に譲るとしよう。気が急くのは私の悪癖である。それに、この二つ目のミュシャとの面会以降も、色々と経緯があるのだ。
鮮烈に、私はミュシャに関する思議について思い出したものの、そもそも当時、受験生であったこともあり、ミュシャの批評に取り掛かる時間は、私には残されてはいなかった。だが、無事大学に合格し、入学しても、私にはミュシャの批評を行う時間も、体力も、残されていなかった。したがって、ミュシャとの二度目の面会を最後として、私はミュシャと関係を断ってしまったのである。その頃には、私の関心はより現実的な思想の構築にあった。その結果、Kindle出版にて一冊本を出版することにありつけたものの、私には既に忘れ去られたミュシャではあったが、私の身体には、それは確かに見えぬ棘として、刺さり続けていた様である。一昨年であったろうか。忘れた頃に蘇るほろ苦い、記憶の様に、ミュシャに関する展覧会が開かれるという広告を目にした。……アルフォンス・ミュシャ、既に私から去った画家。しかし、私は、その展覧会へと足を運んだ。……その理由は、分からない。きっと、綺麗な絵でも、また見たくなったのだろう。そこで私は、ミュシャの絵が「Q構図」という構造を有していることを初めて知った。「花」、「円環」、「人間」、「Q構図」。アルフォンス・ミュシャが、ある意味では私に近い存在である「フリーメイソン」と関係を有していたことも。「花」、「円環」、「人間」、「Q構図」、「フリーメイソン」……。これらの概念が、急速にアルフォンス・ミュシャを核として結晶し始めた。私は、昨年の12月まで、批評というものは余りしたことがなかった。ある機会、というよりも気紛れで、今でもそれを続けているのだが。そして、最良であると思った。アルフォンス・ミュシャを、批評してみるというのには。故に、ここにアルフォンス・ミュシャの批評を行おうと思うのである。
ただし、この批評というのは、決してこの画家を公平に公正に見て、これを評価したものではない。私はあくまで批評というものは、作品から新たな意味を取り出す行為であると考えている。即ち、印象批評に、本批評は近いものとなる。「私のミュシャ像」があるミュシャ愛好家は、本批評を読むのを避けた方が良いかも知れない。また、厳密にこの画家について研究したいという研究者(本批評はそういった向きの方々には、読まれないとは思うが、念のため)も。私は学問的な厳密さを、本批評に求めない。私にとって重要なのは、ミュシャが、何を絵に書きたかったのか、という問いに対する答えである。今からは、その答えについて、不慣れではあるが、記してみたい。
*
興味のある方は、下記のURLから本編を読まれたい。
宜しければ御支援をよろしくお願い致します。全て資料となる書籍代に使わせていただきます。
