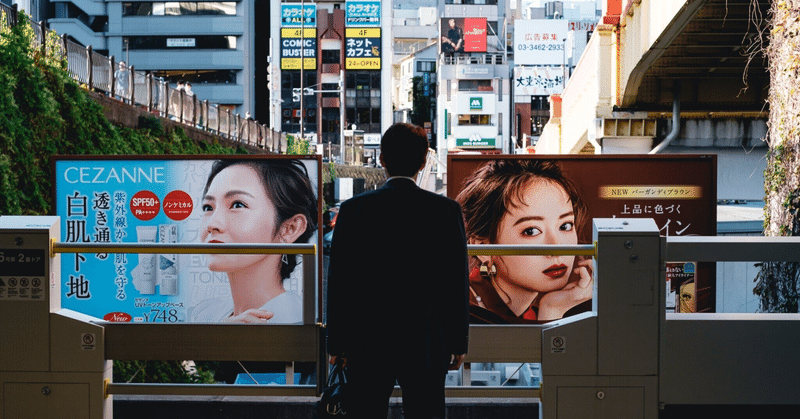
情緒障害とは?~子供の笑顔を守るために~
みなさんは、情緒障害とはどんな障害かご存じでしょうか?
私は知っていたつもりになっていましたが、改めて勉強し直すことで、
新たな理解や発見ができましたので、ここで皆さんと共有できればと思い、
記事にまとめます。
情緒障害とは、周囲の環境から受けるストレスによって生じたストレス反応として環境に合わない心身の状態が持続し、それらを自分の意思ではコントロールできないことが継続している状態をいう
つまり、情緒障害は
医学的に明確な定義を持っておらず、
おおむね心理・環境的な要因による
不適応状態を示す用語として用いられています。
自分の意思ではコントロールできず、
学校生活や社会生活に適応できなくなるとき、
情緒障害という診断が下されます。
近年、家庭環境や地域社会の変化により、
周囲から大きなストレスを受けることが
多くなりました。
普段、小学校に勤務していても、
それを大きく感じることがよくあります。
「もっとがんばればできるのに、どうして…」
「家族のサポートがあれば…」
などモヤモヤすることもあります。
しかし、家族も生活することで
いっぱいいっぱいだということが
痛いほど分かります。
私も、仕事で朝早くから
夜遅くまで働くことが多く、
「もっと子供たちと関わる時間を取りたい!」
と反省する毎日です。
家庭環境や地域社会の変化の他にも、
・学習面で、周囲からの過度な期待によるストレス
・いじめなどによる友人関係の破綻
・教師との信頼関係の破綻
・部活動での教師や先輩、後輩との関係によるストレス
・SNSでの様々なトラブル
挙げてはキリがありません。
このような社会生活上のストレスで
情緒障害が引き起こされるのです。
よって、
情緒障害は、医学的診断はなく、
知的障害や発達障害とは診断はされないが、
生きづらさを抱える子供たちを特別支援の対象として
引き上げることができるのです。
だからこそ、自閉・情緒障害学級は生きづらさを抱える子供たちを救うことができる場所として効果的に機能すべきなのではないでしょうか。
ここで、大きな課題となるのは保護者への説明です。
保護者と話し合いを続け、学校や家庭での困り感を共有し、
最も子どもが安心して過ごせる方法を共に考えていく必要があります。
決して、学校は子供や保護者の敵ではありません。
味方なのです。
未来の子供たちの自立と社会参加のために、できる最大限をしていく。
その選択肢の1つとして、
医療にかかり、情緒障害の診断を受けたのであれば、
自閉・情緒学級で個に応じた支援を
受けることを提案することができます。
特別支援教育に携わるものとして、
問題になる前に子供のサインに気づき、
早めに本人が安心・安全に過ごせる環境を整備し、
成功体験を積ませ、
保護者と医療、必要に応じて福祉と連携し、
よりよい対処方法を習得していくことが
子供の笑顔を守ることにつながります。
ぜひ、皆さんも情緒障害について学んだことを活かして、
我が子や周囲の子供たちの見方を広げ
よりよい支援につなげていただければと思います。
今日の記事は以上になります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
