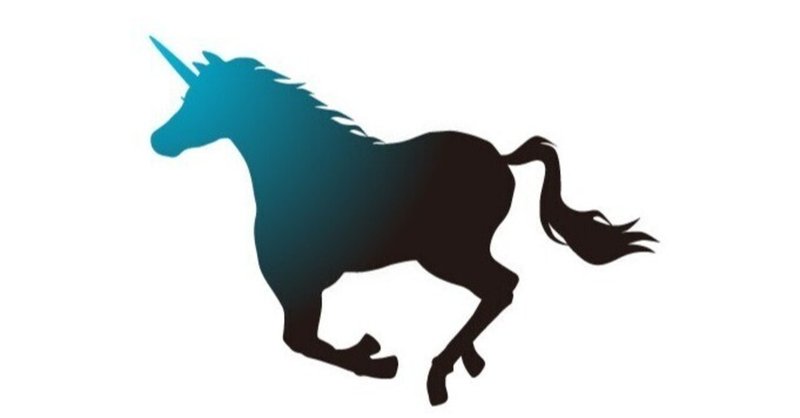
#75 学校教育で育む「能力」ってなんだ? 中編
■単眼と複眼
酒場の「与太話」に端を発する問いだった。
人はそれぞれに、若気の至りや後悔、挫折、苦しみを乗り越えて生きている。
40年前の教師なり立ての頃を思い返してみた。
通常、教師は自分より教科知識や大人としての振る舞いが劣っている子どもたちを対象に教えている。
私自身、自分の限界が露呈しないギリギリのところで教えている、というのが正直な思いだ。
大学出たての若いうちは、質問に答えられなくて恥ずかしい思いをしたことが何度もあった。
今だって時々ある。
いいや、毎日かもしれない・・・・・

それでも、何年かアウトプットを繰り返していると、学習すべき量と内容を熟知し、それに応じた説明の仕方が身に付くものだ。
学習者がどこで引っかかるかも経験的にわかるようになる。
ちょっと難しい質問をされてピンチになることもあった。
その場はちょっと誤魔化しておいて、あわてて調べ、後日改めて補足する。
「君たちに考えてもらうために、前回の授業ではわざと答えを示さなかったけど、実はこういうことなんだよ」
・・・なんてことをやっていた。
何年も教壇に立っていると、「まあこんな程度で大丈夫かな」と妥協しそうになる。
そこで教師としての成長を自ら止めてしまうのか、あるいは
「なおもっといい教え方をしたい」
「教科の面白さをいっぱい伝えたい」と思のうか・・・・
それが教師人生の分岐点になるどころか、子どもの人生の分岐点になるのだと考えれば、やはり日々アップデートしようと懸命になる。
私は学生たちにいろいろな表現の仕方を試みる。
同じことを教えるにしても表現方法は増やした方がいい。
授業内容や教師の言っていることが「わかる」「わからない」という現象は必ず起こる。
一人ひとりの理解の仕方や能力は異なるからだ。
昨日の講義で次のような例え話をした。
あなたは「教師」だと仮定しましょう。
(ホワイトボードに円を描く)
絶対に外してはいけない学習の重要事項を円の中心点にします。
そこに軸足となるコンパスの針をしっかりと刺します。
「起点はここだ!」と、しつこく生徒に強調します。
学習内容と量の基準は半径で決まります。
円の面積が、その学習から得られる総量です。
半径を固定してコンパスで円を描き、その後も同じ円周の上を何度もグルグルと回り続けて、
「わかった!」
「点数が取れるようになった!」
という安心感を与えて終わらせますか?
それとも、半径を徐々に長くして(新たな課題を設定して)円の面積を広げていきますか?
定型の解き方や考え方を反復するだけなのか、それとも徐々にレベルアップしたり、異なるアプローチを経験させて、教科の面白さや醍醐味に気付く複眼を身に付けさせるのか、という話です。
ある学習事項に対して、複眼で見る方法を教えると、生徒は新たな興味がわいて、そこから思考力を駆使しながら答えを導き出せる可能性が高まる。
そこから発展・応用学習にも興味を持つようになる。

『教育とは、子どもの中に宿る成長の「可能性・確率」を高める営みである』と言ったのは誰だったかな?
私か? いつもそう表現しているので・・・・
■能力の固有性
生徒に求める「能力」は単体では機能しない、ということを前回書いた(ような気がする)。
教育や訓練で育てようとする「能力」は、ひとつの能力に特化されるものではない。
結果として得られる単体の「能力」は、他の認知能力(興味・関心、意欲、態度、思考力、判断力・・・・等々)と紐付いて身に付くものだが、評価する際には「能力」を単体で評価してしまう。
社会活動や経済活動は、ユニコーン企業やユニコーン人材だけで成り立っているわけではない。
知の共有、協働だ。
個人に置き換えて考えてみても同じだ。
例えば、数学者の能力は数的処理能力、空間認識能力だけで成り立っているわけではない。
国語の力だって必要だ。
すべては他との関係性。
突出した角(つの)は、他の見えないの個別の角に支えられている。

レーダーチャートに示される能力や評価は、限りなく全方位的に伸びて円形に近づいた方がいいと考えがちだが、そんなスーパーマンは滅多にいない。
個人の能力にはデコボコがある。
努力によって開発される能力や何かの拍子に勢いづいて伸びる能力もある。
ある時点の評価データだけで個人の特性を固定化し、あなたの職業適性は営業ですよ、販売ですよ、エンジニアですね、プロレスラーかな、君は文系向き、理系向き‥‥といった進路指導ばかりしていると、教師も生徒も単眼になってしまう。
後から身に付く適性もある。
適性だって成長する。
あっ、またやっちまった!
今回は1900字も書いてしまいました。
要約力がないんです(T-T)
反省しています。
これを「中編」にして、次回こそ「後編」を書きます。
