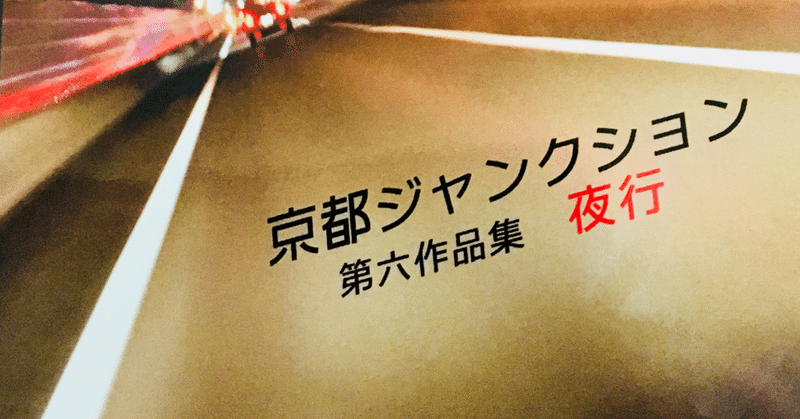
夜の貨物列車
小さい頃から貨物列車が好きだった。ブルートレインを引っ張る姿も、長い貨車を延々と運んで通過していく様も、良いなあ、カッコイイなあ、と思いながら写真集をめくったり、駅に停まっている列車を眺めたりしていた。
どうして好きになったのかは思い出せない。そもそも何かを好きになるということは、きちんとした筋道を辿って起こる現象ではないはずだ。不意にやってきて、熱を帯び、場合によっては急激に冷めてしまう。実際、僕の貨物列車好きも、鉄道ファンの人には笑われてしまうような些細なもので、もし父親が僕に乗り物の写真がたくさん載った図録を買い与えなかったら、この感情は存在しなかったはずだ。それでも僕は、そうした幼少期のほのかな趣向を思い返す中で、自分が惹かれたのは恐らく、貨物列車のメカニックの部分ではないのかと推測している。あれだけ長い貨車を引くのに、全ての動力源はあの先頭車両にある。おかげで運転席以外はほとんど機械で占められている。そうした空間の秘密に対して、あこがれとも好奇心とつかない感情があったのだと思う。
実家が線路沿いの、最寄り駅から歩いて五分ほどのところにあるものだから、二階の窓からは通過する電車がよく見える。線路の反対側にはJTの工場やセメント工場が並んでいて、昔は貨物が出入りしていたらしいが、最近はあまり見なくなったような気がする。それでも、日に何度かは赤いボディーのEF81が通り過ぎていくし、駅の空き線路に貨車が待機していることもしばしばあった。
長い貨車が動き出す時、いかにも引っ張られているという風の、重々しい金属の音が一帯に響く。連結が長ければ長いほど、その音は地鳴りのように連鎖して、線路の長さ分だけ鳴り渡る。貨車全体が太いひとつのこだまとなって、少しずつ、本当に少しずつ、前へ前へと進んでいく。家の中にいても、道を歩いていても、身体が音に反応して、別段こちらには何の危険も及ぶはずもないのに、音がし出すと何故か身構えてしまう。そして、無事に運動が全体に行き渡り、平穏な日常な風景として一連の貨車が走り始めると、ほっと胸をなでおろすのだ。
住んでしまうと、こうした感覚にもすっかり慣れてしまうのだが、たまに来客があるタイミングで外からこの音が聞こえてくると、大抵驚かれる。よくもこんなところに住んでいられますね、と言われたこともあるが、何のことはない。人は意外とどこにでも住めるものである。だいたい、通り過ぎるのは貨物だけではないのだ。最寄りの駅を素通りする特急列車の方が、建物の窓ガラスを揺らしていくだけに、たちの悪い存在と言える。
貨物列車の運行は、通常の旅客運転が終電を迎えた深夜でも続く。地元の駅は、午前1時過ぎに最後の下り普通電車が通過すると、駅のホームが消灯して、それまで明るかった線路の先が真っ暗になる。中学の終わりぐらいからずっと夜更かし体質だった僕は、月に2、3度は、窓の外で駅の灯りが消えるその時を、一日の終わる瞬間として目撃していた。線路を挟んで両側に、駐車場を照らす強い灯りがついていて、夜の線路の存在を、夜通しでぼんやりと照らし続けている。
自分以外がみんな寝静まった家の、自室と台所との間を、コーヒーを淹れるために繰り返し何度も往復するわけだが、その途中、二階の階段を上がってすぐのところに、ちょうど線路と垂直の方向に向いて出窓があり、そこから顔を出しては、よく夜の線路を眺めた。庭木の向こうに、線路の上に連なった電線が見える。たまに、パンタグラフとの摩擦で火花の散る音が聞こえてくることもある、と言えば、線路との距離も分かるというものだ。
遠くから貨物が近づいてくるのに気づく。僕は窓を開け放って、コーヒーカップを片手に目と閉じる。まぶたの裏側には、今しがたまで眺めていた電線が、ぼんやりと浮かび上がる線路の輪郭が焼き付いている。貨物の音は、特急列車の滑らかさからは程遠い。モノが近づいてくる、という感覚が、片方の耳に迫ってくる。その気配の塊が、いよいよ目の前に現れる時、僕は自分の閉じた目の奥で、ある風景が動き出すのを感じる。
その風景の中で僕は、先頭の電気機関車にいる。こっそりと進むにはあまりにも長すぎる貨車の群れを率いて、それでもほとんどの人に知られることのないまま、夜の街を、人のいない田畑の中を突き進む。信号灯をいくつも通り過ぎるたびに、誰も知らない夜の世界を支配しているような気分になってくる。目線を少し上へやると、電線の向こうに夜空の明るさが見えてくる。これだけやかましい音を立てているのに、僕は今、夜の一部としてここにいる。その不思議さと愉快さをない交ぜにしつつ、やがて僕は、空気の振動そのものと化して、夜の中へと姿を消していく。
目を開けると当然ながら、空のコーヒーカップを手にした寝間着姿の自分がいるだけなのだが、夜行の貨物列車が立てるあの音は、鬱屈して眠れなくなりがちの夜をほんの少しだけ楽なものにしてくれる。貨物は夢を運んでいるんだと、鉄道好きの人が力説していたのを聴いたことがあるが、夜の貨物は確かに、僕自身に未知の空間を、夢を与えてくれたように思う。
自分はこんなもんじゃないんだ、まだまだ先に行けるんだ、という根拠の乏しいやる気や自信と、現実の自分の不甲斐なさとの間で押し潰されそうになっていた10代の僕にとって、空想の夜へ誘ってくれるあの巨大な音の群れは、強い感傷を呼び覚ますスイッチのように働いていた。街が寝静まった隙に、線路の上を我が物顔で走り去っていく夜行の貨物列車は、20代の半ばをとうに過ぎても、自由の象徴として僕の心に汽笛を鳴らしている。
だが、あの頃から比べると、僕は乏しいながら様々な経験をしてしまった。強い感傷は、都合よく働けば、自分を鼓舞するのに有効な手段だ。だが、僕は今、26歳になって、このまま走り尽してしまったらどうなってしまうのだろうかと、今まで考えたことのなかった不安に襲われた。無数の貨車を引き連れて、奈落へと消えていくことだってありうる。貨物列車は無事に荷物を届けてこそ、おのれの任務を果たすのではなかったか。
それでも僕は、今でも時折静かに目を閉じて、自分の内側から線路の軋む音がするのを待っていることがある。やがて汽笛を鳴らして近づいてくる貨物列車は、僕の身体に風を起こしては、風の名残ばかりを残して過ぎ去っていく。
何もうまくいかなくたって、行き先がどこであろうと、進まなければならない。どれだけの貨車を引きずっているのか、数ばかりを気にしていた頃もあったが、今はもう、それすら受け入れて、少しでも前へ進みたいと思っている。そうすれば再び、運転席から星空を眺める余裕が僕にも訪れるのだろう。
(初出:「京都ジャンクション」第6作品集『夜行』、2014年11月)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
