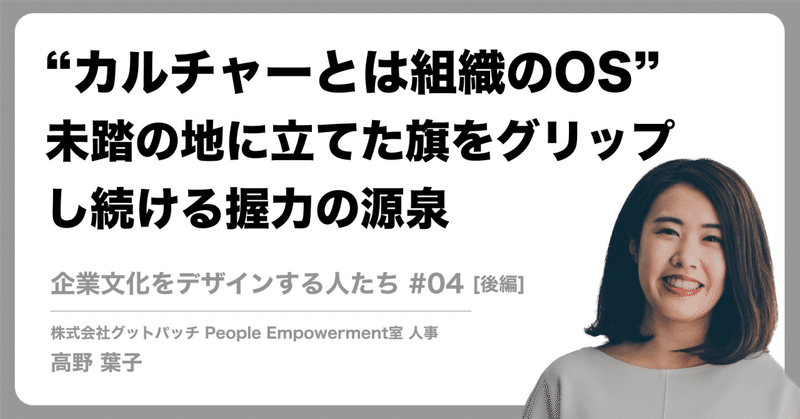
“カルチャーとは組織のOS”未踏の地に立てた旗をグリップし続ける握力の源泉|企業文化をデザインする人たち#04[後編]
2023年6月1日に出版された「企業文化をデザインする」を執筆する過程であらためて実感した「企業文化」の底知れぬ奥深さと影響力。
そんな「企業文化」をさらに深め、多くのビジネスリーダーにとって「デザインする価値があるもの」にするため、「企業文化」と常に向き合ってきたIT業界・スタートアップのトップランナーにインタビューする短期連載企画。
ーー「企業文化をデザインする人たち」
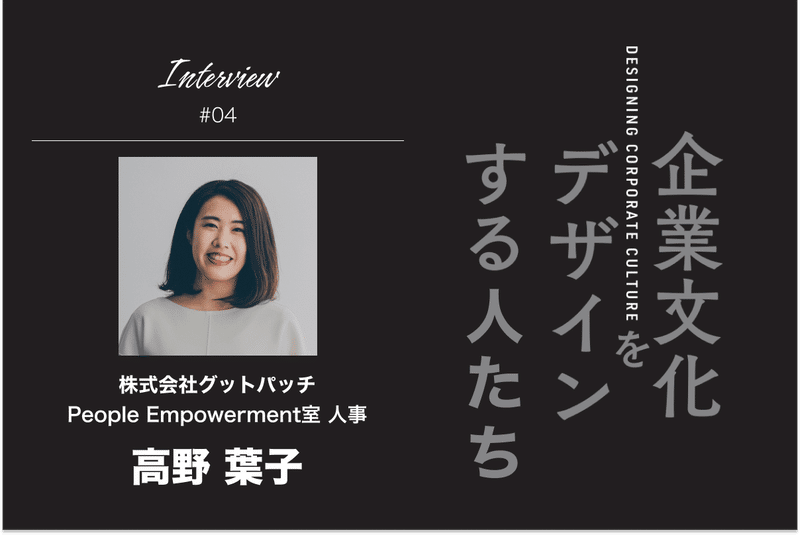
第4弾となる今回は、株式会社グッドパッチで同社のカルチャーの基礎を築いてきた高野葉子さんです。
前後編2回にわたって公開する後編です。
前編はこちら。
話し手|株式会社グッドパッチ People Empowerment室 人事 高野葉子

千葉大学大学院工学研究科デザイン科学コース修了。学生時代にはデザイナーを目指し6年間かけてUI/UXデザイン、デザインマネジメントを学ぶも、2013年に卒業後はベンチャー・スタートアップ企業にて新規事業開発・事業推進を担当。2016年より株式会社グッドパッチに社長室広報として入社。2019年 経営企画室PR/PXグループマネージャーに。グッドパッチは2020年6月に日本初のデザイン会社として上場。産休育休を経てデジタル庁の立ち上げに携わる。2022年9月よりグッドパッチの広報から人事へジョブチェンジ
聞き手|株式会社ラントリップ 取締役 冨田憲二

2006年、東京農工大学大学院(ビークルダイナミクス)卒、株式会社USENに入社。その後ECナビ(後のVOYAGE GROUP、現CARTA HOLDINGS)に入社し複数の新規事業を担当後、子会社として株式会社genesixを創業、スマートフォンアプリの制作とプロデュースを行う。2013年に創業期のSmartNewsに参画し、グロース・マーケティング・セールス事業立ち上げを経て当社初の専任人事となり50名から200名への組織成長と企業文化形成を担当。現職は株式会社ラントリップで事業・組織推進に従事しつつ、複数社のスタートアップで企業文化・人事組織アドバイザリーを担当。2023年6月1日に初の著書「企業文化をデザインする」を出版。
カルチャーはOS、ソフトウェアと同じくアップデート前提である

冨田|企業文化に携わる上で、ご自身の「デザイナー」としてのキャリアがプラスになったことがあれば教えて欲しいです。
高野|もうプラスのことしかないんです。
グッドパッチでも一般的なビジネスパーソンに「デザイン」の価値を伝える時は、例えば「戦略から表層まで一気通貫してすべてを設計すること」がデザインですと。グッドパッチでは「デザイン五段階モデル」を再解釈してその図で説明するんですよね。

(詳しくはこちら)
「デザイン」は人や課題を起点に考え紐解いていくので、企業文化や組織課題に対してのアプローチとして凄くフィットすると思っています。
例えばデザインの対象物。プロダクトだったりサービスだったり、目に見えるもの、手に触れるもの、具体的なものだとしても、作っていく過程では具体と抽象を行き来してデザインします。
それに比較すると組織って、デザインをする対象物としても抽象度が高いし、企業文化は目に見えないし形もないから、難易度が高くて面白いなとも思いますね。その時の事業状況やシチュエーション、そこにいる人の気持ちで考慮すべき点は大きく変わります。
代表の土屋も当然この思考法がベースとしてあって、さらに
「会社がプロダクトだと思ってデザインしてる」って言うんです。
会社自体がデザインの対象だと考えている。
冨田|なるほど。会社自体がプロダクトで、会社というプロダクトもデザインされているんですね。ビジョン・ミッション・バリュー見せ方含めて、本当に素晴らしいし徹底されてますよね。
例えばその会社の文化の「可視化」という観点だと、私は全ては無理だと思っています。可視化できない「カルチャーの余白」があるとしたら、それをデザインのプロ集団であるグッドパッチさんはどのようにデザインされているのでしょうか?
高野|「カルチャーの余白」って「らしさ」みたいな言語化しにくいところの集合体ですよね。日々の無意識な「習慣」になってるところだったり。それを普通にやり続けたら、気づいたら普通の会社になっちゃうようなことだと思うんです。だから、当たり前の行為の積み重ねだと思うんですけど、一つ一つに立ち止まって「自分たちにとって良いやり方ってそうなんだっけ?」とか、ベースのマインドとして「アップデート前提」ですべての物事を捕らえるのがグッドパッチなんですよね。
よく「カルチャーはOS(オペレーティングシステム)だ」みたいな話をしています。OSだから、前提としてアップデートされ続けるものだよねと。作って終わりではないから、凄くソフトウェアのデザインに似ている。リリースしてからも改善を重ねてバージョンアップして行くという考え方が重要だと思うんです。
冨田|まさにカルチャーはOSですよね。そしてカルチャーって「グレーゾーン」の塊だと思うんです。白か黒か、右か左かハッキリしないような。何かに直面した時に、そのグレーゾーンから逃げずに答えを出していくことが、可視化できない余白も含めた絶え間ないカルチャーデザインにおいて凄く重要だと思います。まさに御社はそれを実践しているわけですね。
高野|グッドパッチのコアバリューの一番上に「Inspire with Why」というのがあって、「そもそもなぜなんだっけ?」みたいなところがカルチャーとして根付いているんです。

まず前提の当たり前を疑う、そんな視点からの行動と、感情的に考える「感情価値」を大切にしていますね。
カルチャーへの継続投資が、あらゆる「選ばれる理由」になる
冨田|カルチャーが自らの組織のOSだとしたら、常により良くアップデートしていくための投資は必然と言えますね。
企業文化にそうやって投資し続けることの最大の恩恵は、あらためて何だと思いますか?
高野|「ここで働く意義を作れている」っていうことじゃないですかね。
つまり「グッドパッチが良い」って選ばれる理由だと思うんです。それはお客様からもですし、求職者の方からもですし、何かをグッドパッチと一緒にやりたいと思ってもらえる、そんな「価値源泉」みたいなところがカルチャーへの投資で育まれている気がします。
短期的には、カルチャーへの投資って非合理なことばかりだと思うんです。でも「デザインの力を証明する」っていう力強い長期的なミッションをみんな信じているから、カルチャーにずっと投資できてるんだと思います。
冨田|なるほど。御社の資料、発信の至る所が「Why」からはじまっていますよね。そこが徹底している。だから短期的な視点にならず、中長期で本当に必要なものに腰を据えて取り組み続けられるのでしょうね。

一方で、やっぱり頭で分かっていても「やり切ること」こそ一番難しいんです。なぜグッドパッチさんはやり切れているのでしょう?
高野|文化と仕組みってセットだと思うので、文化醸成に必要な「仕組み」を抑えてるっていうところでしょうか。カルチャーを醸成する仕組みとチームをセットで置いてます。
あとは「People Experience」っていう考え方が、組織に定着したっていう点が大きい気がします。どんな局面でもシンプルに「人の体験として良いのか」みたいな考え方が根付いているんですよね。
冨田|行動の起点には、常に人に起因する課題がある。会社をしっかり「デザイン対象物」として常に意図的にデザインし続けているということですよね。
高野|そうですね。私もその視点ですし、コーポレート側のメンバーはデザイナーとしてグッドパッチをプロダクトとしてどう魅力的に磨き上げられるかを常に考えてます。
組織に高潔であれ。
冨田|そんな「人」に起因する組織文化なんですが、今のグッドパッチさんの組織文化を体現する人を、敢えてひとり挙げるとしたらどんな人なのでしょうか?
高野|すごく悩むんですけど、敢えて挙げるとしたら、佐宗 純さんです。イントレプレナー気質で、新規事業の立ち上げを行い、事業をスケールさせ自社サービスを取りまとめました。
何より彼は「事業と組織の両輪」をしっかり回せる人。そのバランス感覚がすごく良いなと思ってますね。「偉大なプロダクトは偉大なチームから生まれる」って言葉が社内であるんですけど、これを誰よりも理解して自らも自己変革を続けてきているんです。一方で、十周年のアルムナイ(卒業生)のイベントも彼が全部リードして、コミュニティの源泉になるような、ハブみたいな人なんです。
冨田|「事業と組織の両輪」をケアできる人材を評価するというのも御社のカルチャーですよね。ちなみに良い意味での土屋さんとの違いはあるのでしょうか?
高野|タイプが全然違いますね。
佐宗 純さんは学生時代から経営を学び、英語も喋れて誰とでもすぐに仲良くなれるような社交家。日系大手企業に新卒総合職で入った際に、デザインの価値に気づいています。
一見スマートに見えますが、佐宗さんは泥臭い努力ができるんです。その泥臭さが土屋と近いですね。短期的には非合理なことでも、長期的な目線を持って大切にできる。
スマートに機能的価値だけを追求するんじゃなくて、感情的価値にも重きを置くことができる。合理的に考えつつも感情で判断したりやり切れるリーダー。これは土屋との共通点であり、当社のカルチャーの源泉かもしれません。
冨田|なるほど。やはり外目から見る「ビジョン・ミッション・バリュー」だけで分からない、カルチャーの深さが透けて見えますね、面白い。
あと御社は「言葉の力」が強いですよね。
高野|そうですね、デザインという観点で言語化、表現方法は凄く気をつけていますし、カルチャーの一つになっているかもしれません。
冨田|高野さんの過去のインタビューですごい印象的だったのが、広報のチームメンバー選ぶときに一つ重要な条件が「組織に高潔」であると。
この言葉のチョイスは凄いなと。
高野|ありがとうございます(笑)
2人目の広報を採用するとなった時、顧問の方と壁打ちで出てきた言葉なんです。「組織に高潔である」ことにコミットメントができないと、自分の保身に走ってしまうリスクや、会社の成長についていけなくなってしまうフェーズでもあったので。特にIPOに向けてストレッチして行かなきゃいけないタイミングだったりと、そんなニーズから捻り出した言葉、採用要件だったんですよね。
冨田|例えば経営の立場からすると「組織に高潔」な人材が広報やコーポレートにいてくることほど心強いことはないですよね。経営者の心理的安全性が爆上がりするというか。
高野|やっぱりそこが一番大事だなと思っていますね。
経営者が組織ごとの壁打ちを出来るとか、弱音を吐ける仲間がどれだけ近くに居るのかっていうのはすごく大事。
冨田|本当にそんな「組織に高潔」でいい人を採用できるかってまた別問題がありますが、それはクリアできたわけですよね。
高野|やっぱりそのカルチャーに投資し続けてるっていうところ、求心力を作れてるっていうところなんだと思いますね。
経営の力不足が引き起こした「組織崩壊」への向き合い方
冨田|御社のカルチャー投資の原点とも言える「組織崩壊」的な現象を、敢えてセンセーショナルに発信している部分がありますよね。
私も土屋さんから直接お話を聞いて、だいぶハードシングスだなって印象はあるのですが、当然身から出た錆な部分も多いわけで。その辺りを、高野さんはどのようにフェアに見ていますか?
高野|これは、土屋本人も認めているところなんですが、やっぱり「力不足」だったんだと思います。
「力不足」というのは、経営者として「未熟」だったと。初めての起業、初めての組織拡大だから仕方ながいと言える部分もある。私はその期待値で見てるし、自分がそうだったらそうなるしと思っています。
ただ、普通の人からすると「社長」ってなんか凄い人に見えちゃうから。失敗は許されないみたいな感じになっちゃうじゃないですか。結局は創業者・経営陣に対する期待値の話でもあるんですよね。
("組織崩壊”に関してはこちらを参照)
冨田|そんな経験を経て、土屋さん始め残ったチームには何があったんでしょう。
高野|特に土屋は組織がそんなに急拡大するなんて思って起業してないし、ビジョン・ミッションも掲げずに起業してますし。土屋自身の変化や成長は大きかったと思います。
組織崩壊の時、全社の前で謝ったんですよね。全員メンバーを対面で集めて「ごめん」って。僕の力が足りなかったって。
社長ってやっぱ立場もあるし、若いうちから自分で意思決定して責任を持ってきてるから、どうしても自分の中に守らないといけない防波堤みたいなものがあると思うんですけど、素直に失敗をみんなの前で認められた姿は凄かったです。
冨田|会社のトップが失敗をみんなの前で認められるって重要ですよね。じゃないとみんな失敗を認めないカルチャーになりますから。これも頭でわかっていても、実際なかなかできないもんです。
高野|失敗をオープンにするっていうところが、土屋の良さでもあるんです。今も結構人の声を聞きに行くんですよ。この経営判断にみんなどう言ってるか、社員の声だったりとか、ユーザーの声だったりお客様の声だったり。クライアントのインタビューに「うちのメンバーの仕事ぶりどうでしたか?」って聞きに行きますし。彼自身のOSがちゃんと成長し続けていますね。
冨田|まさに御社が上場時に掲げた印象的な言葉が「Goodpatchは青いまま生きる。」ですよね。
その「青い想い」が、常にカルチャーをOSとしてアップデートし続けるという点に繋がっているわけですね。
失敗して、学んで、常に成長していく。その期待値が前提にあるから「青い想い」を大切にしている。素晴らしいカルチャーデザインだと思います。どうしても外から見ると「点」の施策しか見えないんですけど、こうやってしっかりストーリーをお伺いすると、良い意味で合理的にカルチャーがデザインされていることに感銘を受けました。
常に青い、カルチャーを絶え間なく耕し続けること
冨田|今組織は何人ですか?
高野|約250名まで増えました。
冨田|今でも自信を持って「良い企業文化を維持できてる」と言えますか?
高野|自分でも分からなくなってくるんですよ。もう八年目になるので。
ただ、新卒採用で学生さんと面談したりとか、中途で入ってくださった方の話などを聞くと、当社のカルチャーが選ばれる理由になり続けてきてるという実感がありますね。中に居るとだんだん麻痺してくるんですが。
毎月皆さん入社してからの体験記みたいなのを書いてくれるし、グッドパッチのここが良いとか、ここがもうちょっとこうだったら良いみたいなブログで気付かされますね。
冨田|最後の質問です。
高野さんにとって「企業文化」とは一言で言うと何でしょうか?
高野|カルチャーは、ハードじゃなくてソフトウェアですね。
カルチャーって語源が「耕す」ですよね。カルチャーって耕し続けなきゃいけないし、プロダクトもソフトウェアも、やっぱアップデートし続けなきゃいけない、耕し続けなきゃいけない。
耕し続けるという、泥臭く実行までやり切って、しかもそれを続けていくこと。だからソフトウェアなんですよね。
アップデートしないと、ソフトウェアは廃れていく、使われなくなっていくじゃないですか。そこの共通点があると思って、今も手を加え続けていますね。
冨田|青いままでいるわけですね、御社は常に。
高野|自分だけだと、まだ全然だよって思っちゃうんですよ。もっと良くできる。プロダクトもそうだと思いますし、ソフトウェアとかもそうだと思います。
グッドパッチに関わってくださる方が良いって言って下さっているから、じゃあ少しは良いものを提供できてるのかなって思えるんですけど。だから逆に常に危機感は凄くあります。一時流行ったよねっていう会社になるのか、常に最先端で憧れ続けられる会社でいられるのか。ここからが本当の勝負だと思います。
冨田|難しいフェーズですよね。もしかしたら今まで良いと思っていた「らしさ」を、違う方向にアップデートしないといけない事も出てくる可能性がありますしね。
高野|内と外の両面に目を向けて、フラットに新しい世代や社会の状況に照らし合わせて、より良いものを見出したり、混ぜたりして常に進化していかないといけないですね。
例えばコロナ前までは、対面のコミュニケーションに拘っていたんです。ただ、コロナとリモート環境でそれができなくなった。ただオンラインでも「コミュニケーション」という観点では工夫次第で質を高められる。
「チームで働くことを大事にする」っていう大上段をブラさなければ、HOWはどうやったって良いんだと。そうやって軸はしっかり持って、常に過去の既成概念に囚われずに、内面と外部環境の変化や成長によってカルチャーをアップデートしていくことの重要性を日々感じています。
編集後記|Inspire with Why。
グッドパッチさんのカルチャーに関する話は何度も聞いてきました。あらゆるストーリーの起点が常に「Why」からスタートしていることに、あらためてカルチャーデザインにおける「一貫性」の重要さを垣間見ています。
トヨタが「カイゼン」の源泉として「なぜを5回繰り返す」ことも、サイモン・シネックが提唱した「ゴールデンサークル」も全く同じ、人類がより良く進歩するための普遍的な生物学上の真理なんです。
出会ったのは10年以上も前。
— Kenji Tomita (@tommygfx90) September 21, 2022
そしていまだに
「Start with why (Whyからはじめよ)」
という極シンプルな生物学上の真理に支えられている。出会ってなければ、私の仕事人生は全く異なるものになっていたと思う
サイモン シネック: 優れたリーダーはどうやって行動を促すか https://t.co/hJRByQoZrj pic.twitter.com/BRWOhTLBPi
その当たり前を逃げずにやり続けられるか。日々360度からやってくる「短期」視点の圧力に押し潰されずに、遠くを睨み続け、突き刺した旗の握力を維持できるのか。普通はそんな嵐のような自然の摂理に負けて押し流されてしまうものです。しかし、グッドパッチさんはその力強いビジョンやミッションを掴んで離さない。掴んで離さないための力を常に内面から、チームから湧き出るようにカルチャーをデザインしているんですね。経営者の覚悟と、それを支えるチームが、これを理解してデザインし続けている。
そんな泥臭さを、美しくデザインし続けている青いカルチャーに、心の底から刺激を受けたインタビューでした。
本書の「はじめに」と「序章」を無料公開しています。
バックナンバー|企業文化をデザインする人たち
#01|CARTA HOLDINGS 取締役会長兼CEO 宇佐美進典
#02 株式会社マネーフォワード People Forward 本部 VP of Culture 金井恵子
#03 ex-SmartNews, Inc. Head of Culture Vincent Chang
#04 株式会社グッドパッチ People Empowerment室 人事 高野葉子
応援が励みになります。頂いたサポートは、同僚にCoffeeとして還元します :)
