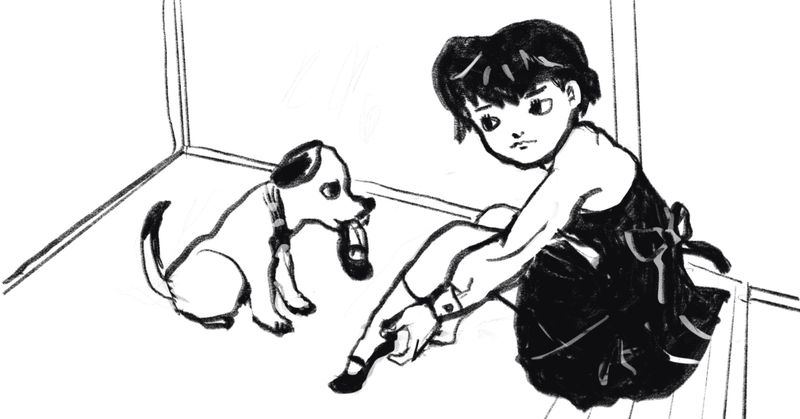
不自由は突然やってくる
よくあるケース「転倒」
今回の入院が、結果的に母の最後の入院となったのですが、そもそものきっかけは「転んだ」ことでした。
転ぶ、って実によく聞く話です。老人は転ぶものですし、初めてでもなかったです。でもこの時は左脚(膝?)に突如力が入らなくなって、階段の下の方でくずれた、と言っていました。
そのときに以前から抱えていた背中の痛みが激痛の域に達してもいたので、母は自分で救急車を呼んで、近所の人にそれを告げて緊急入院したのでした。
偶然ですが、運び込まれた病院は彼女の自宅から歩いてほんの5分のところでした。老人医療には蓄積のある大きな病院です。
そこで詳しい検査をする運びになりました。
同居していた弟は仕事で横浜におり、あたしは出演している演劇の地方公演で、京都におりました。
近所の人たちは弟と懇意にしていたので、弟にはすぐ連絡が行きましたが、母はあたしにそれを知らせませんでした。本番直前のことでもありました。
私は帰ってきてはじめて母の入院を知らされたのです。
結婚して外に出ているということもあるのでしょうが、母はあたしにはなるべく心配をかけないようにしていたようで、それは随所にあらわれていました。
病室では携帯電話は特に禁止されていなかったので、電話をかけて「大丈夫なの?」と訊くと、「私は病院にいるのよ。ケアされているんだからなんの心配もない」と答えていました。
少しでも元気な時は、見舞いに行ったあたしに「早く帰って旦那さまを大切にしなさい」と説教していました。だいたい小言が出るのは元気な証拠でした。
弱音を吐かない人が弱気になる時は
でも痛い時は別です。母の背中の痛みは深刻でした。
電話をかけてきて、「具合が悪いから早く来て」と言って来たことがあります。
ほぼ毎日病院に行くようにしていた時期で、あたしはそのときそこに向かうバスの中にいました。
母がそのような弱音を吐くことは本当に珍しかったので、びっくりしたし、うろたえました。母の体の状態が、深刻であることを思い知らされました。そのときそれまでとはまったく違う痛みか、あるいは気分の悪さを感じたのかもしれません。
着いた時には弟も来ていて、痛み止めが効き始めて、母の顔は穏やかになっていました。その痛みがどこから来るのか、最初の検査の結果が出たときに、医療に詳しい人ならすべてを覚悟したかもしれません。
でも自分たちは、母自身も含めて、いろいろなことを直視しながらも楽天的でいるということをやめませんでした。
「楽天的でいること」と「理解度が低い」ことは似ているので(笑)、人からは痛々しくみえることもあるだろうし、言うことや考えることがだんだん矛盾してくる難しさがあるのですが、あたしたちはそんな風でした。人間のことですから、何がどうなるかはわからないじゃないですか。
本人が診断画像を見ないことも選択
最初の主治医は神経内科だったと思います。整形外科とチームになっていたかもしれません。若い女医で、弟には「若い女医トラウマ」もあるので、気の毒でしたが、病院とのやりとりは任せていました。
私は医者が検査結果を説明する場に行きませんでした。弟が過不足なく伝達してくれるからでもあります。弟は画像のコピーを見せて、説明してくれました。
母自身はCTスキャンの画像すら見たいと言いませんでした。見たいと言ったとしても、見たくないと言ったとして、どちらも母らしいのです。母は本能的に、楽天的でいられる選択をしていたと思います。
画像は現実を突き付けていました。
背骨に腫瘍らしきものが映り、その部分の骨が小さくなってずれていました。
だるま落としの1ピースが、まったく不完全なままかろうじて立っているようなものです。今にもつぶれそうで、つぶれたら神経に影響して四肢にマヒがでるかもしれないし、そうでなくても悪い腫瘍なら浸潤が起きて神経を侵す可能性はあります。
背骨の他のピースも密度が脆いことを示していました。骨の場所は痛みのあるところと一致してもいました。この画像が、それ以降の「寝たきり」を決定したのです。
母にとっては晴天の霹靂ですが、一度転んだことをきっかけに、立って歩いてはいけない、トイレに行ってもいけない、ベッドを起こす角度も制限して、この病巣にかかるであろうリスクを最大限に避けることに方針は決まりました。
介護の現場の言葉にあたしはあまり馴染んでいませんが、母は「要支援1」(時々杖をつくことがあるから。でもその杖も時々どこかに忘れてきたりする)という状態から、いきなり「要介護4」か、「5」かというところにぽん、と跳んだことになります。
それが後戻りのないベクトルであることを、あたしたちはなかなか受け入れることができませんでした。あの元気な人が、もう二度と歩けないかもしれないと思うと胸がつぶれました。
トイレとオムツの狭間
病院に入った当初は介添えをしてもらいながらトイレに立っていました。
それだって不満だったでしょうが、画像診断が出たとたんに寝ていろ動くな、排泄はオムツにどうぞと言われたら、どんな気持ちでしょう?
母が従姉のひとりに電話で「病院は牢獄のよう」と本音をもらしたのは、その頃のことだったと思います。従姉はそれをあたしたちきょうだいに言うことができなかったといいます。
母にとって“牢獄”とはすなわちオムツだったかと思います。排泄の問題は尊厳に大きくかかわります。
「何かもっといい方法はないの?」「すっきりしない」「申訳ない」と、毎日のように言っていました。
それを言わなくなる過程が、入院生活のプロセスであり、また一人の女性が終わりに向かってゆくことの道筋だったのだろうなと、あとになって思います。
少しでも長く生きて欲しかったけれども、この「不本意」が消えないのであれば適当なところで終わりにしたいという、母の望みを感じなかったわけでもありません。
さあそれで、私はこれからどうなるの?
でも、そういう心情のすべてをわかってしまうことは、あんまりにも辛かったから、あたしは独特に察しの悪いしゃべり方やら、余計なことを言わないテクニックやら、むしろ無神経なぐらいに何も気が付かないふりをする“技術”を磨いてゆくことになりました。
母は頭脳明晰な人でしたが、あたしのしゃべり方はそれに輪をかけてはっきりくっきりしていますので、母がそれを期待して質問を仕掛けて来ることもありましたが、ウソはつかない程度に逃げておりました。
母の質問のしかたは例えばこうです。「さあ、それで、わたしはこれからどうなるの?」
「背骨に放射線をあてて、痛みがどのぐらい取れるかやってみるんだって」というのが、例えばの答えです。「それで痛みが劇的に取れるかもしれないし、それはやってみないと」
「それで、背骨にあるものは癌なの?」母は訊きます。
「それはわからないの。わからないけど痛みが取れることを期待してとりあえず放射線をかけるの。だから弱い放射線なんだって」
「わからないの?」
「それをハッキリさせるには、骨髄にハリをさすとか、またひどくリスクのある検査をしなきゃならないのよ。そうしないとそれが癌なのか、どんな性質の癌なのかも特定できないけど、検査そのものが危険なの。そんなの嫌でしょ」
「ああ、嫌ね」
あたしが言っていることに嘘はありませんでした。その時点では背中の痛みが一番の問題でしたが、CTスキャンに映ったものの正体「おそらく骨癌だろう」としかわかってなかったのです。
でもいろんなことを「言わない」でいました。
スキャンの他の部分から、癌の転移はおそらく全身に及んでいることや、だとすれば骨癌は他の臓器からの転移であろうと医者が見立てていたことなど、です。
医者の見立ては見立てでしかなく、はっきりしたことではありませんでした。この後も負担の少ないものを選んで検査は進み、医者の見立てはだいたい正解であったことがわかって行くのですが、あたしも母もある意味で、「はっきりしていないことは見ないでいる」ことを選択していたと思います。
そして、本当の意味で、はっきりさせることや、病気の正体を知ることはまったく重要ではありませんでした。
一番大切なことは、最期まで、苦痛や不快がなるべく少なく、母が笑っている時間が少しでも多いこと、そのためにどうするかを考えるってことでした。
つづく
おひねりをもらって暮らす夢は遠く、自己投資という名のハイリスクローリターンの”投資”に突入。なんなんだこの浮遊感。読んでいただくことが元気の素です。よろしくお願いいたします。
