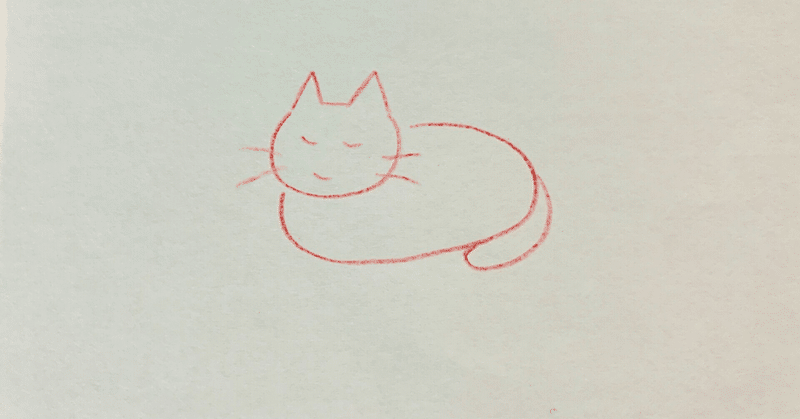
ライターズ俱楽部課題テーマ:あの出会いがあったから
永遠に穏やかな日常を過ごしたい彼とまた会うために
私は死ぬことが怖くない。
むしろ、楽しみにしている。
あの世で再会できる彼が待っているからだ。
私のことを誰よりも愛してくれた。
私のことを誰よりも信頼してしてくれた。
誰も信じられなかった私の心を開いてくれた。
かけがえのない彼の話。
私は幼いころに母と生き別れ、父と生活することになった。
両親が19歳の時に結婚し、20歳で私が誕生した。
20歳しか離れていない父は、体力も気力も十分な若者であり、父というよりも兄のような存在だった。自宅に訪問販売で訪れた男性にも、「ご兄弟ですか?」と実際に聞かれたこともある。
私にとって父は、仲のいい兄弟ではなく、威圧してくる恐怖の存在だった。
父は仕事ができる人で、若手の中でも出世頭で管理職についていた。私に対しても、しつけや言葉使いなどにとても厳しい人だった。
父からの言葉は強く、常に追い詰められていた。
それだけではなく、実際に手を出されることも、しばしばあった。
父がいるときには、談笑して笑顔で過ごしたことはほとんど無く、自宅では隅の方で丸まっていたような記憶しか残っていない。
しかし父は、モテた。
母がいなくなった後からも、彼女が何人も変わり、その都度、私に紹介された。実際には、全員を紹介したわけではないのかもしれなかったが、再婚を考えている相手には、漏れなく紹介された。
その都度、生活環境も、住む場所も変わった。
やがて私は、心を閉ざすようになり、人を信用することをやめてしまった。
人を信用しないため、人の心がわからず、自分の心も見えなかった。
人との距離感がわからず、自分の気持ちを言葉にすることすらできない学生時代を過ごした。
19歳のある冬、彼女ができた。
人の心が見えなかった私は、他人からは「近寄りがたい人」と言われていた。そんな私に告白してくれた、とても風変わりな人だった。
私たちは、一緒に住むことになった。
当時の私も父とともに住んでいたが、その家にも父の彼女が住んでおり、家に帰りたくない気持ちを悟ってくれた、彼女の両親が提案してくれたのだ。
私と彼女の同棲生活が始まった。
しかし、人の気持ちが理解できない私には、同棲生活はとてもハードルの高いもので、すぐに関係はギクシャクした。
小さな言い争いから、大きなケンカまでを、何度も繰り返しながら日々を積み重ねていった。
それでも生活が破綻しなかったのは、お互いに帰る場所が無かったからである。私は勿論だが、彼女の両親が提案してきた以上、彼女も簡単には戻れなかったのだ。同棲を始める前に、彼女の両親から「始めた以上、簡単にやめることは許さないからね」と言われた言葉を思い出した。
これは、彼女の両親の作戦だったのかもしれない、と思った。
翌年の冬。12月1日の日に、彼女のお母さんが、一匹の猫を拾ってきた。
捨て猫だった彼は、全身がグレーの毛並みをしており、右目がグリーン、左目がブルーのオッドアイだった。珍しく神秘的な見た目をしていたのは、今思うと運命的な出会いをするために、神様からのプレゼントだったのかもしれない。
本来、私は動物が苦手だった。
犬は、幸せいっぱいの感情を爆発させ、こちらの気持ちを無視して距離感を詰めてくるところが苦手だったし、猫は何を考えているのかわからないところが、まるで馬鹿にされているようで、嫌いだった。
一生、ペットなどを飼うことは無いだろうと思っていた私のところに、彼はやって来たのだ。
この時点では、私はまだ、全然気がすすまなかった。
彼女は喜んでいたものの、私は憂鬱な気持ちで渋々自宅に連れ帰った。
潔癖症だった私は、帰ってからすぐに、猫を風呂に入れた。
手のひらに納まるほどの大きさしかない彼は、ようやく男の子だとわかる程度の情報しか、全身からは受け取れなかった。
私は、お風呂の間中、彼の命の儚さを実感していた。私がその気になれば、簡単になくなってしまう小さな命。ほんのりと感じる温もりが、手のひらから伝わってくる。なんだか、ジーンと温かい気持ちが湧いてくる。
初めて感じる気持ちだった。
心から、優しくなっていく自分を感じた。
お風呂から出た彼は、混じりけの無い真っ白な毛並みに生まれかわった。
全身が、何も描いていないキャンバスのような、美しい白。
これほどまで、美しい白を見たことは無かった。
彼は、お風呂から上がると、それまでのおとなしかった態度とは裏腹に、元気に鳴き始めた。
「見た目も、性格も、猫かぶってやがったな」
二人で笑って彼を撫でまくった。楽しい三人家族が形成された瞬間だった。
彼が来てから、彼女との関係も、それまでのギクシャクが嘘のように滑らかになった。彼が潤滑油になっているようだった。
子供がいる家族は、夫婦仲が良くなる原理と同じものなのかもしれない。
しかし、私にとって、この体験は特別なものだった。
今まで、人間関係に苦しみ、人との距離感が理解できずに苦しんできた。そうした苦しみが嘘のように、彼女との関係はとても居心地のいいものになった。それまで生きてきた人生の中で、初めて『私の居場所』を見つけることができた。
彼が登場してからの私の人生は、まるで別の人の人生を生き直しているような感覚になっていった。
彼女と私は、それまでの生活の中では、相手のことを考えて何かをすることができなかった。私が相手の気持ちを理解しようという心が無かったことが原因だとわかっていたが、相手に思いを伝えることが、お互いにできていなかったのだ。
そんな私に彼は、愛とは何かを教えてくれた。
段々と成長を見せてくれるだけでも、私に与える影響は十分すぎるほどにあった。
しかし、彼はそれだけではなかった。
無償の愛というものが、どのようなものかを教えてくれた。無償の愛というのは、家族間では当たり前に存在しているものであるが、私は見返りの無い愛というものが、どういうものか理解できなかった。それを身をもって教えてくれたのだ。
彼はどんな場面でも、無防備に私の胸に飛び込んできた。
私が話しかけると必ず返事をし、胡坐をかいていると中で眠ってしまう。布団に入ってきては一緒に寝て、私が何かをしている時には、体の一部をピッタリとくっつけて座っていた。
「信頼しているんだね」
彼女は言った。信頼している。そんなことを言われたのは初めてだった。
猫が私に対する愛情表現が激化して行くにつれて、彼女も負けじと、私に対する気持ちを言葉にするようになっていった。
「思いって、行動や言葉にしないと伝わらないものなんだね」
彼が来てからの数日間で、彼女の気持ちを変化させていることに気がついた。
彼女は私のことを考えて、好きな食べ物を作ってくれ、好きなものを覚えていてサプライズでプレゼントしてくれた。そうしたことを今までの私は、心から温かい気持ちで、感謝することができなかった。
彼女も私も、彼によって人に対する思いやりを学んでいった。
私は通勤に原付を使っていた。
毎日帰宅すると玄関前で必ず待っている彼は、彼女の話では原付が駐輪場に着いたときから玄関で待機しているらしい。
玄関で待っていても、待っていなくても、何も変わらない。
待っていたからといっても、早くご飯がもらえるわけでも、おやつをもらえるわけでもない。強いて言えば、声をかけて、頭を少し撫でてもらえる程度だ。
頑張って毎日やることではない。
体調の悪い時も、気分がすぐれない時もあっただろう。それなのに、彼は毎日、玄関の前で私の帰りを待った。どんな気持ちだったのだろうか。
「大好きなお父さんが帰ってきてよかったね〜」
彼女が言う。私はお父さんで、彼女はお母さん。彼はいつの間にか、私たちの子供のようになっていた。
繰り返すが、元々動物が嫌いだった私は、ペットなんて飼うことはないと思っていた。
それなのに、自然と私たちの間にスルスルと入り込み、私たちの考え方を数日で変化させた猫という動物は、恐ろしくも素晴らしい生き物だと思い直した。ペットを飼っている人の多くは、きっとこのような気づきをたくさんもらっているのだろう。
私たちはいただいているばかりだが、生活の中で無防備に愛情表現をすることで、彼は幸せを感じてくれているのだろうか。自然とそのように考えていた私は驚いた。愛というものが何なのか、それまで知ることができなかった私は、知らず知らずのうちに、彼の幸せまで考えることができるようになっていたからだ。
彼が来たことによって、私たちの関係性も、彼との関係も良くなった。
幸せな日々が、これからもずっと続いていくものだと思っていた。
しかしそうした幸せな日々は、クライマックスを迎えるように、急展開によって終焉へと加速していった。
彼が来た日を誕生日と設定していたが、彼が16歳を迎えた頃から、急に痩せ細ってきた。年齢的に、老衰と言っても過言ではない彼の体を見て、私たちは悲しい気持ちになっていた。
確実に年老いた彼は、若い頃のように動くことができなくなっている。走ることも、ご飯を食べることも、躍動感がなくなってしまっていた。
静かに、私たちは、彼が迎える宿命を受け入れていくための、心の準備を整えていた。
ある時から、彼はトイレではないところに粗相をし始めた。
それを、あろうことか、怒ってしまった。
私は、彼に対して、お尻を叩き、怒ってしまった。
今、そのことを、とてつもなく、後悔している。
もう、年老いた猫だった。
拾われてウチに来たのだから、本来は16歳だったかどうかもわからない。17歳だったかもしれない。年老いて、うっかり、記憶を失うこともあっただろう。
私は、そんな彼に対して、怒った。
叩いてしまった。今でもその時の感触と、彼の表情がまぶたに焼き付いている。
それから間も無く、17歳を迎えた日の夜に、彼は天に召された。
偶然なのか、必然なのか、彼がウチに拾われた日と同じ12月1日だった。
ちょうど17年。
私はその日、仕事だった。
彼の調子が悪く、様子を見ていると彼女から連絡があり、急いで帰宅した。
原付を止めて、自宅に入ると、彼女が毛布に包まれた彼を抱きかかえていた。
「ただいま」
そう語りかけると、「んー……」と弱々しい声がする。
虫の息なのに、返事をしてくれる。
「とにかく、動物病院に行こう」
と彼女と共に動物病院へ向かう。歩いて向かっている間、ずっと話しかけると、ずっと返事をしてくれていた。
動物病院に到着し、診察台に乗せると、聴診器をあてていた先生がそっとつぶやいた。
「もう最期です。声をかけてあげてください。もう目は見えていませんが、耳は聞こえているはずです」
もう、最期。
ショックで頭が真っ白だったが、私は精一杯の思いを込めて、彼の名前を叫んだ。
「ありがとう! ありがとう! ありがとうな!」
彼は両足をピンと伸ばし、痙攣した後、穏やかに眠った。
開いたままの目を閉じてあげた。ゆっくり休んでほしい。
自宅に帰ってきた私は、彼が使っていたベッドやトイレを見て、涙が止まらなくなった。
泣き崩れていた彼女が、ポツポツと話し始めた。
「帰ってくるのを、待っていたんだよ……。たぶん、もう限界だったんだと思う。……でも、最後まで、大好きなお父さんが帰ってくるまで待っていたんだよ……」
最期まで待っていてくれた。
年老いた彼に対して、ひどい怒り方をしてしまった私なんかを待っていてくれた。
「ごめんな……」
もう、目を覚ますことがない彼に向かって、心から謝った。
彼は私と彼女に、心から相手のことを思いやる心を教えてくれた。
彼がそうであったように、見返りを求めない愛というものが、どれだけ温かい気持ちを育んでくれるかを、教えてくれたのだ。
それだけ酷いことをされても、彼の私たちに対する気持ちは変わらなかった。
どこまでも、気持ちを真っ直ぐに、私たちにぶつけてきた。
この世のものとは思えないほどの、真っ白な毛並みを少しだけもらった。
カプセルには、彼の形見が少しだけ入っている。
これで、いつも一緒だ。
私は、子供の頃から、居場所がなくて寂しい思いをしていた。
そんな時は、自分が生きているのか死んでいるのかわからなかった。
しかし、今だから言える。
愛情を全身で表現した彼に教えてもらったことを、私も誰かに伝えようと思う。
相手を思いやる心というのは、人の人生を変えるのだ。
そして、精一杯生きたあかつきには、あの世で彼と、永遠に穏やかな日常を過ごそうと決めている。
とっても嬉しいです!! いただいたサポートはクリエイターとしての活動に使わせていただきます! ありがとうございます!
