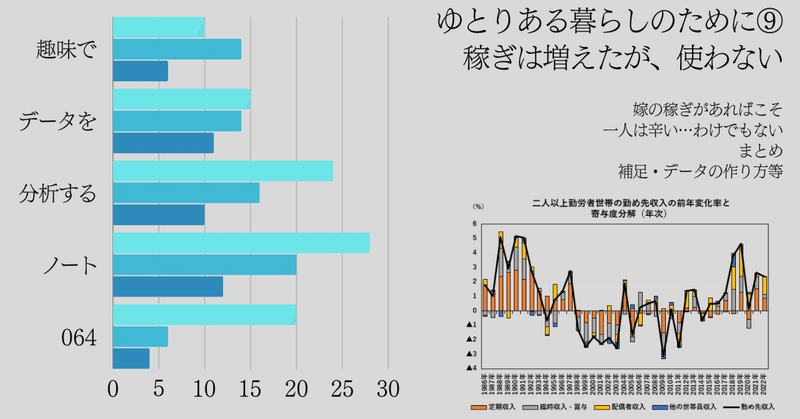
趣味のデータ分析064_ゆとりある暮らしのために⑨_稼ぎは増えたが、使わない
062、063では、年次、月次で黒字率の推移を確認した。結果、以下のことが分かった。
・黒字率は1985年以降、20%台後半でほぼ横ばいで推移した後、2015年過ぎから上昇し、2022年には30%を超える水準。
・所得年齢別で見ても、(水準は別にして)概ね同様に推移。無職や単身世帯も、2015年ころから黒字率が上昇し、2022年が過去最高水準となっている。
・月次で見ても、黒字率は2017年以降概ね上昇傾向で、コロナ禍以降高止まり。2022年後半以降の、物価上昇の黒字率への悪影響は、ほぼ見られない。
ほかエンゲル係数が、黒字率にやや先駆ける形で上昇するという謎も発見できた。
今回は、この黒字率の上昇を順番に要因分解していくこととする。
(構成/概要)
■嫁の稼ぎがあればこそ
・二人以上世帯の2015年以降の黒字の増加要因は、主に可処分所得の上昇のためで、消費支出の減少ではない。
・可処分所得の上昇は、最終的には勤め先収入の増加だが、その中でも配偶者所得の伸びが大きい。
■一人は辛い…わけでもない
・単身世帯でも、黒字増加要因は可処分所得の増分が主だが、消費支出の減少も小さくない影響。
・配偶者所得は存在しないが、勤め先収入の伸び率だけでも、二人以上世帯と並ぶ水準にはなっている。
嫁の稼ぎがあればこそ
黒字率変化の要因分解は、033でも少しやっていて、そのときは、黒字率の増加は可処分所得の増加だけでなく、消費支出の減少(伸び悩み)が奏功した、つまり、稼ぎは増えたが使わない、という消費行動が奏功していることが分かった。今回は、それを少し違う形で示すところから始めよう。
033では、黒字「率」の変化の要因分解をしたが、これは変化の寄与度分解等がいかにも難しい。何より、加法で示す場合、消費支出の変化が明示的に出てこない。今回は、黒字そのものの変化率を使うこととする。
黒字=可処分所得 - 消費支出なので、黒字の変化率は、可処分所得と消費支出の2つの寄与度に分解できる。年次の変化率で見たのが図1である。
033で確認したことと概ね同様だが、
【平成初期】1986年から1997年までは、可処分所得プラス、消費支出も概ねプラス(グラフ的には下に伸びる)で黒字額も増加。
【2000年期】1998年から2003年まで可処分所得がマイナス(消費支出もマイナス)で、黒字も概ね減少のフェイズに入る。
【リーマン期~アベノミクス初期】2004年から2014年まで、可処分所得も消費支出もまちまちの時期(マイナス幅のほうが大きい)で、黒字の変化もまちまち。
【2010年代後期以降】2015年から(2021年を除き)可処分所得上昇フェイズ。ただ1986年から1997年とは異なり、消費支出の増減はまちまちで、黒字額の増加率は平成初期以上。
という形になっている。2015年ころからの黒字率の上昇は、主に可処分所得の増加でもたらされたことが分かる。

(出所:家計調査)
次に可処分所得だが、可処分所得=実収入 - 非消費支出で計算できる(いわゆる手取り給与)。非消費支出には、所得税や社会保険料が含まれるので、実収入そのものにある程度比例することに留意して分解したのが図2で、可処分所得の変化はほぼ実収入(つまり額面給与)の変化でもたらされている。

(出所:家計調査)
では、実収入を分解するとどうなるか。図3がそれ。収入の種類もデータ城は色々あるのだが、平均で均してしまうと、結局はほぼ勤め先収入である。コロナの2020年のみ特別収入が急増、翌2021年は特別収入が急減、という形になっている。

(出所:家計調査)
最後に勤め先収入を寄与度分解しよう。勤め先収入の変化は、2010年ころまでは世帯主の定期収入と賞与等が大宗を占める(この2つはプラマイの方向も基本的に同じ)が、2012年以降、配偶者収入のプラス幅も大きくなっている。特に2018年は勤め先収入が3.8%伸びているが、うち2.5%が、配偶者収入と他の世帯員収入の伸びによるものである。

(出所:家計調査)
別途世帯人員別の収入の実額(合計は勤め先収入となっている)と、配偶者+他の世帯員を合わせた割合を見ると、2010年以降、勤め先収入に占める世帯主以外の収入も大きくなっており、元々10%台前半だったのが、2022年には20%まで上昇している。
そして、世帯主の収入自体は、1997年にピークを付けて以降緩やかに減少、20年を経た2017年ころから再び上昇しているが、水準的にはせいぜい2000年前後と同じである。しかし、勤め先収入の総額は、特に配偶者収入が大きく伸びたことが奏功し、2022年には、1997年を超え、過去最高水準となっている。

(出所:家計調査)
一人は辛い…わけでもない
二人以上世帯では、2017年以降の黒字(率)の上昇は、最終的に配偶者等の、世帯主以外の者の所得の上昇に起因する可能性が高いことが分かった。では、世帯主しかいない単身世帯の場合はどうだろうか?単身世帯の場合、黒字率の上昇は二人以上世帯と比べるとあまり明瞭ではなく、上昇幅も小さい(図6)のだが、要因分解するとどうだろうか?

(出所:家計調査)
二人以上世帯と同じ流れで、一気に寄与度を見ていこう。2008年からしかデータが取れないが、二人以上世帯とほぼ同様に、2016年までは可処分所得の増減率はまちまちだが、2017年以降、安定してプラス圏となっている。消費支出は、全体を通じてまちまち。
二人以上世帯との違いとしては、二人以上世帯では、可処分所得も消費支出もせいぜい数%の変化率だったが、単身世帯だと10%以上の変動が頻繁に見られること、消費支出の可処分所得と比べての影響が、二人以上世帯に比較して大きいことが挙げられる。分母が黒字額で、単身世帯はその水準自体が低いので、結果として変動も大きくなっていることが要因の一つと思われるが、やや謎ではある。

(出所:家計調査)
可処分所得の分解も二人以上世帯と同じく、実収入の影響を多とする。また、2017年から、2021年を除き安定して、4%前後の伸び率となっている。というか、2009年と2016年のマイナスがスゴイ。特に2016年は、二人以上世帯はプラスだったのに単身は大きいマイナスで、伸びの方向に食い違いがある。プラス分は、絶対水準も二人以上世帯とそこまで変わらない。

(出所:家計調査)
実収入の内訳も二人以上と同じく、勤め先収入が大宗を占める。2020年の特別収入の伸び率が相対的に低い程度だろうか。

(出所:家計調査)
勤め先収入は、配偶者所得等がないにも関わらず、最終的なプラス分は二人以上世帯とそこまで変わらない。定期収入の伸び率が比較的大きいことが奏功しているようだ。

(出所:家計調査)
最後に、勤め先収入の実額の推移を確認しておくと、単身世帯は水準自体は二人以上世帯より低いけれども(049でみたとおり、他の条件を統制しても、未婚者より既婚者のほうが所得が高いという謎がある)、データが取得できる2007年以降、2016年を底にして上昇しており、最高レベルではある。ただ二人以上世帯では1997年が最高であり、単身世帯でも過去遡れば、もっと高い水準であった可能性は十分あると思われる。

(出所:家計調査)
まとめ
今回は、黒字率上昇の要因分解を試みた。033で得たのと概ね同じ結論だが、2015年以降の黒字率の上昇は、基本的には消費支出の減少ではなく、可処分所得の上昇によってもたらされていることが判明した。
更に要因分解していくと、可処分所得の上昇は、非消費支出の減少ではなく実収入の上昇で、実収入の上昇は勤め先収入の上昇でもたらされていることも分かった。まあある意味当然ではある。
ただ勤め先収入の内訳は、二人以上世帯か単身世帯かで異なっている。二人以上世帯は、世帯主の定期収入の上昇…はそれはそれであるのだが、それ以上に配偶者所得の上昇の寄与が大きい。一方で、単身世帯は、あくまで自身の定期収入等の伸びだけで、二人以上世帯の勤め先収入全体と同じくらいの伸びを示している。
ここで、単身世帯では定期収入が伸び、二人以上世帯ではそこまで伸びていないことを鑑みて、低所得ほど定期収入が伸びているのでは、と思ったが、二人以上世帯で年収別に推移を見ても、そのようなことはなさそう、というか、低収入ほど定期収入は低位安定で、伸びが顕著なのは、せいぜい上位40%のみである。

(出所:家計調査)

(出所:家計調査)
単身世帯は絶対水準ベースでは収入が低いはずなので、下位40%くらいでも定期収入がもっと伸びているのではと思ったが…「定期収入」が、特に単身者のみで伸びているのは、引き続きの謎である。
ただ、配偶者所得については、年収に関係なく、1985年対比で3倍近く伸びている。特に、2011年ころからの伸びが大きい。配偶者所得も、基本的に世帯年収と単純比例しているので、年収分位間の格差が広がっているとは言えるのだが…

(出所:家計調査)
ともあれ、黒字率の上昇は、単純に労働所得が伸びているためと考えて差し支えがないだろう。具体的に2015年がなぜ労働所得(勤め先収入)上昇の画期となったかは不明ではある。定期収入も配偶者収入も、2015年が特に画期となっている感じはしないのだが、両者の合わせ技で、2015年程度から伸びているように見える形に落ち着いている、ということかと思う。
ていうか、これだけ見ても、若いうちの金のない時代は、単身ではなく二人以上世帯で暮らすべきですな。絶対そっちのほうがいいじゃん。
なお、男女別に賃金の推移を見ても、2015年で特に給料が増加したというわけでもない(男女に程度の差はあれ、2013年以降の継続的な現象である)。

(出所:賃金構造基本統計調査)
次回はエンゲル係数の詳細について分析することとしよう…と思ったが、別にやりたいことができたいので一回休み。
補足、データの作り方など
ソースは従前どおり家計調査と、賃金構造基本統計調査。今回は基本的に寄与度分解を行った。都度説明したが、各要素が、どのように加法で分解できるのかを一覧的に整理しておく。
まずは二人以上勤労世帯について。データは1985年から(変化率を取っているので、実質的には1986年から)で、1999年までは「農林漁家世帯を除く」データである。
①黒字 = 可処分所得 - 消費支出 = 実収入 - 実支出
②可処分所得 = 実収入 - 非消費支出
③実収入 = 勤め先収入 + 事業・内職収入 + 農林漁業収入 + 他の経常収入 + 特別収入
※農林漁業収入については、1999年まではなし、2020年以降は事業、内職収入に合算。
④勤め先収入 = 定期収入 + 臨時収入 + 賞与 + 配偶者収入 + 他の世帯員収入
※配偶者収入は、1992年以前は「世帯主の配偶者の収入(女)」となっている。女性世帯主で配偶者が男性の場合の扱いは不明。
単身世帯については、④の勤め先収入で、配偶者収入と他の世帯員収入が存在しないが、それ以外の定義は同じ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
