
イマニュエル・カント「実践理性批判」
自分自身はいったい何者なのか、世界はいったいどういう存在なのか、ということを考えるときに、自分や世界がどのようにあるのか、と考える方向と、自分や世界がどうあるべきか、と考える方向と二つの方向がある。本来、「どのようにあるのか」がわかれば、「どうあるべきか」がわかるはずだ、と考えてもよいはずなのだが、考えれば考えるほどどうにもおさまらない。
「どのようにあるのか」を徹底的に理性を駆使して論理で考えつくすと、結局「どうあるべきか」はわからない、ということになる、というのが「純粋理性批判」の主旨であった。そして、純粋理性批判の最後のパートで論議しているが、その「どうあるべきか」を考えるのが「実践理性批判」ということになる。
ということで、去年は1年間かけて「純粋理性批判」を読んだが、そういう事情だから「実践理性批判」も読まなければなるまい。ページ数はぐっと少ないが、「どうあるべきか」というのは、ある意味もう一つ難しい。論理だけではなくなるからだ。7月から読み始めているのだが、まだまだこれから、ときに「純粋理性批判」を読み返しながら、予定では半年かけて、じっくりと読みこむつもりだ。
「純粋理性批判」で明らかにされたのは次のようなことである。
私たちはあくまで、自分自身を含む世界であるところの「もの自体」を直接見たり経験することはできない。私たちは、そこに現れる現象を私たちの持つ様々な感官器官を通じて入ってくる雑多な信号として直観し、アプリオリに持っている時間と空間の枠組みにあてはめて受け取り、それを悟性によって概念化する。自分の内側にある感覚も、外側にある感覚も同じく、そのようにしてしか私たちは世界を知覚できない。
私たちは、ある知覚とそれを表す概念を分析することで新たな概念を作ることができる。分析的な思考である。また、ある知覚とそれを表す概念と、その他の知覚と概念を結び付けることにより、より適用範囲の広い新たな概念を作る。総合的な思考である。
これらの理性の働きは、性質の細分化や抽象化であったり、視点を違えたり、原因ー結果の関係を用いるなどする。
しかし、どこまでいってもそれは尽きることはない。つまり、世界の内側でいくら考えても世界の内側のことしかわからない。世界がどう生まれたのか、と考えるとすれば、世界を含むもうひとつ外側のことがわからなければ答えはない。世界が生まれた「場所」は世界の外側から見ることで初めて見えるからだ。
だから、世界がどういうふうにあるのか、私がどういうふうにあるのか、ということは、私たちが経験している世界について、その世界の内側は、わかる範囲でわかるけれども、本当にそれが実在するのか、なぜそのようにあるのか、ということになると「あるかもしれないし、ないかもしれない、理性では証明できない」となるわけだ。
「そんなこと議論したってなんの役にも立たないじゃないか」という人もいるかもしれないけれど、このヘンのことをじっくりと考えていないと、科学技術が万能であるかのように妄信してしまったり、宗教に傾倒して科学技術を否定したり、「科学が証明した○○」とか「科学では証明できない○○」という言葉に簡単にだまされて似非科学に走ってしまったりする。
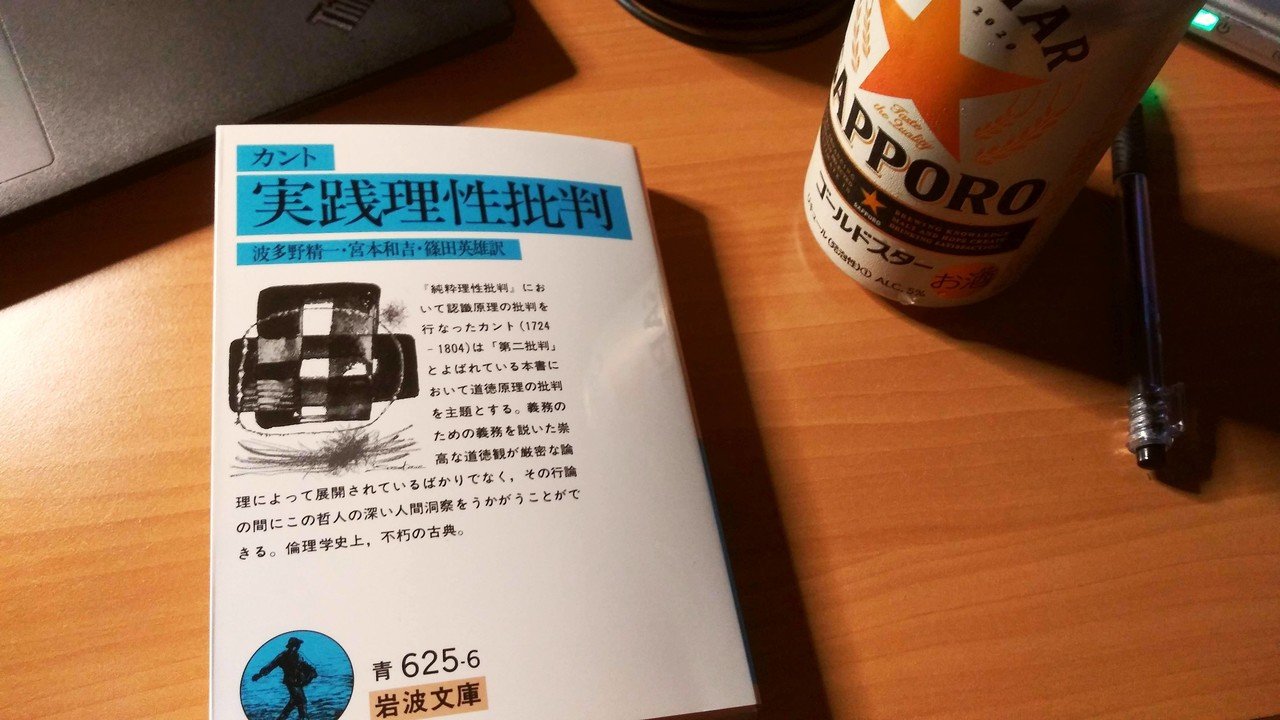
「自分は大丈夫」と思う人ほど注意するほうがよい。理性とはなんだろうか、数学や科学とはどういうものなのか、その限界はどこにあるのか、わかっていることはどこまでなのか、自分とは世界とはどう捉えたらよいのだろうか、ということを批判的に考える(=よく考える)というのは、よりよく生きるうえでとても大事なことだと思う。
そういえば、スタンフォード大学の熱血公開授業のマイケル・サンデル教授の、 "Justice" でも、カントはアリストテレス、ジョン・ロウルズとともに扱われていた。
この本も、これまでに何度か読み直し、今年の前半にも、再度、読み返した本だったが、COVID-19の問題でいろいろ考えさせられた2020年、ちょうどよかった。
私たちがどうあるべきか、というのは、正義、道徳、正しいこと・間違っていることに処する態度・行動の基本だ。とはいえ、直面する困難な状況に直接役にたつかどうか、というと、役に立つかもしれないし、立たないかもしれない。
だが、困ったとき、悩んでいるとき、古の知の巨人がどう考えたのか尋ねてみるのは悪くはない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
