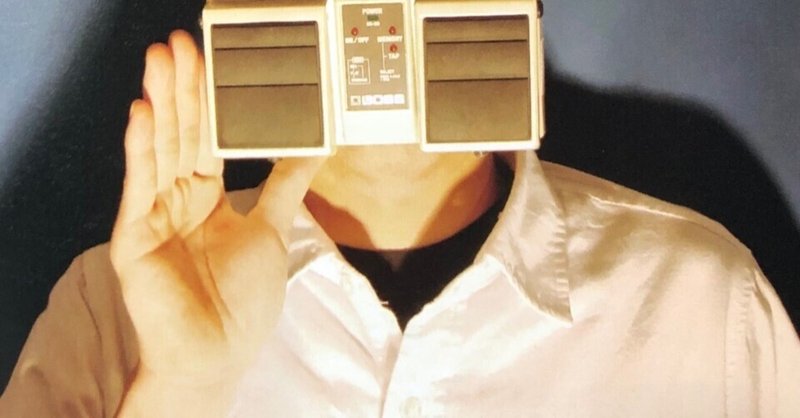
アツレキまくる世界を諦めろ-ZAZEN BOYS『らんど』を聴いて-
朝、アラームが鳴り薄く意識を取り戻してからいつも30分ほどは生きているのか死んでいるのか、意識の混濁した曖昧な時間を過ごしている。この30分を有効に使おうといつも決意を固めてから毎夜床に着いているというのに、何か人智を超えたとてつもない力によって、シナプスを束縛され体を支配されているような、どうしても抗うことができない時間。
自分は死ぬまでこの30分を克服することはないのだろう。
震度7を超える大地震で幕を開けた令和6年。如何とすることもできない自然災害の無慈悲で強大な力を脳裏に焼き付けられ、そして薄れゆく記憶が思い出された最中、2024年1月24日にZAZEN BOYSの12年ぶりとなる新譜『らんど』がリリースされた。
自分はこのアルバムを1音楽好きとして、本当に純粋な音への期待感を持って待ち望み、そして迎え入れた。だが一聴して心から沸き起こったものは
両手をあげて素直に喜ぶことなんてできない、莫大な畏怖の感情だった。
なぜ自分がそう思ったのか、そして向井秀徳という人物がこの作品を通して訴えたいことは一体何なのか。あくまで主観的に整理するために向井秀徳という人間の歩んできた足跡を辿り、その視点の変遷を追体験する形で文字に書き起こすことにした。
まず初めに向井秀徳という人間について、そしてNUMBER GIRLでの表現、ZAZEN BOYSでの表現、そしてそれらの変遷を経た上での『らんど』での表現についてそれぞれ言及をしていきたい。
今を生きる者のため、またこれからを生きる者のため、そしてこれからの自分の糧とするために改めて向井秀徳と向かい合いたいと思う。
・向井秀徳とは?
向井秀徳(むかいしゅうとく/むかいひでのり)とは、人である。
※以下、自身の著書である「三栖一明」(2017 株式会社ギャンビット 発行)より情報を引用
出生は1973年10月26日で兄と姉の3人兄弟の末っ子。現在50歳、今年で51歳を迎える。
生まれは佐賀県というのが一般的な認識だが、実際の生まれは大阪府が正しいとのこと。父親が転勤族だったため大阪在住は本当に幼いころの短期間のことであり、説明の便宜上佐賀県出身として統一しているらしい。
小学生の頃から映画や漫画を好み、それも洋画や手塚治虫作品などクラスで共通の話題になるようなものではなかったため、メインストリームに対するマイノリティという意識がすくすくと育っていったようだ。その中でサウンドトラックもよく聴いていて、それが直接音楽に興味を持つきっかけになったと言及している。
また兄の影響でPrinceに興味を示し、エレキギターを初めて買う時にプリンスが使っていたからという理由でテレキャスターを選ぼうとしたり、USA for America(85年にアメリカのスーパースターが一同に介したことで全世界的な話題を呼んだチャリティープロジェクト)に楽曲提供しながらもPVには参加しなかったそのメインストリームに対するアティテュードに思索を巡らせたりと、プリンスからは人格形成への根幹的に大きな影響があるように強く感じる。(それはリズムへの熱心なアプローチという音楽性にしても、エンターテイナーなライブパフォーマンスという点でも同様に)
自分のギターを初めて手にしたのは中学時代。その頃は遊びの一環で宅録を行いながらも本格的に音楽活動にのめり込むことはなく、高校進学後に周囲がしているのをきっかけにコピーバンドを始める。その頃はロッキング・オンで毎月のように紹介されるPixiesを始めとしたギターロックを聴きあさっていたとのこと。
高校時代から飲酒・喫煙を嗜んでおり、ウイスキー片手に飲み屋に立ち入るなど酒豪っぷりの片鱗を見せつけている。
高校からの進学時には幼い頃からの夢…というわけではなく、勉強したくないからという理由で映画監督を志し芸大をいくつか受験するが、もちろん勉強していないため学科試験で不合格。そのまま進学することもなく、フリーターとなる。
そして後の「TATOOあり」の元ネタとなる女性への大失恋を経験し、本格的に作曲にのめり込むことになる。
※そういった淡い恋愛体験話がいくつかあるが、女性に好意を抱いた時にはいつもThe La'sのThere She Goesが脳内で流れているらしい。
自らの事を「すごく影響は受けやすいんだけど、それを、自分なりにアウトプットしたいという気持ちがとにかく強い」と評しており、また「表現することで世間、他の世界と関係を持ちたい」という思いで創作にのめり込んでいったとも話している。
向井秀徳という人間はとにかく強固で甚大な自我を内に拵えていて、その自我を創作で表現し、その表現を持ってして他者と繋がりたいという強い性的衝動を持ち合わせているのだというふうに自分は捉えている。
つまり、向井秀徳が創作をすること=作曲することは彼の内なる自我をあるがまま表現し伝達することであって、描かれている景色や歌詞が表現するものを知ることは、そのまま彼自身を知ることに繋がるものだと強く感じている。
自分(のみならずきっと他の皆も含めて)が向井秀徳という表現者を好きな理由は、その等身大の自己表現に対する絶対的な信頼感と、圧倒的な説得力があるからではないだろうか。
向井秀徳とは、人である。
自分は確信を持って、そう言いたい。
・NUMBER GIRLでの向井秀徳
本格的に作曲に取り組み始めた向井秀徳は、No.5(ナンバーファイブ)という名義で個人での音楽活動を始める。名前の由来はThe Beatlesの国内編集盤「ビートルズ No.5」からとのこと。
ミュージックバーやホテルのホールのPAなどのバイトを経て福岡の音楽界隈での交友関係を広めていき、「チェルシーQ」というインディペンデントなイベントをPANICSMILEと共に主催。
並行して正式なバンドメンバーを探し求め、その中でカウガールというバンドの元メンバーと出会うことになる。
No.5とカウガール、その二つを合体させて「NUMBER GIRL」としようとしたのがバンド名の由来になる。
その後、
ベース:中尾憲太郎
ギター:田渕ひさ子
ドラムス:アヒトイナザワ
この3名が加入してからの躍進劇はご存知の通り。
NUMBER GIRLとしてフルアルバムは4枚リリースしている。
『SCHOOL GIRL BYE BYE』(1997)
『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』(1999)
『SAPPUKEI』(2000)
『NUM-HEAVYMETALLIC』(2002)
今回はこれらフルアルバムの歌詞を基に、あくまで自分の所感を羅列して、視点の変遷を整理したい。
・SCHOOL GIRL BYE BYE
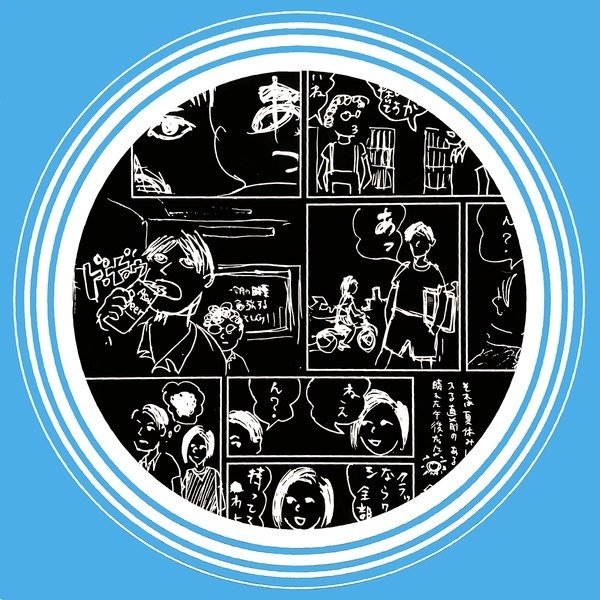
1997年、向井秀徳は24歳。
インディーズで全曲一発撮り、メジャーデビューへのきっかけになるSCHOOL GIRL BYE BYEではひたすらにモラトリアムに感じた情景を描写しまくっている。
登場人物は俺と君。あの娘と共に過ごした中でThere She Goesのようにキラキラと流れ行くプリミティブな感傷をこれでもかと言語化して吐露している。
そして夢と現を行き来しながら風景や言葉を復唱し、より強い自分が明日を生きていくと胸を張っている。思い出が与えてくれる感動の素晴らしさに打ちのめされながら。
これからの自分たちが歩んでいく、眩く輝いて見えんばかりの、来るべき未来への希望と確固たる決意がアルバム全体に満ち満ちているように感じる。
向井秀徳という人間の視点から見える景色は、この時まだ不安のかけらも伺うことができない。
・SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT

1999年、向井秀徳は26歳。
上京し東京で録音を始めたが、やはり自分たちの納得するものを作り上げるため地元福岡に戻り制作された東芝EMIからのメジャーデビューアルバム。
向井秀徳とは、他者と繋がりあいたい人間である。
そして今作ではアツレキという単語が頻出する。
アルバム冒頭「タッチ」で即物的で表面的なコミュニケーションについて言及する。
SCHOOL GIRL BYE BYEで夢と現実を行き来しながら感動をただただ吐露し続けていた向井は、聴く者に訴えかけるようになる。「お前はどうなんだ?」と。
今作では他者、そして世界と通じ合うという目的。それを果たすための手段だった創作という表現が、それのみでは成し得ることができない都市の現実に直面したことによる苦悩が滲み出ているように強く感じる。
その苦悩が最も表れているのは、ラストトラックの「EIGHT BEATER」ではないのだろうか。
そういった苦悩のみではなく、青春の焦燥感に身を任せることもある。ただ、そのどれもが当事者目線というより傍観的な、うっすらとした虚無感を纏っているようでどこか寂しさを自分は感じてしまう。
地方とは全く異なる東京という街の、そこに住む人間への不信感を、夕暮れまみれの幻想から現実へと降り立ったことによるどんな映画よりも生々しい感情の変遷が垣間見える1枚なのではないか。そう思う。
・SAPPUKEI

2000年、向井秀徳は27歳。
今作で支配している感情は渋谷109にたむろしているJK100人に聞けば間違いなく100人が「怒り」だと答えるだろう。
それほどにこのアルバムはオラついている。とにかくささくれ立っている。
黒地に女性の後ろ姿の線画のみというジャケット、脳に直接届くような生々しい音響処理と刺すように鋭角なギターリフ。向井の作り上げた作品史上最も暴力的だと思う。
対個への訴えを続けていた向井が「冷凍都市」と母数を引き上げ、抵抗を宣言する「Brutal Number Girl」から幕を開ける。
前作で感じた「軋轢」を生む都市に住む人への違和感、そしてマジョリティに対するどうしようもない無力感。それらに抗いながらも創作をするため、対個のフィールドまで引き摺り込むために、向井は最も暴力的な手段を取らざるを得なかったように感じる。
そしてかつて輝かしく希望に満ち溢れた感動の象徴として訴えかけてくれていた夕暮れを、今作では憂いの象徴として表現している。もう取り戻すことはできないモラトリアムの幻想。
その視点の変遷が、あまりにも辛く悲しい。
向井は今作で、解り合えない他者に対して、少しでも心を揺さぶり通じ合う道を模索するため、煽動的で直接的な怒りという手段を用いたのではないかと感じる。
まだ、この時は諦めていなかったのではないだろうか。
・NUM-HEAVYMETALLIC

2002年、向井秀徳は29歳。
音楽的にも歌詞においても、向井はセンチメンタルな感傷を表現することから明確に遠ざかっていくことになる。
それは表現で他者への繋がりを相手へ求めることを「諦めた」が故ではないのだろうか。
レコーディング時にはキワキワを冷徹に追求し続ける向井と他メンバーとの温度感の差が顕著に出ていたという話は有名だ。また向井自身、当時は自分は常に夢状態であったとも話している。
その「諦め」によって、相互間の繋がりではなく、溢れ出す甚大な我の一方的な誇示という手段が残された手段となり、また一線を引いたことで他者の意思が介在することなく、その表現の虜となっていったのではないだろうか。
その転機となった決定的な出来事が一体何だったのか、なんてことをよく妄想している。
明確に、断定的に、向井は今作で不平不満を覚える対象に影響を与えようとしていない。ただ自分のスタンスを表明するのみで、どうしようもないと吐き捨て、耳を塞げと断絶を命令する。
諦めが顕著に出ているのは個人的には「MANGA SICK」だと感じている。
あれだけあの娘と触れ合う煌めきをキャンパスに描いてきた人間が、恋なんてなんするのとぶっきらぼうに、おちょくったように歌う。
そんなもの結局今となってはどうだってよかったと言わんばかりに。
しかし、完全にセンチメンタルな感傷と縁を切っている訳ではない。
少女のように微笑む転校生への淡い思い出を、懐かしむように、そして憐れむように思い出しもしている。
そのわずかな慕情が垣間見えるところに、胸が締め付けられる思いになる。
以上でNUMBER GIRLは4枚のフルアルバムを世に発表し、中尾憲太郎の脱退表明と共に解散を選択する。
NUMBER GIRLで向井が映し出してきた視点は、その一瞬一瞬の景色を本当に鮮明に切り取っているように感じる。
写実的で、映画を見ているような感覚になる。
だが、向井秀徳というセンチメンタル過剰でありのままの人間が全身全霊で表現し、無力感に苦悩し、いたたまれない冷笑に激怒し、最終的には諦観に包まれながら青春そのものを終えてしまう。
これは映画のあらすじではない。フィクションではない。
一個人の人生の現実で、その救いのないストーリーに自分は愕然としてしまうのだ。
そしてその諦観の末に、向井秀徳は己の我を提示することを確固たる主目的に据え、ZAZEN BOYSを本格的に始動することになる。
・ZAZEN BOYSでの向井秀徳
NUMBER GIRLを解散後、ドラムス アヒトイナザワを引き連れて向井はZAZEN BOYSを始動する。
その標榜は「法被を着たレッド・ツェッペリン」。
骨と骨のぶつかり合うようなアグレッション極上なプレーヤーの演奏を血肉とし、自我向井秀徳というシュールレアリスムの権化がバキバキと剥き出しの関節の節と節を打ち鳴らしながら現世に受胎をするためのモビルスーツ。
自分の認識はそんな感じ。
ZAZEN BOYSがリリースをしたフルアルバムは現在6枚。
『ZAZEN BOYS』(2004)
『ZAZEN BOYS 2』(2004)
『ZAZEN BOYS 3』(2006)
『ZAZEN BOYS 4』(2008)
『すとーりーず』(2012)
『らんど』(2024)
本項ではその内らんど以前の5枚について言及する。
・ZAZEN BOYS

2004年、向井秀徳は31歳。
メンバーは
ギター:吉兼 聡
ベース:日向 秀和
ドラムス:アヒトイナザワ
メンバーに現金を渡し、演奏家として雇うことからレコーディングが始まった1stアルバム。
賃金を発生させることで、向井秀徳はひたすら自らの望むバンドサウンドを目指すことを明確に提示する。
これからの己が行うだろうことに向けて、完全に覚悟が決まっている。
今作で向井は自らの目で見て感じた都市の冷たさ、それによるフラストレーションをありのままに言語化し聴衆の眼前に提示している。
その中で蔓延る性の乱れ、その猥雑さについて言及する。
背水の陣で都市の人間の隔たりを明確に糾弾するためには、避けては通れなかったのだと思う。
そして今作では、向井秀徳という人間を知る上で重要な意味合いを持つ2曲が収録されている。
一つはその創作活動の原動力である自己表現による相互理解の欲求、
それを一糸纏わず赤裸々に告白する「Kimochi」。
ただ一人になったとしても抗い続ける覚悟を決めたが故に生み出された、血の通った生の人間だからこそ作り上げることができる、音楽史上でも最も美しい曲の一つだと自分は思う。
もう一つは頭脳で巻き起こる思考の巡りを飾り気を一切排除して、朗読のようにあるがままをぶちまける「自問自答」。
これまでの音楽活動の中で苦悩に染まっていった向井秀徳という人間が求めているもの、変えたいもの、大切なもの、それらが全てこの曲に詰め込まれていると言っても過言ではないのではないだろうか。
そしてこの曲のタイトルは「自問自答」。
表現の結果で他者の介在が起こり得ないという固執した諦念が突き刺さる。
個人的には、向井秀徳が焦燥感のある感傷的表現をすることは今作が最後だったと思っている。
それは今後の創作活動を行っていく上での明確な線引きのようで、裸のままの向井秀徳を知ることができる個人的にはキャリアの中での最重要作だと思っている。
・ZAZEN BOYS 2

初期衝動による即興演奏的だった1stと同年にリリースされ、ミュータントディスコテックなポストパンクへと昇華した2nd。
強い思いが込められた前作とは対象に、今作では向井はふざけ倒している。
特に印象的なのは「黒い下着」。
ナンバガに瓜二つなド直球ギターロックに、意味の無い歌詞を載せる。
敢えて、そうしているように自分は感じる。
初めて聞いた時はZAZEN BOYSとして新たな音像を追求していくと予想していた中、自らの過去を冷笑しているようで、サーカスのピエロの商売道具として用いているようで少し寂しい気持ちになったのを覚えている。
そして既発曲(それはNUMBER GIRLも含めて)の歌詞をひたすら引用しているだけの曲もある。
音もどクラシックなロックバラードまんま。
歌詞に意味を持たせていない。意味を持たせることに意味を見出していないと強く感じる。自分はそのぶっきらぼうなどうでもよさに都会の無機質さがダブる。NYアンダーグラウンドの味がする。
このアルバムはなぜこんなにもナンバガを彷彿とするレベルで、ストレートにオルタナティブなサウンドなのだろうか。
前作で拭い去った過去への慕情を、音楽的にも出し尽くそうとしたのだろうか。
聞くたびに不思議な気持ちになる。
そして今作を最後に、これまで向井のビートを支え、共に生み出してきた盟友ドラムス アヒトイナザワが脱退することになる。
・ZAZEN BOYS 3

2006年、向井秀徳は33歳。
ドラムの後任に柔道二段 松下敦が加入。
「HIMITSU GIRL'S TOP SECRET」を2005年に発表後、本腰を据えて作成された3rdアルバム。
松下敦のドカッと重心を据えたグルーヴに焦点を当てたコールドファンク。
今作でZAZEN BOYSの音楽性が、そして本気と冗談の境目が曖昧になっていき
面白酒飲み弾き語りおじさんとしての向井秀徳のキャラクターが定まった認識だ。
前作から顔を覗かせていた歌詞の概念化、傍観化が今作でより洗練される。
まだ見ぬ音像の探求心が、プリミティブなアティテュードの表層化よりも遥かに勝っていたのではないだろうか。
念仏のように深夜の空虚さを唱えている。
ただただ街を見つめて、その風景を描写する。
それは音楽的にも湿度が不要だったということもあるだろう。
くり返される諸行は無常という単語がうな垂れるように横たわる。
音楽の先鋭化が進むにつれて無味無臭に進んでいく歌詞表現、それで省かれていったものは「くだらない感傷」だったのだろう。
だがこの3~4の頃のZAZEN BOYSは演奏が本当に凄まじく、向井秀徳という巨木のようにそびえ立ち、冷徹に正確無比なリズムの化身に対し一瞬の乱れも引き起こすまいと全神経を集中するメンバーの鬼のような気迫は完全に体育会系のそれだった。
あの歴戦の漢たちの肉肉しいマチズモな演奏の前では、感傷なんてものが吹き飛ぶのも個人的に納得する。
・ZAZEN BOYS 4

2008年、向井秀徳は35歳。
前作を持ってベースの日向 秀和が脱退。ストレイテナーでの活動やセッションミュージシャンとして引っ張りだこの多忙具合、そして向井曰く「向井のノリに合わなかった」のが要因だったこと。
そして新メンバーに吉田 一郎を加えコワモテ度が更に極まったメンツで制作された4枚目。
まずオープニングの「Asobi」では一夜の関係を持つ男女を描写する。
軽い気持ちで接近する女性、そしてそれを大きな感慨もなく受け入れる男性。
女の(幼稚だと切り捨てる)たわいもない話を男は全て聞き流す。
お互いの相手に対する無関心が透けて見える。
そして別れ際に残した女の遊び足りないという言葉がこだまする。
この曲の登場人物は向井本人なのだろうか。それとも女性こそが向井なのだろうか。
自分には、それが未だによくわからないでいる。
己の目から見えたものを誇示し続けてきた向井秀徳の作る詩の中で、初めて語り部のように第三者視点に立ったものなのかもしれない。
Asobiのように、今作はプリミティブで感傷的な表現が見事に復活している。
傍観的ではなく主観的に、どれも異性が相手にいる。
やっぱり繋がらないか、という言葉に滲み出る悔しさが性急に伝わってくる。
そしてラストの「Sabaku」で、孤軍奮闘の旗を掲げて徹底抗戦を続けてきた向井の口から溢れる
「割と寂しい」
これまでの向井秀徳という人間が辿ってきた思い、行動、道を顧みて、
この一言はあまりにも重い。
そして切ない。
歌に、メロディに重きを置いたこの1曲は今後の向井の表現手段に、そして『らんど』へと直接繋がっていく。
今作では、今まであくまで間接的に他者との繋がりを求めていたが、それを直接的に表し始めている。
年齢を重ね経験を増やし、見栄も体面もどうでも良くなったのではないか、なんて個人的に思っている。
その全ての思考の変遷が納得できるのは、恥も後悔も包み隠さず表明してくれているからこそに他ならない。
その姿にどんなフィクションよりも、自分は感動を覚えてしまうのだ。
・すとーりーず

2012年、向井秀徳は39歳。
向井秀徳としては間にLEO今井とのKIMONOSを挟み、4年の期間を経てリリースした5作目。
人間同士の無関心や猥雑な喧騒といった都市への怒り。
向井を突き動かしていたその激情はすっかりと鳴りを潜める。
ただただ、幼い頃からの好物のポテトサラダが食いたい。
そんな朴訥な思いだけで曲が出来るくらい、もう片意地を張ることはないのだろう。
ささくれ立つ苛立ちは未だに覚える。
ただ、明らかに以前までとその表現の仕方が異なっている。
その眼で捉えた直感をぶちまけるのではなく、ただその状態を俯瞰している。
年齢を重ねるということ、多くの時を過ごすということ。
人間が成長をしていくということ。
その物語を感じるように、向井秀徳の視点はもう既に、己の内面のみではなく大局的に物事を見据え始めているように感じる。
そうして向井秀徳は青春の終わりを告げた後、恥も外聞もかなぐり捨てた軍隊の如きハードコアな表現を追求し、そしてまた只一人の等身大の男に戻っていった。
NUMBER GIRLの1st「SCHOOL GIRL BYE BYE」から数えて15年の歴史になる。
その視点の変遷を改めて思い返してみて、やはり向井秀徳は人だと思う。
凡人に理解できない天才というにはおこがましい、ありふれた感情にただただ素直に従って行動をしただけの自分達と何ら変哲のない人間だと思う。
行動に起こすか起こさないか、違いはただそれだけなのではないのだろうか。
そして、12年もの長い長い時を経て、向井秀徳は『らんど』を発表した。
・『らんど』での向井秀徳

2024年、向井秀徳は50歳。
12年という長い長い時を経て発表された、ベーシストの吉田 一郎が脱退後MIYAが加入しての初めての作品となる6作目。
その間、向井はNUMBER GIRLを再結成した。bloodthirsty butchersが伝説のライブを行ったRISING SUN ROCK FESTIVALに出ること、また金を稼ぎたいという発表時の謳い文句も実に向井秀徳らしいと思った。
何より、「感傷」を「くだらない」と切り捨てていた向井が、センチメンタルの具現化だったNUMBER GIRLを再び演奏しようと思った。
その事実だけで自分は無性に嬉しい気持ちになった。
もちろん自分も公演を一度見に行った。
それぞれ音楽活動を続けていたメンバーたちは本当に当時と変わらないようなバッキバキの演奏をしていた。
最高の演奏だったが、一度で満足した。
あの時のままの演奏を見せてくれたけど、それ以上でも以下でもないと感じてしまったのが理由だと思った。
これからまた曲を作る、なんて事になったらずっと追いかけていたと思う。
ZAZEN BOYSとしてライブ活動は続けていたが、音源の完成まで時間がかかった経緯は以下のインタビューに記載がある。
「まだ俺を決定したくない」「次の時間にいる俺を探し続けて12年経った」とのこと。
そんな『らんど』を聞いて、自分が感じたものは畏怖の感情だった。
それは、より具体的に言えば、
あの向井秀徳の人生も、終わりが近づいている。
というものだった。
改めて、かいつまんで『らんど』での歌詞表現について言及していきたいと思う。
『らんど』の幕開け、「DANBIRA」はお決まりのフレーズから始まる。
繰り返される所業は無常
それでも蘇る性的衝動
そして糾弾を続けてきた都市に蔓延る悪意を改めて提示する。
全て知っている。向井の視点でいつも見据えていたものだった。
「遊び足りない」とこだましていた新宿革命記念公園を、だんびらを振り回しながら通り過ぎる。健康のために。
50歳、痴情より健康の方が目下気にかかるのだろうか。
そして明確に第三者視点で展開をする「八方美人」。
向井秀徳は一人称視点で自分の我を表現することを常に軸としていた。
他人視点でその心の機微を描写することが、恐らく今までなかったのではないだろうか。
(もしかしたらAsobiが例外かもしれない)
ただ自我の表現を辞めたのではなく、その視点を広く共有するための手段として用いるようになった。
(失礼な言い方になるのは承知だが)その余裕が生まれたのではないのだろうか。
「黄泉の国」では人と人が交わり合う、その酸いの思いを表現する。
感動するでもなく断絶するでもなく、複雑に絡み合いながら生きていく。
子供も大人もないまぜになって、人生を謳っている。
これは完全に歌謡曲だし、それを歌う姿がとても様になっている。
そして、確実に今作で最も重要な1曲である「永遠少女」について。
この曲で向井は少女である「君」に向けて言葉を重ねていく。
君がそうであったように、母親や祖母もかつて少女だった。
そうしてかつての少女たちも生きて、悩み、そして親となる。
その紡がれていく歴史の中に君もいるのだと。
その合間合間に唐突に挟まる戦時中の不条理で強烈な死の描写。
この世にはセンチメンタルな感傷に浸ることや不条理に抵抗することもできず、
無為に命を奪われるだけの少女もいるのだと。
その生と死の対比の後に「諦めている」少女に向けて向井は、
「人間なんてそんなもんだ」
とあっけらかんと諭す。
だがそれでも「探せ」と強く強く訴える。
何度も繰り返し言うが、向井秀徳は自らの我を表現することを至上としてきた音楽家だ。
だが、この曲は明らかに独りよがりな自己の表現ではなく、次の世代を生きる若者に向けて歌われている。
そしてこの「諦めている少女」は、「かつての向井自身」の様に感じてならない。
自己そのものでしかなかった向井秀徳の自我は、これまでの作品でその視点を聴衆に共有し続けてきた。
そんな向井の自我はそのものである作品達に触れていき、共感をしていくこれからを生きてゆく若者たちの自我ともリンクしていると、悟ったのではないだろうか。
そんな「かつての向井自身」のようなセンチメンタル過剰な若者に対して、自分の人生を通して得たものを、託そうとしている曲だと思う。
言ってしまえば唯我独尊、傍若無人な生き方をしてきた向井秀徳という人間が、
ここまで他者に寄り添い、無償の思いを捧げるような曲を作り上げた事に、歴史を感じ時を重ねることの偉大さやその言葉の力強さに、自分は感動を超えた感情=畏怖の思いを感じるに至ったのだった。
そしてその思い、主張に、向井秀徳の人生の終末という、来たる日の心構えをしないといけないことを強く意識する。
・最後に
とかなんとか言ってるがアルバムの最後は相変わらず飄々としていて、普通にまた次の作品が楽しみな次第です。
自分は向井秀徳という人を知ってから、まるで他人とは思えないというほどの強烈な共感を覚え、その生き様を見届けるべく追ってきました。
その生き様、言葉をキモに叩き込み、自分も「探し」続けたいと思います。
また向井秀徳がNUMBER GIRLのラストライブで挙げられたバンドたち全てが、自己の表現での相互理解というものを目指していたと思います。
もしそれらのバンドを詳しく知らない方がいれば、その音や生き様や言葉に耳と目を傾けてみてください。きっと豊かな心と確かな勇気をもらえるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
