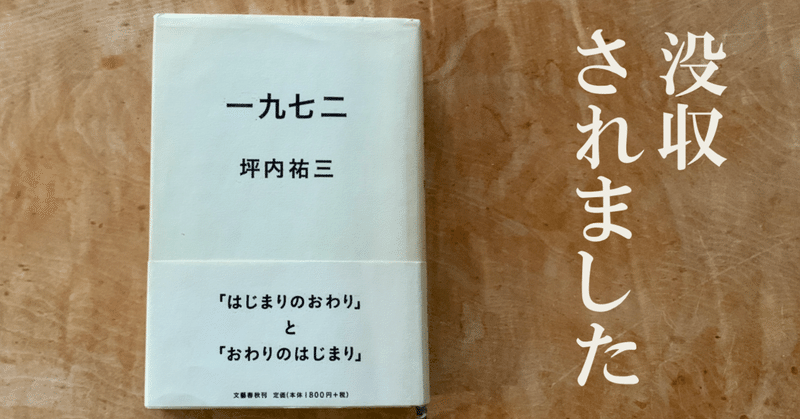
夫の仕返し、妻のはかりごと
「読まないんだったら返せよ」
夫は普段、妻の私に対してちょっと距離感のある敬語で話す。
なのに今、この高圧的かつ攻撃的な口ぶり。
これは相当、怒ってる。
私の机の横には積ん読だけを収納する無印の2段ボックスがある。ここは積ん読という呼び名の通り、本は平置きの積み上げ状態。いや、投げ入れ状態というのが正しいか。
たまに夫が私の部屋に来ると、何かしらの諍いが起きてしまう。見なくていいものを見つけるからだ。今回は夫から借りた本が見つかってしまった。ほぼ積ん読本の下敷きだ。こういう乱雑さすら嫌がる夫は、すぐに自分の本を救出した。それがサムネール写真の本『一九七二』である。
夫「人の本なんだからもっと大事に扱えよ。全然読んでないだろ」
妻「だって無理やり読めって言われた本やもん。先客優先やわ」
夫「読みたいって言ったから貸したんだよ!」
妻「そうやったっけ。オススメ理由はなに?」
夫「はあ!? それすら忘れてるの?」
8月から借りっぱなし。ゴメンゴメンと謝って、丁重にオススメポイントを聞いてみる。
そしたらけっこう面白そう。しかも夫の説明、書評みたいにうまかった。
前はもっとザックリしか言ってなかった気がするけれど。
勿体ないからここで紹介してしまおう。
自分で読んでもない本だけど、ま、いいか。今、読みたくなったから。
夫の言葉で再現、スタート。
●『一九七二』 坪内祐三
ちっちゃい頃さ、返還前の沖縄出身の南沙織が「17才」を歌ったんだよ、初紅白で。同じ日の夜に、連合赤軍事件の一人目の殺人が確認された。これは71年12月31日のことだけど、ああそうか、そういう時代だったなって。『一九七二』にはこういうことが書かれている。
オレはこの本でマルチヒストリーって考え方を知ったのね。普通、音楽は音楽史、映画は映画史、文学は文学史みたいにバラバラで考えるわけ。
でもその時代に生きた人って、映画も音楽も世の中の出来事、週刊誌の見出しとかも全部ひっくるめて1972年なり73年っていうのを記憶してるでしょ。
これはそういう本。歴史を縦軸で語るんじゃなくて、1972年って輪切りにして、その年に何が起こってどんな年だったのかって視点でまとめた本なんだよ。坪内祐三が認識する1972年っていうのは、高度成長期が終わる年。新しい時代への凄まじい変化が完了する年。1972年こそが「はじまりのおわり」で、「おわりのはじまり」。その意味するところは、読めばわかる。
妻「面白そうやん。読みたいから貸し出し延長させて」
夫「ダメ。今すぐ読まないなら二度と貸さない」
妻「大人げないな。今すぐはアカンで。とりあえず読了したい本あるから」
夫「なんだよ」
妻「火星人ゴーホーム」
夫「……それ、何年がかりで読んでんだよ!」
妻「2年くらいかな……」
私は大体、3冊くらいを同時進行で読む。
そのうちの1冊が、フレドリック・ブラウンの『火星人ゴーホーム』なのだ。地球に現れた10億体の火星人たちが、地球人に嫌がらせをして喜ぶだけの侵略系お笑いSF。
数ページ読んでひと笑いし、しばらく間をあけて他の本を読むというスタイルを死守していたら2年越しになってしまった。
でも優先的に読みたい本、実は『火星人ゴーホーム』ではないのだ。
大江健三郎の短篇全作である。とあるnoterさん(コニシ木ノ子さん)の影響で、数十年ぶりに読み返したくなった。正直に夫に言おうものなら「また後回し!?」と嘆くだろう。
しかもその翌日、また別のnoterさん(やまとたけるさん)のコメント欄で、サスペンスの名手B.S.バリンジャーの話しに触発された。ハイ。『消された時間』『赤毛の男の妻』の再読も決定。
夫は私がnoteに投稿していることは知らないし、いちいち読みたい本のことなど言わなくていい。『火星人ゴーホーム』でお茶を濁しておく方が我が家は平和なのだ。どうせ『一九七二』は没収されるんだし。
とりあえず没収本の写真は撮った。
一旦返して、来週くらいにまた借りに行こう。今度こそ読みますよ。大江健三郎とバリンジャーも読みながら。
