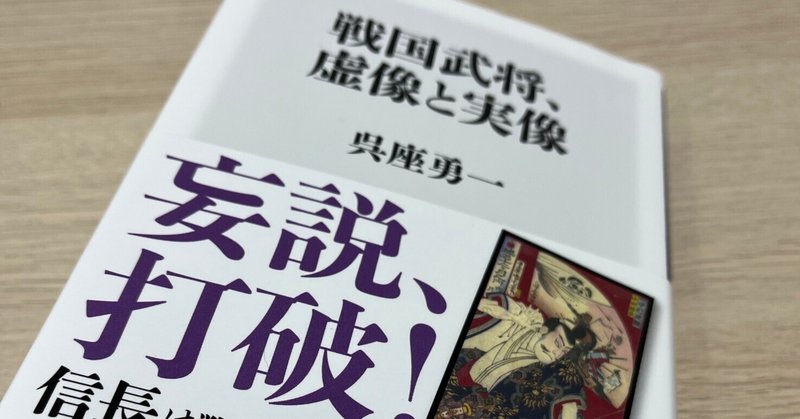
[書評]『戦国武将、虚像と実像』
戦国武将と聞けばこんなイメージを思い浮かべないだろうか。
既存の権威・常識を打ち壊す革命児・織田信長
一介の油売りから大名に上り詰めたマムシ・斎藤道三
古典的教養を備えた常識人・明智光秀
狡猾な策略を巡らす狸親父・徳川家康
空前絶後の知略を持つ人たらし・豊臣秀吉
などなど。一度はどこかで耳にしたこともあるフレーズもあるはずだ。
だがこのような戦国武将イメージは、ほとんど作家によって形作られた虚像である!といったらみなさんはどう思うだろうか?
もしかしたらそこまで言い切ってしまったら語弊を招くが、世間一般に流布する「歴史とはこういうものである」という素朴な歴史観は、往々にして人物史を核に、小説・ドラマ・映画などの文芸作品を通じて形成されてきた。
こうした「大衆的歴史観」がどのようにして形作られてきたのか?を丹念に追ったのが、歴史学者・呉座勇一さんの『戦国武将、虚像と実像』である。
例えばこの人。

油売りの商人からあれよあれよと成り上がりを果たし、しまいには美濃国(岐阜県)を治める戦国大名にまで上り詰めた「乱世の梟雄」として悪名高い武将・斎藤道三。「美濃のマムシ」なんてあだ名を耳にしたこともある人は多いだろう。
だが意外にも、道三を「マムシ」と呼ぶ資料は、同時代にも江戸時代にもみられない。なんとその初出は、昭和27年。無頼派の作家・坂口安吾の書いた『信長』が最初だ。
そして「マムシの道三」というフレーズが一般に広く知られるようになったのが、戦後歴史小説を牽引した作家・司馬遼太郎の『国盗り物語』。道三は進取の気性に富んだ改革者で、その革命気質が婿の織田信長に引き継がれていった、というストーリーラインが爆発的な好評の中で広まったことで、人々にイメージとして定着したという。おそるべし、司馬遼太郎。
だが残念なことに(?)に、道三は油売りの出身ではない。昭和33年から始まった『岐阜県史』編纂事業の中で発見された『六角承禎条書』によれば、いわゆる道三の前半生における国盗りは、道三の父・長井新左衛門尉の功績という。さらにその新左衛門尉も元は僧侶ではあるが、油売りでもないらしい。
では「道三=油売り説」はどこから出てきたのか?司馬の創作…かというとそういうわけでもない。この逸話が最初に出てくるのは、江戸中期の正徳3年(1713)。よく日本史教科書に出てくる新井白石が「正徳の治」と呼ばれる政治体制を敷いていた時代に出された『老人雑話』。ただこの本も、道三が「油売りの子」と言っているだけで、道三が油売りとは言っていない。
ところがその後、18世紀ごろ書かれた『美濃国諸旧記』に初めて「道三=油売り」の記述が出てくる。そしてこの本が、司馬を始め、近現代の道三関係の小説の下敷きになったことが、この説が人口に膾炙する契機となったらしい。

それにしても、後世の人々の歴史イメージを形作るんだから、司馬の筆力はすごいなぁ…というのもさることながら。同じ人物でも、時代の価値観や制約によって、その評価は大きく変わっていくのも興味深い(というか呉座さんの本はこれが主題)。というわけで、もう1人取り上げてみたい。

豊臣秀吉といえば、天下統一を実現した戦国武将。今も昔も人気で、明治40年(1907)に有名人約120人にとった「好きな歴史上の人物」アンケートで、秀吉は20票を獲得し堂々の1位になっている。
ところが面白いのが、その人気の「理由」は時代によって大きく異なる。まず江戸時代、幕府にとって秀吉は批判対象であった。それもそのはず、江戸幕府は「秀吉から天下を奪った家康」がつくったのだから、体制にとって秀吉の人気が高まるのは好ましくなかった。
さらに江戸時代に主流だった儒教思想の影響もある。儒教では「仁徳によって人を従わせる政治こそ王道」であり、「武力・策略で人々を抑えつける覇道」は好ましくないとされていた。
なので先述の新井白石は豊臣秀吉のことを「主家・織田家から天下を奪った不忠者」と酷評している(ちなみに同じ理由で、足利将軍家を利用して天下を握った信長に対しても、白石は辛口評価だ)。

といってもこの理屈をつきつめると「豊臣家から天下を奪った徳川家」も不忠者になる。なのでさらに秀吉を批判する材料となったのが、朝鮮出兵である。
「武力による覇道」を嫌う儒学者からすれば、とうぜん朝鮮出兵は愚行の極み(また儒教は中国より影響を受けているので、明侵略を狙った出兵は言語道断でもある)。徹底的に批判された。
ところが、そんな低評価の秀吉を大きく顕彰したのが、江戸後期の思想家・頼山陽である。日本史受験者以外は聞き馴染みのない名前だろうが、彼が記した歴史書『日本外史』は空前のベストセラーとなり、幕末~明治にもっとも読まれた歴史書となった。幕末には尊皇攘夷志士たちのバイブルともなり、明治以降の歴史観に多大な影響をもたらすことになった(ちなみに本書でも触れられているが、江戸中期までは物語の脇役に過ぎなかった信長を絶賛して主役級に持ち上げた最初の本も、この『日本外史』だ)。

どうして山陽がそこまで秀吉を持ち上げたのかといえば、一言で言うと「秀吉が勤王家だった」と捉えたから。朝鮮出兵時の明との和平交渉の中で、秀吉は、明が自らを「日本国王」に任命すると言う内容の国書に激怒する。なぜなら「日本には天皇がいるのに、それを無視して国王とは何事だ!!」と。多分に山陽の創作も混じっているのだが、以降「秀吉=勤王家」というイメージはさらに広がり、幕末~明治期に秀吉を絶賛するムードが形成されたという。
そして明治維新がその傾向に拍車をかける。明治政府は「攘夷・尊皇・立身出世」という政治理念の体現者として、秀吉をさらに称賛した。江戸時代に荒廃していた豊国社(秀吉を祀る)を再興して、豊国神社を造営したのもちょうどこの頃。
その後、日清戦争・日露戦争と日本の対外進出が本格化するにつれて、「海外進出の先駆け」とも言うべき秀吉人気はさらに高まった。欧米列強がこぞって植民地競争に奔走する帝国主義の時代において、「侵略=悪」とは見なされていなかったという時代背景は押さえておかねばならない。
だが「立身出世・勤王・海外雄飛」の3点セットで秀吉を評価する世評は、日本の敗戦を機に180度変わった。日中戦争~太平洋戦争期は「日本の大陸進出の嚆矢」という肯定的評価だった朝鮮出兵も、戦後には「軍国主義の開祖」と否定的評価に変わる。
結果残った秀吉像は、江戸時代以来様々な講談や芝居で描かれ続けた「人たらし」という評価だ。「天性の才覚で人々を魅了し、仲間を増やす」という秀吉の姿は、長い歴史の中で削がれ続けた秀吉像の結果なんだとか。
ただ残念なことに、著者の呉座さん曰く、秀吉の「人たらし」エピソードのほとんどは後世の創作で、本当に秀吉が人間的魅力にあふれる人物だったかどうかはわからないとのこと。これほどの有名人でも、その実態を掴むのは難儀なことだという、これまた教訓かもしれない。
このように、現在私たちがもつ戦国武将のイメージは、往々にして後世の歴史家や作家が膨らませた想像・創造の上に成り立っているみたいだ。ここでは書ききれなかったが、本書を読むと、明治期の思想家・徳富蘇峰の『近世日本国民史』の影響も絶大だ(頼山陽が持ち上げた信長像をさらに進めて「革命児・信長」のイメージを作ったのも、何を隠そうこの徳富蘇峰)。

とはいえ、こうした大衆的歴史観が醸成される素地には、その時代ごとに「重んじられてきた価値観」がある。もちろん呉座さんも指摘するように、「この時代はこう言う価値観だからこう言う人物像が誕生」と言えるほど単純ではない。だがあえてデフォルメしてみると、
江戸時代:徳川家中心史観・儒教的価値観
幕末:尊皇攘夷
明治~昭和前期:忠君愛国思想・帝国主義・立身出世
戦後:平和主義・経済重視
こういう価値観がベースにあると思われる。そしてこうした価値観を知れば、自ずと自分が持っている「無意識のバイアス」に気づくきっかけになる。この本の終章を呉座さんはこのように締めくくっている。
専門的なトレーニングを受けた歴史学者であっても、その時代、その社会の価値観から自由ではない。どんな人であれ、客観中立公正に歴史を評価することは不可能である。大事なことは、自身の先入観や偏りを自覚することである。
ぜひ自らの歴史観を紐解く第一歩に、本書を読んでみてはいかがだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
