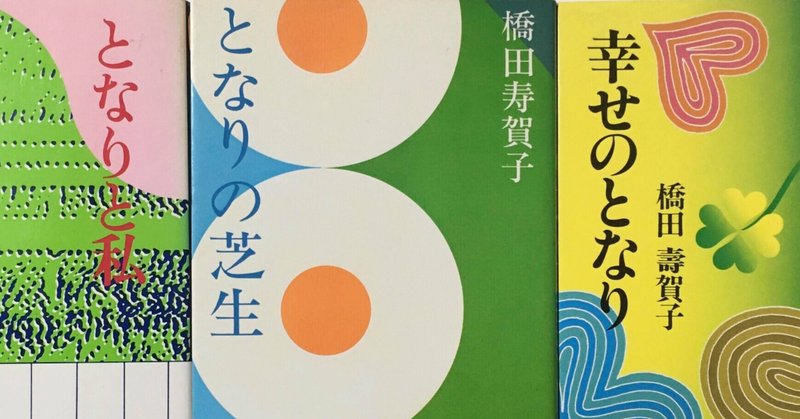
脚本家・橋田壽賀子『となりの芝生』を読む|戦後の住まいと家族の物語
『おしん』『渡る世間は鬼ばかり』といった大ヒット作を数多く手がけた脚本家・橋田壽賀子さんが今月4日に亡くなられたとのこと。ご冥福をお祈りします。
戦後の家づくりに関心をもつ身としては、橋田壽賀子といえばNHK銀河テレビ小説『となりの芝生』(1976年)が真っ先に思い浮かびます。夢のマイホームを手にしたのも束の間、夫方の母親が同居することになり巻き起こるドタバタ劇。前田吟・山本陽子が高平夫妻役。姑役には沢村貞子というキャスティングのもと、嫁姑トラブルあるある満載なドラマとあって高い視聴率を獲得しました。
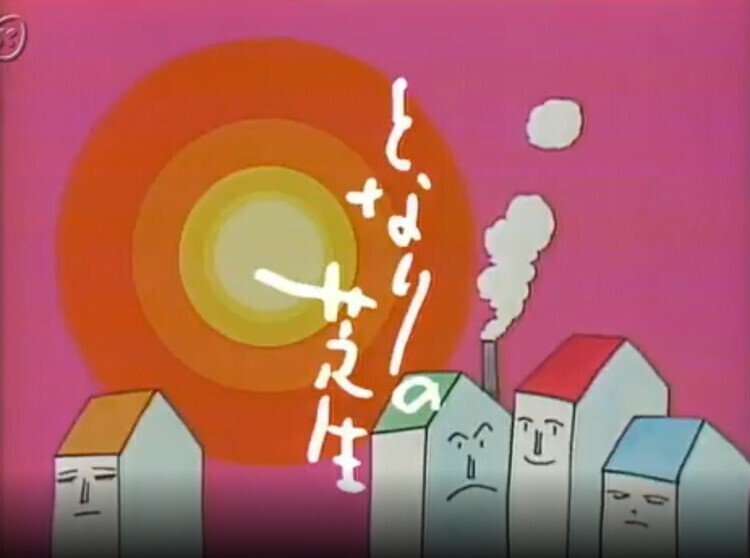
さらに姉妹作『となりと私』(1977年)は小住宅地の近隣トラブルを描き、次いで『幸せのとなり』(1979年)では相続問題、会社倒産など、その時代時代で社会問題化しつつあった問題を、庶民の目線から鋭く描き出しました。

「となり三部作」と後に呼ばれるこれらドラマ群は、昭和50年代の住文化を探る資料としても貴重なものです。
『となりの芝生』とニセ持ち家層
ところで、嫁姑問題を描いたドラマとして注目された『となりの芝生』ですが、橋田壽賀子の「私の履歴書」を書籍化した『人生ムダなことはひとつもなかった』(大和書房、2019年)によると、義母けいとの関係が着想のもとになったのだそう。
わたしが結婚し、お姑さんや小姑の義妹たちができたおかげで「ドラマは家庭の中にある」ということが身に染みてわかった。姑は嫁のどんなところが気になるのか。嫁は姑や小姑のどんな言葉や態度に傷つくのかということも理解できるようになった。『となりの芝生』のセリフにも私の実体験が少しばかり投影されている。(pp.102-103)
『となりの芝生』の物語展開にリアルさを添える嫁姑問題ですが、このドラマで橋田さんが書きたかったことは、もう少し別のところにあったようです。
『となりの芝生』で私が本当に書きたかったのは、背伸びして家を建てたばかりにバラバラになっていく家庭の悲劇だったが、いざ放送されると視聴者の目は嫁姑問題に向いた。(pp.98-99)
ナルホド。「背伸びして家を建てた」ことからおきる家族崩壊。西山夘三の言葉を借りれば「ニセ持ち家層」(朝日ジャーナル、1983.12.9)が自民党の持ち家政策に踊らされたがゆえにおこる疎外を描いたのだと。
「土地は大分前に買ってあったからね。そっちのローンのメドがついたから思い切って建てたんだ。……お次はこの家のローンて訳だ」「どうしても自分の家が欲しかったんだ」と同僚に語る高平要。同期の勝田は妻・知子にこう言います。「奥さん、高平がこんなに立派な家を建てることができたのも、ひとえに奥さんの内助の賜物です」と(橋田壽賀子『となりの芝生』pp.16-17)。
住宅ローンの返済に四苦八苦する高平一家。後に夫・高平要の浮気問題を招来させてしまう妻・高平知子の就職は、一軒家で姑と過ごす息苦しさから逃れるためだけでなく、住宅ローンの返済が家計のゆとりをまったくなくしてしまったことへの対応策としても選択されたものでした。
また、もう一つに要因に、長男・太郎の学力問題もあります。新築・引越・転校、さらには姑との同居と波乱がつづいた太郎は、すっかり意欲喪失して学校では「おちこぼれ組」に属することに。マイホームの役割が、子供の教育=優良企業への就職をバックアップすることであり、その役割を主婦=教育ママたる妻が担うという構図が、その背景にはあります。要はこう言います。
「……太郎は長男で、俺の子なんだ(中略)。母親であるお前が、しっかり教育してくれなきゃ困る……太郎を落伍者にするなんて、母親失格だぞ」
(橋田壽賀子『となりの芝生』pp.114-115)
視聴者の注目を集めた嫁姑問題は、持ち家取得がもたらす疎外を描くための一小道具であってメインテーマではなかったということ。実際、1960年代半ばごろから「住宅ローン」の大衆化が進むも、土地価格高騰のなかのマイホーム取得が至難を極めました。しかも『となりの芝生』が放映される前にはオイルショックが襲来。マイホームは「家族」をバラバラにする危険ととなりあわせでもあったのです。
街を歩くと、やたら質屋の看板が目につくようになり、知子は苦い思いを飲み下した。
家計のやりくりで頭が一杯なのだ。
家のローンの為の預金を赤字にする訳にはゆかず、月給日まで、綱渡りをしなければならない。
今まで暢気に暮らして来た自分は、なんという箱入り女房だったろうと思う。
(中略)
知子にはもうなんの張り合いもなかった。
家を建てることだけを楽しみに、欲しいものも我慢し、苦労も苦労と思わないできた。
道は険しくとも、家という目標があった。
(橋田壽賀子『となりの芝生』p.97)
「家を建てる」という目標、楽しみを実現してしまった知子にとって、「教育ママ」として担う役割の失敗は、おのれの無力さを突きつけられる現実であったでしょうし、また、その失敗の過程に、想定外の姑との同居があったことが、余計に気持ちを沈ませたことでしょう。
『となりの芝生』と『泣いてたまるか』
ドラマ『となりの芝生』の10年前に、同じく橋田壽賀子が脚本と担当したは『泣いてたまるか』第25話「お家が欲しいの」(1966年12月18日放送)が放送されました。この話は渥美清・長谷川裕見子演じる木下栄作・秀子、そして子ども3人の一家が、いまとなっては狭くなった公団住宅から、郊外の庭付き一戸建て住宅を獲得するまでのドタバタ劇を描いたものです。
このドラマについては以前、noteにも書きました。

『となりの芝生』のテーマが「背伸びして家を建てたばかりにバラバラになっていく家族の悲劇」だとすると、「お家が欲しいの」で描かれる話は、公団住宅脱出の願いと住宅ローンの普及が重なり「背伸びして家を建てようと計画・実行してしまう家族のドタバタ劇」だったわけで、渥美清・長谷川裕見子演じる木下一家のその後が、前田吟・山本陽子演じる高平一家ともいえます。
そう思うと、すでに木下一家の住宅資金計画には、破綻の予感が込められていました。
秀子「月収税込72,300円、ボーナス二期税込328,600円、概算して年収100万ちょっと越えるわけね、三倍までだから、300万は融資してもらえるわ。300万あれば、ま、なんとかここよりはましな家が…」
栄作「300万、300万って、ホントにそんなに借りられるのか」
秀子「ええ、年収の三倍まで大丈夫」
栄作「し、しかし、どうやって返すんだ、そんな大金」
秀子「15年間に分割して返済すればいいのよ。月にしたら大したことないわよ」
栄作「いくらくらいになるんだ?払いきれるのか?」
秀子「ここの家賃だっていらなくなるから、そっちへまわせるし。ま、任しておきなさいよ。これは財布を預かってる女房の仕事よ」
まだ「住宅ローン」という仕組みが大衆化していなかった当時(この第25話が放映された1966年に日本不動産銀行が住宅ローンのサービスをスタートさせます)、最新トレンドとしての「住宅ローン」情報を仕入れてきた秀子の言葉を栄作は信じられません。
秀子がすらすらとそらんじてみせる返済計画。毎月返済額4万円に栄作はうろたえます。
秀子「全部で4万円くらいじゃないかな」
栄作「4万円って、秀子、お前一体オレの月給いくらだと思っているんだ」
秀子「手取り68,500円」
栄作「そのうちから4万円も払ったら一体いくら残るんだ!」
秀子「28,500円」
栄作「ばっ、ばかっ。それで一家5人が暮らせるとでも思ってるのか!」
秀子「ボーナスが二期で30万円あるわ。月にならせば2万ずつ、5万円もあればやっていけるわよ。せいぜい十年も我慢すれば返済金も楽になるし(※元利償還のため)、茂雄が大学に行く頃には学資くらい出せるようになりますよ」
栄作「そんな綱渡りみたいなことして。そんなことまでして家がほしいのか!」
秀子「ほしい。これからも私も遣り繰り上手くやるわ。うんと節約する。だから、あなたも協力してね。お小遣いも今までみたいにはあげられないけど。がまんして。タバコもやめてくださると助かるんだけどなぁ」
それでも尻込みする栄作に秀子は衝撃の説教を繰り出しますが、それは過去noteに託します。木下秀子のスキのない資金計画は、たぶん高平要・知子のそれと同様だったことでしょう。でも、スキのない資金計画だからこそ、まさかの姑同居が隠されていたリスクを浮き彫りにしたのでした。
「これからも私も遣り繰り上手くやるわ。うんと節約する。だから、あなたも協力してね」という木下秀子の言葉は、高平要の「家のローンを払っても、充分やっていける約束だったぞ。今更泣き言を言うなんて、恥ずかしいと思わないのか」という言葉を思い出させます。
二世帯同居のうつりかわり
『となりの芝生』に登場する姑・高平志乃は、長男・透が暮らす社宅に同居していましたが、そこでもやはり嫁姑問題がふつふつとわきおこり、志乃にとっても居心地が悪い。そんなところに、次男・要が夢のマイホームを持ったという朗報が。「ねえ知子さん、なかなか三十五、六で家を建てられる旦那さまなんて、そういないわよ」と我が息子をベタ褒めします。そんな志乃を大いに勘違いさせるのが、要の一言。
要の案内で、旅装も解かぬうちに、志乃は家の中を見て歩いた。
志乃の喜びが頂点に達したのは、二階の和室へ案内された時であった。
「さあ、ここが母さんの部屋だからね」
要が志乃のスーツケースを片隅に置いた。
「まあ、ここが私の部屋なの?」
「ああ、いい部屋だろう?」
「……私の為に、こんな部屋まで。……わりがとう、……ありがとうよ」
(橋田壽賀子『となりの芝生』p.26)
もともとは夫婦・子ども二人という核家族のための住まいだったはずが、二階の客間を「母さんの部屋」と口走ったことで、まさかの二世帯同居へと展開してしまいます。
『となりの芝生』放送の前年、1975年には旭化成ホームズ「ヘーベルハウス」が日本ではじめて「二世帯住宅」をコンセプトにした商品住宅「Wシリーズ」を販売します。1972年に住宅事業を立ち上げて以降、数件の物件で「玄関が2つある家」がみられたことから、プラン分析を開始。結果、これまで単世帯を想定することが当然だったのに対して「親子で住む」スタイルが増加していることに気づいたのでした。
余談ですが「二世帯同居」が増加するなか、その動きをいちはやく察知した旭化成ホームズの「Wシリーズ」は販売が振るわなかったそう。「二世帯住宅」の需要はあっても、新規の概念であるそれが住宅購入者の購買意欲を刺激するためには、また時間が必要だったのでしょう。
もうすこし、旭化成ホームズの動向に沿って「二世帯同居」を追ってみましょう。1970年代から80年代にかけては「土地取得が困難で二世帯住宅にせあざるを得ない時代」。地価高騰に伴う背に腹は替えられない「二世帯同居」が展開しました。1980年には旭化成ホームズは「二世帯住宅研究所」を設立します。
ところが、1990年代に入ると地価が抑制され、単世帯での住宅取得のハードルが下がり「二世帯同居」は低迷することに。再び「二世帯同居」が盛り返すのは2008年頃といわれます。つまりはリーマン・ショックを受けての変化でしょう。
共働きが増えて保育園に入れない待機児童が増加していることや、高齢者はなるべく在宅で介護サービスを受けつつ自立して生活を送っていくという世の中の動き。これらはたびたびニュースで取り上げられている話題ですが、こうした社会情勢を受けて、二世帯同居での暮らしが注目されています。
(『ヘーベルハウスの二世帯百科』p.3)
共働きが一般化したことから、住宅取得と子育てへの親世代の動員が必要になったということ。それに伴う「同居志向」の復活なのでした。1960年代までの「大家族社会」では【べったり同居】が一般的であったものが、1970~80年代の核家族社会を通過した後に、1990年代からの少子高齢化社会になって【融合志向】の同居が注目されているのだと指摘しています。
ふたたび「二世帯同居」が注目されはじめた。そんな2009年にあの『となりの芝生』がリメイクされます※。TBS日曜劇場「橋田壽賀子ドラマ・となりの芝生』(2009年)。高平夫妻役には大倉孝二・瀬戸朝香。姑役には泉ピン子がキャスティング。やばいなこの二人の「笑顔」。

時代の変化に即応して橋田壽賀子が召喚される。とはいえ33年後のリメイクです。内容が陳腐化してはいなかったのか。あたらしいキャスト・スタッフによって生まれ変わったドラマを見た橋田壽賀子は、こうインタビューに答えています。
全く違うドラマを見ている気がしました。
知子を演じる瀬戸さんも山本陽子さんとは全然違いました。瀬戸さんは、すごく爽やかですね。山本さんは耐えている感じでしたが、瀬戸さんはカラっとしていて、面白いですね。
志乃も全く違います。沢村貞子さんの方がイジワルだったかな。棘があるんですよ。「私が一番偉いのよ」って顔していましたね。ピン子さんは、一生懸命自分の意見を言っている感じ。普通に言っていることが意地悪いというか、正論を言っているのが怖いところがいいなと、私は思いました。
要も前田吟さんと大倉さんでは全然違う。前田吟ちゃんのときは関白亭主的なところがありましたけど、大倉さんのほうが現代的になっていますね。大倉さんは、気が小さいというか、線の細い、可哀想なご亭主って感じがします(笑)。
セリフは33年前と変えてないのに、俳優さんでキャラクターがこんなにも違うものかと思いました。
(ドラマ『となりの芝生』番組HP「インタビューvo.4」)
さして設定も台詞すらも変えない橋田イズムが徹底されながら、役者の持ち味や演じ方が違うことで、ちゃんとそれぞれの時代にピッタリと沿い、しかも視聴者の共感を得られるというのは、橋田脚本おそるべし。それと同時に、33年の歳月を経てもなお共感される二世帯同居の諸課題や、住宅取得に伴う困難も、なんら陳腐化していない。むしろ「ニセ持ち家層」はぶあつい幅を形成しているのではなかろうか。これまたおそるべし。
『となりの芝生』は、最後にあわや離婚かという危機に直面しつつも、なんとか持ちこたえます。夫・要、妻・知子、長女・花子、長男・太郎、そして姑・志乃。すったもんだの挙句、それぞれの立ち位置と距離感をつかむことができました。「新しい家で、新しい生活を築くことが新しい知子の目標」になったのです。「平凡な家庭を大事に」と誓って。
あとがきに、橋田壽賀子はこう記しています。
日本の狂った、貧困な住宅政策のしわよせをもろに受けながら、それでも夢を捨てずに無理をしてやっと建てたマイホーム。が、家を建てたばかりに起こるさまざまな問題や、日常のなかのトラブルや事件を通して、家族とは……、親子とは……、夫婦とはなにかを考え直し、ともすれば現実に押しひしがれそうになりながらも、懸命に生きようとする庶民の哀歌を私なりに描いてみたのがこのドラマである。
(橋田壽賀子『となりの芝生』p.305)
あらためて偉大な才能が天に召されたことに合掌いたします。
(おわり)
注
ドラマ『となりの芝生』は橋田壽賀子脚本のもと「NHK銀河テレビ小説」枠で1976年に放送された後に、TBSの「花王愛の劇場」枠で『ああわが家』(1989年)というタイトルでも制作されています。ただし、タイトルが異なるほか、橋田壽賀子は原作にとどまり、脚本は石井君子が担当しています。また、住宅取得の経緯も公団住宅の抽選に何度も外れていたのに、たまたま建売住宅の抽選に当たってしまい…というもので「手狭な公団住宅からの脱出」や「取得済の土地に注文住宅で家を建てる」といった設定がなくなってしまっています。橋田がふたたび自ら脚本を担当したことから、当時は「不朽の名作が33年ぶりに完全復活…甦る嫁姑対決」と謳われたそうです。
参考文献
橋田壽賀子『となりの芝生』、日本放送出版協会、1976年
橋田壽賀子『となりと私』、日本放送出版協会、1977年
橋田壽賀子『幸せのとなり』、日本放送出版協会、1979年
橋田壽賀子『人生ムダなことはひとつもなかった。私の履歴書』、大和書房、2019年
『泣いてたまるか』シナリオ復刻委員会『渥美清の泣いてたまるか:シナリオ集2』、サンマーク出版、2005年
毎日新聞社編『親と子の同居:嫁姑』、毎日新聞社、1977年
旭化成ホームズ『ヘーベルハウスの二世帯百科』、旭化成ホームズ、2010年
松本吉彦『二世帯住宅という選択:実例に見る同居の家族』、平凡社、2013年
サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。
