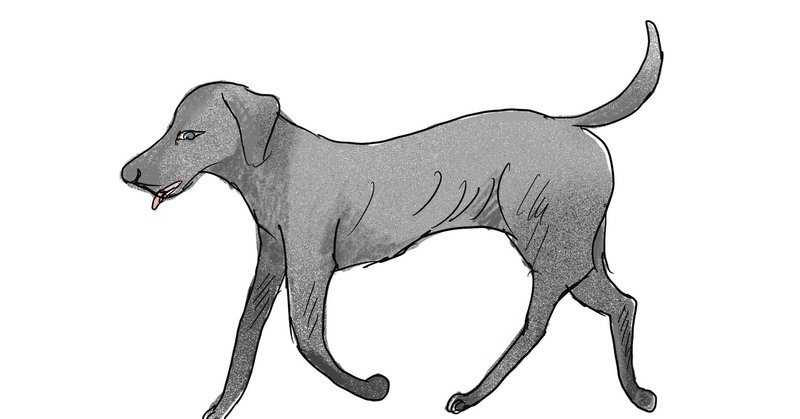
自分の選択、魂の返事を信じるんだ。なにがどうなるかなんて、分からないんだから。 「さとりをひらいた犬/ほんとうの自分に出会う物語」無料公開/第10話
主人に仕える勇敢な猟犬・ジョンが主人や仲間から離れ、「ほんとうの自分」「ほんとうの自由」を探しに、伝説の聖地・ハイランドを目指す物語。旅の途中、多くの冒険、いくつもの困難を乗り越えながら、仲間や師との出会いを通じて、聖地・ハイランドに導かれていく。そして、ついにハイランドへの到達を果たすことになるのだが、そこでジョンが見た景色とは…。
【第10話】
第3章:ベレン山
コウザとアンガスの元を出発して約二日、北へ向かって歩き続けた。
お腹がすいたらイモを掘ったり、木の根っこをかじったり、落ちている木の実を食べてお腹を満たした。いのちの循環とはいえ、なるべく狩りはしたくないと思った。
落ちていた木の実カリカリとかじってしばらく、そう、二時間ほども歩いたころだっただろうか、周囲に複数の気配を感じ取った。
また、イノシシか? ついてきたんだろうか?
僕は気配に気づいたことを悟られないように、歩きながら周囲への感度を高めた。
一…二…全部で四つ。後ろからついてきている…
そのまま、また二時間ほど歩き続けると、その気配に「殺気」がないことに気づいた。僕はいざとなったら安全に脱出できる場所を見はからって立ち止まり、振り返った。
「何か用かい?」
話しかけられた気配たちは、しばらく草むらに潜んでいたけれど、僕が動きそうもないことを悟ったのだろうか、一つが草むらから出てきた。
それは、僕と同じ犬だった。その犬は言った。
「お前、どこへ行くつもりだ」
「君こそ、何で後をつけてくるんだ」
「ふん、お前の行き先にちょっと興味があってな」
その犬が答えると、隠れていた気配たちも次々に草むらから姿を現した。全員で四匹の犬だった。その目つきや立ち振る舞いから、僕と同じ猟犬のようだ。でも、犬たちはやせこけて、毛のつやもなく、人間たちから離れてずいぶん時間がたっているようだった。
「君たち、猟犬か?」
「ふん、『元』猟犬、と言ったところだな」
「元?」
「お前…“鷹の羽”のところのジョンだな」
「僕を知っているのか?」
「まあな…」その犬はクフフと含み笑いをした。
僕のご主人様の帽子に大きな鷹の羽がついていたので、僕たちは“鷹の羽”と呼ばれていた。
「そういう君は、誰だ?」
「俺はマフィー。こいつらは右からジンガ、フート、アイカだ。みんな俺の仲間だ」
「どうして僕のことを知っているんだ」
マフィーはうっすらと笑った。
「眉間の三日月、ちぎれた尻尾、抜け目ない目つき、俺たちの間ではお前は有名なんだよ。俺たちは一年前まで“赤鞍”のところにいたんだ。お前は覚えていないだろうが、一緒に狩りをしたことだってあるんだぜ」
“赤鞍”とはご主人様の狩り仲間で、真っ赤な鞍に乗っていることでつけられたあだ名だった。いままでに数回、一緒に狩りをしたことがあった。ちょうど一年前はガルドスを討ち取った頃だっただろうか。
「お前のような人間さまにバカ忠実で単純なヤツが、どうして一人ぼっちでこんなところにいるか、それに興味があるのさ」
マフィーはそう言うと、後ろの仲間たちを振り向き、ニヤリと笑った。三匹もマフィーに合わせてニヤリと笑った。
「僕は、ベレン山に行く」
犬たちはさも面白そうに顔を見合わせ、クックと笑い始めた。
「何がおかしい」
「お前さん、ダルシャに会ったのかい?」フートと呼ばれた犬が言った。
「そうだ」
「お前さんもだまされたんだな~…かわいそうに~…」アイカがバカにしたように言った。
「何だと!?」
一人だけ真顔だったジンガが言った。
「ベレン山、あそこへ行って戻ってきたものはいない」
マフィーが真顔で言った。
「ジョン、お前も、だまされたんだよ」
「どういうことだ?」
「べレン山、あそこにいるのは誰だと思う?」
「知らない。誰なんだ?」
「ジョン、お前は『赤い魔獣』の伝説を知っているよな」
『赤い魔獣』とは七年ほど前、ベレン山から北の谷、ジョンの住む森から西の森まで、動物はおろか人間たちさえも恐怖に陥れた巨大な大熊のことだった。多くの人間たちが協力して殺そうとしたけれど、逆に大きな被害を出し、結局断念したということを先輩の犬たちから聞いていた。
ご主人様も狩りに参加し、僕の先輩の猟犬たち七匹のうち五匹が無残に殺されたとのことだった。
「ベレン山、あそこにいるのは『赤い魔獣』だ。ダルシャは『赤い魔獣』の手先で、お前みたいな頭の悪いヤツをだまして山に誘い込み、『赤い魔獣』のえさにしていたのさ」
えっ?
そんなばかな。
「どこにそんな証拠があるんだ」
マフィーは自信たっぷりに答えた。
「証拠か、それは俺たちさ。俺たちもダルシャに会った。一年ほど前のことだ」
僕はマフィーをじっと見つめた。マフィーの目は嘘を言っていなかった。
「『赤鞍』は俺たちを手ひどく扱っていたんだ。だから、俺たちはダルシャの話を聞いて本当に行きたいと思った。自由ってやつが欲しかったんだ。ガルドスがお前たちに倒された後だったから、谷を抜けるのは大変だった。そして、命がけで北の谷を抜け、ここまで来たんだ。その時、俺たちは八匹の集団だった」
マフィーは少し遠くを見つめ、そして再び僕を見て重い口調で続けた。
「ベレン山に入った俺たちを待っていたもの…それは“恐怖”だった」
「 “恐怖”?」
「そうだ“恐怖”だ。俺たちも人間たちとの狩りである程度の経験はしてきたつもりだ。チームで連携して動くことも出来るし、ひとりひとりだってそれなりだ。しかし、後にも先にもあんな恐ろしい思いをしたことはない。気づくと俺たちは四匹になっていた」
「他の四匹はどうなったんだ?」
「翌日の朝、俺たちも心配になってその場に戻った。そこは地面に血がしみ込んで真っ赤になってた。他になにも残ってなかった。みんな、ヤツに食われちまったんだ」
僕は何も言えずにマフィーを見つめた。
「ジョン、お前、ガジョを知っているよな」
「ああ、知っている」
ガジョは赤倉の猟犬たちのリーダーだった。そして、完璧なリーダー、そういう存在だった。僕はガジョのりりしい姿を思い出した。強靭な身体、常に冷静で的確、そして勇敢。仲間のために働き、全力の努力を惜しまない。
完璧だった。
ガジョは僕たち猟犬仲間たちの中でも、常に尊敬を集め、多くの犬たちの目標とされる存在だった。
「ガジョは、あのとき死んだ」
「あのガジョが…死んだのか?」
僕はにわかには信じられなかった。あの…ガジョが?…
「そうだ。あのガジョですら抜けられなかったあそこを、お前が抜けられるはずがない。しかもお前はひとりぼっちだ。お前のこの先に待つものは“恐怖”そして“死”だ」
“恐怖”と“死”…
「悪いことは言わない。ベレン山に行くのはやめておけ。ここから引き返せ。鷹の羽のところに戻れ。俺たちみたいな野犬になってもいいのか? 俺たちは戻りたくても、もう戻れないんだ」
マフィーの言葉はウソではなさそうだ。確かに、このまま進めば『赤い魔獣』に殺されるかもしれない。しかし、ベレン山に行かないと、その先へは進めない…ハイランドへは行けないんだ。
どうする…?
どうする?
ゆっくりと目をつぶった。
そう、迷ったときは『魂の声』を聴く…
僕は自分の胸の深くに問いかけた。
どうする?
どうしたい?
僕が目をつぶって黙ってしまったので、マフィーたちも黙って僕を見つめた。
このまま進む?
それとも引き返す?
どっちが君の答え?
そう、引き返すという選択をすれば、命は永らえることが出来るだろう。でも、それが本当に僕の行きたかった場所なんだろうか? それが僕らしい生き方なんだろうか? それが、ほんとうの僕なんだろうか?
すると、言葉にならない答えが返ってきた。それは、あたたかな太陽の光みたいな返事だった。僕はそれが『このまま進むんだよ』と言ってように感じた。
そうだ。
確かにマフィーの言うように『赤い魔獣』に殺される可能性だってある。でも、それはそれで僕が選択した道なんだ。自分の選択、魂の返事を信じるんだ。なにがどうなるかなんて、分からないんだから。
「マフィー、ありがとう、でもやっぱり、僕は行くよ」
マフィーはびっくりして目を丸くした。
「行くのか?」
他の犬たちも口々に言った。
「やめとけ、バカなことはするな!殺されるぞ!」
「死ぬぞ」
「食われるぞ!」
「みんなには感謝する。ありがとう。でも僕は行くよ。たとえ殺されても、僕はそれでもいい」
唖然としている犬たちを背にして、僕は歩き始めた。
「戻ってこい、ジョン! 戻って俺たちの仲間になってくれ!」
マフィーの叫び声が後ろから聞こえた。僕は心の中でマフィーたちに感謝しながらも、振り向かずにベレン山に向かった。
第11話へ続く。
僕の肺癌ステージ4からの生還体験記も、よろしければ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
