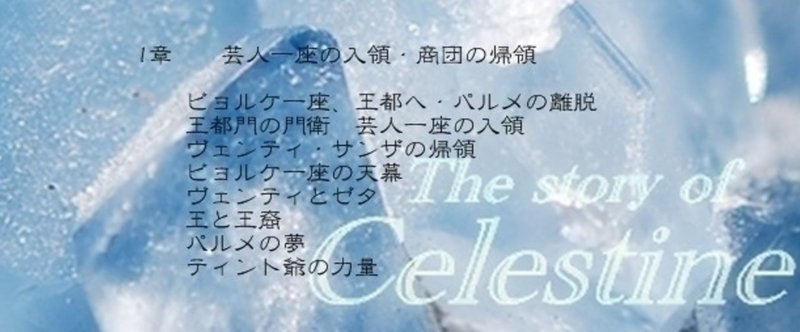
セレスタイン物語 1
1章 芸人一座の入領・商団の帰領
* ビョルケ一座、王都へ・パルメの離脱 *
王都領門の手前、馬車駐まりの広場の片隅である。
「……というわけだから。とにかく、ここで別れるから。わかった? セレス」
と、パルメは言った。
旅芸人の一座は輪になってパルメとセレスと、座頭ビョルケを囲んでいる。
曲乗りのムントン、棍棒使いのジジ、剣術舞のアガプ。
鳥使いのヘクタス、道化のボンスン、踊り子のソフィ。
それぞれの弟子達、大道具小道具の職人、動物の飼育係、それと用心棒代わりの武術の達人。
総勢五十人近いビョルケ一座である。
パルメが座を抜けると聞かされて座頭ビョルケは渋い顔だ。
「そうは言ってもなあ、パルメや。お前さんがここで座を離れたら、セレスが寂しい思いをするじゃろうが」
「ふん」
パルメはセレスの顔をちらと見てから、突き放すように鼻で笑った。
「寂しくなんてないわよ。あたしと違ってセレスは芸ができるから、一座のなかでじゅうぶん、やっていけるでしょ」
何人かが、納得したように頷いた。
セレスは綱渡り組の有望株だが、パルメの場合はまるっきり無芸で、座向きじゃない。芸も裏方仕事も、旅暮らしも嫌いだからだ。と、誰もが思っているし、事実、そうだった。
パルメや、と、ビョルケ座頭は軽くため息をついた。
「お前さんとセレスが本当の姉弟じゃないんだってことは、まあ、わかった。わかりはしたが、セレスはお前さんが連れてきた子だ。セレスの素性についてお前さんはほとんど知らない、だからセレスの家族を探せないと言うが、わしらだとて、お前さん以上にセレスの家族のことを知ってるわけじゃない」
「そりゃそうだけど」
「座を離れて自分の家に帰るというなら、それはもちろん止めやせんが。お前さんとセレスが五年前に暮らしていた村の誰かしらが、セレスの家族のことを知ってるんじゃないのかね。それを確かめてから座を離れても遅くはないじゃろう、どうかね」
「だから何度も言ったでしょ?」
パルメはいらついた声で言って腕組みする。
「あたしはね、もうこりごりなの。いつまでもこんな旅暮らし、やってらんない。野宿したり馬と一緒に寝たり、どんなに働いてもたいして儲からないし、うんざりなんだよ。いいかげん、自分のために生きて、独りで自由に暮らしたいの。寝るのも起きるのも食べるのも自分のやりたいようにしたいの!」
パルメが座の暮らしの中で、好きなように寝て起きて食べていたのを、一座の全員が知っている。今以上に『やりたいようにしたい』となると、それはかなり難しいのではないか。なので、皆、難しい顔になった。
だが、押し問答を続けても、いいことは何もない。パルメの決心は固いのだ。それはセレスが一番よく知っている。
セレスは一歩前に出て、押し黙っている座員の皆を見回した。
「パルメ、わかったよ。町暮らし、したがっていたものね。僕は座のみんなと一緒に行くことにするよ」
パルメが一瞬で笑顔になり、ちょっと大げさに頷いて、セレスの肩に手を載せた。
「セレス……あんたっていい子ね」
そう言ってぎゅっとセレスを抱きしめたが、すぐにぽんと突き放してくる。
「で、どうなの? あんたは座に入る前に暮らしてた村のこととか、これから調べるつもりがある? そうならあたしにわかる程度のことは教えるけど」
「ううん、いい。村の名前は覚えてるから、自分で調べるよ」
「そうよね、それがまあ、賢いかもね」
「僕は僕でやっていく。パルメは望み通りの暮らしをしたらいい」
セレスや、そうは言うがと、座頭が言いかけたとき、馬車の向こうから、領門を守る門兵が近づいてきた。
「そこに集まっているのはビョルケの一座か?」
「へい、さようでございます」
ビョルケ座頭は振り返って手を振った。
「門を通過する手続きをするなら、急いでくれ、座頭。このあと、大きな商団が王都へ戻るために近くまで来ていると報せがあった。商団の通過は手間も時間もかかる。商団の到着前に入領してもらいたい」
「王都の商団様でございますか」
「そうだ」
「承知いたしました、すぐに参ります」
商団の通過を待って入領となると、夜になってしまう。大きな商団ともなると数百人規模であり、人数の確認だけでなく、ものによっては荷の改めもするからだ。
「そういうことなら急がにゃならん。商団の前に門を通ろう。それじゃパルメ、すまんがここでお前さんの名前は名簿から消すよ。ソフィ、金庫から今月ぶんの銀貨一袋を出してパルメにやっておくれ。それとボンスン、座名簿を持って一緒に来てくれ。すぐに手続きにいく」
道化の練達ボンスンは座名簿の入った鞄を持って、ビョルケ座頭と一緒に門衛詰所へと歩いて行った。
パルメは今月ぶんの賃金を受け取るためにソフィについていき、もうセレスのほうを振り返ったりはしない。素っ気ない態度に、ちょっと寂しい思いのするセレスだった。
「むしろ、これでよかったんじゃないか、セレス」
曲乗りのムントンが、セレスの肩を軽く叩いて、励ましてくれた。
「じきにお前の初舞台だからな。言っちゃ悪いがパルメは座のお荷物だった。いないほうがお前も気楽だろ?」
「そんなこと、ムントンさん……あれでも案外、いい人なんだよ。パルメを悪く言わないで」
「人が好すぎるぜ」
ムントンは呆れ果てた様子だったが、すぐに笑顔になった。
「だがもう、パルメは行っちまった。お前はお前で、ここで仲間と一緒にやっていくんだろ? じゃ、最初の仕事だ。荷駄から座旗を出して棹につけな」
「うん」
「座頭が戻ってきたらすぐに入領だ」
「僕、王都は初めてなんだ」
「何、他の町と変わりゃしない。気楽に行こうぜ」
ムントンは逞しい腕を振り上げてセレスの背をパンと叩き、何がおかしいのか、ハハッと大きな声で笑った。
* 王都門の門衛 *
ビョルケ座頭の提出した名簿を二人の門兵が確認している。
「ひとつ前の領境より一人少ないが、どうした?」
門兵のひとりが尋ねた。
「パルメという雑用係ですわ。座を抜けて町暮らしをしたいというので、ついさっき、賃金を持たせて別れたとこです」
「座を抜けた? 王都の領門前まで来ていたのに?」
「芸ができないもので、もうずっと、やめたがってたんですわ。領門手前の宿屋に泊まって、明日、故郷の村へ帰ると言うておりました」
そうか、と門兵は名簿に通過許可の署名をした。
門兵の背後では、次に入領する商団の名簿が届けられたらしく、確認作業のためか、数人の役人が忙しそうに行き来している。
他領に比べると、王都の入領は審査が厳しい。大きな商団が入領するとなれば、門兵は総出で審査せねばならないのだろう。ビョルケの審査をしていた門兵も、一人を残して外へ出ていった。
「門兵様、私らのあとに、商団様が通るそうでございますね」
「そうだ。半年の旅商を終えて戻ってきた。ビョルケ、いい日に入領したな。商団から戻った商人達は懐具合がいい。大挙して興業を観に押し寄せてくるだろう」
へい、ありがたいことでございます、とビョルケは神妙に頭を下げた。
王都での興業は、貴族や豪商といった富裕層を相手にするので儲けが多い。その反面、彼らは目が肥えていて、芸の不出来について当たりが厳しくもあるので、やりにくい客でもあるのだ。
正直なところ、ビョルケは富裕層の客は苦手だ。王都での興業はせいぜい五年に一度でじゅうぶんだと考えている。
さほど大きな都市でなくても、芸で人を楽しませることはできる。中程度の村や町を、のんびりと渡り歩いて人々の歓声に触れ、土地の雰囲気を感じ取りながら旅をする、そのほうがビョルケの好みだった。
今回は王様の在位十周年ということで、副座頭のボンスンが、ぜひとも王都興業をしたいと言い出し、芸人達の大半も賛同したので、押される格好で王都入領を決めたのだ。じつに五年ぶりの王都入領である。
「それと、ビョルケ一座は……前回の王都興業からだいぶたつな」
「へい」
「座頭、じつは去年の秋ごろに芸人達の入出領について、規制が変わったのだ。特に人数については厳しく調べるよう、通達が来ている。王都に入ったときと出るときとで、人数が違うと出られない。気をつけるように」
「去年の秋、からでございますか」
「そうだ。さきの秋ごろ、十人以下の小さな座が次々と入領してな」
「何かあったので?」
「どの座も、さほど熱心に興行した様子もなく、七日ほどしてから、子どもを棄て置いて領から出て行こうとしてな。大騒ぎになった」
にわかには信じがたい話だった。
「子どもを、棄て置き、ですか」
芸人の座にとって、子どもは宝である。一人前の芸人になるためには、幼いころから先輩芸人の芸を観て、芸を好きになり、芸を磨く必要があるからだ。
ビョルケも何人もの子どもを座に入れて育ててきたし、どの子も大切にしてきた。ただ単に、ビョルケが子ども好きということもあるかもしれないが、その大事な子どもを棄てるなどとは、もってのほかである。
「座が子どもを棄てるとは……そんなことが本当に?」
「棄て置かれた子どもは、そのほとんどが北峰村のあたりで、無理矢理押しつけられたと、座頭達は言っていたが」
「北峰のあたりといいますと、干ばつのためでしょうか」
「その通りだ。王都の慈善院に預けてやると騙して、棄農した小作や、貧農達から金を取って、子どもを連れてきたらしい」
「とんでもないことですわい。芸人の風上にもおけん」
「まったくだ」
門兵は言いながら、王都市街地の地図を広げた。
「さてと。天幕だが、いくつ張る?」
「興行用に舞台付きの大きいのをひとつ、芸人達の寝泊まりに小さいのを十ほどですわ。それと、動物専用に柵付きがひとつ。頃合いの空き地がありますか」
「うん、そうだな……。市場の東側を水路沿いに五百歩ほど南へ行くと広い空き地がある」
門兵は地図を指さし、
「この地図でいうと、このへんだ。三年ほど前まで、貴族の馬場があった。平地だし、天幕も張りやすいだろう」
北と東に小さな林があり、風よけになる。西側には川があり、動物たちのための水がまかなえそうだ。
「ありがとうございます、そうさせていただきます」
「それとな、座頭。法の下で保護されている年齢、男女とも十三歳に満たない者は、興業に出してはならない」
「へい」
「この法に背けば座員全員、即刻退去の上、子どもは王都内慈善院預かりとなる。一座は向こう十年間、王都入領禁止という厳しい沙汰だ。気をつけるように」
「存じております、はい。座の者にも言ってあります。じつは門兵様、私どもの秘蔵っ子、十三歳まであと少しという子がひとりおりまして、初舞台に立てる日を励みにして一生懸命、練習しておりまして、これがまた、たいそう、可愛らしい子なんでございます。綱渡り組なんでございますが、三尋の高さに張った綱を、小鳥みたいに身軽に跳び渡ることができるんでございますよ。長年座頭をやっておりますが、あれほどの器量を持った子はなかなかおりませんで、門兵様もぜひ、非番の日には私どもの座へ」
門兵は苦笑いしながら手を振って、ビョルケの話を遮った。
「そうかそうか。それは楽しみだな。さ、これでよし。ビョルケ一座、通過を許可する」
「ありがとうございます。ところで門兵様」
立ち去ろうとした門兵の袖を、ビョルケが掴んだ。
「なんだ。まだ何かあるのか。弟子の自慢話ならあとにしてくれ、ビョルケ」
「このビョルケは、どの領でもそうなのでございますが、付け届けはいたしませんのです」
門兵は怪訝そうな顔をした。
「踊り子も宴席に差し出しません。すまんことです」
「けしからんな」
門兵は怖い顔をしてビョルケを睨んだ。だが、すぐに相好を崩して、笑い出した。
「それで良いのだ、ビョルケ。我ら門兵をはじめ、王都の兵士は全員が、陛下と領兵監オルクス殿の薫陶を受けている。陛下からいただく報酬以外には、一切の益を得てはならない、それが鉄則だ。ゆえに、もしも袖の下を要求するような兵士がおれば、そいつは騙りかもぐりだから、ただちに領兵監殿へ訴え出るように。さ、じきに商団が門に到着する。早く入領するといい」
「承知いたしましてございます」
通過印の押された名簿を持って、ビョルケ座頭は領門詰所を出た。末弟子、綱渡り組のセレスの自慢話を途中で遮られたのは残念だが、門兵は忙しいのだ。商団の通過が控えているのならなおさらで、しかたがない。
門兵の詰所の脇で、ボンスンが鞄と小さな布袋を持って待っていた。
「座頭、どうでした」
「うん、許可が出た。広場もいい場所を貸してもらえる。ボンスン。手に持っているそれはなんだ?」
「あ、これは、さっき出てった門兵が、座に子どもはいるかと聞くもんだから、十二歳のがひとりいると答えたら、これをやるって言って。蜜胡桃なんだそうで」
蜜胡桃とは、胡桃を煎って蜂蜜に浸した、手軽な菓子である。
「子どもに菓子をくださるとは……ふーむ」
この五年で王都の兵士もずいぶんと変わったなと話しつつ、ビョルケとボンスンは芸人達の待つ馬車駐まりへと歩いていった。
* 芸人一座の入領 *
荷駄を積んだ馬車の横で、セレスは五つ玉の練習をしていた。
三つ玉から四つ玉までは簡単に修得できたが、五つ玉はちょっと難しい。五つめの玉の高さがどうにも決まらなくて、受け損なって落としてしまうのだ。
荷馬車を引く馬のダンテの頭に玉がぶつかって、ブヒヒと叱られたりしながら練習をしていると、
「ビョルケ一座、出発!」
飾り馬車のほうから座頭の声が聞こえてきた。領門通過の許可が下りたらしい。座頭の合図で、一座の面々がそれぞれの持ち場につく。
「セレス、荷馬車の御者台に乗りな」
曲乗りのムントンがセレスをひょいと担ぎ上げて馬車に乗せた。
「え? 僕が御者?」
「そう、お前だ。荷馬車は最後尾だから、つまらない、なんて思うなよ。荷馬車がうまくできたら、次は飾り馬車に乗せてやる」
「ひゃっ、ほんと? じゃ、頑張らなくっちゃ」
「ダンテは頭のいい馬だから、かけ声だけで歩いてくれる。安心してついてこい」
「うん」
「さあ、みんな、それぞれ位置について! 楽器の準備はいいか?」
王都入領と同時に、芸人一座が来たと、都下の人々に触れて歩くのである。
ラッパと太鼓と笛の楽隊は六人、行列の先頭をゆく。踊り子が練り歩き、玉乗りが続く。剣術舞と座旗が続き、飾り馬車がゆく。最後がセレスの乗っている荷馬車である。
セレスは綱渡り組だ。入領のときの行進では出番はない。本当は半年前から練習してきた長脚をつけて馬車の前後で歩きたかったが、座頭に止められていた。
芸人一座では十三歳に満たない子どもを働かせてはならない、という法がある。さきの王様が定めた王令だ。
セレスは十三歳まであと少し。月の三巡りほど待たなければならない。王都にいるあいだに芸人として初披露となるよと、座頭には言われていた。
十三になれば、芸を披露して座の皆と一緒に働いて、一人前とまではいかないけれど、少しは役にたてる。
綱渡りは好きだし、セレスだけができる技もあって、ちょっと自信もある。綱渡りをしながら五つ玉をする、それはとても難しいが、練習を重ねていけばきっとできると信じていた。
じきに初舞台。気持ちよく晴れた夏のある日、三尋の高さに張られた綱の上に乗る。
軽々と飛び上がる五つ玉。
歓声と拍手が自分を迎えてくれる。
座頭と、芸人仲間もきっと喜んでくれる。それがセレスの今一番の希望だった。
セレスはビョルケ一座の最年少であり、先輩芸人達と違って、親子代々の芸人ではない。
座に飛び込んでから、綱渡りを習い始めた、いわば見習いである。
わけあって、五年前、セレスはパルメに連れられて、旅芸人のビョルケ一座に加わった。
逃亡の身を隠すのには芸人一座が一番だと言ったのはパルメである。
その折りに、ふたりの身の上をあれこれ説明するのは面倒だから、食いつぶして逃げてきた農民の姉弟ということにしようと提案したのもパルメだった。
座に加わった当初、セレスはまだ七歳で、ほんの子どもだった。パルメは当時、二十歳をいくつか過ぎていたけれど、かなり無理をして自称十五歳ということにして、半ば強引に座に潜り込んだのだった。
人の良い座長は、パルメの話を鵜呑みにしたわけでもないのだろうが、深くは追求せず、セレスとパルメのふたりを座に受け入れてくれた。
セレスには芸を初歩から仕込んでくれたし、パルメには軽い作業をさせてくれて、そうして五年間、旅を続けてきたのである。
無理な姉役も旅暮らしもやめて、町に住みたいと、パルメはこの一年ほど言い続けていた。
じつはパルメは、少しばかりちゃっかりしているのである。
入場料のちょろまかしなど、朝飯前だった。後入りの裕福な客から、袖の下を受け取って前の座席へ連れて行ったときはさすがに座頭から、こっぴどく叱られたが、それで懲りるパルメではなかった。
座の動物たちを見たがる客から、心付けを取って裏方へ案内したかと思うと、天幕の設営時や撤収時には、馬車の上で寝ていたりした。はなから力仕事は嫌いなのである。
それやこれやで座の仕事はほとんどしないで小金を稼いだり、作業を怠けたりしてきたため、パルメに対する座の仲間の視線もそれなりだった。
セレスの姉だという嘘も、ほとんど通用しなくなってきて、
「本当に姉弟なのか? 似てないよな」
などと言われるようになって、居心地の悪さが限界まできていたのだろう。それはセレスにもよくわかっていた。
だがパルメは、セレスのために五年間ものあいだ、肌に合わない旅芸人の一座にいてくれたのだ。
セレスが七歳のころ、自分の身の上に起きたことは、いまだに理解できない。
けれど、パルメが途中でセレスを放り出さず、とにかく安全なビョルケ一座に加われるようにしてくれて、その後もなにくれとなく気を配ってくれたことには、感謝している。
ありがたい反面、パルメに申し訳ないような、そんな気がしてくるセレスである。
パルメは座を離れたあと、どうするのだろう。小金は貯めていたようだけれど、不自由なく暮らしていけるのだろうか。
振り返って荷物越しにパルメの姿を探したが、見つからなかった。その代わりに、街道の向こう、傾きかけた金色の日差しの中に、たくさんの美しい旗をきらめかせ、大勢の人と馬車の群れを率いた一団が姿を現した。
「さっき、門兵が言っていた商団かな」
たしか王都の商団が戻ってきたと言っていた、きっとそうなのに違いない。
伸び上がってみてセレスはその商団の規模に驚いた。今まで、あちこちの町や村で、小さな商団を見かけたことはあったけれど、これほどの数の馬と荷車を率いる商団は見たことがない。
「ものすごい人数だ……何人くらいいるんだろう」
ビョルケの一座も旅芸人としては人数が多いほうだが、後方から近づいてくる商団にはとてもかなわない。
商団の先頭に、まばゆいほどに真っ白な、立派な馬に乗った人物がいた。
芸人の一座に座頭がいるように、商団には団統がいる。
「ダンテ、後ろから真っ白な馬がくるよ」
御者台から荷馬のダンテに話しかけてみる。ダンテはくるくると耳を回し、首を軽く上下させた。年老いて芸はできなくなったけれど、気立ての良い、優しい馬である。
「僕は王都みたいに大きな街は初めてだよ。お前は何度も行ったんだよね。よろしく頼むよ、ダンテ」
ブルル、とダンテが返事をしてくれたとき、石造りの大きな門を通り過ぎた。
いよいよ、王都の都下である。
芸人と踊り子と馬車の一団は、旗を振り立て、にぎやかな音楽を鳴らしながら、王都の中へと進んでいった。
* ヴェティ・サンザの帰領 *
「若、ヴェンティ若。ちょっとお耳を」
副統のティントが小声で呼びかけてきた。
商団の領門通過を待って、領門前の馬車駐まりで休んでいたときである。
ヴェンティは愛馬からひらりと飛び降りてティントの腕を素早く掴んだ。
「ティント爺、若はよせよ。俺は団統だぞ」
小声で、だが少しばかり脅す口調で言うと、ティント爺は眉間に皺を寄せた。
「威張ってる場合じゃありません、若、ちょっとこちらへ」
年の割には衰え知らずのティント爺は、ヴェンティを強引に引っ張っていく。
サンザ家商団の大馬車前まで行くと、周囲を警戒するように見回してから素早く扉を開け、自分が先に乗り込んでから、これまた怪力ぶりを発揮して、ヴェンティを馬車の中へ引っ張り込んだ。
「おい、ティント爺、なんだってんだよ」
「若、えらいものが出ました」
「お化けか」
「お化けならまだましですよ。へたすりゃこっちがお化けになりそうです、とにかくこれを。これを見てください」
「領門前で何が出るっていうんだよ。取引は昨日で全部終わってる……」
言いかけてヴェンティは言葉を失った。ティント爺が、小箱を差しだしている。小箱の中には大人の拳大の透明な石があった。ちょっと見かけないほどの大きな菱形をしている。
「……方解石か?」
「そうですよ」
「方解石の母岩の中の、これはなんだ?」
「なんだと思います?」
方解石に包み込まれるようにして、子どもの拳ほどの大きさの、淡青色の石がある。
取り上げると、思いがけない重量があった。
「この色と重さからすると……天青石か」
「あ、やっぱり、若もそう思いますか」
「誰がこんなだいそれたものを持ってきた。来歴書は?」
「それが、これを持ち込んで来たのは旅の女でして。来歴書はないそうです。もらい物だと、本人は言ってます」
「もらい物? ふん、そいつは怪しいな」
「ですよね?」
ヴェンティは石を箱に戻して蓋をした。
「売り主はどこにいる」
「隊の中程の馬車脇にいます」
「すぐに会おう……いや、連れて来い。外で話して誰かに聞かれたら不味い」
「承知しました」
ティント爺は馬車を降りていった。
ヴェンティはもう一度、蓋を開けて中を見た。
方解石には細工がしてあった。この石を母岩にして、内部に天青石を抱かせた細工師は、そうとうに腕がいいと思われた。
天青石は稀な貴石である。国内での産出記録はない。所持者は限られるはずだ。
硬度が低いので装身具としてはあまり使われない。母岩に据えた形のまま、室内装飾用として売られることが多いものだ。勢い、この石の保有者は女性ではなく、富裕層の男性、年配者であることが多い。
「盗品か。にしても、でかすぎるな、お前」
石に囁きかけてみる。透き通るような青い石は冷たい沈黙を保っていた。
この珍しい石を、しかもこの大きさで、卓越した技術で母岩に抱かせる加工をさせるとなると……王室としか考えられないなと、ヴェンティは思う。
ティント爺の台詞ではないが、うかつに持っていればこちらが犯罪者扱いされてしまうだろう。いったい、どこの誰が、こんなものを持ち歩いていたんだか。
馬車の外に足音がして扉が開き、
「団統がお会いになる。お入り」
ティント爺の声が聞こえてきた。
「やだ、何さ、買い取ってくれるって言ったじゃないの、どうしてこんな馬車にあたしを」
騒ぎながら乗り込んで来たのは三十がらみかと思われる、ややくたびれた旅装の女だった。あまり手入れの行き届いていない肌と髪。手にはごくわずかな旅道具を詰め込んだと思われる薄汚れた袋を握りしめている。
ヴェンティの顔を見ると、女は軽い怯えを見せて黙り込んだ。
「この石を売りたいと申し出てくれたのは、あなたですか」
ヴェンティは商売用の顔を作って笑いかけた。
女はややのけぞり、何度か瞬きしたあとで、軽く息を吐き、それから口元を引き締めた。
「ええ、ええそうよ。売りたいの。いくらになるの?」
「見立てでは金三百枚」
「ひえっ!」
女は両手で口元を覆い、それから満面の笑みになった。
ふーん、やっぱりこの石の価値は知らずに持ち込んで来たなとヴェンティは思ったが、そんなことは顔にも言葉にも出さない。来歴さえはっきりすれば、金千枚が妥当な価格である。
「来歴書があれば、もう少しお出しできますが。もらい物だそうですね。前の持ち主は?」
「あ、旅芸人一座の、元踊り子さん。引退して農場にいた女の人よ。それ、あたしが貰ったの。本当よ。盗んだものじゃありませんからね。疑ってるなら、取引はなしよ。他へ持っていって売るから、返してちょうだい」
「お引き取りいたしますよ」
「じゃ、金三百ね。すぐに貰える?」
ずいぶんと急いてるなと、ヴェンティはおかしくなった。
値をつり上げるとか、駆け引きをするとか、そういう考えはなさそうである。王室の財宝を盗んだり、転売する稼業とは縁がないと思われた。
「すぐにお払いしますよ。ティント爺、金庫を持ってきておくれ」
「はい、若」
ティント爺は素早く馬車の外へ出ていった。
「ところで、王都から出て来られたところですか? それとも、これから王都へ?」
「あ、わけがあってね。あんまり聞かないでほしいんだけど。王都近くまで仲間と一緒に来たけれど、ちょっと気まずいことがあってさ。あたしは王都に入らずに、他の町へ行くことにしたの」
「お仕事は何を?」
「旅芸人の一座。でもあたしには向いてない。あたし、芸はできないし、一座ってやつは雑用は多いし、仕事はきついわ気疲れするわで。あたし、旅なんか好きじゃないの」
「わかりますよ」
態度から察するに、寝食を共にして旅を続ける一座では、浮いた存在だっただろう。
ヴェンティも旅をしてきた。商団の団統として、半年の旅暮らしだった。目の前の女が集団の旅に不向きなたちだということは一目でわかる。
「私はサンザ家商団の団統ヴェンティと申します。あなたのお名前をお聞きしていいですか?」
「えっ、あたしの名前? どうして?」
「王都へ戻ってから、正式な鑑定をします。そして、今回お払いした金額より、査定価格が大幅に上回った場合には、不足金をお払いしたい。なので、あなたのお名前と、当面のお住まいをお聞きしておきたいのです」
「あ、そういうこと? もっともらえるかもしれないのね?」
「そうです」
「あ、じゃあ、あたしはね、出身は北峰領の村だけど、じつはそこへ戻るつもりはないの。おたくがこれの代金を追加で払ってくれるっていうのなら、近くの村で宿を取って待ってる」
「そうしていただけると助かります。ではこうしてはいかがでしょう。領門の手前に私の一門の者が経営する宿屋があります。お待ちいただいてるあいだ、宿代はサンザ家で持ちましょう」
「さすが、団統さんね。太っ腹だわ」
「お名前は?」
「パルメ。あたし、どれくらい待っていればいいの?」
「七日のうちには」
「いい値をつけてね。楽しみにしてるから」
うきうきした顔で、パルメは嬉しそうだ。万が一、持ち込まれたものが王家の財産だったとわかれば、ただちに捕らえて、この石をどういう方法で入手したのか聞き出さねばならない。
だが宿代を商団で持つという提案に、たやすく乗ってくるところをみると、彼女が盗人である可能性は低い。
「パルメさん、この石の前の持ち主も、北峰領の村にお住まいでしたか?」
「そうよ。芸人一座の売れっ子の踊り子だったそうだけど。知り合ったときはちっちゃい子どもを抱えて、苦労してたみたい。で、あたしがちょいちょい助けてやったってわけ。そしたら、これをくれたの。お礼よ、って言って」
「元踊り子さんは、暮らしに困っていたとき、何故、これを売らなかったのでしょうか」
「さあ? そのへんの事情はあたしにもわからない。なんかわけありだったんでしょうよ」
「わけというと……」
「男の子ひとり、育ててたけど、父親は一緒じゃなかった。死に別れたとか言ってたけどね。本当のところはどうなんだか」
「そうですか」
馬車の扉が開き、ティント爺が小ぶりな金庫ひとつを持って入ってきた。
「金三百です。どうぞ、ご確認を」
「あ、いいわ。宿に入ってからゆっくり数える。こんな大きな商団でごまかしがあるわけないしね。買ってくれてありがと、団統さん」
「いいえ、珍しいものをお譲りくださって、こちらこそ感謝しています。ティント爺、パルメさんをサンザ鴛鴦亭(おしどりてい)へご案内しておくれ。宿代は私持ちだよ、わかっているね」
「承知いたしました、若」
ヴェンティは軽く目配せし、ティント爺は目顔で頷いた。長年勤めてきただけあって、こういうときは素早く察してくれるので助かるのである。
ヴェンティは先に馬車から降り、パルメに手を貸した。ティント爺が彼女を案内して宿へ向かうのを見ていたとき、商団の最後尾のあたりから、怒声が聞こえてきた。
同時に、商団の若い者が一人、猛然と走ってきて、
「団統! 喧嘩です! 学舎の奴らが羊毛に火、つけやがった!」
手に水桶を持ったまま叫んだ。
* ビョルケ一座の天幕 *
ビョルケ一座が馬場跡の広場に天幕を張り終えるころ、陽が沈んだ。
ひとつ前の興業をした町から半月の旅を終えての王都入領だったので、一座の全員がここで三日のあいだ、休息をとりながら公演開始の準備にかかる。
五月半ば、満月の夜に初日の幕を開け、三日続けて興行して一日休み、客の入り具合を見て出し物を替える。そうして三か月の長丁場を乗り切ることになっていた。
王都では農民がいないので、興業の時期は年間通じて安定するというのが、座頭の弁である。
天幕の脇では踊り子組の組長ソフィが、五人の踊り子と、早くも練習を始めていた。王都から新しい演目を披露するので、今は踊りの仕上げにかかっているらしい。腕、もっと優雅に! とか、もっと大きく回って! とか、ソフィの厳しい声が響いてくる。
荷馬のダンテは夕食中だ。飼い葉桶に顔を突っ込んで、嬉しそうに尻尾を揺らしている。
その向こうで鳥使いのヘクタスが、白鳩達に餌やりをしていた。
ヘクタスの脇では、一座の人気者である猫のリンクスが、彼のための特等席、すなわちビョルケ座頭専用の椅子に乗り、丸くなってくつろいでいる。
道化のボンスンが太っちょの衣装をつけて、この椅子からリンクスをなんとかしてどかそうとして、右往左往する演目は、子ども達に大人気だ。リンクスは演技しているわけではない。とにかく柔らかくて居心地のいい椅子に乗りたいと思っているだけだ。ボンスンが頑張って椅子を動かしても、リンクスを抱き上げて箱に入れても(箱の底は抜いてある)いつの間にか猫は椅子に戻っているのだった。
セレスも『リンクスの椅子』の演目は大好きである。何度観ても、涙が出るほど笑ってしまう。それはボンスンの修練の賜であり、賢いリンクスの、唯一の、そしてとっときの芸なのだった。
「セレス、足場が組み上がったぞ」
ムントンが綱の束を肩にかけ、呼びに来てくれた。
「ありがと、ムントンさん。今から綱がけしていい?」
「そう言うと思って、用意してきた。手伝ってやるよ」
綱渡りの綱は伸縮に注意が必要だ。夜露、朝露、雨に当ててはいけないのである。使用時や練習の時だけ掛け渡し、使用後は片付けることになっていた。
ムントンに手伝ってもらって足場の一番高い棹に綱をかける。綱締めには力が要るので、ムントンがしっかり留めつけてくれた。
「前の練習から半月たってる。いきなり三尋で大丈夫か」
ムントンは心配そうだ。綱渡り組の組長ではあるが、ムントンは高綱の綱渡りはしない。体重がありすぎて綱がたわむため、危険なのだった。
今、一座の中で高綱を渡れるのはセレスだけである。綱の張り具合を確かめてから息を整え、セレスは最初の一歩を踏み出した。
「セレス、命綱つけろよ」
三尋下からムントンが心配そうに声をかけてくる。
「大丈夫だよ」
セレスは笑って答え、足の裏に気持ちを集中させた。
半月のあいだ渡っていなかったが、一歩を踏み出しただけで、感覚が戻ってくる。
最初はややゆっくりと、足裏に当たる綱の感覚を確かめながら渡り、二度めには毎回の練習と同じように綱上での跳ね、腰掛け、旋回と試してみた。
「大丈夫、いけると思う。ムントンさん、三つ玉、やってみたい。下から投げてくれる?」
「暗いのに……」
だめだぞ、とは言わなかったが、玉は飛んで来なかった。
十往復ほどしたあとでセレスは綱から足場へと降りた。高い足場の上からは、王都の町並みがよく見える。セレスが今までに見たどの町よりも、建物が多いし、人もたくさんいた。
西側には市場が広がり、日が暮れたのに大勢の人々が買い物をしている様子がうかがえた。
市場の北側、小さくて白い天幕が途切れたところに、ひときわ大きな館があり、そこにも大勢の人が出入りしている。この広場に来る前に、その館の前を通った。王都の商業活動全般を統帥しているサンザ家の館だと、座頭が教えてくれた。いわば豪商のお屋敷である。
夕方、領門前で見かけた、あの白い馬に乗った人も、あの館に帰っただろうか。自分とは関係のない人だけれど、あの大きな館を我が家として出入りする感じって、どんなものなんだろう、と想像する。
サンザ家の大きな屋根の向こう側に、高木の立ち並んだ一角があって、そちらは王国内の各地から集まった学生が起居する、学舎がある。
若いうちから勉強して学士になったり、実学や工芸を学んだりするという。セレスの着ているこの服も、製糸から織り、縫製まで、もともとはあの学舎で学んだ人達が考え出したものだと座頭に教えてもらった。
世の中にはすごい人達が大勢いるんだなあと、驚くような、感心するような、僕なんかまだまだだなとちょっと落ち込むような、複雑な気持ちだ。
学舎から少し離れた北西の方角に目を向けると、大きな塔の並ぶ建物があった。
「ムントンさん、あの塔のあるところって、お城?」
「塔があるなら王宮だ。王様がいらっしゃるだろう。見えるか?」
「見えないよ」
セレスは吹き出し、ムントンも下で笑っているようだった。
「そろそろ降りてこい、セレス。じきに晩飯だ」
「はい」
王宮の高い塔のところどころに、橙色の灯りが見える。
塔の右側に石造りの、これまた相当な高さがあると思われる塀があり、塀の上には等間隔で人が立っていた。歩哨がいるのだろうか、と、セレスは目をこらして建物を見つめ続けた。
塀の一部に門がある。人の出入りがあり、馬も通っているようだ。
王都での興業はほぼ三月。興業の最後のころが、セレスの初舞台となる。 もしかしたら王様も、三尋の高さの綱渡りと聞いて、観にきてくださるだろうか。
そしてお褒めの言葉なんか貰っちゃったりして?
『見事であるぞ、セレス』とか。
うふっ、そうしたら最高なんだけど。
想像すると何かしら嬉しくなって、一人で笑ってしまったセレスだった。
* ヴェンティとゼタ *
「親父殿ー、すまん、助けてくれー」
ヴェンティは屋敷の廊下を大股で歩いていった。突き当たりの扉が開き、
「親父殿はよせ、ヴェンティ。父上と呼べ」
強面のサンザ家当主、ノーヴェが顔を出した。ヴェンティが思わず足を止めてしまうほど、怖い顔をしている。
「んもー、親父殿、なんとかしろよ、その悪人面」
ヴェンティは部屋に入って、父親のお気に入りの長いすにどっかと腰をおろした。長い足をぶんと振り上げて、父の机に載せる。その足をノーヴェが拳をふるってたたき落とした。
「いってー、何すんだ、クソ親父」
「父上と呼べと言っただろうが!」
「クソ父上」
「クソは余計だ。ヴェンティ、領門前で喧嘩だったそうだな」
「俺が仕向けたわけじゃないぜ」
ノーヴェの拳が上がり、ヴェンティは頭を庇って身体を丸めた。
「殴りはせん。わけを話せ」
「拳を開いてよ。まったく怖いんだから」
「蹴りのほうがいいか?」
ノーヴェは足を上げたが、ヴェンティの膝の高さにもならなかった。ノーヴェは長年の運動不足がたたって肥満気味となり、足が上がらないのだ。
体重のせいで椅子がよく壊れる。ヴェンティが今、座っている椅子も、さきの冬に新しく作らせたばかりだった。値は張ったが、たいそう丈夫である。
「ねえ、頼むから。今度喧嘩したら謹慎だって、陛下に言われてるんだよう、親父殿」
「いきさつを話せ。わしから陛下に、とりなしをお願いするから」
「それがさあ」
ヴェンティは商団と学舎の学生のあいだで起きた、領門前の喧嘩について説明し始めた。
商団の若い衆の話では、領門通過に時間がかかっていることに腹を立てた学舎の学生達が、
『都民の迷惑も顧みず、夕方に大挙して通過するとは。商団の常識知らず』
と、ののしったのが発端らしい。
商団の若い者が、
『遊んで暮らしている学生が何を言うか』
鼻でせせら笑った。かっとなった学生側が、
『学舎の研究があったればこその商団の儲けだろう。常識だけでなく恩も知らないな』
と、切り返した。
『学舎の技術開発の予算は商団から出ているんだ、えらそうなことを言うな』
商団の若い者も、相手の弱いところを突いた。それで学生のひとりが商団の荷を蹴った。若い者が飛びかかって止めた。学生がそれを振り払おうとして、筒灯りを振り回したら、手から離れてしまった。筒灯が空を飛び、荷の上に落ちたところ、たまたま羊毛の荷だったので、あっという間に燃え上がってしまった。
「……で、学生も商団の若い連中も羊毛以上に燃え上がっちゃって、あとは乱闘」
ふーむ、とノーヴェは渋い顔になった。
「そりゃ、学生が悪いな」
「そうなんだけどさ。でも学生は、先に手を出したのは商団だから、自分達は悪くないと言ってんの。ねえ、どうすりゃいいの?」
「よりにもよって、お前の最初の団統としての仕事だったのになあ」
「まったくだ。俺、こんなバカみたいな喧嘩の責任とって謹慎になんてなりたくないよ」
「ま、大丈夫だろう。ところで商売はどうだったんだ」
「取引高、収益とも、サンザ家始まって以来の新記録だと思う。って、ティント爺が言ってた。俺って商売上手みたいよ? 顔がいいから?」
ノーヴェの顔がさらに渋くなった。
「色気が役立つのは若いうちだけだ。図に乗るな、色男め」
「うん」
「領門前の喧嘩だけが、汚点だったな。まあ、学舎から訴えが上がって、じきに陛下から呼び出されるだろう、わしが出向いて謝罪してくる」
「いつだって商団が悪いって結果になるんだよなあ、くっそー、頭に来る」
「頭を下げても負けとは限らん。相手は学舎だ。もう、こればっかりはどうにもならん」
学舎と商団はヴェンティの祖父の代あたりから、王都で知らぬ者のない、犬猿の仲だ。
もともとは、産業振興のためにと、サンザ家が陛下に奏上して、技術者を育てる学舎に資金援助した。学舎は領民の暮らしに役立つ技術を調査研究してまとめ上げ、職人を育てた。
ところが学舎の活動が軌道に乗ると、当時の学博が、商団の儲けが多すぎる、価格が不適切だ、商業権の独占が領民と国民を圧迫していると言い出した。それは一部、本当のことではあった。
しかしながらヴェンティの祖父は、学舎の厳しい追及に腹を立て、サンザ家から学舎への資金援助を打ち切ったのである。
学舎はそれへの対抗措置として、技術供与した領内のすべての職人に、一か月のあいだ、作業を停止させた。王都の経済と流通は大混乱に陥った。
結局、王室が商団と学舎の調停に乗り出した。学舎は商団の商法に口出ししないこと、商団は学舎への援助を続けること、それがさきの国王陛下が提示した和解案である。
双方、この条件をのんで、一応の解決をみたのだが、学舎と商団はそれ以降、ずっと折り合いが悪い。学舎にも商団にも、年若い者が大勢いるせいか、小競り合いが乱闘に発展してしまい、そのたびに陛下からお叱りを受ける。
一年前の都内での喧嘩にはヴェンティも加わっていた。若さに任せて暴れたら、陛下とノーヴェと学博からこってり叱られ、次に騒動を起こしたら謹慎だと言い渡されていたのである。
「いくらなんでも、もう喧嘩して喜ぶほど子どもでもないんだけどなあ……俺ももう十八なんだしぃ」
「妻でも迎えるか、そろそろ」
「早すぎるよ。親父殿と違って、俺はもてるの。今結婚したらもったいない」
「このお調子者めが」
ノーヴェが拳を振り上げたとき、扉を軽く叩く音に続いて、
「旦那様、領兵監オルクス殿がお見えです」
ティント爺の声が聞こえてきた。
「そら、おいでなすったぞ。領兵監様のお迎えときた。それじゃ王宮へ行って頭を下げてくるからな。お前は一応、反省して自宅でおとなしくしているフリでもしておけ」
「わかった」
「だがいい旅商だった、それは事実だから褒めてやる」
「親父殿、大好き」
ノーヴェはにこにこして息子の頭に軽く手を乗せ、部屋から出ていった。
入れ替わるように入室してきたのは領兵長のゼタだった。
「おっ、ゼタ。ひさしぶり」
領兵長の中では最年少ながら、国王陛下の信望厚いゼタは、ヴェンティの親友である。
「無事に帰ってきたか」
ゼタは控えめな笑みを浮かべてヴェンティの座っている椅子の横に、軽く寄りかかった。
「ゼタ、領兵監殿と一緒に王宮へ行かなくていいのか」
「陛下は父にだけ命令されたんだ。私はお前の顔を見に来た」
ゼタの父は領兵監オルクスである。ゼタの父オルクスと、ヴェンティの父ノーヴェとは同年で、長年の友人でもあった。親同士が仲がいいので、ゼタとヴェンティも赤ん坊のころからの友人同士である。
「ここへ来る前に、学舎のルーシェ学博殿のところへも寄ってきた」
「あ、どうだった? 怒ってた?」
「そうでもなかった。ルーシェ殿は温厚なかただ。たぶん、学舎の学生に注意して、商団にも同様の注意を促し、それで終わりだろう」
学舎の頂点に立つ学博ルーシェは、王裔である。現国王ラズライト三世の従兄にあたる人物だ。
「なあゼタ、一年前の学舎西館との大喧嘩のあと、陛下から、二度と騒ぎを起こすな、次は謹慎させるって、すんげー厳しく叱られてんだけど、俺」
「陛下には何かお考えがあると、父が言っていたが」
「それが怖いよなあ……商売は好きだし楽しいけど、学舎とのつきあいだけが苦手だ」
ゼタは微笑み、軽く頷いただけだった。
同じ年だが、ゼタはヴェンティよりずっと落ち着いて見える。
近衛兵隊長から領兵監と、破格の出世を遂げたゼタの父オルクスも、同じように老成していて、どこかしら侵しがたい風格とでもいうべき雰囲気を漂わせているのだった。
ヴェンティは商売の場ではそれなりに、商人風を装うが、帰宅して父といるときはほとんどだだっ子である。父も仕事以外ではヴェンティを甘やかす。
だがゼタの家では、自宅でも領兵監オルクスと領兵長ゼタとして暮らし、その関係は崩れないらしい。
ゼタはいったいいつ、息抜きしているのだろうかと、ヴェンティはそれが不思議だ。
「ヴェンティ、旅はどうだった?」
「面白かった、儲かった」
「人々の暮らしぶりは?」
「北峰領あたりが厳しい。慈善麦を無償で放出してきた。冬小麦の収穫まで保つといいけれど。小作達が棄農して一部は逃げ出して、町で浮浪してるんだ。小さい子どもの物乞いがいて、可哀想だった」
「ヴェンティは優しいな」
「優しいもんか。商売になれば怖いぞ。びしびし、だ」
「そうか」
ゼタはにっこりし、ヴェンティの肩を軽く叩いた。
「そういえば、さっき、門兵から聞いたんだが、芸人一座が入領してきたらしい」
「芸人なら王都にいつでもいるだろ?」
「それが、五年に一回くらいしか王都へ来ない、すごくいい一座なんだそうだ。門兵の話では、観て損はないとか」
「ふうん。なんていう座?」
「ビョルケ一座。ここへ来る途中で見かけたんだ。祖父の屋敷の馬場跡に天幕が張られていた」
「お前が芸人一座に興味を持つとは。どうしたんだ、ゼタ領兵長」
ふふふ、とゼタは笑った。
「あ、笑ったね、こいつってば。さてはのぞき見したら、美人がいたんだとか?」
「まさか」
だがゼタの顔には笑みが浮かんでいる。
「美人かどうかは、わからなかった。だが、相当な高さの……三尋はあったか、足場が組んであって」
「ふんふん。透けたドレスの美人がブランコしていたか」
「いや。小さな子だった。一人で綱渡りの練習をしていた」
ヴェンティの脳裏に疑問符が飛び交った。
「子どもなんか見て何が楽しいんだ、ゼタ」
「小鳥みたいだった。綱の上で跳ねたり回ったりくるくると。それが楽しそうで、可愛かった」
「あ、こいつってば、俺というものがありながら、芸人の子どもなんかに浮気しやがって。許さないぞ」
ヴェンティはゼタを羽交い締めにして、脇腹を思い切りくすぐった。
ゼタは笑い転げた。さすがに武術の達人だけあって、ヴェンティの腕を軽くほどいてしまったが、顔はまだ笑っている。
「座が開いたら、観にいこう、ヴェンティ」
「うん」
「半年ものあいだ、働いてきたんだ、気分転換も必要だろう?」
「綱渡りする子どもはどうでもいいけどな」
「初日に迎えに来る。三日後の夕方からだ」
ゼタがこう言うということは、その日は勤務を休んで、ヴェンティにつきあってくれるという意味である。
ゼタらしい思いやりを感じて、ヴェンティの胸がふっと温もった。
* 王と王裔 *
王宮では執務室でなく、国王の居室へ通されたノーヴェである。
当然、周囲に近衛兵もおらず、深閑として、むしろ居心地が悪い。賑やかな商家育ちのせいか、あまりに静かな場所にいると落ち着かない。
しばらくすると、国王が学舎学博のルーシェ公をともなって入室してきた。
ノーヴェが慌てて立ち上がろうとすると、
「そのまま、そのまま。立たずともよい」
王はノーヴェを制し、学博ルーシェ公が笑みをたたえて軽く会釈をよこした。ルーシェ公の品の良さはまぎれもなく王裔のものであり、ノーヴェには逆立ちしても真似のできない雰囲気を漂わせていた。
「ルーシェ公、座られよ。もてなしなどはせぬ、直ちに話し合いに入る」
ノーヴェの右隣にルーシェ公が、左斜め前に王が着座した。王と王裔に挟まれて、さらに居心地悪くなってしまったノーヴェである。
「さて、それぞれ忙しい身なので、前置きは抜きで参ろう。ルーシェ公からあらかたの顛末は聞いた。ノーヴェも息子から事情は聞いていると思う」
「は」
国王は小さな結晶時計を取り上げると、さっと一振りして卓上に置いた。容器内の結晶が底面に沈むまでの短い時間で、解決するという合図である。
「先刻、王都西の領門前で騒動が起きたと報告を受けた。サンザ家商団と学舎西館学生のあいだで言い争いがあり、学生が振り回した筒灯からサンザ家商団の荷に火が移り、仕入れてきた羊毛一駄が燃えた。その後、サンザ家四名、学舎学生五名の乱闘に至った。相違ないか」
「相違ございません、陛下」
ノーヴェは頭を垂れた。
「騒動の場に、サンザ家商団団統のヴェンティが駆けつけて騒ぎをおさめ、燃える荷を鎮火し、双方のけが人の有無を調べて、商団学舎の隔てなく手当を施し、火傷を負った者を商団付き医師に診せるなど、配慮があった。これは学舎学生のうち、筒灯を投げてしまった者の証言である。ルーシェ公からそのように聞いている」
「さようでございます、陛下」
ルーシェ公も軽く頭を下げた。
「これはささいな諍いである。サンザ家ノーヴェ、及び商団団統ヴェンティ、そして学舎学博ルーシェのあいだには、騒動を起こそうなどという気はない」
「むろんでございます、陛下」
ノーヴェは素早く同意した。横でルーシェも頷いている。
「ゆえに、今回の騒動は半ば事故と見なし、サンザ家商団団統のヴェンティには咎なしと認める」
「ご高配、痛み入ります」
「だが、学舎側に一部、見逃せぬ言動があった。ヴェンティがけが人を医師に診せようとした際、学舎側のひとりが、診療は余計なことだなどと反対して阻害し、なおかつ暴言を吐き続けていたと聞く。それは誰か、ルーシェ公」
「学生を引率しておりましたソロン序学士です、陛下」
「たしかか」
「ソロン序学士本人が、いまだに商団の治療について、越権であり、治療が適切でなかったと主張しております」
「騒動は不可避だったとしても、怪我火傷の類いは、一刻も早い治療が必要である。ソロン序学士の行動には多大な過ちありとして、厳しく注意するように」
「謹んでうけたまわりました、陛下」
「よって、ソロン序学士は一か月間の就労禁止、半年間、減俸十二分の一を申し渡す。異論のあるときは王都裁判所へ訴え出るように。ただし、ヴェンティへの抗議であれば、訴訟は受け付けない」
「陛下、お伺いしてもよろしゅうございますか」
ノーヴェは小声で口を挟んだ。
「かまわぬ。何か」
「我が倅ヴェンティにはおとがめなしと?」
「そうだ」
「ですが、学舎の序学士殿には就労禁止の上に減俸となると、それはまた別の不満の元になりはしませんでしょうか」
「ヴェンティに落ち度はない」
「監督不行届き、とかの」
「それは言いがかりの類いだ。ノーヴェ、自分の子に罰を望むのか?」
「滅相もございません。ですが、私どもは商人です。序学士殿だけが御処分となれば、その恨みが商団に向くのは明らかと、それを心配するのです。息子へのお咎めなきことはありがたく思いますが、私へ、何か処罰をいただければ、序学士殿のお気持ちも少しは晴れるのではないかと」
「処罰というと?」
「向こう半年間で、この身の重さを十二分の一、減らせとご命令を賜りたく」
ハハハハ、と、王は笑った。
ルーシェ学博も朗らかな様子で笑っている。
「本当にノーヴェといい、ヴェンティといい……サンザの当主は面白い」
「恐縮でございます」
「ではそうしよう。必ず体重を減らせよ、ノーヴェ」
「しかと承りました」
机上の時計の結晶は半分ほど沈んだところだった。笑いがおさまると、王は砕けた様子で、珍しく頬杖をついて見せた。
「さて、これから余が話すことは、命令ではなく、提案である。気楽に聞いてほしい」
王の目が悪戯そうに細くなった。
むむ、これは何か来るぞと、ノーヴェは身構えた。
「ヴェンティはたしか、この春に十八歳になったな」
「はい」
「ルーシェ公の娘マージ姫は十九歳か」
「この夏に二十歳に相成ります、陛下」
「結婚してはどうか」
「ひぇっ?」
ノーヴェはひきつって思わず声を立て、横でルーシェ学博ものけぞった。
「提案である……強制するものではない。だが、余がこのように提言する理由を、両人ともよく考えよ」
「陛下、我が倅はてんでもって不埒者でして、学博様の姫君をいただけるような者ではありませんのです」
「そうか? いい男ではないか」
「ご冗談を!」
ノーヴェのこめかみからどっと汗が噴き出した。
「ルーシェ公はどう思う」
返事はなく、ルーシェ公は無言である。何かを思い出そうとするかのように、難しい顔をしていた。
ノーヴェののどは、小麦粉でも飲んだように乾きひきつってしまった。
「へへへ、陛下、それは今、今すぐにお返事申し上げねばならないので?」
「そうではない。が、ルーシェ公は十日後にたしか、北峰領の視察の予定であったな。その前に、双方の返事があると期待しよう。商団と学舎の融合は、この王都に暮らす商人、職人達の、ものの見方を変えるだろう。よく考えてほしい」
「私どもの娘を嫁がせること、同意いたします」
ルーシェ公がきっぱりと宣言し、
「ひょえっ、えっ?」
ノーヴェは二度目の悲鳴をあげた。
「陛下の近裔として、この国と民とのためにいかに身を処すべきか、幼きころより教え込んで参りました。娘もよく理解しているはずです。ご提案に従います」
ルーシェ公は静かに言い、彼らしい柔和な笑顔を見せた。
焦っているのはノーヴェだけである。
「……というわけだ、ノーヴェ。帰ってヴェンティと検討せよ」
「は、はあ、しかしながら陛下」
「何も、そなたが娶るわけではない、そう慌てるな」
「陛下、ご冗談が過ぎます」
「さて、時間だ。次の会議がある。散会」
宣言して王は立ち上がった。
ルーシェ公も品よく立って王を見送る作法である。王が完全に背を向けてしまってから、ノーヴェも慌てて立ち上がった。
「ルーシェ公様、あのその、姫君はこの話に」
「抵抗すると思いますが、説得します」
「そんな、それでは姫君がお気の毒で」
「いえ、いいのです。そのほうが娘のためです。私はむしろ、ヴェンティ殿のほうがお気の毒と思います」
「そ、それはどういう意味で?」
ノーヴェの問いにルーシェ公は答えず、やはり品のいいもの柔らかな笑みをたたえたまま、部屋から出ていった。
* パルメの夢 *
宿屋の一室で、パルメはうっとりと金の山を見つめていた。
三百枚、何度数えても嬉しい。サンザ家商団団統の、名前は忘れたが、『金三百枚』と言ったときの声色、表情まで、輝くように麗しい記憶である。
「これだけあったら、あたし……」
それなりの町で、手頃な店を買って、人を雇って商売ができる。酒場がいいかな、生地屋か小間物屋あたりでもいいなと、夢はふくらんだ。
あの宝石がもしも偽物だったりしたら、たいしたお金にはならず、場末の酒場の片隅でいんちき占い師でもやるしかないと、考えていたパルメである。
やっぱり、大事に持ち歩いてきて正解だったわと、パルメは金貨の山を優しく撫でた。
心のどこかに、軽く不安もあった。買い取ってくれた商団の、若い団統が、
『元踊り子さんは、暮らしに困っていたとき、何故、これを売らなかったのでしょうか』
と尋ねてきたのが気になった。
パルメは立ち上がって窓を閉め、部屋の入り口の扉の鍵がきちんと閉まっているかを確認し、それから机に戻って、金貨を一枚ずつ、丁寧に袋に詰めた。
悪いわね、セレス。
一応、謝ってみる。
だが、セレスはあの宝石の存在を知らないし、母親があれを持っていたことも知らないはずである。
さらに、あれの本来の所有者がセレスであることも知らない。
もうひとつ、あの宝石を、どこかの誰かの元へ持っていく約束があったとかいうことも、セレスは知らない。
青い宝石の秘密を知っていたのはセレスの母親と、パルメだけなのである。
セレスの母親は、本人の話では、元芸人一座の踊り子だった。たしかに村の祭りで彼女の踊りは村娘たちとはどこか違い、素晴らしく華があったとパルメは思う。
セレスの父親のほうは、パルメは見たことも、会ったこともない。わけあって、死に別れたと、元踊り子は言っていた。それもきっと、嘘ではないのだろう。
村人達は、美しくて踊りの上手なセレスの母親とその幼い息子に、適度な距離を持って接していた。親しすぎず、かといって疎外もせず、辺鄙な村なりのつきあい方の見本のようなものだ。
パルメは三日に一度、自分の家の牧場から牛乳を届けているうちに、彼女から少しずつ、話を聞く機会に恵まれたのだ。
不思議なのは、セレスの母親も、息子と同じセレスという名前であった、ということだ。
母親と息子が同じ名前だなんて、紛らわしくてしょうがない。
そのセレス母が五年前の冬の朝、息せき切ってパルメの牧場へ駆け込んできた。
「兵士が来たの」
と、彼女は肩で息をしながら言った。
「私が兵士を引きつけるから、お願い、パルメ。セレスを連れて逃げて」
「え、逃げるって、どこへ?」
「隣の村に、芸人一座が来ていると聞いたわ、座頭はビョルケという人なの。とてもいい人だから、頼めばセレスを守ってくれる、お願いよ、パルメ」
彼女は大きな瞳をうるませて懇願してきた。必死の表情から察するに、嘘や冗談ではないと、パルメにもわかる真剣さだった。
「それと、これを」
渡された小箱を見て、パルメは仰天した。
見たこともないような、大きな青い宝石の細工物が入っていたのだ。
「これは、私がいつかセレスを連れて、あるかたのところへ会いに行くとき、必要なものなの。これをセレスに、決してなくしてはいけないと、言い聞かせて、持たせてちょうだい。セレスがビョルケの一座の中にいれば、あのかたはきっと気づいてくださる。それまではこれを持っていることを誰にも知られてはいけないと、あなたから教えてやって」
「わ、わかったわ、で、セレスはどこなの」
「川沿いの、ガンボさんの店へ使いにやったわ。そこで林檎を食べながら待ちなさいと言ってある。お願い、パルメ、私は兵に捕まってもいいの、でもあの子だけは、逃がしたい。必ずビョルケの一座へ、セレスを」
話しているあいだにも、牧場の柵の向こうに、騎馬兵の姿が現れた。
セレスの母親はパルメの手に宝石の入った小箱を押しつけ、素早く立ち上がると、身を翻して、川とは反対の方向へ走り出した。
元踊り子の軽やかな足は、悲しいけれど、馬の速さにはかなわない。牧場のなだらかな丘の途切れるあたりで、セレスの母親の周囲を騎馬兵が取り囲むのが見えた。
パルメは牛の皮で作った背負い袋に宝石の小箱を押し込み、チーズいくつかと、食べかけのパンを放り込んで、川沿いの道へと向かった。
セレスはガンボの店の外の、小さな椅子に腰掛けていた。手には林檎がふたつ。食べてはいない。母親と一緒に食べるつもりなのだろう、そのよるべない姿を見たとき、パルメは彼女の人生では初めて、正義感のようなものが胸にわき上がるのを感じた。
母親の代わりにパルメが駆けてきたのを見て、セレスは驚いたに違いない。丁寧に説明している余裕はないと思われたので、セレスの手を引っ張って、半ば走りながら、あらましを話して聞かせた。
セレス、よく聞いて。あんたのお母さんのところへ兵士が来て、理由はなんだかわからないけれど、捕まった。あんたは私と一緒に逃げるのよと、山沿いの道を選んで隣の村へと逃げ延びた。
食いつぶした農民の姉弟のようなふりをして、ビョルケの一座を探し、そして座に潜り込んだのである。
だが、そこでパルメの正義感は途切れてしまった。理由はやはり、あの途方もない大きさの青い石である。
パルメは青い宝石を預かっていることを、セレスにも、座の者にも、話さなかった。
セレスの青い宝石はそののち五年のあいだ、パルメの心をとらえ、惑わせ続けた。
じっくり考えてみたけれど、パルメにはわからないことが多すぎた。
とにかく、セレスにせよ、その母親のセレスにせよ、不思議なまでに大きな宝石にせよ、謎だらけだ。座の芸人達に囲まれて村から町へと渡り歩きながら、パルメは注意深く青い宝石を隠し通し、そして考え続けた。
そもそも、セレスの母親は、何者なのか。踊りのうまさから考えて、元芸人一座の踊り子だったという話は、嘘ではないのかもしれない。
ビョルケの周囲をうろうろして、過去の芸人の話題が出ないかと、聞き耳をたててみたりしたものの、何もわからなかった。
セレスという名の元踊り子について踊り子のソフィに遠回しに聞いてみようかとも思ったが、下手に尋ねて青い宝石の存在が露見するのを恐れるあまり、ついに聞き出すことはできなかった。
そして謎のひとつ、『あのかた』とは誰なのか。ビョルケか。それともセレスを猫可愛がりしているムントンか。いや、違う、おそらくは、名前を明かすことがはばかられる誰かが、『あのかた』なのだ。
そして、おそらくは、『あのかた』とは、セレスの父親とは違う人物であり、簡単には会いに行けない身分の人間なのだろう。
『母親は元踊り子』
『謎めいた大きな青い宝石を持って会いに行く約束』
これらの条件に加えて、セレスという名前であること。
そう、セレスという名前が大事なのだ。
『あのかた』はセレスが芸人世界から名を現すのを待っているに違いない。
途方もなく大きな宝石だから、もとの所有者は庶民ではないとパルメは踏んだ。となると、怪しいのは王族、貴族、豪商ということになる。
最初のうち、パルメは座に加わって旅をするうちに、『あのかた』が、セレスを見つけ出すだろうと考えていた。万が一、セレスがどこぞの御曹司だったら、『あのかた』が迎えにきたときに、セレスを助け出して座に隠した自分の手柄を持ち出して、それなりの謝礼をいただこう、その程度に思っていたのだ。
しかし、座頭ビョルケは案外と堅実な人間で、セレスを町や村の興業に出さない。理由は『まだ幼いから、働かせてはいかん』。
冗談じゃないわよ。パルメにしてみれば、そうである。座の一員としてセレスという名を出してもらわなければ、『あのかた』は、セレスの存在に気づけない。
もうこうなったら、宝石を持って座を抜け、どこかで売り飛ばして金に替えよう。いや、それはやっぱりセレスに悪い、もう少し待ってみよう。と、迷ったり思い直したりしながら、五年が過ぎた。
そしてついに、セレスが芸人として世に名を知らしめる十三歳まであと少しというこの時期に、王都での興業という話が持ち上がった。
さらなる相克がパルメを襲った。
王都の中で、『あのかた』がセレスを見つけ出してしまったらどうなるか。
当然、宝石の所在を尋ねられるだろう。何も持っていないととぼけることはできる。
だが、そうなれば宝石を売ることはできなくなる。売り飛ばしたとたんに、本当の所有者にばれて、泥棒扱いされて捕まってしまうかもしれない。そんな危ないことはできない。
では、おとなしく宝石を差しだすか? セレスに付き添った五年間への、感謝の報酬はどの程度になるのか? 青い宝石を売り飛ばした場合、どれほどの額になるのか?
損だけは絶対にしたくない。昼も夜も、パルメは考え続けた。
宝石は手元にあり、売ればきっと儲けになる。しかし謝礼のほうは、感謝の言葉と薄謝で終わってしまう可能性もある。
『あのかた』というのが、死んでしまっている可能性も、ないとはいえない。
そうであれば、パルメは手の中に宝物を持ちながら、わびしい人生を送るだけだ。どう考えたって、それはまともじゃない。パルメは宝石を選ぶことにしたのだった。
もう、いいんじゃない? パルメは自分で自分を許した。
この宝石は、五年間セレスを隠し続け、守ってきたあたしへの、ご褒美として、貰ってもいい。いや、むしろ、そうでなくちゃ。だってあたしは、自分の家の牧場から、身一つで飛び出してセレスを逃がし、座に送り届け、そのあとずっと、姉代わりとして世話してきたんだもの。
王都の領門手前で、最後の野宿となった夜、パルメは小箱から青い宝石を取り出して、つくづくと眺めた。
小箱の底に接する面に、細かな彫り込みがあり、どうやらどこぞの紋章のように見える。 宝石の背面を路傍の小岩にこすりつけ、紋章を消した。こうすれば出所がごまかせる。 これでよし、ちょろいもんよ。小箱に宝石をもどして、パルメはにんまりした。
セレスって子は幸いちょっと抜けてて、今は綱渡りに夢中だし、この宝石の存在にも気づいていない。子どもながら律儀でもあり、座に入るときにパルメがついた嘘、『食いつぶして逃げてきた貧農の姉弟』のふりを、今までずっと続けてきた。
いつでも軽く微笑んでいて、じつは何を考えているのか、わからないような一面もあるけど、ただ単にぼうっとしてるだけかも。
大丈夫、あたしはこの石とともに座を離れる。誰にも悟らせない。好機っていうのは、まさにこういうことなのよね……。
性に合わない座の旅暮らし、かつての、きつくて単調な牧場の仕事も、全部捨てる。
取り立てて贅沢をしたいわけじゃない。ただ、好きなときに寝て起きて食べて、気ままに自由に暮らす。その最後の機会。だから決めた、誰がなんと言おうと、決めた通りにするんだわ……。
そして今日、パルメはついに、その夢を実現したのである。金三百枚と、もしかしたら追加でもっと金。なんて素敵なのかしら。
サンザ鴛鴦亭の小綺麗な一室で、小さな灯りひとつに照らされ、自分の幸せにうっとりと浸ってみたパルメだった。
* ティント爺の力量 *
元気に出て行った父ノーヴェが、夜になってしょげ垂れて帰ってきた。
ヴェンティの顔を見ると、
「うわおおおえええっ!」
それこそお化けでも見たような顔になって、ノーヴェは逃げるように自分の部屋へ入ってしまった。
「親父殿? どうしたんだ!」
ヴェンティが声をかけても、返事がない。扉のすぐ内側に立っているらしく、叩いても押しても開けられない。
「どうしたんだよ! 陛下からお叱りがあったのか、おい、親父殿、開けろ! やっぱ謹慎処分ってか? おーい!」
やや間が空いてから、
「謹慎はなしだ。心配するなヴェンティ」
力のない声で返事があった。
「あ、なんだ。謹慎はなし? それじゃ他に何か、処罰が下ったのかな?」
「わしが、向こう半年で十二分の一、体重を減らす」
「なんだそりゃ」
その程度のことがそんなに衝撃的だったのか、父の心はいまひとつ理解できないヴェンティである。
「若、どうなすったんです?」
ティント爺が怪訝そうに訊きながら近づいてくる。
「親父が王宮から帰ってきた」
「何か御処分がありましたかな?」
「痩せろってことらしい」
「ほう、お痩せになると……若、この爺が訊いて参りましょう、おどきくだされ」
長年の奉公でこうした場合の対処はヴェンティよりずっと慣れているティント爺である。
「頼むよ、ティント爺」
「お任せください」
ティント爺は呼吸を整え、三歩ほど下がってから扉に体当たりした。扉はなんなく開いてティント爺の身体は室内へ飛び込んでいった。直後に勢いよく扉が閉まった。
「年寄りのくせになんなんだ、あの馬鹿力」
何かしら呆れる気分のヴェンティである。何を話しているのか、扉に耳をつけて聞いてみたが、ぼそぼそとした話し声は不明瞭で、内容まではわからなかった。
さほど時をおかず、扉が開いた。
「あ、どうだった? 親父殿は何か言ったか、ティント爺」
勢い込んで問いかけると、ティント爺は険しい顔でヴェンティを睨んだ。
「おめでたい話でございますよ、若」
「親父が懐妊したってか」
「そうです」
冗談なんだからもう、爺はこれだ。と、ヴェンティは噴き出したが、ティント爺はにこりともしない。
「で? なんだって? 本当のところを、手短に頼む」
「思えば十八年前、若がお生まれになってからというもの、この爺はそれこそ寝食を忘れて一途に若をお育て申し上げ」
「うんうん。感謝してる」
「うんちのお世話から着替え入浴、夜泣きの若を抱いて深夜の散歩」
「そのへん省略してくれ。親父殿は王宮で何を言われてきた」
「若。結婚しましょう」
「爺と?」
「この爺には妻がおります、あしからず」
「うん。残念だ。で、誰が、誰と、結婚するんだって?」
「若と、学舎学博ルーシェ公ご息女マージ様とです」
ヴェンティはぽりぽりと頭を搔いた。
「うんうん。冗談はそのへんで終わりにして、親父殿が王宮で何を言われたのか、教えてくれ」
「大旦那様は王宮において、陛下から、若とマージ姫を結婚させるようにと、ご提案を承って来られたのです。これは冗談ではありません」
ヴェンティは口を開け、しばらく開けたままにし、ティント爺が指で顎を押して口を閉じさせてくれた。
そのまましばし、二人とも無言で見つめ合った。
「嘘……」
「ではありません、若。それで大旦那様があのように」
ティント爺は部屋の中を指さした。
長いすに座って半ば呆然と、宙に視線を泳がせているノーヴェの姿が、そこにはあった。
「えと……陛下から、ご提案。ってことか。ご命令ではなくて」
「さようです。ですが、ルーシェ公は即決なさり、このお話を受けられたそうで」
「げっ」
ヴェンティは両手で口を押さえた。
ティント爺はものすごく怖い顔になり、下からヴェンティを睨みつけてくる。
「若、よっくお考えくだされ。これはえらいことですぞ。お相手は王族です。ルーシェ公は陛下のお従兄であり、ただいま陛下にはお子がおられない。このまま行くと、ルーシェ公が継承権を得られて、ご息女マージ姫はいつか女王様です。そこのところ、よくお考えなさいませ」
「いやっ、いかん。そんなだいそれた相手と結婚なんて、絶対だめだ。王族の一員になんてなったら商売ができない」
「むろんです」
「こ、断ってこよう、断ればこんな話はなかったことに」
ティント爺はヴェンティの両手首をがっしりと掴み、軽く揺さぶった。
「こういうことは、姫君から断っていただかねばなりません、若のほうから断ってごらんなさい、姫君に大恥かかせたことになります。そしてマージ姫様が、万が一即位なすった日には、若は結婚話を断った不埒者として、縄でぐるぐる巻きにされて荷車にくくりつけられて、崖から落とされますぞ」
「うわーん、いやだ、そんなのいやだ、爺、ティント爺、なんとかしてくれ、頼むよ」
想像しただけで、泣きたくなってくるヴェンティである。
「お受けするしかないと思います、なるべく早く」
「やだよう、姫の夫になんてなりたくないよう」
「お受けしたのち、あちら様から断っていただくのです、若。どうあっても破談にしたくなるような、そういう状況に持って行けば良いのです、知恵を使いましょう」
「知恵?」
「見目良く、気立てもよく、デキる男であり、なおかつ気働きの効く、相応の身分で年頃の、色気ある男を探すのです」
「俺じゃないか」
「若の他に、ですよ。そして姫とその男との出会いを画策する」
「あ、なるほど」
「姫が、その男にゾッコンとなって、サンザのヴェンティなんて目じゃないわとお思いになれば、この話は流れます。陛下のお話はご提案であり、ご命令ではありません」
「爺、頭いいな」
「すべては若のおん為……」
ヴェンティとティント爺は互いの手を握りしめ、見つめ合った。が、凝視して嬉しい相手でもないので、咳払いなどしながら目をそむけ、手を離した。
「親父殿、聞いた? 今の話」
室内に問いかけてみると、ノーヴェは長椅子の上に寝そべっており、返事がなかった。
「親父殿? どうした、具合でも悪くなったか」
「寝ましたな」
ティント爺が冷静に言った。
「寝た? 嘘だろ?」
ノーヴェの部屋の鐘時計が、チーン、チーンと澄んだ音をたてた。
サンザ家当主ノーヴェの就寝時刻を告げる音である。
「寝たか……」
繊細なんだか、図太いのか、父の心はいまひとつわからないヴェンティだった。
…セレスタイン物語 2章 へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
