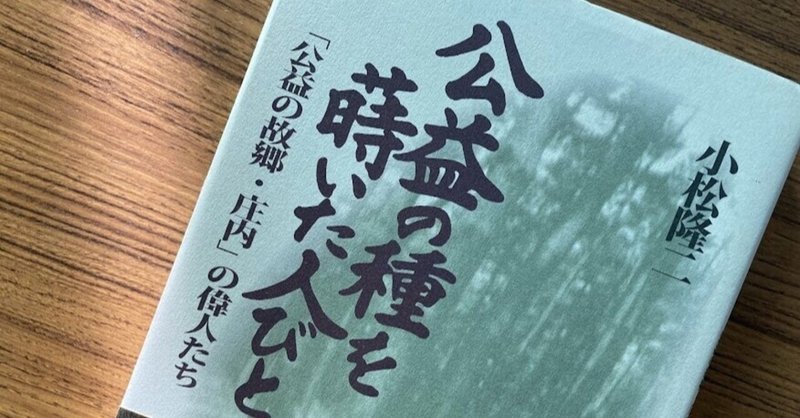
悩める学問の「自画像」――小松隆二『公益の種を蒔いた人びと:「公益の故郷・庄内」の偉人たち』(東北出版企画、2007年)評
庄内地域は「公益の故郷」であるという。その始まりは、江戸期の酒田の豪農=豪商・本間光丘。砂防林のクロマツ植樹など公益活動に幅広くかかわった彼が先導者となって、その後の庄内は、公益活動にかかわり公益精神を宿す人びとを、主に明治期、数多く輩出してきた。
当時は国家による行政サービスが未整備ゆえ、今日なら公的機関が実施する社会政策のほとんどが、地方名望家たちの自助努力によって担われており、その背景にはそうした行為を支えるノーブレス・オブリージュ(高貴な者の責務)の精神が存在した。本書は、そうした「公益」の体現者であった庄内の地域リーダーたちを取り上げた「公益偉人伝」である。
著者は東北公益文科大学(酒田市)学長。開学五年目の「公益学」の中間成果であるという本書の議論は、しかしながら、学問的に見たときに幾つかの問題点を含んでいる。第一に、本書のような地方名望家はおそらくは日本全国どこの地域にも存在する。とすれば、庄内のそれが他と比べてより「公益的」とする根拠が不明だ。単なる地域学ではない「公益学」を名乗る以上は「公益」概念をめぐるより厳密な定義が必要であろう。
第二は、本書で「公益」の担い手として取り上げられているのは専ら地方名望家(持てる者)のみ、という問題である。例えばワッパ騒動のように、明治期の庄内には民衆による異議申し立て行動も存在したわけで、それら民衆運動を下からの公益活動として記述することも可能であったはずである。あえてそうしなかったのだとすれば、それは公益へのアクセスから民衆(持たざる者)を排除した歴史観である。ここに見られるパターナリズム(家父長主義)に問題はないか。
とはいえ、民間公益活動の資金源を有力企業(持てる者)のCSR(企業の社会的責任)に頼らざるを得ないような現状からすれば、持てる者のノーブレス・オブリージュを喚起する物語が必要なのは確かで、それを「地域の偉人」なる物語を介して調達しようというのが本書の真のねらいだと深読みできなくもない。地域に寄付文化を敗退させるための「あえてする」物語。とすれば本書は、学問や研究というよりは、むしろマーケティングや広告の言説により近い。
ここには、「公益学」が抱えこんでしまった、ある困難が露呈している。学問的真実の追究か、特定地域のニーズか。価値中立志向か、特定価値志向か。公共性か、地域性か。こうした二者択一に通底するのは、学問(大学)と地域との関係性のありかたをめぐる難問である。本書は、異なる二つの価値に引き裂かれた「公益学」の悩める自画像そのものだ。とはいえ、そうした葛藤や揺らぎこそ、「公益学」というものの、そしてそれを採用した庄内という地域の、ほかにはない面白さなのかもしれない。(了)
※『山形新聞』2007年10月20日 掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
