
美観地区の会社が考えるこれからの観光戦略
こんばんは。
倉敷の美観地区で『株式会社行雲』という会社をやっている犬養といいます。
今日は「日本インバウンドサミット2020」というオンライントークイベントに登壇しました。
僕が登壇したのは中国エリアに関するトークセッションだったのですが、そのトークの準備をするにあたり、改めてインバウンドや観光に関する考え方を整理することができました。
整理できると何がいいって、これもnoteの #オープン社内報 の使い方として、社内に僕が考えていることを整理して伝えやすい、っていうことですね。笑

コロナ流行以降、インバウンドに関しては正直なところやや後回しにしてしまっていたところがあります。
戻ってくるのがまだ半年〜1年はかかるため、まずは当面の資金調達や社内の整理、そして例えば国内ECの強化などを優先していたので。
ただ、今後必ず戻ってくるインバウンド観光客のための準備にアクセルを踏むという面でも、今日のイベントは良い機会を与えてくれました。
機会を与えてくれた「MATCHA」の青木くん、そして一緒に登壇してくださった中国エリアのキーパーソン3名の方にはとても感謝しています。
そういった機会をもらって、改めて観光やインバウンドのことを考えました。
ところどころ、自己紹介でつかったスライド画面も使いながら整理してこのnoteに書いておこうと思います。
観光で本質的に大事なこととは

観光で大事なこと、僕は「地域の資源 × ユニーク or ハイクオリティ」だと思っています。
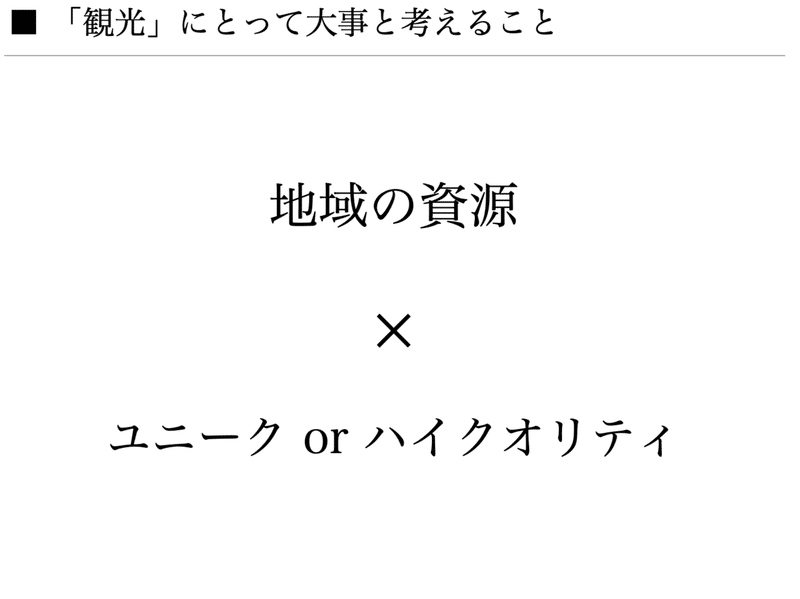
地域の資源というのは街並み、文化、伝統、歴史、食材など。
このあたりの分類は、デービッド・アトキンソンさんの著書にもよく書かれています。
「ユニーク」や「ハイクオリティ」というのは、例えば農業が盛んな日本、野菜や果物が地域の大きな資源となっているところは多いです。
ただ、それを普通のジャムにしても、それをやっているお店は無数にあるので、なかなかそれでは来てもらう理由・買ってもらう理由ができません。
そこで例えばジャムにひたすら特化して日本で最もジャム好きが通いたくなるような専門店を作るとか、その地域のトップシェフが他にはないレシピのジャムを作るとか、そういった要素が必要になる。
という意味で、「ユニーク」や「ハイクオリティ」と書いています。
インバウンドで弊社が狙いたいターゲットは、完全に海外からの個人旅行(FIT、Foreign Independent Tour)。
団体旅行ではありません。
「ユニーク」や「ハイクオリティ」に磨きをかけて、個人の旅行者に地域をより深く知ってもらう、学んでもらう体験を提供したいというのが基本方針です。
また、その際に決して安売りはしないでいたいと思ってます。
日本の観光は安売りし過ぎだとも思っているので。
コロナ後に必ず起こる観光・インバウンドバブル

コロナが収束した後、一時的に観光やインバウンドのバブル的な賑わいは起こると思います。
ただしそこは弊社としてはあまり狙っていません。
それよりも、観光が平時の当たり前のものになったときにいかに魅力的な選択肢となっているか、という点を考えています。
バブルによる観光消費は表層的なものでしょうし、それは観光地の側にとっては目先の売り上げにはなれど、より強いファンは生めないからです。
中国エリアの観光文脈の例

今回のトークセッションは中国エリアでの方々とお話をしたので、少し中国エリアの中での話をしてみます。
ただ倉敷に来てもらおうと思っていても限界はあり、、周りの地域とも連携した取り組みをするべきですし、観光客の視点からみてもいくつかの都市や町を回ることでより多くの発見がある体験になりますよね。
観光文脈の例 1. 歴史ある街並み
例えば今すでにある観光ルートとしては倉敷、尾道、宮島というルートがあります。
これはわかりやすいですよね。
昔ながらの日本を分かりやすく感じられる町並みがあり、その裏に歴史と文化があることも想起しやすい町を結ぶ線というのは確実にあります。
観光文脈の例 2. アートをめぐる
直島、豊島など瀬戸内のアートな島々から美観地区の大原美術館をめぐる方はすでにとても多いですし、岡山市は「岡山芸術交流」というアートイベントで観光客を大きく増やしました。
美術館が大好きな僕から見ても、まだまだここは提案の余地が大いにあると感じます。
現状ではまだ、上で挙げた代表的なルートに多くの人が留まってしまいがちなんですよね。
例えば岡山や倉敷を起点に島根の『足立美術館』に行くとか、岡山県の中でも『奈義町現代美術館』という素晴らしい現代美術館があったり、そういったアートをめぐる旅です。
観光文脈の例 3. 手仕事のものと民藝
以前、うちの『ゲストハウス有鄰庵』で僕が話したゲストさんで、とても印象的なフランス人がいました。
彼女は児島の繊維のものづくりから、瀬戸大橋を渡って徳島の藍(インディゴ)を作る現場を見たいとフランスからやってきていたのです。
インバウンドの方は、日本人でも多くの人がまだ知らないような、それでも確実にその土地の特色としてあるものを見つけに来てくれます。
(特に欧米の方はそういう傾向が強いです)
似たようなクラフトの面で僕がとても推したいのは、民藝運動と手仕事をキーファクターにした観光文脈です。
例えばうちの会社でも「暮らしの宿 てまり」という手仕事のものを主役にした宿をやっていますが、それは倉敷が民芸運動の拠点となった地からです。
美観地区には日本で二番目にできた民藝館(倉敷民藝館)をはじめとして、今も多くのうつわ屋さんがあります。
その民藝運動は島根や鳥取など山陰にも波及していて、『出西窯』など立派な窯元も多く存在しています。
バーナード・リーチや柳宗悦が倉敷から山陰も訪れて、その思想を広めていたんですよね。
すると、手仕事のものやクラフトというキーワードをもとに、倉敷から特急やくもにでも乗って島根や鳥取をめぐる観光文脈が浮かび上がってきます。
地域の歴史や特徴を活かしたお店・スポットが増えてほしい
ここで何が言いたいかというと、そのように地域に昔からある伝統や文化をストレートに抽出したスポット、飲食店、宿、窯元などが増えると、それらに興味がある人が回る観光ルート(文脈)が半ば自動的に浮かび上がってくる、ということです。
(もちろん浮かび上がるのが半ば自動的とはいえ、それらを紹介するPR活動も必要ですが)
それだけに、それぞれの地域で大事なことは、最初に書いた「地域の資源をいかにユニークなもの、もしくはクオリティの高いものにできるか」です。
そういった観光文脈を、文化や資源や食などいくつも用意しておくことが、その地域の観光的な豊かさを生み何度リピートしても新しい発見があるエリアになることにつながると思っています。
なので民間の会社としてうちができることとしては、まずは自分たちが地域の資源を生かしながらユニークなもの、ハイクオリティなものを作り上げること。
そして、同じエリアの中でそういった同じ志を持つ仲間を増やすこと、です。
行政によりしてほしいことをリクエストするなら、そうした民間で野心ある会社や個人の取り組みをサポートしてくれる体制づくり、でしょうか。
そうしていくことで観光の面で魅力的なエリアは作られていくのではないでしょうか。
もちろん倉敷や中国エリアが他エリアに比べて勝ちたいというよりも、日本各地でそういった地域のものを良い形で生かした場所がどんどん増えると、僕自身が国内旅行する時ももっと楽しくなるだろうなと思っています。
以上、こうして書いてみるとまだまだ当たり前のことを書いているようですが、改めて弊社のインバウンドや観光における基本戦略の整理としても書いておきました。
==================
これを書いた僕のTwitterです。
よかったらフォローしてもらえると嬉しいです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
