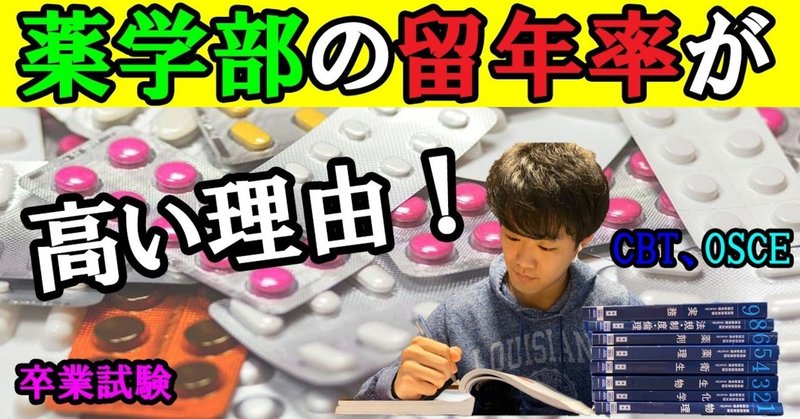
薬学部が留年率高い理由!
薬学生TAKUYAです。
薬学部の留年率は他の学部に比べて高いです。6年生になると学年の約半分は留年生になるほどで自分の大学では350人中170人は留年生でした。
ではなぜ高いのでしょうか?

そのことについて自分なりに考察してみようと思います。
それではレッツゴー!
①科目数が多く1科目の内容が濃い
薬学部ではかなり多くの科目数があります。すべての学年で毎日1限から始まり、夕方までみっちり授業が入っているくらいです。

薬学部で単位を取得するには、ほとんどすべてが試験でレポートや資料持ち込み可能な試験がほとんどありませんでした。
そのため、すべての科目の知識をしっかりと勉強しないといけません。

また、すべての科目の試験を行うのに1科目の内容がすべて濃いです。
1科目、約13時間の講義があるのですが教科書1冊+13時間分のプリント量があります。
全てに目を通すには試験直前だけでは絶対に終わらない量なので早めに勉強を始めないと留年する確率が高くなります。
②大事な試験が多い
薬学部には大事な試験が多くあります。
その試験に合格しないと一発で留年することがあります。
✅総合演習試験
4年生で行う試験で1年~4年までに勉強した内容、すべての範囲の試験を行います。

約4科目に分けて試験を行います。
①物化生
②衛生法規
③薬理病態
④薬剤実務
もし、この4科目のうち1科目1点でも足りない場合留年が決まってしまいます。
この試験で躓いて4年生で留年する学生が多くいます。
※総合演習は大学ごとで形式が異なる場合があります。
✅CBT
CBTは4年生で行う試験で総合演習試験とは違い、すべての範囲の試験になります。
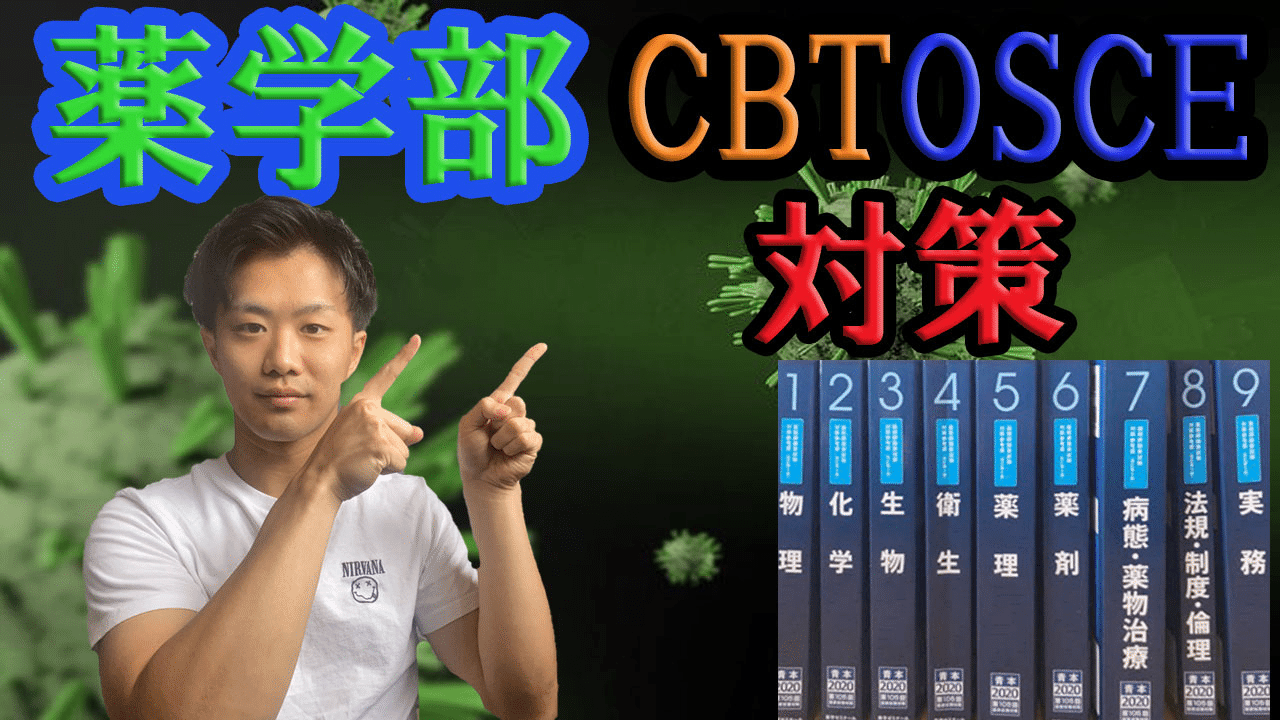
また、この試験は全国すべての薬学部で試験を行い、個人個人で解く問題が違います。問題はパソコンで行う仕組みとなっています。
試験の難しさは薬剤師国家試験の必須問題に近いレベルが出題されるため、ある程度勉強すると合格することができます。
98%ほどの学生が合格しますが全ての範囲を勉強する必要があるので今までの期末試験をギリギリで合格してきた学生は心が折れかけます。
✅OSCE
OSCEはCBT同様、4年生で行う実務試験です。
5年生の薬局実習や病院実習に行く前に身につけるべき技能を試験されます。
散剤、軟膏、水剤、服薬指導、監査など
調剤、調剤に必要な計算、患者さんとの接し方などを試験されます。

毎年、試験内容が異なるため全ての技能を身につける必要があります。
試験中は放送で教室移動、試験開始、終了を支持され、移動中も他の人と話すのは禁止されています。そのため、かなり緊張する試験です。
試験中は審査員が数人いて前後で評価を受けます。
✅卒業試験
6年生で全ての単位を取得すると卒業試験を受けることができます。
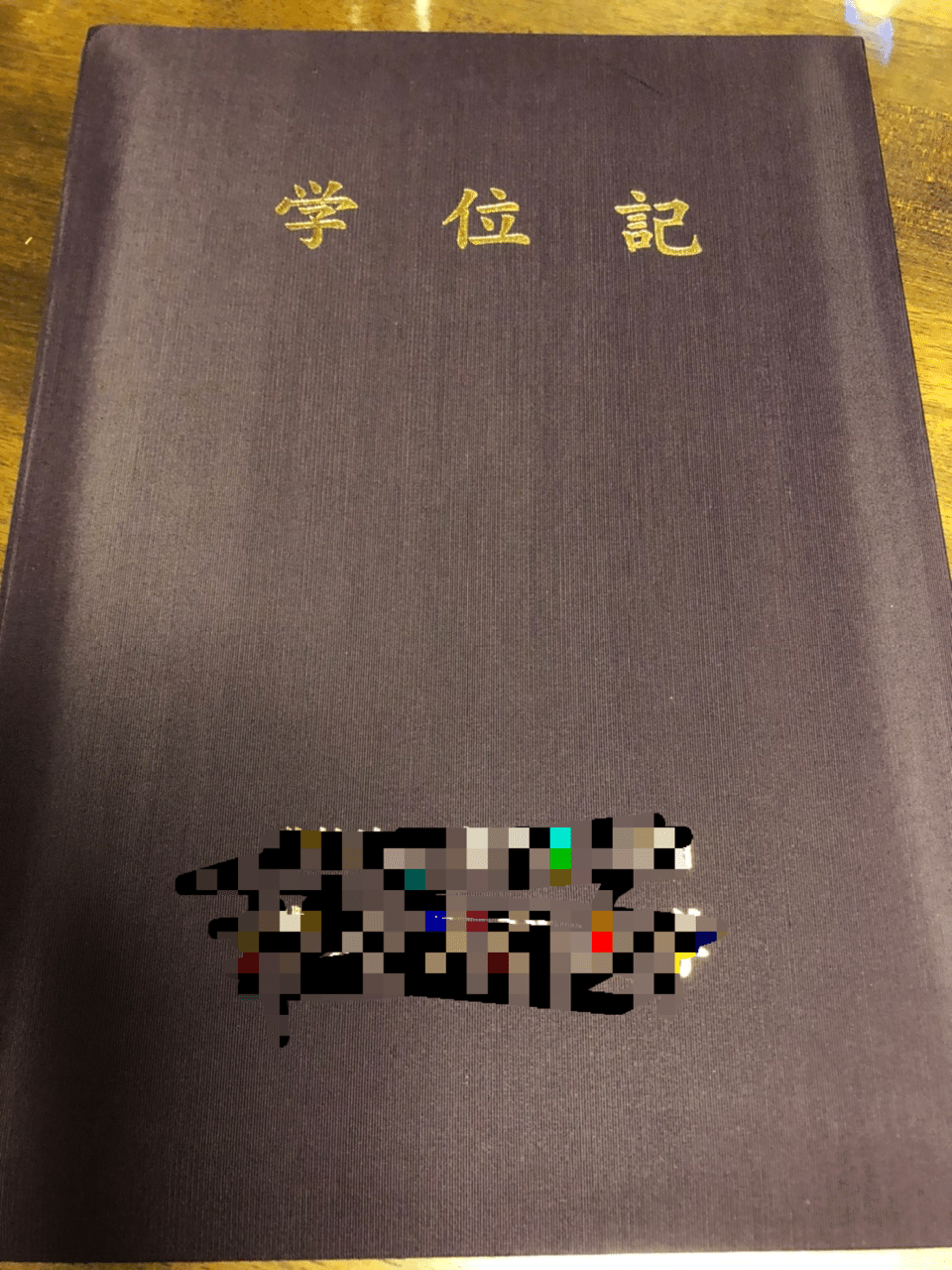
単位や卒論をクリアしていてもこの試験で不合格になると一発で卒業延期になります。試験形式は大学によって異なります。
試験難易度は薬剤師国家試験より難しいイメージです。
大学としては国試合格率を上げたいため難しくし、かなりの人数を落とします。
自分の大学では去年、約半分の学生が卒業延期になりました。
※卒延率は大学ごとで大きく異なります。
③まとめ
今回は薬学部の留年する理由について考察しました。
記載したように試験の難易度が高く、大事な試験が4年生から頻繁に行われるのが留年率を高めている主な要因だと考えます。

薬学部に入る前は留年率が高いことも知らなかったため、薬学部にはいってから驚きました。
薬学部に入る前にこのことを知っていたら大学選びをかなり慎重に選んでいたと思うので今回記載しました。
少しでも皆さんの役に立つと嬉しいです。
Twitter、YouTubeもやっているのでよかったらフォロー、チャンネル登録お願いします。
それでは、バイバイ菌!
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
