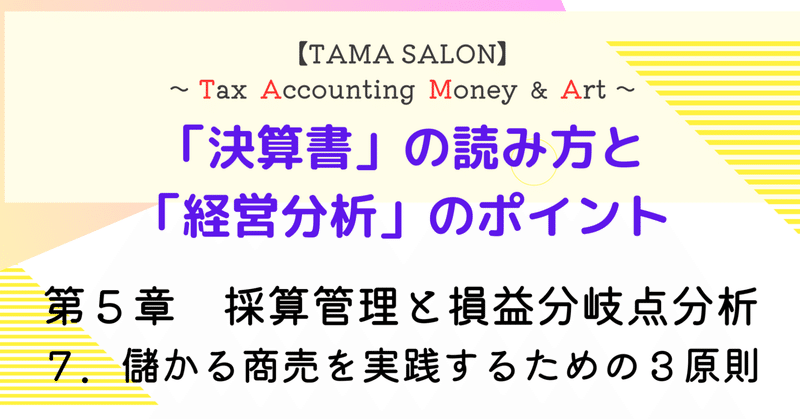
第5章 採算管理と損益分岐点分析
7.儲かる商売を実践するための3原則
儲かる商売を実践するための3原則
損益分岐点図表には、売上高ライン、総費用ライン(固定費も含んだ変動費の右上がりの傾き)、固定費ラインの3本の線がありました。

この図表を基に考えれば、もっと儲かる商売を実践するためには、
①固定費ラインを下げる → 固定費の額を節約する
②販売単価を上げる → 売上高ラインを右上にトントンと上がっていく
③変動費率を下げる → 総費用ラインの傾きを下げる
という3つの方策があることが分かります。
「いちご大福屋🍓」で考えてみましょう。
まず、固定費の額の節約です。
売上高が増加しても、その増加額を超えて固定費が膨らまないようにし、売上高が減少する場合は、その減少額以上に固定費の削減に努力します。
もしも、固定費500を400に削減できたならば、利益は100増加します。
節約は第三の利益ですね。
ただ、もちろん、ムダなコストがないか目を光らせることは大切ですが、重箱の隅をつつくような縮小均衡的なコスト削減では疲れてしまいますね。大胆かつ効果のあるコスト構造の見直しが求められます。
また、人件費削減は「最後の砦(とりで)」として、他の固定費を見直した後に考えるべき項目です。
せっかく美味しい「いちご大福」を作れる腕前の職人さんが、給料引き下げのためにライバル会社に引き抜かれたのでは、元も子もありません。
続いては、1個当たりの販売価格を上げる高付加価値戦略です。
これまで1個100円で販売していた「いちご大福」を150円で販売します。
当然ながら、同じ製品の値札だけ張り替えて値上げして売るのではなく、1個あたり30円だった材料費を、高級の苺、餡に変えて45円とします。
材料の品質を見直すことで、より一層、美味しくなったいちご大福を1個150円で販売することとするわけです。
変動費率は値上げ前と同じ30%(=材料費45円÷売上高150円)ですが、10個作ったいちご大福のすべてが売れた場合には、限界利益は1,050円(=売上高1,500-変動費450)となります。
固定費が同じ500のままだとすると、儲けは550円(=限界利益1,050-固定費500)となります。
高付加価値戦略は利益の貢献度がもっとも高いことが分かります。
安さに重きを置く価格競争という消耗戦での勝負だけではなく、お客さまが価値を認める付加価値の高い製品・サービスを提供し続け、適正な値段を通す企業力も大切です。
最後は、1個当たりの材料費を下げる、つまり変動費率の見直しです。
苺や餡などの1個当たりの材料費を、現状の30円から25円に見直せれば、変動費率は25%に低下します。
この場合、「いちご大福」が10個売れた場合の限界利益は750円(=売上高1.000-変動費250)となります。固定費が同じ500のままであれば、儲けは250円(=限界利益750-固定費500)と若干ながら増加します。
ただし、材料の品質を下げて「いちご大福」の味が落ちたのでは、お客さまが減少してしまいます。
一度去ったお客さまを、再びファンにするのは難しいので品質低下を起こさないように注意が必要です。材料のロスをなくす、大量仕入で付随費用を節約するなど変動費率を見直す余地がないか検討します。

損益分岐点分析図表アプローチで考えると、儲かる商売を実践する方策は
①固定費の見直し
②高付加価値戦略で値段を通す
③変動費率の見直し、 の3つです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
