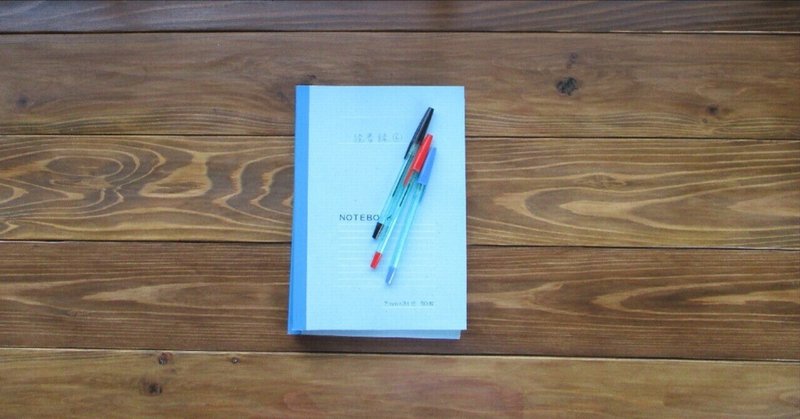
川上未映子「すべて真夜中の恋人たち」読書感想文
供述調書には種類がある。
まず1日目は、身上調書となる。
どう生まれて、どう育ち、どのように学校に通い、どのようにして社会で仕事をして、どのように生活していたのかを時系列で書いていく。
もちろん、話したくないことはそう言えばいいし、以外に公平で、良い面もふんだんに書かれるし、悪事については弁明も盛り込まれる。
次から事件の供述調書になる。
まずは、逮捕された直後に『弁解録取書』を作成するのだけど、それを補足する供述調書。
次に証拠合わせの供述調書。
刑事が証拠を見せるのを認めていく流れになる。
容疑者が自供している最中という形になっている文章に、突如として次の一文が挿入される。
『この時、本職は、当署○○課司法警察員、巡査部長○○が作成した[写真No.○]のコピーを示した。』
そのあとに『まちがいありません。これは私です。』などと認めていく様子が、ライブ感を持って書かれていく。
取調室の容疑者が、いきなり独白した体になっているので、文体は話し言葉となる。
ですます調で、一文は短めで、句読点は多め。
主語は省くことはない。
「あれ」とか「それ」という語句はないといっていい。
カタカナ言葉は少ない。
漢字は多用される。
・・・ また余談が過ぎた。
要は、硬質な文体が好きということである。
はっきりと覚えているくらいだから。
1冊目の川上未映子
官本を選ぶ時間は5分。
今日は “ 偶然 ” で選ぶことに決めている。
まったく知らない作家を、まったくの偶然で5分の間に選ぶ。
方向としては、気分転換として読める本がいい。
かつ、なにがなんでも完読してやると興味が持てない本。
5冊目ほどで手にしたこの本の表紙は、いかにもつまらないテイストがするし、ピクリとも興味が沸かない。
しかもだ。
表紙裏の紹介文には『究極の恋愛』とある。
自分データでいえば、こんなことを堂々と紹介文に書いてあるということは、かなりの確率で究極ではないとみた。
よほどつまらない本だ。
湊かなえパターンか。
ムリだったら、あっさりと放り投げればいい。
よって、川上未映子とやらのこの本は、挫折したとしてもカウントしない。
なかったことにする。
何ページまで持つか・・・と意地わるく借りてみた。

川上未映子に謝罪しなければ
ひらがなを多用した文体が好きになった
よいではないかぁ!
なによりも文体がいい!
はっきりと “ いい ” と感じる。
なんてたってリズムがいい。
文字を目で追っていて楽しさを感じる。
受刑者となって性格が歪んだようだ。
読む前の本に対してまで、悪意を抱いてしまった。
それを実感してしまった。
とにかくも、字ズラもいい。
漢字を開くというのか。
多めに、漢字をひらがなにしている具合がいい。
主人公の内心がページにびっしりと続くのだけど、すらすら目に入ってページが進んでいく。
自分は硬質な文体が好きではなかったのか?
漢字が多用された昭和な文体が好きではなかったのか?
でも、こういう柔らかいというか、しなやかというか、さらさらした文体も好きだったんだ。
発見した気分になった。
セリフもしっかりと重量感がある
校閲の仕事をする主人公の日常が、静かに伝わってくる。
空気が、よく伝わってくる。
日常の描写など、飽きが感じることも多々あるのに、この本はそれがこない。
こうもよく感じるってことは、今日は体調がいいのかな・・・とは思ったけど、いつもと同じだ。
むしろ、シモヤケは悪化してるくらいだ。
やっぱ、文体なのだ。
セリフもいい。
重量がある。
登場人物の言が妙に響く。
リアル感がないセリフばかりの小説ってあるけど、・・・小説だからいいのだけど、ともかくこの本では、ああ、こんな会話が今もどこかでされているのだなと思わせる。
苦い反省をさせられた
主人公は、一言でいえばイタい女なのだけど、その不安定な様子が可愛らしく思えてくる。
2年かけて失恋を忘れていく結末に「よかったなあ」という気持ちが交じったモヤモヤが心に残る。
で、自分が自分で残念である。
女性に対して、こんな余裕ある気持ちが、10代や20代のときに欲しかった。
檻の中だからか、ただ単に年をとっただけのか、どちらもだと思われるけど、ここのところ、恋愛小説を読むと反省しか沸いてこない。
コンクリの天井を見上げた。
で、読書録の続きを書いた。
登場人物
入江冬子
34歳、独り暮らし。
フリーランスの校閲者。
友人は少ない。
というよりも、まったくいない。
性格は引っこみ思案。
はっきりしない、他人に意見を言えない。
どころか、普通に会話することさえもうまくいかない。
が、校閲の仕事はそつなくこなす。
仕事している以外は、寝ているかボーとして過ごす。
なにか趣味をとカルチャーセンターにいき、三束と出会い、恋愛感情を持つ。
仕事量を減らすほどの恋の病となる。
クリスマスイブの誕生日には、2人でお祝いする約束もするが、三束からは別れの手紙が届く。
三束
58歳。
独身。
数年前に食品工場の職を失う。
入江冬子には、高校で物理の教師をしていると嘘をつく。
その嘘を除けば、誠実な態度で接する。
喫茶店でのデートを重ねる。
物理の本、クラシックのCD、などを貸したりする。
入江冬子は、緊張のあまりに、昼間から酒を飲んで現れたり、突然立ち上がって帰ってしまったりしたが、三束は温和に寛容に接する。
が、物理の教師という嘘が心苦しくなり、謝罪と別れの手紙を入江冬子に送る。
石川聖
大手出版社社員。
誰に対してもハッキリと意見を言い、頭の回転も早い。
仕事もできて美人でもある。
校閲の手伝いとして顔を合わせるようになった入江には、フリーランスになることを勧める。
その後も担当者として仕事を発注する。
入江と同じ長野県出身の同い年。
それ以外には、2人の間には共通点と呼べるものがなく、性格も大きく異なるが、仕事以外でも関係は続いている。
浪費癖も少々あり、もう着なくなったブランド服や下着をダンボール1箱分プレゼントしたりする。
飲みにも誘ったり、様子をきくために電話をしてきたりと、面倒見よく接する。
恭子
40代前半。
入江が勤めていた出版社の元編集者。
独立して編集プロダクションを経営。
入江を心配して、石川の悪評を伝えてくる。
それによると、相手の状況も個人差も考えない言動に、もう一緒に仕事をしたくないという人も多い。
友達もなく孤立している。
男癖がわるい。
仕事相手の男とも、同僚や後輩の交際相手でも、お構いなく関係を持ってしまう。
ちょっと気に入った男とゲーム感覚で寝ておしまい、というのを延々と繰り返している。
自分の生き方や考え方を正当化して、日々強化していくために、ふんふんいって話を聞いてもらう人がいないと彼女自身が困るからと、入江に忠告する。
ネタバレあらすじ - 供述調書風
※ 筆者註 ・・・ よくよく読書録を見返してみると、供述調書風の文体になっているのです。せっかくの川上未映子のいい文章が台無しになってるのです。おそらく、川上未映子によって深く反省させられたから、こうなったと思われます。が、そのままキーボードしました。内容には忠実です。
入江冬子 34歳 身上について
私は、自営で校閲の仕事をしていました。
毎日、ひたすら原稿を読んで、訂正するのです。
そのため、日常には、職業病が出てました。
テレビが見れないのです。
なぜかというと、画面の下に流れる字幕の間違いが気になり、それを直せないのが苦痛になるからです。
それに、私は、チラシを見ると、誤字脱字を見付け出すのが、癖となってました。
また、本を手にして開くと、言葉の使われ方に間違いを見つけて、気が滅入るのです。
ですので、本を読んでみても、事実誤認が気になってしまって、内容が頭に残らないのです。
カルチャーセンターでの出会いについて
私は、仕事以外では、今までに何をしたのだろうと、自身でもわからないほど静かに過ごしていました。
ですので、カルチャーセンターに行ったと思います。
向かったカルチャーセンターのロビーで、私は、三束さんと出会ったのです。
そのときの私は、どの教室にしようかと迷うばかりでした。
そして、緊張のあまり、水筒にいれて持参した日本酒を飲んでいたのです。
気がつけば、トートバッグが盗まれていたのです。
この盗難については、警察へ被害届は提出しておりません。
私は、被害届がよくわからなかったからです。
たまたま居合わせており、見かねた三束さんから、1000円を借りたのです。
この1000円は、返済するつもりでした。
ですので、三束さんとは、喫茶店で会う約束をしました。
返済も行ったのです。
交際内容について
初夏だったと記憶しております。
1000円の返済後も、三束さんとは、何度も喫茶店で会いました。
私は、恋愛感情を抱いたのです。
冬になったころは、三束さんの誕生日を祝うために、レストランで食事をするまで親しくなったのです。
会った日の、冬の日の、別れ際のことです。
私は、三束さんへの好意を伝えたのです。
そして、途端に泣き出してしまったのです。
最後に泣いたのは、もう、思い出せないほどの、久しぶりの涙だったのです。
「わたしの誕生日をいっしょにすごしてくれませんか?」
「・・・」
私からの泣きながらのお願いに、三束さんは、何度もうなずきました。
私の頭のてっぺんに手の平を乗せて、微笑しているようでもあったのです。
私は、誰かに見守られながら泣くというのは、こんな気持ちがするんだ、と初めて知ったのです。
嘘の露呈から難詰に至る経緯
三束さんと別れてからの、アパートまでの帰り道でした。
先ほどの、手の平の感触を思い出して、胸が痛くなるほどのうれしさがありました。
熱に浮かされるような喜びでした。
私は、スキップするように歩いたのです。
すると、自宅の前に誰かがいるのです。
石川さんでした。
電話も出ず、メールの返信もないのを心配して、石川さんは見舞いに訪れていたのです。
私は、気まずい思いをしました。
どうしてかというと、ここのところ、三束さんのことを考えてばかりで、なにも手につかなくなり、偏頭痛がすると嘘をついて仕事を減らしていたからです。
石川さんとの関係は、以前にお話しした通りです。
私とは親しかったのです。
石川さんは、私の嘘には気がついたのかもしれませんが、気にしてない様子でした。
私は、気まずい思いをしながらも、石川さんとは、部屋で2人きりになったのです。
石川さんは、さっそく訊いてきました。
「会っていたのは男の人でしょ?」
「・・・」
私は、黙りこみました。
言葉が詰まってしまう性格なのです。
石川さんは、それを知っているはずです。
ですが、さらに訊いてくるのです。
「友達じゃないでしょ?ひょっとして彼氏?」
「・・・ううん」
「彼氏じゃないんだったら、セフレかぁ」
「・・・」
石川さんは、からかうように言ったのです。
笑いながらでした。
お酒を飲んできたようでもありました。
「誰なの?」
「・・・好きな人」
「じゃ、つきあおうとかなかったの?」
「・・・」
「わたしだって、ちょっとは貢献してるでしょ?」
「・・・」
「聞かせてよ」
「・・・」
以前に、石川さんからプレゼントされていた服を、そのときの私は着ていたのです。
石川さんが言う貢献はもっともでしたが、私は話したくありませんでした。
口論に到った経緯
石川さんは、次第に責めてくる口調となってきたのです。
「じゃ、気持ちをちゃんと伝えたの?」
「・・・いまは、あまり話したくなくて」
石川さんは、腹を立ててました。
私が、めずらしく化粧をして、お洒落をして外出しているのに、恋愛話に乗ってこなかったからだとわかりました。
「その男と、もう寝たの?」
「・・・」
「とりあえず寝てみたら?」
「そういうんじゃない」
私がはっきり言うと、会話が止まったのです。
そして、石川さんは、鼻先で笑いながら言ったのです。
「それにしてもさぁ」
「・・・」
「涙にしろ、精液にしろ、たかだかティースプーンの1杯か2杯くらいの量でさ」
「・・・」
「そんな量の体液を体から出すことが、なんでこんなにも大変で、なんでこんなにも重要なんだとおもう?」
「・・・」
「わけがわからないよね?」
「・・・」
「でも、重要なのよね、おかしいくらいに重要なのよね」
「・・・」
「わたし、おかしくて、ときどき笑っちゃうもの」
「・・・」
私たちは、言い合いになったのです。
しかし、言い合いにもなりませんでした。
石川さんがいうことに、私が一言でも返すと、5倍10倍、いや20倍ほどになって強く返ってくるのです。
罵倒について
石川さんには、次のようなことを言われました。
「傷つくのがこわいだけ」
「小学生みたいなセンチメンタル」
「自分の欲望を美化して気持ちよくなっているだけ」
「やりたいだけ、ただのグロテスク」
「できないからって都合よく考えているだけ」
「お粗末な欲望でぐちゃぐちゃ」
「どうせ、わたしがあげた下着をつけているくせに」
「ごまかして、うっとりしているのがムカつく」
「見ていてイライラする」
そのように、言われ続けたのです。
私は、椅子に座ったまま、うずくまりながら、目をぎゅっと閉じて、三束さんのことを思い出そうとしました。
しかし、何かが邪魔をしてるのです。
もう、うまく思い出せないのです。
頭のてっぺんに置かれた手の平のぬくもりが、もう、どこにもないのです。
私のことを、まだ三束さんは覚えているのかと、言いようのない不安がこみ上げてきました。
私は泣いたのです。
謝罪について
石川さんも泣きました。
大泣きしたのです。
謝ってきました。
ひどいことをいってしまった、そんなつもりはなかった、いつもイジワルになってしまう、いつもダメにしてしまう、いつもこうなってしまう、あなたのことは友達だとおもっている、と言っていたように記憶しております。
石川さんは、顔をグシャグシャにして泣き続けて、ひたすら謝ってきたのです。
私たちは、お互いに床に座り込んで、さらに泣き続けたのです。
交際の破綻について
私と三束さんですが、それっきりになってしまいました。
私の誕生日には、2人でお祝いする約束をしていたのですが、当日は、待ち合わせの喫茶店には来なかったのです。
それからしばらくして、三束さんからの手紙が届きました。
謝罪と別れの手紙でした。
高校の物理の教師というのは嘘だった、とのことです。
恥ずかしくて、心苦しくて、もう会えないというのです。
2年かかりました。
私は、2年をかけて、三束さんのことを思い出すとおこる胸のざわめきの渦が、だんだんと小さくなっていくのを感じることができるようになってました。
私の2年後の誕生日は、訪れた石川さんと一緒に祝いました。
石川さんは、妊娠をしてました。
結婚はしないで、1人で育てるとのことでした。
2人だけの誕生日会が終わりました。
石川さんは、駅まで送りました。
ラスト2ページについて
私は家に帰ってから、しばらくの間、校閲の原稿に向かい会いました。
すると、急に眠気がきたのです。
ベッドに入りましたが、眠るまでは至りません。
なにかが、すっと通りすぎていくのです。
なにかが、こちらを見つめています。
なにが、気になっているのだろう、と私は思いました。
それは言葉でした。
ノートと鉛筆を手にとって、白いページを開きました。
そこに “ すべて真夜中の恋人たち ” と書いたのです。
それが、なんなのかは、見当がつきませんでした。
なにかの原稿の一文でもありません。
なんの言葉なのか、さっぱりわかりません。
原稿でもない場所に、目的もない言葉を書くのは、はじめてのことでした。
私は、その言葉をじっと見つめてました。
それからノートを閉じて、電気を消して、静かに目を閉じたのです。
