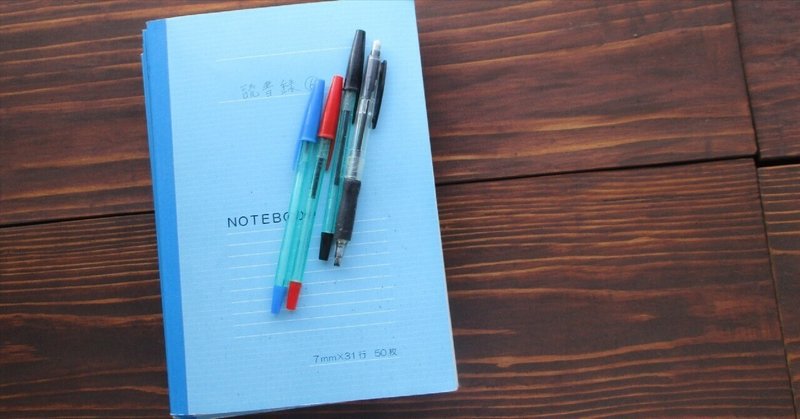
カズオ・イシグロ「わたしを離さないで」読書感想文
受刑者となって2年が過ぎた頃に読んだ本。
2年を超えてガラッと変ったことは、甘さへの飢えだった。
とにかく甘いものが食べたい。
毎月第一水曜日の昼食には「ぜんざい」が出る。
月が変わったあたりの作業中に、誰かが「水曜、ぜんざいい・・・」とつぶやく。
誰かが、わかってるというように「やっとぜんざいだ・・・」とつぶやく。
誰かが「豆おおいかな・・・」とつぶやく。
刑務官はすばやく見つけて「おい!そこ!なにはなしとんじゃ!」と怒声が飛んできて「はい!すみませんでした!」と直立する者までいる。
不正交談として、下手すれば調査である。
水曜日は、11時30分が過ぎただろうのころには作業を控えて「10分まえ!」の号令のときには、すぐ動けるように作業してるフリをする。
もし、作業が終わってなければ大変だ。
ぜんざいを味わう時間が減る。
「さぎょうやめ~!」の号令がかかると、すぐさま工場の25名は食堂前の廊下へ整列に向かう。
整列を装いながら、配食係からの「豆多め・・・」というつぶやきが次々に伝わり、皆、顔が明るい。
受刑者になって工場にきた頃には、なんで1杯のぜんざいのことで、皆こんなに必死なのだろうと不思議だった。
というか、えらく滑稽に見えた。
自分は、そこまで甘いものは好きじゃないし、食べ物にこだわりもない。
ぜんざいの1杯くらいで・・・と思っていた。
が、今では「ぜんざい・・・」とつぶやきながら、目を見開き気味にして、前のめりになって整列に向かっている。
情けない・・・という自覚は十分にある。
けど、どうしようもなかった。
この本を読むきっかけ
この本は、官本にあるのはわかっていた。
もちろん、作家名と本の題名は知っていた。
なんてったって、ノーベル文学賞の作家だ。
記憶に新しい。
日本の長崎で生まれたイシグロさん。
現在はイギリス在住。
で、クローン人間のことを書いた小説・・・というのも記憶にある。
出所までには読むつもりでマークしていた。

「わたしを離さないで」の設定
政府の「ホーム」によるクローン人間の育成
1950年代の初期のイギリスでは、クローン人間を誕生させる技術が確立。
クローン人間からの臓器提供による治療方法は、意味を考える余裕もなく開始された。
疑問を発する間もなかった。
政府が運営する「ホーム」で、クローン人間は誕生から提供を終えるまで管理され育成された。
彼ら彼女らの育成は、長い間、劣悪な環境となっていた。
クローン人間を普通の人間と見なすと、臓器摘出に抵抗が生じる。
そのため、収容されている犯罪者から、クローン人間を生成していたからだった。
やがて社会が、クローン人間の扱いに目を向けようとしたときには、臓器移植はなくてはならない医療となっていた。
クローン人間にも心があるという運動と変化
1970年代になると変化がある。
クローン人間の育成に保護運動が起きた。
彼ら彼女らにも心があるとして、劣悪な育成環境を改善して、よりよい環境で育てようという運動だ。
人道的で文化的な環境で育てれば、普通の人間と同じように感受性が豊かな理知的な人間に育ちうる。
理念に賛同する支援者も現れて、いくつかの民間の「ホーム」が開設されて運営された。
クローン人間に社会を乗っ取られてしまう
1990年代になると、ひとつの事件が起きた。
ある科学者の研究が問題視されたのだ。
特別に頭のいい、抜群に運動神経がいい、それら能力を組み入れたクローン人間を生成する技術を研究していたのだった。
その事件は、人々を恐怖せた。
臓器提供用のクローン人間を生成するのは仕方ない。
が、普通の人間よりも明らかにすぐれた能力をもつクローン人間を生成してしまうと、いずれ社会が乗っ取られる。
クローン人間に対する社会の雰囲気が変わった。
保護運動への風向きも変った。
手を引く支援者も現れた。
いくつもの民間の「ホーム」が閉鎖に追い込まれた。
1990年代末になると、保護運動の痕跡はほとんど残ってない状況になる。
クローン人間の待遇は、過去へ逆戻りしたのだった。
民間施設へールシャムと臓器提供計画
数少なくなった民間の「ホーム」のへールシャムでは、クローン人間の彼ら彼女らは “ 生徒 ” と呼ばれる。
全寮制の学校というのが日常の雰囲気だ。
広い敷地内には、寮や教室、グランド、体育館などがある。
生徒たちは、のびのびと授業を受け、スポーツに励み、友人たちと仲良く過ごす。
外の世界とは繋がりがない。
“ 保護官 ” という先生が、日常の指導をする。
クローン人間の保護運動の理念に賛同している保護官たちは、規則を守らせる厳しさはあるが、接し方には熱意があり優しさがある。
生徒たちも慕っている。
へールシャムでは、月に1回の販売会という行事がある。
お金の代わりに交換切符が配布されて、外の世界の服や生活用品を手に入れることができる。
展示会もある。
授業で作成した工作物や文芸品を展示する。
そこで秀逸とされた作品は、へールシャムの施設長が外部へ販売して、運営のための寄付を募る。
いい作品を作ることは名誉だとされた。
臓器提供者としての使命
16歳となると、へールシャムを出て他の施設へ移る。
“ コテージ ” とか “ マンション ” と呼ばれる施設で、何をするでもなく2年3年と過ごす。
不自由はない。
そこで初めて外の世界を知る。
が、皆には、さほど感激がない。
彼ら彼女らにとっては、世の中とは、周囲の友人たちがすべてとなっている。
その頃までには、クローン人間なので親はいない、と知る。
近い将来には臓器提供があると、長くは生きられないと、はっきりと知るようにもなる。
が、彼ら彼女らには悲壮感はない。
臓器提供者となるのは、使命だと思っているからだ。
ひとり、またひとりと、臓器提供のために姿が見えなくなっていく。
彼ら彼女らは、臓器摘出手術のあとは “ 回復センター ” に入院して静養するが、その後にも、2回目、3回目と臓器提供は続く。
4回目となると、死亡率はかなり高くなる。
一方で介護人となる者もいる。
回復センターでの提供者に付いて、心の平静の手助けをする役目となるのだった。
登場人物
キャシー・H
へールシャム出身の介護人。
31歳。
臓器提供者となるのが決まっている。
彼女の回想で本編は進んでいく。
トミー・D
へールシャム出身。
キャシーとは幼少組から仲がよい友人。
コテージまで一緒に過ごす。
回復センターで再会して介護もする。
4回目の臓器提供で死亡。
ルース
へールシャム出身。
キャシーとは喧嘩もしたが仲がよい友人。
コテージまで一緒に過ごす。
トミーの交際相手でもあった。
2回目の臓器提供で死亡。
エミリ先生
民間ホーム・へールシャムの主任保護官。
生徒たちには、嘘をついてでも希望を持たせて生きることを教えようという考え。
ルーシー先生
民間ホーム・へールシャムの保護官。
生徒たちに現実を教えるべきと主張。
誤りだと非難されて、へールシャムを去る。
ジェラルディン先生
民間ホーム・へールシャムの保護官。
優しい先生で、女生徒から人気がある。
キャシーたちは秘密親衛隊をつくる。
マリ・クロード
民間ホーム・へールシャムの施設長。
“ マダム ” と呼ばれる。
クローン人間にも心がある、という考えでへールシャムを運営していたが、寄付が集まらなくなり閉鎖となってしまう。
幼年のキャシーのある出来事をずっと覚えていた。
読感
読み終えた直後の感想
心にモヤモヤが生まれる読書だった。
悲しさか。
クローン人間は悲惨な扱いをされるのに、当人たちはそう思うことない内奥をのびやかに書いている。
それがかえって悲しく感じさせる。
欧米と日本の違いを感じさせた
クローン人間を臓器移植のためだけに育成するという設定は、多くの日本人には生理的に受け付けないのではないか。
スイスやオランダやアメリカの一部では安楽死が行なわれているが、日本では受け入れられないな・・・と感じるのと同じように生理的にというか何かがある。
だからなのか。
たぶんだけど、本当にたぶんだけど、自分が知らないだけかもだけど、日本人が日本を背景にして、このような設定のリアルな小説は書かれない気がした。
合理的に物質的に考える欧米人と、人工物にも魂が宿ると考える日本人。
その両方の目線を持つカズオ・イシグロだからリアルに書けたのかも・・・と勝手に思った。
3重ほどの驚きがあった
年頃の女の子のたわいもない日常を、中年男性のカズオさんが、カズオ・イシグロが、なんの違和感もなく繊細に書き上げるのに驚いた。
三島由紀夫も女性の内心をよく書くけど、ああ、三島が書いている小説だな・・・としっかりと思わせながら読ませる。
ところがカズオ・イシグロは、女の子のキャッキャッ感が伝わってきて、女の子がリアルに書いているかのような錯覚をときどきさせた。
訳者の力量なのか。
よくわからないど、そこに驚いた。
クローン人間が臓器移植に抵抗をしない状況も、受け入れていく心境も、とくに不自然は感じなく書かれている。
反乱がおきた、とするほうが納得感はあるのに、そうならないところが悲しさを増させる。
“ 筆致 ” という言葉を理解できた読書だった。
ネタバレあらすじ
キャシーが話す思い出
へールシャムの幼少期の思い出はたくさんある。
友達との日常は楽しかった。
おもしろかったこと、不思議だったこともたくさんある。
寮の窓から見える森が、すごく怖かったことも覚えている。
保護官の先生との思い出は多い。
大好きなジェラルディン先生の秘密親衛隊を、同志の女の子で結成もしたのも忘れられない。
想像が膨らんでいって、秘密親衛隊として先生の暗殺計画を阻止しようともなって、みんなで敵の動向を報告し合った。
先生から内緒で筆入れをプレゼントされた、と嬉しそうに話す友達もいた。
嘘だとはわかっていたが、それをわざわざ暴いて泣かしてしまったのは今でもわるいことをしたと思ってる。
年長期になって、セッ○スに興味を持って、男友達と行為もした。
将来を教わったようで教わらなかったが、それは使命だと疑問はなかった。
16歳になってへールシャムを出て、コテージで過ごした。
仲のいい友達と、ドライブしたこともある。
ドライブしながら、自分たちの親ともいうべきクローン元の人を探した。
似ている人が、自分の親となる人かもしれない。
社会から疎まれている人たち、ということも知っている。
もちろん見つけることはできなかった。
やがて回復センターの介護人となった。
担当したルースが、2回目の臓器提供で死んでしまったときは悲しかった。
大人になってからマダムと再会
3回目の臓器提供を終えたトミーが回復センターにきた。
トミーとは幼少からの友達でもあって、今でも好意もある。私が介護人となった。
その頃には、すでにへールシャムは閉鎖されていたが、マダムの住所を知ることとなり、トミーと2人で訪ねてみた。
カップルには臓器提供が猶予される、という噂を耳にしたからだった。
4回目の臓器提供は、死んでしまうかもしれない。
でも、トミーも私も、臓器提供を拒むわけではない。
私たちの使命だから。
でも、トミーだけには猶予がほしかった。
そこにはエミリ先生がいた。
マダムと同居していたのだ。
そしてエミリ先生から、それはただの噂であって、臓器提供にそのような配慮はないことを告げられる。
保護官であっても、どうすることができないのだった。
ここには、くるべきではなかったのかもしれない。
トミーと帰りかけたときだった。
マダムが、私の思い出を話した。
私にも、その出来事の記憶はあった。
まだ幼年のころのことだ。
ジュディ・ブリッジウォーターのカセットテープを交換会で入手して、それを寮の部屋でかけながら、1人で踊っていたら、通りかかったマダムに見られたのだった。
小さかった私は「わたしを離さないで」という歌詞が気に入って、待望の赤ちゃんを授かった女の人を想像して踊っていたのだった。
その私の姿を見て、マダムは泣いた。
それが不思議だったから、ずっと記憶に残っていた。
「あの日、あなたが踊っているのを見たとき、わたしには別のものが見えたのですよ。新しい世界が足早にやってくる。科学が発達して、新しい治療法が見つかる。すばらしい。でも、無慈悲で残酷な世界でもある。そこにこの少女が古い世界を胸に抱きかかえている。目を固く閉じて、それをしっかりと抱きしめて、離さないで離さないでと、懇願している。わたしはそれを見たのです。あなたの姿に胸が張り裂けそうでした。あれから忘れたことはありません」
トミーの死
トミーは4度目の臓器提供で死んでしまった。
私も、これからは介護人ではなく、臓器提供者となるのが決まっていた。
自分でそう決めた。
その2週間後、ノーフォークまで、1人でドライブした。
ノーフォークにはイギリス中の忘れ物が集まると、友達同士にしか伝わらない冗談で使われていた場所だった。
コテージにいたころにも、友達5人でドライブで訪れたこともある。
トミーも一緒だった。
あのときトミーは、失くしてしていた「わたしを離さないで」の歌詞がある同型のカセットテープをノーフォークの雑貨屋で見つけてくれてプレゼントしてくれた。
ラスト1ページ
車を止めた。
広大な畑を見渡して、トミーを思い出す。
やがて地平線に、トミーの姿が現れて呼びかけてくる。
私は涙しながら、空想はそこで自制して止めた。
また車に乗る。
出発した。
