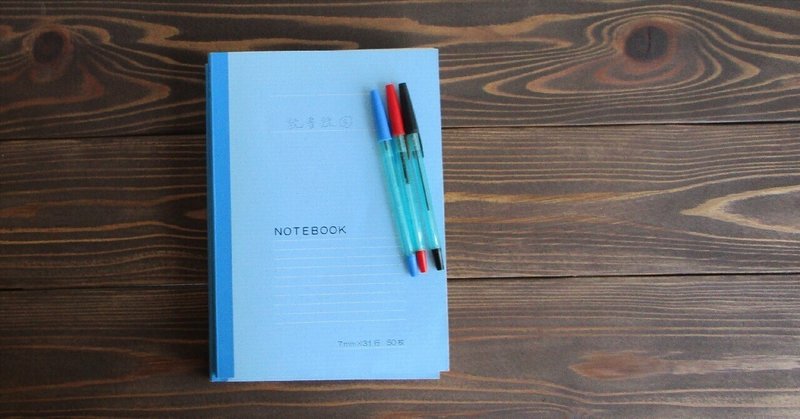
川上未映子「あこがれ」読書感想文
ここで見る “ 夢 ” は質が違う。
娑婆だったら「これは夢だな」と、頭のどこかでわかっていながら夢をみる。
だから、目が醒めたあとも「やっぱり夢だったのか」とすぐに現実との区別がつく。
ところがここでの夢は、目が醒めても、ここがどこなのかわからない状況に陥っている。
コンクリの天井や壁を見回しても、記憶喪失になったような呼吸が何度かあって「ああ、まだ刑務所だったのか・・・」と驚きを以って現実に気がつく。
夢の中への没入感が深い。
今が現実だと、夢の中で疑いもしてない。
ましてや、すべての夢が檻の外の出来事なので、目が醒めたあとの引き戻され感は今までにないものだった。
半年に1回か2回は、そんな夢を見た。
そんなころに読んだ本。
きっかけ
初めての湊かなえの「ユートピア」に、あっけなくぶちのめされた自分だった。
本が嫌いになりそうなほどでもあるし、人気作家の本がおもしろくないなんて人としてヤバイのではないかと悩む気分。
もちろん、おもしろくないと感じたら、その作家の本は2度と読まなければいい。
しかし、おもしろくないで終わらせるのではなくて、世間の皆がどうして感動して絶賛しているのか、それを知りたい。
受刑者としてそれはしなければ、という義務感すらある。
だから2冊目も読むつもりではいた。
しかし、今は2冊目の湊かなえにいくのに躊躇している。
また、おもしろくないと感じてしまったなら、社会不適合者の烙印を自分で押してしまいそう。
次の読書は確実にヒットさせたい。
それも女性作家で。
気分を広げてから、2冊目の湊かなえに望みたい。
そんなときのために、官本室でマークしてあった1冊だった。
初めての川上未映子は「すべて真夜中の恋人たち」で済ませていて、すごくよかった印象しかない。
これは鉄板の1冊だろう。

読感
読み終えた直後
よかった。
読書ってこんなに楽しいものなのか、と実感する。
なにがって、好きな女性作家が増えていくうれしさがある。
今までは、好きな女性作家といえば桐野夏生のみだったのに、川上未映子、瀬戸内晴美(寂聴)、田辺聖子・・・と、とはいっても1冊か2冊づつしか読んでないけど、とにかくも、好きな女性作家が増えるのはなんだかうれしい。
1章と2章から成り立っている本
「ミス・アイスサンドイッチ」が1章目の題名。
小学校4年の “ ぼく ” の目線で描かれていく。
「苺ジャムから苺をひけば」が2章目の題名。
小学6年生となった “ ぼく ” の “ 女友達 ” の目線で描かれている。
1章の “ ぼく ” の名前も明かされる。
1章、2章とも、それぞれ短編としても成立するのだけど、2つ合わせて「あこがれ」という本になっている。
リズムが好き
ひらがなが多用された文章の雰囲気が、前回に読んだ「すべて真夜中の恋人たち」に似ている。
いったい川上未映子のひらがなを多用した文章の、どこがいいと思わせるのだろう。
不思議。
漢字交じりの、昭和の文章が好きなはずなのに。
短歌のリズムがあるようには感じる。
57577の短歌のリズムが日本語には合うと、誰だったか、林真理子だったか、誰かのエッセーで読んだ。
ひらがな多用の文章を指先で追ってみると、その短歌のリズムが繰り返し施されている。
だから好きなのかも、と思ってもみた。
ぼやかされているところが好き
ここのところ読んでいた女性作家とちがうな、・・・まあ、湊かなえしかいないけど、とにかくも、ちがうなと感じるのは “ ぼやかし ” が本文中に施されていることが挙げられる。
“ ぼやかし ” というのは、適切ではないかもしれない。
おそらく、文学的で学術的な専門用語があるのだろうけど、それがなにか無学な自分にはわからないので、ぱっと浮かんだ “ ぼやかし ” としておく。
この本の題名の「あこがれ」という語句は、1章と2章を合わせた本文中に1度だって使われない。
ぼやかされている。
1章では “ ぼく ” が、スーパーのサンドイッチ売場の女性にあこがれを抱いている。
“ ぼく ” は、あこがれの意味をまだわかってない。
「それは好きってことだよ」と “ 女友達 ” から言われて、スーパーをやめる女性に声をかけて似顔絵を渡す。
2章では “ 女友達 ” が、会ったことがない異母姉にあこがれを抱いている。
“ 女友達 ” は、それがあこがれだと気がつかずに「1回でいいから遠くからでも姉を見てみたい」と相手の自宅までいく。
家に招き入れた異母姉も、それがあこがれとはわからずに「すごい好奇心!」と口にする。
本の題名が「あこがれ」だから、読んでるこっちも、次第にそれだと気がついていくように書かれている。
静かなところも好き
この「あこがれ」が、もし、あの、湊かなえで書かれたとしたら・・・と比較してしまう。
以下は、独断と偏見と無学と妄想である。
まずは「あこがれ」が連呼されるだろう。
だって、あの「ユートピア」の中で「ユートピア」が連呼されちゃってるくらいなのだから。
その流れで「あこがれ」があったから見たくなった、「あこがれ」があったから会いたくなった、「あこがれ」があったから行ってみた、「あこがれ」があったから話したくなった、とにかく「あこがれなんですぅ!」と叫びながら展開されて迫ってきて、こっちも「わかりましたから!」と声を荒げなければならない。
で、過去の家族関係に起因を求めて、それらを力強く糾弾しながら突進していく。
おそらく本書の何人かは、私設裁判にかけられて、厳しい判決がくだされる。
そして、突如として火事が発生。
湊かなえに火事は欠かせない。
重傷者、もしくは死亡者がでるという非常事態になってと、なかなか騒がしく慌しく話が進んでいく。
だからこそ、ミステリーなのだろうけど。
対して川上未映子は静かだ。
「あこがれ」という核心の語句を一切使わずに、ぼやかしを施して読み手に想像させる。
「あこがれ」とは一方的であって、だけど自分ではわかりづらくて、他人にもわかりづらくて、はかなく消えるものだな、でもそれでちょっと大人になるのだな、と1冊を通じて気がつかされた。
静寂を以って気がつかされた読書だった。
登場人物
麦彦
一章の「ぼく」で小学4年生。
おとなしい性格で絵が好きでよく描く。
あだ名を付けるのが得意。
4歳のころに父親は病死しており、母親と祖母の3人暮らし。
ママ
麦彦の母親。
占い師をしている。
自宅を改装して占いのサロンにしている。
麦彦が小学校6年になるころ再婚をする。
ミス・アイスサンドイッチ
スーパーのサンドイッチ売り場の店員。
アイシャドーが濃すぎて、塗られた水色がアイスキャンディーの色に似ていることから、麦彦があだ名をつけた。
無愛想で美人とはいえないが、大きな目がカッコイイと麦彦は思っている。
夏休み中には毎日サンドイッチを買いにもいく。
彼女がスーパーをやめるときには、麦彦は似顔絵を渡す。
ヘガティー
2章の「女友達」で、麦彦の同級生。
麦彦がヘガティーというあだ名もつけている。
父親と2人で暮している。
お互いの家が歩いて5分という距離ということもあり、一緒に下校したり遊んだり、どきどきは映画のDVDを観たりと仲がよい。
ミス・アイスキャンディーがスーパーをやめるとき、会いにいくようにと麦彦に強くいう。
ヘガティーのお父さん
映画評論家。
自宅には映画のDVDが壁一面にある。
バツイチで、前妻との間に一女あり。
苺ジャムをつくり毎朝食べている。
新田咲子
ヘガティーの父親の前妻。
突然に訪れたヘガティーに温かく接する。
新田青
新田咲子の一人娘。
高校生。
ヘガティーの異母姉となる。
ダンス3人組
クラスの女子の3人組。
ミス・アイスサンドイッチのことを「こわい」「おばけ」「整形の失敗」「目がいちばんヤバイ」などとおしゃべりをして、それを耳にしていた麦彦は意味がわからず混乱する。
また、うち1人が麦彦に告白して、一方的につき合ってることにして困らせたりしている。
チグリス
ヘガティーの友達。
チグリスの姉が、新田咲子の名前を調べてくれる。
アイフォンの操作も教えてくれた。
あらすじ
1章 ミス・アイスサンドイッチ
「いちばんむずかしいことっていうのはさ、いなくなっちゃった人に会うってやつでさ」とへガティーはいう。
だから会うべきだと、ぼくにいう。
ミス・アイスサンドイッチが、スーパーをやめたのだった。
ぼくは、目がかっこいいと思っていて、夏休み中は毎日サンドイッチを買いにいっていた。
やめたのだけど、1度だけ荷物を持ちにスーパーに訪れることを知って、そしたら会いたくもあって、どうしたらいいのかヘガティーに相談したのだった。
ヘガティーにいわれたぼくは、その当日にスーパーの入口で待ち続けて、姿を見せたミス・アイスサンドイッチに「すみません」と声をかけた。
驚いた顔をしたミス・アイスサンドイッチだった。
立ち止まって「どうしたの?」とたずねてきた。
ぼくを覚えていたのだ。
ぼくは顔を熱くしながらも、描いた似顔絵を手渡した。
「ありがと」とお礼をいわれたし「じょうず」と似顔絵を褒められもした。
ほんの数分だけ会話をして、ミス・アイスサンドイッチが結婚することも知った。
「元気でね」とミス・アイスサンドイッチは帰っていく。
それだけのことだった。
ぼくは、なにをしたかったのかわからなかった。
2章 苺ジャムから苺をひけば
ヘガティーは、小学6年生となった。
ある日のパソコンの授業で、映画評論家をしている父親の検索結果から、離婚経験があり、前妻との間には一女がいるのを知る。
ということは姉がいるのだ。
ベガティーは姉の想像を膨らませる。
同時に父親と口をきかなくなる。
家出も考えるほど、急に父親が疎ましくなったのだった。
姉を遠くからでも見てみたい・・・との思いにベガティーは捉われるが、それをしていいかわからない。
麦彦に打ち明けると、まずはそれができるかどうか、チグリスの姉に頼んで前妻の名前を調べてもらことに。
その名前は判明した。
父親のアイフォンの操作も教えてもらい、アドレス帳を開いて、その名前を見つけた。
住所は、電車で1時間ほどの場所だった。
計画は実行された。
ヘガティーと麦彦が遠くから見てると、その家から犬の散歩に出てきた彼女がわかった。
一目だけ見て帰るつもりだったが、2人は追いかけて、角を曲がったところで、彼女とばったりと出くわす格好になる。
犬がウンチをしていて、足を止めていたのだ。
ヘガティーは話しかけて、犬の話がはじまり、言うつもりはなかったのだけど「わたし、妹なんです」と言ってしまう。
せっかくだからと、彼女は2人を家に招いた。
家には母親もいて、お茶もケーキもふるまわれた。
が、そこでヘガティーは、涙が出てきそうになった。
今では父親代わりの人だっている、と高校生の彼女はいう。
今の自分の現実を大事にしたい。
本当の父親は知らない人だし、関係もないし、興味もないから他人以下。
たとえ病気になったりしても、大変だねと知らない人の災難をテレビで見てる感覚。
極端な話、死んでもなんとも思わないし、と明るくはっきりと言いきったのだった。
「あなたは妹ではないし、わたしはあなたの姉でもなんでもないのよ」とサラリとニッコリとしながら告げてきたのだった。
胸が苦しくなってきたヘガティーは、突然の来訪を母娘に謝り、麦彦と家をでる。
駅までの道では、2人とも無言だった。
ヘガティーは、気持ちが落ち着いてきた。
母娘のいうこともわかる気がする。
正直いってショックだけど、ああいうふうに思っていることをいえるのは高校生ってスゴイね、と麦彦と話した。
そこで気がつく。
すんなりと家に招かれ、ショートケーキがおそろいのティーセットで4つ出てきたことだ。
人数分のショートケーキが、せっかくだからとサッと出てくるなんて。
あの母娘は、わたしたちが来るのが最初からわかっていたみたい。
妹ですって言われても、たいして驚きもしないで、冷静に家まで招いて、思っていることをスラスラと言えてもいる。
「そうだよ、来るってわかっていたから、まえもってあれこれ考えれたんだよ。知ってたんだよ。わたしが来るのを」
でも、どうして。
話かけることまで知っていたのだろう。
ばったりと出くわす瞬間までは、わたしでも話しかけるなんて思ってなかったのに。
ヘガティーは考えてから、麦彦を問い詰める。
麦彦は白状した。
アイフォンのアドレス帳を、新田咲子のページを開きっぱなしでスリープにしたため、父親は娘がなにかをしようとしているのか察した。
父親は、どうしたらいいのか弱り果てて、麦彦に頼みこみ、計画も実行日もバレる。
父親は先方に何年ぶりに連絡して、彼女の散歩の段取りとなったのだった。
父親としては、彼女の姿を遠目で見させてあげるだけのつもりだったのだけど、母娘のほうは会うことを考えて、準備して、見かけたら話しかけるつもりでショートケーキも用意していたのかも。
「みんなグルだったんじゃん!わたしだけが知らなかったんじゃん!」と、麦彦の話も聞かずに走り出した。
人気のない団地まで走り、泣きつづけた。
母親がいないこと、父親が死んでもなんとも思わないと言われたこと、その父親が苺ジャムをつくり続けていること、散らかっているリビング、絡まった洗濯物までごちゃまぜに思い出し、なんで泣いているのかもわからなくなる。
さんざんと泣いてから駅に向かったへガティーだった。
麦彦は駅前で待っていた。
帰宅してからは、何事もなかったように父親と晩ごはんを食べた。
翌朝のへガティーは、ひさしぶりに父親と一緒に朝ごはんを食べた。
新田さんの家にいって母娘と会ったとも話すと、父親は驚いてから真剣な顔をして黙る。
しばらくして話そうとしてきた父親を止めて「今晩きくよ、わたしも話したいこといっぱいあるよ」とドアを開け学校へ向かう。
教室ではいつもの出来事が、窓の向こうの風景のひとつひとつが、いつもと少しだけちがうようにも感じられもした。
放課後は麦彦と一緒に帰宅した。
今度の金曜日に、久しぶりに映画のDVDを観る約束をする。
「じゃあね」と大きく手を振りながら、なぜだか、今日のことは忘れないだろうな、とへガティーは思ったのだった。
