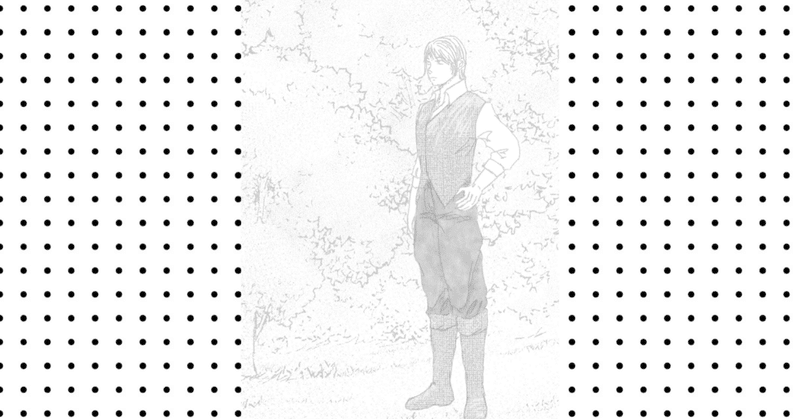
10話 いっときの出会いと別れ

10話 いっときの出会いと別れ
「おいおいロニー。お前踏み台壊したって?」
軽食屋の店主はロニーの顔を見るなりニヤリとからかうように笑う。
「俺が壊した訳じゃない」ロニーは弁明するように口を尖らせ、「前からガタはきてたんだ。直そうにも釘を切らしちまってて…」
「釘はどうしても錆びやすいですからね」
両脇に抱えた材料を一旦おろしたジャスティスはその場で胡座をかいて木材の端を削り始めた。
「おい坊主、お前何してるんだ?」
軽食屋の店主がそう聞けば――
「え? 踏み台を直してます」
至極真っ当な答えを返すジャスティス。
「いや。そりゃあ分かってるんだが…釘とか必要ねぇのかって話なんだが……」
店主は言うのはもっともだった。本来なら踏み板と支柱の部分は釘を刺して接着するのが一般的だからだ。
「釘は必要ないですよ」
ジャスティスは視線を手元から離すと店主を見てニコリと笑う。
「釘はどうしてもサビがきてしまうし、そこから材料が腐りやすいので――」
再び視線を手元に戻す。
「接着部分を加工して継ぎ目を作った方が釘を使わなくても済みますしね」
口では軽く言っているジャスティスだが手は器用に材料を刻み加工していっている。
ロニーや店主が呆気に取られつつ見守る中、踏み台はすぐに出来上がってしまった。
「おお! 坊主お前すごいな!」
「お前大したもんだ!」
完成した踏み台の強度を確かめつつロニーと店主は口々にジャスティスを褒めたたえる。
「いえ…そんな大した事してないので」
ジャスティスは照れ臭くなって顔を赤らめてしまった。
「ぼ、僕もう行かないといけないので…」
それを悟られたくなくて荷物を持つと、その場から逃げるように村の門へと一直線に走り出した。
――モルファル村の東門を抜けるとファルフォム丘陵と呼ばれる道に出る。緩やかな登り坂を進む途中ジャスティスは村を振り返った。
「別にすごい事なんてないのになぁ…」
と、鼻の頭をぽりぽりと掻く。
ジャスティスにとって、家具などの修理はもう趣味の一つで、皆が言うほどすごい訳ではなく寧ろそう言われるとどうも照れ臭くてしょうがない。
「とりあえず、こっちを進めばいいのかな?」
道なりを目で辿れば遥か先まで続いており奥の方は登り坂なので道しか見えない。視線を上にあげれば空が見え少し真上には陽が照っている事から自分が東に進んでいる事が分かる。
数時間歩いただろうか、丘道の中腹あたりに差し掛かった時だった。
「―…ッ」
ジャスティスはふいに足をピタリと止める。
数メートル先に数体の影――その影は六つあり、一番背の高いものでもジャスティスの頭ひとつ分は低い生き物。
前方に一人いたものはジャスティスの行く手を遮り、
「…お前、食ベ物よこせ」
自身の身長と同じくらいの長さの棍棒(こんぼう)を右手に構え赤褐色の瞳をギョロリとジャスティスに向ける。
「……」
ジャスティスは目の前に立ちはだかった生き物を訝しげに見つめ、
「ドワーフ?」
問い掛けるように首を傾げた。
「そうだ」
ジャスティスの問いかけに律儀に答えるドワーフ。
ジャスティスが言う『ドワーフ』とはこの世界にいる種族の一つで、主に錬金細工や薬草学に長けているものが多く山や森を住処にしている。濃い茶色の肌で耳の先がとんがっており背が比較的低いのが特徴である。
一番前にいたドワーフはジャスティスを威嚇するように、
「お前、なんか食いもん寄越せ」
「僕、食べ物持ってないよ…」
ジャスティスが肩を竦めてそう言えば「…ハァ……」と、これみよがしに溜息をつくドワーフの一人。それに倣い、後ろにいた五人のドワーフも同じように肩を落とし溜息をついた。
「…食べ物、探してるの?」
一番前にいたドワーフ問うジャスティス。
「…お前…食べ物持ってないか…?」
「持って、ないけど……ってッ?!」
ドワーフに同情したジャスティスは何かに気づき、
「危ないッ!」
叫び目の前のドワーフを庇うように抱きかかえ横に飛び退く。
「…な、何が…ッ!?」
驚き呟くドワーフの真横を何かが素早く走り去った。
「…あれはッ? イノシシか?!」
「……来るッ!」
頭を上げるドワーフを後にしてジャスティスは方向転換して再びこちらに突進してくるイノシシの前に立ちはだかる。
ズザザザァァッ!
地を引きずる音とともに土埃が舞う。
双剣を抜き正眼で交差して構えたジャスティスと力比べをするようにイノシシが頭部を突きつけていた。
「…ッ、興奮してるッ?」
足を踏ん張りジャスティスは刃ごとイノシシの突進に耐えている。そこからどうにかして片側の短剣を滑らせて柄でイノシシの頭と首の境目 (頸部)に衝撃を与え気絶させる。
「ぉおッ?! お前、強い……ッ!」
「食いもん出来た!」
「飯食える……!」
六人のドワーフたちは口々にジャスティスを褒めたたえ、小躍りしつつ『イノシシ』とジャスティスを自分らの棲家に連れて行った。
丘道の途中の岩肌に風穴があり、その奥側は海に面しておりちょっとした入り江が出来ている。
入り江の周りは少しばかりの木々が茂っていて自然の洞穴を利用したのがドワーフたちの住まいのようだった。
「お前、飯くれた。今日はご馳走。お前泊まっていけ!」
先頭にいたドワーフは青い綿生地を胴から巻いており上半身は動物の毛皮で作ったベストを羽織っている。
「ご馳走ご馳走ッ嬉しいな!」
前髪を真ん中で分けて肩まである焦茶髪のナン。赤い綿生地のワンピースを着ている事から女の子でこのドワーフらの長女のようだった。
ナンは笑顔とは似合わない大きな刃の包丁でイノシシの肉を軽々と削いでいく。
「嬉しいな! アンタさんとぉ〜っても強いのねッ」
ナンが切り分けた肉を焚き火の鍋で煮込むのが桃色の服を着たネロ。軽快な歌声に乗せて身体も踊るように動き回ってる。
「あれもこれも食べれるよ!」
ちょっと太め (?)で緑の腰巻きを着けてるのがヌイ。細かく刻んだ肉を香草である大きな葉で色とりどりの木の実と一緒に包んで葉が取れないように木の棒で刺していく。
「捨てるところはないのさ!」
ヌイに続けて焚き木を運んでくる長男のラオ。先頭にいた棍棒を持ったドワーフだ。
「…に…にーちゃん…、アタイたち怖く…ない……?」
「…いじ…、苛めたり…しな…い……?」
兄や姉たちに隠れるようにモジモジしているのは三女と三男。まだ幼いのか、ラオたちの腰くらいまでしかない。
「怖く…ないし、苛めるって事もしないけど…」
ジャスティスが戸惑いつつ、握手を交わすように目の前に手を差し出せば、
「アタイは、ニケだよ!」
「ボ…ボクは…リク……!」
二人同時にジャスティスの身体に飛びつくように満面の笑みでやってきた。
「あはは、僕はジャスティス。よろしくね!」
反動で尻餅をついたジャスティスだが特に気にする事もなく、ニケとリクを膝に乗せた。
「…お前、変わったやつ」
ラオが少し安堵したように呟く。
「にーちゃん今日泊まってく?」
「ボクたちと遊ぶ?」
ニケとリクが交互に聞けば、
「…ぇ…ど、どうしようかな……」
ジャスティスが困惑してラオに助けを求めるような視線を送ると、
「お前、これ獲ってくれた。俺たちからの礼だ。急ぎじゃなければ泊まっていけ」
と、ラオはすでに焼き上がった串刺しのイノシシの肉を豪快に齧り付いてみせた。
「じゃあ。一晩だけお邪魔していいかな?」
ニケとリクがジャスティスの腕にしがみついてじゃれているのでジャスティスは断るに断れず苦笑いしつつ頷いた。
「みんな…の、お父さんお母さんは?」
食事を終えて、集めた藁に布を敷いただけの簡素なベッドに案内されたジャスティスは気になっている事を聞いた。
「…俺たちに親はいない」
「…ぇ、…あ…ごめん……」
俯いて言うラオに、ジャスティスが聞いてはいけない事を聞いてしまったようで小さく謝ると、
「…いや。いいんだ」
ラオは少し寂しそうに首を横に振った。
「…殺されたの」
「…よせ、ナン!」
下の弟妹を寝かしつけたナンが静かにそう言うと、それを咎めるラオ。
「…殺され……た…」
「いいんだ。聞かなかった事にしてくれ」
ジャスティスが重く呟くと、ラオは端的に言って布団に頭から潜り込んでしまった。
「……」
「…ごめんなさい。忘れて、ください…」
口噤んだジャスティスに呟くように言うナン。彼女もまたそれ以上は口を開かず、既に夢うつつの弟妹たちと一緒に寝てしまった。
ジャスティスもまた布団を被り目を瞑った。しかし脳裏にはラオやナンの言葉。この兄妹たちは、両親を殺されてしまったらしい。可哀想だとは思うが、この数日で自分の環境が目まぐるしく変化しているので心身共に疲れてしまったジャスティスはすぐに眠りに落ちた。
――翌日。
ジャスティスが目を覚ますと、ラオとナンは既に朝の支度に取り掛かっていた。
「…おはよ」
少し気恥ずかしげに言えば、それに気づくラオ。
「おう、起きたか」
「ジャスティスは、どこへ行こうとしてるんだ?」
「…僕はえっと……」
ジャスティスは言葉に詰まった。本当の事を話そうかと思ったが、ラオ達には関係のないことだ。巻き込んでしまってはいけない。
「ちょっと港で人と待ち合わせしてて」
それは事実だったので、当たり障りなくそこだけを口にすれば、
「そうか」
ラオは特に気にする様子もなく頷いた。
「じゃあ…」
と、おもむろに桑の葉でくるんだ包みをジャスティスに渡してくる。
「え? な、何これ?」
手のひら程の包みを両手で受け取るジャスティス。中身は携帯用に調理された干し肉だった。それを手に困惑しつつ包みとラオを交互に見比べてると、
「『獲物』をとってくれた礼だ。お前よく食べそうだしな!」
と、ラオがニヤリと笑う。
「ぼ、僕…そんな食いしん坊じゃないよ…」
ジャスティスは少し唇を尖らせた。そんなジャスティスを見たラオは堪らず吹き出し、ジャスティスもまた釣られて二人して大声で笑い合った。
「…じゃあ、気をつけて行けよ」
「うん。コレありがとう!」
住処から丘道までラオが見送ってくれた。ジャスティスは受け取った包みを手に礼を言ってドワーフの住処を後にした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
