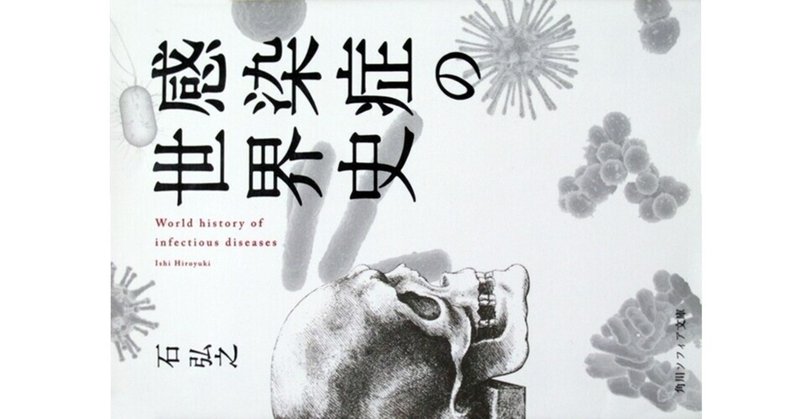
『感染症の世界史』(石弘之・角川ソフィア文庫)
新型コロナウイルス感染症以前の本である。単行本としては2014年に出ており、この文庫も2018年である。新型コロナウイルスについて知るところのない本である。おそらく2003年のSARSまでは十分知るところであるにしても、文庫版はその後の情勢をも踏まえて加筆修正を施しているのだという。
微生物が人や動物などの宿主に寄生し、そこで増殖することを「感染」といい、その結果、宿主に起こる病気を「感染症」という。簡潔な定義から本は始まる。感染症の世界的な流行は、30~40年ぐらいの周期で発生してきたことを挙げ、1968年の香港かぜ以来大流行が起きていないことから、2017年12月の「まえがき」で、警戒するように著者は書いている。その2年後、人類はその周期の渦に取り込まれてしまう。
その感染症に対する見方は、「微生物は、地上最強の地位に登り詰めた人類にとってほぼ唯一の天敵でもある。同時に、私たちの生存を助ける強力な味方でもある」というものである。本書は、この考え方を以て、人類と微生物との関係の歴史を説いていくことになる。
私たちの記憶に新しい、エボラ出血熱とデング熱の問題を序章とし、話は本章に入っていく。人類の移動の問題、環境変化の問題、ここに大きな感染拡大の要素を見る。いつごろ何々の感染症がありました、というような編年体ではない。人類とウイルスなどとの関係を縦横に捉え、人類の知恵や対処、そして考え方を拾い上げる。
後は読み物のように、ピロリ菌の話、トキソプラズマ原虫を取り上げたと思うと、セックスに関するウイルスに向かう。ヘルペスの話になってくると、日本がワクチンに関しては後進的であることが明らかにされ、世界と言いながら、絶えず日本のあり方を問うているのは、私たちにとっては大切なことが強調されていてよいものである。インフルエンザも、感染の広さに加えて、死者の数にしても無視できない怖い病気であるために、簡潔でありながらその仕組みから感染に関する注意まで、たくさんのことを教えてくれる。時折、それにより命を落とした有名人が列記されることもあり、しみじみ偲ばれる。
エイズ患者が日本においては実は増え続けているという点は、マスコミはもう紹介すらしないこととなっているが、決して過去の病気ではなく、これからどうすればよいかも改めて問うものとなっている。その日本においては、ハシカにおいて世界のお荷物となっている実情も明らかにされ、風疹が止まらない有様も目の前に突きつける。縄文という時代を持ち出して、成人T細胞白血病が紹介されると、いったい日本人がどこから来たのかという問題にまで関心は及ぶ。確かに、この感染症という観点からも、人種あるいは民族という研究に新たな光が当たるのだ。
そして縄文とくれば次は弥生人となるが、ここでどうやら結核が持ち込まれたようだ。この結核、たんに過去の病気であるわけではなく、近年また発生している。それにしても、明治以降の文化人が結核について非常に傷つき、落命し、また芸術の中にも描いたということで、日本人にとっては実に切ないものでもある。
こうして終章に入る。これからの感染症についての眼差しであるが、やはり中国は警戒地域であるという。それは新型コロナウイルスについても正にそうだとされており、予言的な著者の言明は、実に的を射ていたということになる。それは、歴史と社会を確かに見つめてきた目の故であり、また、科学的に微生物について調べ尽くしてきた研究の故でもあると言えるだろう。コウモリやサルなど、病原菌を抱えた動物を食用にしてきたことが、これだけ世界的な疫病の蔓延を繰り返してきたという歴史を、知らないためにまだ今なお同じ轍を踏まんとするほどに、いまなおやっているという現実がここにある。文化だと言われたらそれはそれで認めないといけないのだろうが、それにしても、世界に死をまき散らす原因について、せめて「知る」ということは、望ましいことと考えてはならないのだろうか。
感染症は、もちろんひとの命を直接敵に奪う。だが、経済を止めることによって、ひとの命を間接的に奪うことにもなるのである。だが、ただの悪者なのかどうか、著者は少し別の視点も提供する。彼らにとっても、賢く振舞うことがあるというのだ。たんに宿主を殺すだけでなく、殺さずして生かし、その中で繁殖するという策略に変更していくこともあるわけである。
最後に、2014年に記された「あとがき」がある。私は全編読んで、最後にこの頁に入り、不謹慎で申し訳ないのだが、噴き出してしまった。著者のどこに、こんなユーモラスなものが詰まっていたのだろう。本編では全く感じられなかった。いや、それは確かに不謹慎である。命を懸けて本書を世に出して、私のような者の目にも触れるようにしてくれた著者に対して、失礼極まりないことをいま書いている。「人と病原体の戦いは、未来永劫につづく宿命にある」と著者は言う。未来永劫は大袈裟であるにしても、人がある限り続くだろうということは、たぶん間違いがないだろう。むしろ、感染症流行のさらなる「二次災害化」が懸念されるというその予感に、私たちは次の警戒を懐くべきであった。コロナ禍において、私たち人類が、まだ路頭に迷っているような中で、私はこれを読んだ。否、あるいは人類はそれなりに対処できているのかもしれない。そのためにも、やはり「知は力」なのであることを、痛感させられた。本書は広くお薦めしたい。
フローレンス・ナイチンゲールは、202年前の5月12日に生まれた。彼女は戦争の場を体験して、看護を体験した。わずかな看護活動の後、統計学を駆使した衛生環境の改善に力を尽くし、政治的な関係が、その提言を現実に活かすのに大いに役立ったと思われる。また、彼女もまたプラトンなどの哲学に理解が深かったとも言われるが、筋の通った考えというもののためには哲学が必要であることは、他の多くの場面でも垣間見るところである。哲学史の知識ではなく、考えることそのものの追究は、日本の教育に決定的に欠落している領域であると、私は主張して止まない者である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
