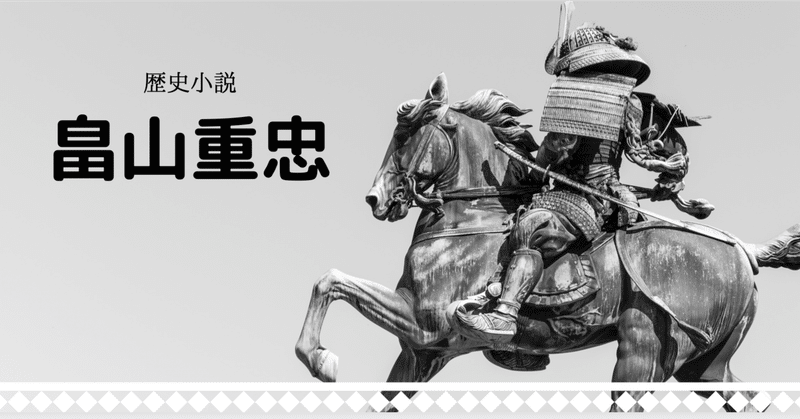
歴史小説 畠山重忠 その5
鎌倉の重忠の館には久しぶりに静かな時が流れていた。
「成清。あの日から五年。世の中はがらっと変わってしまったな。」
「誠にもって。殿のご活躍で、畠山党の所領も増えました。それに、何よりも鎌倉第一の武者としての殿の声望は、我ら畠山党の誇り。先日の南御堂勝長寿院落慶法要の際も、我ら畠山党は随兵の先陣を賜り、面目をほどこしました。」
「所領が増えたといっても、このように日本国のあちこちに散らばっていては、管理のしようがない。きちんとした代官を送るように心がける必要がある。」
「とくに、西国に新たにいただいた所領は、未だに源平の争乱の余燼がくすぶっておりますので、気の利いた者を派遣せねばなりません。」
「昨年設置された守護、地頭の制度も各地で荘園領主と軋轢を生じているようだし、世の中には何もかもが変わってしまう時というものがあるものだと、つくづく思う。」
「それはそうと、明日は九郎殿の妾であったという静という白拍子が鶴岡にて舞うとのこと。」
「うむ。供を仰せつかっているのでわしも行かねばならぬが、気が重い。」
「九郎殿はやはり奥州に逃れられたのでございましょうか。」
「たぶんそうであろう。」
「梶原殿の讒訴が原因で頼朝殿はこれほどまでに義経殿を嫌うと、皆の者が申しておりますが。」
「それもあろう。だが、義経殿は勝ちすぎた。あの平氏をわずか一年余りで滅ぼしてしまったのだ。頼朝殿も恐れているのであろう、あの戦の才能を。」
「奥州と合戦になりましょうか。」
「義経殿の事がなかろうと、いずれ奥州とは合戦となろう。なんと言っても、源氏にとっては奥州は因縁の地。その際は、我らも白旗たてて先陣を駆けねばなるまい。」
「小紋の藍皮を押した白旗ですが。」
二人は顔を見合わせてにやっと笑った、
翌、四月八日、頼朝は政子を伴って鶴岡八幡宮寺に詣でた。静は、その時に合わせて鶴岡の回廊に召し出されていた。
静は、三月に京から鎌倉に連れられてきていた。義経の行方を尋ねるためである。だが、静が知っているのは義経と別れる間際までで、尋問の結果、新しい事実は何も浮かんではこなかった。
しかし、京でも評判の白拍子である静が鎌倉に下ってきているのなら、是非とも一度その舞を見たい、と政子が言い始めた。固辞する静を今日無理矢理に連れ出したのだった。
この期に及んでも静は舞おうとはしなかった。
「私は確かに身分もなき白拍子にすぎません。しかし、義経殿と縁あって結ばれた身。このように衆人が見守る中で舞うなどいうことは決して出来ません。」
こうなると頼朝も意地になり、
「今日の舞は我々が見るのではない。八幡大菩薩がご覧になるのだ。神前に捧げる舞なのだから断ることは決して出来ない。」と、あくまで静を舞わせようとした。
静はあきらめて舞うことを承知する。伴奏は、鼓を工藤祐経が、銅拍子を重忠が受け持つことになった。重忠の音曲の才は誰もが認めるところで、普段は、はやりの今様なども歌った。
静は歌を吟じ出す。
「吉野山 峰の白雪 踏み分けて 入りにし人の 後ぞ恋いしき」
その声、朗々としてあたりに響き、聞く者の胸を打つ。
重忠の銅拍子が奏でる音が哀れな静の身上を際だたせる。静は舞い始めた。その舞は皆の目を釘付けにする。さらに静は、
「しずやしず しずのおだまきくり返し 昔を今に なすよしもがな」
と、再び吟じた。その妙なる歌声はこの世のものとは思えぬほどであった。静の義経を思う気持ちの純粋さは、さすがに武骨を持ってならす鎌倉武者たちの心根にも響いた。
が、頼朝だけは不機嫌であった。反逆の義経への思いを堂々と鶴岡の神前で歌われたのだから当然だろう。結局、政子によって説得させられた頼朝は、褒美の布を静に賜って事なきをえた。
静の舞に伴奏をつとめた翌年の文治三年【一一八七年】六月、員部の大領家綱によって重忠は訴えられる。
これは、重忠の伊勢の国の所領沼田の御厨で起こった事件がきっかけだった。御厨というのは、神社の所領のことで、沼田の御厨は伊勢神宮外宮領であった。
守護、地頭の制度は創設されたばかりで、あちこちでいざこざが続いていた。とくに伊勢の地はもともとが平氏の所領であったところが多く、さらに義経が伊勢を通って奥州に逃れたということで、地頭の詮議は厳しくならざるをえなかった。
沼田の御厨でも、重忠が送った代官、内別当真正というものが、厳しく検断を行っていた。家綱の所従は外宮の権威をかさに、地頭を軽く見る所行が多く、たびたび代官真正とぶつかった。
重忠が訴えられる一月前にも、宇治蔵人三郎義定が伊勢斎宮領であった櫛田郷で起こした押領事件で訴えられ、所領を没収されている。頼朝は深く伊勢神宮を崇拝しており、神宮領内の地頭に、押領をしてはいけない、神宮の神役を必ずつとめなければいけないと、下し文を出していた。
こうしたこともあって、家綱の所従の横暴は目に余るものとなり、ついに代官真正は、その所従の宅を検断し、私財を没収するに及んだのだった。
頼朝は即座に雑色の正光を調査のために伊勢に派遣した。大神宮の神人長家は強引なまでに代官真正の横暴を訴える。正光の報告は、重忠にとっては不利なものとなった。
九月二十七日、頼朝は重忠を囚人として千葉新介胤正に召し預け、その所領四カ所を没収する命を下した。
地頭の横暴を訴えられた御家人はたくさんいたが、重忠への処分は他の例とくらべて厳重すぎるきらいがあった。少なくとも囚人として召し預けられるような処分は重忠がはじめであった。
実は、治承四年に長井の渡しで頼朝に帰服した者でこの時まで生き残っていたのは重忠だけであった。河越重頼は義経の舅ということで、所領を没収の上、殺されていた。婿舅の関係だといっても、重頼の妻は頼家の乳母比企の局の娘であり、頼家の乳母でもあった。それにも関らず殺されたのだ。
重忠はこの時二十四歳になっていた。
頼朝殿はわたしを許していなかったのだ。いや、心から信頼していなかったというべきか。重忠には身を粉にして働いたこの数年間が音をたてて崩れていくように思えた。
だが、重忠のこの数年間の働きが今回の処置を招いたとも言えた。そうした面では、重忠も義経と同じだったのかもしれない。
重忠の合戦での活躍を、頼朝は賞賛しながらも恐れつつあったのだ。義経も重忠も、御家人たちの間ではとかく人気があった。重忠は強すぎた。
さて、囚人として胤正に預けられた重忠は絶食した。夜も眠らず、一言もしゃべることもなかった。それが重忠の頼朝への抗議であった。
成清と重忠の郎党三十名ほども、重忠と同じように、鎌倉の畠山の館にて絶食し、夜も眠らず、広間に集まったままこの度の重忠への仕打ちに抗議の姿勢を取った。あの宇治河の合戦で重忠に投げられて岸に上がった大串次郎の姿もその中にあった。
一日、二日、三日。一週間がたった。重忠も、成清も、大串も、みなこのまま死ぬつもりであった。
胤正は、少しでも食べるように、と重忠に勧めるが、頑として聞き入れない。困り果てた胤正は、御所に参上して頼朝にこの事を告げる。
頼朝はちょっと困ったような顔をしたが、とりあえず、重忠の振る舞いは立派である、と言うことで赦免することにした。そうする他なかった。重忠が少しでも今回の処置に対して不満を述べたのであれば、不忠者として成敗も出来た。が、重忠の余りに潔い所作に、御家人たちの頼朝を見る目が変わりつつあった。
胤正は、すぐに屋敷に戻ると、許しが出たことを重忠に告げ、すぐに出仕するように促す。侍所に出仕した重忠は、傍輩に囲まれた。
「合戦にて手柄をたて、所領をいただくのも良いが、良い代官を見つけるのが先決だ。」
重忠は誰にともなく述懐する。もちろん、頼朝に聞かせるつもりで話していることは、その場の誰もが理解している。
「わたしは清廉を第一義として行動することを旨としてきた。命の取り合いの場でさえも、清い心でいたいと願い、いついかなる場面でも私欲のないよう心がけてきた。」
重忠の言葉にはその場にいる者の誰もが肯かざるを得なかった。重忠ほど私欲のない武者は鎌倉にはいなかったし、そのことは誰もが認めていたからだ。
「そんなわたしがこの度のような恥辱を得たのは、何よりも良い代官を持たなかったからだ。皆さまも重忠の先例にならい、何よりも良い代官をお持ちになるべきでしょう。」
重忠はそこまで言うと座を立ち、そのまま本国である武蔵の国の菅谷の館に帰っていった。成清らもそれに従った。重忠は菅谷の館で絶食によって衰えた体力の回復に努めた。一月もしないうちに成清たちをともなって牧を馬で走るまでになった。
十一月十五日になった。この日、侍所の所司である梶原景時が頼朝の所に伺候して重大事を告げた。
「畠山重忠謀反。重忠は、無実にもかかわらず囚人として恥辱を受けた事をうらんでおります。多くの勲功をたてたにも関らず、このような仕打ちを受けては我慢ならん、と一族の者を菅谷の館に集め、着々と謀反の準備を進めています。」
頼朝は即座に、和田義盛、小山朝政、結城朝光、三浦義澄、下河辺行平、等の有力御家人を召集して討議する。
「梶原景時の申すには、畠山が謀反を企てているとのこと。使いをやって詳しく様子を調べるが良いか、このまま軍を催して攻めるがよいか討議せよ。」
頼朝の言に朝光が即座に答える。
「重忠という男は生まれつき廉直にして道理をわきまえております。敢えて謀計を企てるようなことはないはずで、謀反というのは何かの間違いに違いありません。」
続けて義盛も、
「重忠とは敵味方に分かれて合戦に及んだこともありました。しかし、重忠の合戦の有り様は常に真っ正直であり、謀を行うなど全くありません。討手を差し向けるのは、詳しく調べてからで遅くはありません。」
と意見を述べる。他の者もみなそうした意見に同意する。
それでは誰を使いにやるか、ということになり、重忠とは幼年からの親友である下河辺行平がよい、ということになった。とにかく重忠とよく話をし、異心がないのであればすぐに鎌倉に連れてこい、と行平は頼朝から命じられた。
十七日、下河辺行平は菅谷の館に到着し、重忠と二人だけで話をした。
「梶原景時がそなたを謀反の罪で御所に訴えたぞ。」
行平が告げた内容は重忠にとって驚愕すべきことだった。
「わたしはそなたに二心あるとは思っていない。だからこうしてそなたを連れに来たのだ。とにかく鎌倉に上り、そなたの心根を御所の前で披露しようではないか。」
「あなたを疑うわけではないが、このように何者かの讒言によって謀反の疑いをかけられたからには、わたしを召し寄せておいて騙し討ちするつもりに違いない。それならば自戮せん。」
重忠は腰の刀を抜こうとした。
「待ちなされ。」行平は重忠の手を押さえて言う。
「そなたは鎌倉に並びなきほどの誠心誠意の人。それには及ばずとも、この行平も誠意を旨とする者。しかも、そなたは鎮守府将軍平良文の後裔であり、わたしも俵藤太以来四代に渡って鎮守府将軍を務めた家の子孫。そんな謀略を以てそなたの命をもらうのならば、この場でそうした計画をすべて話し、正々堂々と戦った方がどんなに痛快か。」
重忠は行平の言葉に納得し、酒を準備させて二人して大いに飲んだ。重忠は数カ月ぶりに笑いを取り戻し、鬱屈していた心を解放することが出来たことを行平に感謝した。
二十一日、行平に伴われた重忠は侍所に出仕した。そして、梶原景時を前にして、逆心は全くない旨陳述した。
「それならば逆心のないことを起請文にしたためて提出すべし。」
景時もこれ以上重忠を追い込むことは不可能と考えたのだろう、起請文を書かせることで事を納めようとした。
これを聞いた重忠ははなはだしく憤怒し、めったにないほど感情を面に現して言った。
「この重忠ほどの勇者であれば、その武威を笠に着て人を殺めたり、人の財物を盗んだりした、と噂されたのであればそれは恥辱なり。しかし、この度のように謀反を企てたと噂されるのならば、それはかえって眉目なり。ただし、この重忠、一旦頼朝殿を主君と仰いだからには、決して二心を抱くような男ではない。それなのに今回のように謀反の疑いがかかるというのは、この重忠に運がないからである。元より、この重忠には心と言葉が異なる、などと言うことはなく、重ねて起請文を書くなどと言うことは必要ない。このわたしが二心などない、と言ったらないのだ。このことは頼朝公が最もよくおわかりのはず。重忠がこのように申していると、疾く告げるべし。」
重忠の言に圧倒されたまま景時はことの次第を頼朝に告げる。頼朝は何も言わずに行平と重忠を呼んだ。
「重忠、明日、鶴岡で神楽がある。その後、別当円行の坊で酒宴を開くつもりだ。その方も来い。京から惣持王なる稚児を呼んである。この横笛は見事だぞ。是非、その方の今様をその横笛で聞いてみたいと思ってな。」
頼朝は謀反の一件には全く触れずに、京ではやりの今様について重忠と談笑した。そして、しばらくしてから奥に入り、行平には掘親家をして刀を与えた。重忠を連れてきた功は何事にも代え難いと言うことだった。こうしてこの一件は幕を引いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
