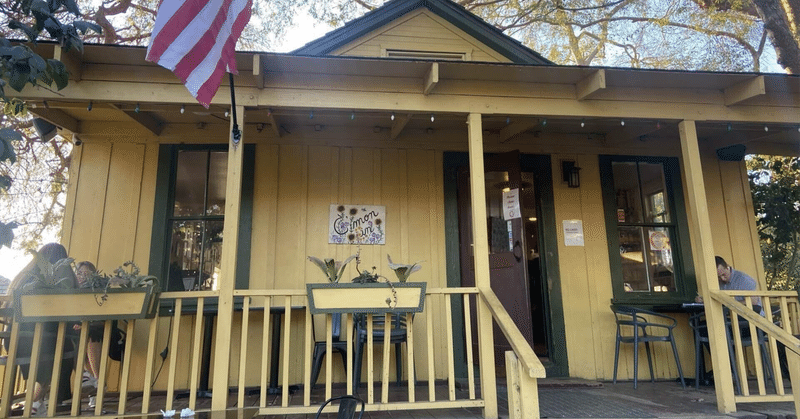
ホームスクールと制度:米国の歴史と法から日本の現状を見る
【ホームスクール研究】
メンバーシップ特典記事です。月額500円のメンバーシップ《ホームスクール資料館》に参加すると無料で読めます。
ホームスクール事例や制度はよく米国を例に取り上げているようですね。私は諸外国のホームスクール制度に詳しい訳ではありません。むしろ関心をあえて向けてきませんでした。
なぜなら。
日本には日本のホームスクールの在り方がある
それを強く感じていたからです。大部分は文化的な背景から成るもので、「学び」や「法体系」の概念の違いがありますね。日本で認識されている日本のホームスクールの在り様を明らかにしたいという衝動ですね。そのとき諸外国で使われている語句を共通用語として使い、説明を試みてきました。「ホームスクール」「ホームスクーリング」「アンスクーリング」「スクールアットホーム」「アンブレラスクーリング」などです。
日本国内で実践されているさまざまなホームスクールのありかたを、共通言語を作って理解を深めておこうと考えました。定義づけではないのですが、ある程度の認識と言語を結び付けておいて説明を簡易にすることで、伝え方を易しく進めていけるようにと整理整頓の手段です。
諸外国(ここでは特に米国)の例を挙げるときに、共通言語だと思っていたものが実は、その制度や認識に日本とは大きな違いがあることがわかりました。例えば「私立学校」です。
日本で「私立学校」といえば、公立に対しての私立であり、公立学校と同等の学習指導要領に準拠した学習課程かつ学校独自のカリキュラムがあるという意味で、公教育の括りとなる認識を持つと思います。ところが、米国の「私立学校」は日本のそれとは違うようです。またよく聞く「訴訟によって勝ち取ってきたホームスクール制度」の解釈ですが、「訴訟」のイメージ、ホームスクールの法的位置づけについても相違があるように思います。
構成は論文からの抜粋、関連すると思われる日本事情、日本でホームスクール制度を整備するための考察の三点とします。抜粋は文そのままである売位もあるし、箇条書きにしてまとめなおしている場合もあります。論文はタイトルを検索するとPDFファイルで見つかるでしょう。
『ホームスクールと学校制度 ホームスクールが問いかけるもの』
目次
『ホームスクールと学校制度 ホームスクールが問いかけるもの』
- 秦明夫(2000年)
はじめに
1学校の役割一社会性
2 アメリカにおけるホームスクールの歴史 ‘ -学校との対立の時代から協力の時代まで-
(1)学校一就学義務一の普及
(2)訴訟の果たした役割
3学校との協力関係の時代
4 ホームスクールを実践する場合の法制上の選択肢
(1)州によって様々であること
(2) ホームスクールの規制カコ厳しい州一ペンシルヴァニア州の例
(3)ホームスクールに対する規制がゆるやかな州の法制一テキサス州
(4)ホームスクールに対する規制が中間的(moderate)と言われる州 一カリフオルニア州の例一
5法制と運用一規制の実態
6学校との連携-ISPへの参加
(1)公立学校の"HomeStudy"Program
(2)私立学校のISP (Independent Study Program)
(3)チャータースクールを選ぶ方法
おわりに
論点
本稿はホームスクールの時代における学校制度の在り方の変化をアメリカの場合について考察し、我が国におけるホームスクールの可能性を探るための材料を提供することを目的とする。
・ホームスクールの登場によって学校制度がどのような影響を受け、どう変化してきたか
・ホームスクールの態様も学校の変化を受けてどのような方向に進もうとしているのか
ホームスクールを語る時に、知っておきたいキーワードや注目したところを太字で印します。
情報時代になれば教育は私事化され個人化され政治的な諸問題から解放されるという。教育の私事化の意味するところは親の教育権の問題であり、 もっと広くとらえれば自己決定権の問題であり、今日の大きな課題の一つである。
子どもの教育について責任を持つ親の権利については、我が国では今まで不思議なくらいに論議されてこなかった。戦後の我が国の教育を規定してきた 文部省対日教組という枠組みのなかでは、国家の教育権と教師の教育権は語られても親の教育権を問うことは少なかった。
教育の私事化や親の教育権については、義務教育における「義務」の意 味と共に今日の観点から改めて検討すべき問題と考える。
親の教育権
「親の教育権」について、日本では注目されてこなかったことはよく知られています。当事者である親の立場にいる人自身が、それを思いつくことが当たり前ではない社会でした。そもそも「権利」についての教育が機能しておらず、ひとりひとりのなかに個人の権利が尊重される感覚が育っていません。それは非常に大きな課題となっていて、日本社会の都合を上手く保つことに一役買っています。ただ、近年、にわかに「権利」に気づいたものの、その根底にある思想は翻されていないままだったりするので、「選択」ひとつとっても「獲得」することなく並べられた選択肢から選ばされている事実に気づかなかったりします。
「権利」の理解について、日本は未熟です。
義務教育における「義務」の意味
公教育=学校教育=義務教育。この解釈が一般的です。公教育とはガッコ教育のことであり、学校教育は就学しなければならない義務教育のことであるという認識です。学校教育の内容でなければこどもたちが受けるべき教育内容とは認められないとするような社会認識を常識だと思われているのが一般的です。のちに述べますが、これは日本の教育体系の構図そのものの課題であり、公教育をどう認めるかの障壁となっています。
果たしてこれは真実でしょうか。憲法の解釈においては「普通教育」と記されますが、普通教育とは学校教育に限定していないとされる解釈が広まりつつあります。
また小学校1年生から中学校3年生までを義務教育期間といいますが、学校の在籍生徒となる就学義務(学校教育法)と普通教育を受けさせる義務(憲法および教育基本法)については、その構造と共に「上位法優先の原則」の概念も理解する必要があります。
1 学校の役割一社会性
「一緒に学ぶことを通じて人間的に触れあうことによってこそ、生涯にわたって続く学校時代の友情ー一番貴重な宝ーが生まれる」。(略)この学校観は良き時代の学校の理念を表す代表的なものの一つであろう。ホームスクールはこのような学校の理念を否定するものではない。正確に言えばホームスクールはこのような学校の理念の否定の上に成立したのではなく、その現実の状況の中で発生してきたのである。ホームスクールと学校と対比させるとき、学校教育の理念をもってホームスクールを批判することはこの意味で方法的に間違っている。
ホームスクール批判と学校批判
どちらにも言えることですが、単純に互いの優位性を示したいばかりに比較することで不足を指摘する傾向が初めに起こりやすいものです。例えば「学校生活は集団生活だから」で始まる論争は「だから社会性は学校で養われるのだ」「だから学校では個性が無く、一律に扱われがちなのだ」などです。「学習機会」では「有資格者が行う授業」「家庭でも同等の教育を受けることができて、学力に差はない」とかです。これらはそれぞれの環境の違いから受ける恩恵について述べようとしている姿勢とは違います。「だから、そちらはだめだ。こちらが正当性があるのだ」とあるべき答えに導こうとするそして抵抗するという対立から逃れていません。
ですが論文で指摘されているように、おおよそのホームスクールの始まりは「学校に期待するこどもにとって望ましい環境が整っていない」と親が判断できるからです。それは自己決定権を持つ姿勢であり、親の教育権の行使でもあります。むしろ学校教育を選ぶときに、それらを行使していたのか否かに気づかない事実を突きつけてもいます。
ホームスクールの登場は、ただ単に学校で学ぶ以外の学習の機会を特別に承認するといったことではないでしょう。既存の教育の在り方を問い直す機会が示されたのです。ですから許可承認を受けるための必死の証明しようとする努力は的外れなものです。むしろ本来の教育の自由を求める目的からは逆効果ですらあり、学校教育の権威の保持をより頑丈なものにする手伝いとなるでしょう。ゆえに「協力の時代」の本質を見極めることは重要かと思います。
2 アメリカにおけるホームスクールの歴史 -学校との対立の時代から協力の時代まで-
(1)学校一就学義務一の普及
1852年 就学義務法の制定。
19世紀終わり 就学義務は全国にいきわたる
公立学校のプロテスタント傾向に反発するアイルランド系移民が設置したカトリック系の教会学校が増大し、学校の普及が進む
20世紀半ば 学校は教育を受けるための必要条件である意識が根付いていく
・常に、少数の人々が(さまざまな理由で)自分の子どもの教育は自ら行うことを選んだ。
1980年代 税制改革により小規模のクリスチャンスクールが次々と閉鎖。
教会学校(チャーチスクール)に子を通わせていた親たちはホームスクールを望ましい選択肢だと考えるようになる。
チャーチスクールを市場としてきた教材会社は、ホームスクールの市場価値に気づいた。
教育が果たす役割
日本で大衆の教育が始まったのは「労働力と人材の確保」といえるでしょうか。日本が世界に並ぶ大国に成長するためには家業を受け継ぐだけの若者が、外の世界を知り、より先進的な生活に憧れ、仕事を得るようになることが望ましかったでしょう。農村の国から、工業化へ、IT産業化へと政策目標が固められるたびに、若者が選ぶべき進路は舗装されます。そのために教育の場は必須でした。また教育産業という言葉もあるくらいには、教育はビジネス市場です。上記の論文で太字にした”教材会社”はkokageのホームページを知る方には心当たりがあるでしょう。日本にも大きな影響を与えています。もちろんそれは教材を扱う会社という意味ではありません。法整備にも影響を与え、公的な承認で販路拡大が実現しようとしています。
教育であれ、医療であれ、個人の生きる問題に深くかかわることはいずれも国策と、それ以上に経済によって動くものなのでした。
(2)訴訟の果たした役割
20世紀初頭
アメリカでホームスクールが認められるうえで訴訟の果たした役割が大きいことは良く知られている通りである。
・連邦憲法には教育に関する直接の規定がない
・教育行政は各州の責任
・親の子どもに対する教育権は自由権の一種(修正憲法1条)
◎親の教育権を制約する州の就学義務法制は修正憲法14条に定める方の適正手続きに適合したものでなければならない
・州が就学義務の正当性ー親の教育権を制約するに足る正当性ーを証明していないと裁判所が判断したとき親の教育権が回復される
(3)主な訴訟-何が争われたか
訴訟の最初の段階:私立学校の教育の自由の拡大
1923年、ネブラスカ州。8学年以前の子どもに外国語教育を行うことを禁止。
ある私立学校の教師がこれに反しドイツ語教育をおこなったとして有罪。
連邦最高裁は教師の教育権、生徒の学習権、一定の制限の中での親の権利(自分の子どもに何が教えられるべきかを決定する)に言及して有罪を破棄。
1925年、オレゴン州。私立学校を認めずすべてのこどもに公立学校への就学を義務付けていた州の法規を無効とする判決。
「この国の政府の基盤となる自由の理論は、州のいかなる一般的権限も子ども達に公立学校の教師からのみ教育を受けることを定めることを許容するものではない。子どもは単なる州の創造物ではない。彼らを養育しその将来に責任を有する人は、高度な義務と共に子ども達の将来の教育を見通して準備する権利を有する」。
1927年、ハワイ州。厳しい私立学校規制によって多民族からなる市民に統合とアメリカ化を強制していることを認めないと判決。
このような規制は公立学校と私立学校と相違を実質的に無いものとし「私立学校の経営者と後援者の双方の有する教師、カリキュラム及び教科書を適切に選択・管理する自由を否定し、さらには法の適正手続条項のもとでの親の権利を侵害するものである」。
1972年、連邦最高裁は、宗教上の理由で子どもに8学年以降は学校に行かせず家庭で教育したアーミッシュの親に対する有罪判決を取り消す。修正憲法14条の法の適正手続条項と同1条の信仰の自由条項の両条項に基づいて親の教育の選択の自由を初めて認めた。
子どもを私立学校で教育しようとする親の権利の問題が常にその背景に意識されている。
アメリカにおいては今日でも 「学校」 といえば公立学校を意味する。
私立学校の意味は、公立学校が共に公教育としてとらえられ両者の間にそれほど大きな差はないと考えられている我が国とはかなり異なるものがある。現在アメリカの幾つかの州ではホームスクールを認める場合、私立学校として扱うということを選択肢の一つに掲げている。 これは我が国の私立学校という観念からは理解しにくいものであるが、学校とは公立学校のことだと(乱暴に)割り切ってみれは理解できるのではないか。
訴訟という手段を取る形式的手続き
訴訟の事例を読み進めてきて、訴訟のイメージが変わりました。日本で「訴訟する」「訴える」と聞いてイメージするその意味は、「相手の非を認めさせ、相応の罰を与えることを承認させる」ことのように思います。だいたいにおいて「規則違反=罰則が与えられる」イメージを持つ人が大多数なような気がします。どちらかといえば「訴えるぞ!」と口にする人は大きな声で(静かな声でも)脅すように使いますし、それは「罰が下るぞ(私が正しい!)」を意味します。そもそも「権利を獲得するための手段」として使われているようには思えませんでした。
ところが米国のこの歴史的事実を見ていきますと、訴訟とは「手続き」であることが分かります。
(前提)ホームスクールを行うことを目的として、もしそれが制約を受けるのであれば、(①)親の教育権に対する制約が適正であるかを争点とする。(②)その正当性が認められないのであれば、(③)制約は不適切であると判決が出る。(④)ゆえに親の教育権が回復する(権利を獲得する)、という手順を踏んだ手続きです。
この手順はアメリカ的文化の土壌になっているともいえるでしょう。そのことは日本の教育現場でも、海外暮らしから日本に住むことになり、ホームスクール実践の承認を取ろうと試みる家族がどのようにして学校と対立するのかからも垣間見えます。
実際のところ日本では「ホームスクールを実践する」ことに制約は受けません。ただしホームスクールを実践することで、学校教育を標準的に受けた生徒と同様の社会的な承認は保証されない場合があるという事実はあります。日本で求められているのは社会的承認の保証のほうでしょう。アメリカでもその道のりは近年においても少しずつ良くなったとはいえ困難なこともいまだ多いでしょう。
私学教育の自由と親の教育権を法の適正手続条項が適用される「基本権」の一つとして認めている。 アメリカでは「基本権」に関わる政府の規制は全て『厳格な審査』 として知られるテストの対象となり、関係する個人の権利は政府の利益と比較衡量されるという原則が根底にある。政府は基本権に影響する行為については、全てそれが優先的利益(compelling interest) を有するものであること、 その行為はその利益を推進するのに必要であること、更に、そうすることは最小限の規制行為(least restrictive means) であることを示さなくてはならない。
私的教育一般は基本権として法の適正手続によって守られているが、ホームスクールという特定の在り方は守られているわけではない。連邦最高裁は今日までのところホームスクールを基本権として認めるかどうかに関わるような問題に直面していない。 この意味で、ホームスクールを行うことは全ての州で合法化されているけれども,未だ基本権として判例上認めらているわけではない。 したがって、ホームスクールは訴訟のなかではより制限的でない合理的な制約の有無を問うテストの対象としての地位に止まっている。
ホームスクールの法的位置づけ
この論文は2000年のものですから、2023年現在の詳細はどのようになっているのか興味深いところです。ただ法的位置づけが確固たるものになっていても、社会的な承認の度合いがそれに比例するわけではありません。世間的にどう受け止められているかについては、論文でも指摘されていますが、法整備の確立とは別の話題です。社会的承認の実現は、よく成功者の登場によってその成果を期待されます。けれども社会的承認を得ることは結果的にそうなることであって意図的にメディアに働きかけてイメージを作っていくようなことではないように思うのですが、どのような考えが一般的でしょうか。個人よりも「みんな」が重視される日本においては、大衆の持つイメージは予想外にいたるところで影響を与えているのかもしれませんね。どのようなことが考えらえるのでしょう。しかし現実に出会うひとりひとりのつきあいでは、それらは個々のつきあいかた、人との距離感で、自分の周囲の環境は作っていくことができます。イメージとリアル(現実)は往々にして一致しないということは心に留めておきたいことです。
米国においてはホームスクールは「私教育」の認識が持たれているといえるようですが、日本ではそもそも「私教育」の存在はあいまいなように思います。日本で意味する「私教育」のイメージは、例えば学習塾や予備校など、家庭が私費で賄う教育のことを主にイメージするのではないでしょうか。けれども重要なのは、実はそのような私教育を「受けることができる」事実のほうです。教育を選ぶことができる。それは経済的な意味ではなく、家庭がこどもに必要だと思う教育内容を選択することができて、それを決定することができるという事実が「私教育」という教育の自由の行使です。
この事実を権利として獲得する手段として米国では訴訟があります。
そして大きな違いとして、米国では「私教育」の地位が日本と比べて高いのではないか、ということです。
日本ではあくまで「私的な教育」に過ぎず、各家庭の経済的格差や地域の地理的な事情に左右されるようなものごとです。しかし米国ではどうやら公教育と並ぶ対等な教育の機会、教育を受ける権利のひとつとして位置づけられ、私教育がおびやかされないことを保障するものであるようにみえます。論文中にあるように私教育の自由は「基本権」として認められており、その基本権を保障する手続きが確立されているわけです。日本で例えるならば、一条校ではないフリースクールやオルタナティブスクール、インターナショナルスクール、ホームスクールで学習の機会を確保したいと考える家庭が、世間的な目を気にしたり、在籍する一条校の先生方や教育委員会や教育支援者や指導員の説得を受けて、その選択をあきらめざるを得ないというような自由の侵害を受けるようなことがあってはならないと公的に認知されることを意味します。(社会的・世間的な認知とは別です。)
日本では、この「私教育の自由が基本権として認められている」段階がありません。なぜなら、「教育=学校教育=公教育」の概念に縛られているからです。このことは法的な事実はなく、「そういうもののはずである」といった社会的認知であるにすぎないのですが、そのことはあまり知られていないのかもしれません。世間的に「学校に行かない」ことへの否定的な感情が強いことがそれを示しています。ここまで私教育の自由が自分たちにも与えられているとは考えられない理由はいったいどこにあるのでしょうか。
そして、もうひとつここでの重要な観点は、訴訟の論点は「基本権(=私教育の自由)」を守ることにあり、ホームスクールが保障されているわけではないということです。
日本でもそれは同様にある事実です。学校に登校せず(在籍手続きはしますが)、学校以外で学習を受ける自由はあります。そのひとつがホームスクールの実践であってもなんら問題はありません。しかし「ホームスクールを選ぶ権利」が法的に確立されているわけではありません。
ここから先は
ここまでお読みくださりありがとうございます! 心に響くなにかをお伝えできていたら、うれしいです。 フォロー&サポートも是非。お待ちしています。
