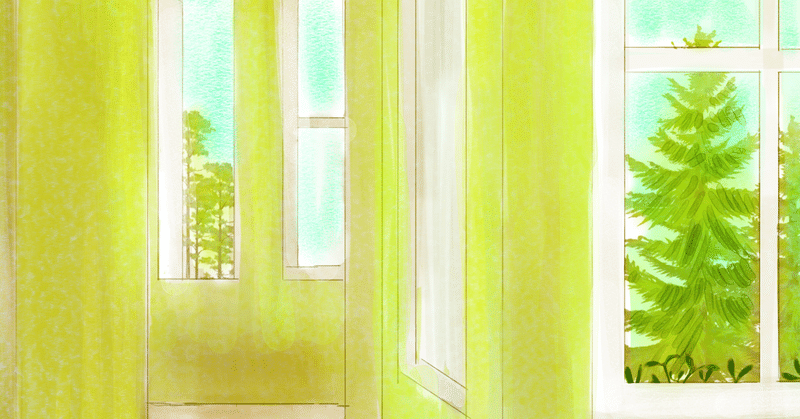
樹堂骨董店へようこそ23
那胡も七緒も互いに話したい事があったがお互い仕事が忙しかったりなんだかんだで会えないまま年末になった。
樹堂は年末の参拝客が休憩や土産物購入で来てくれるため、わりとにぎわっていた。ここ最近の売れ筋は桜杜まんじゅうだ。店の一角には休憩スペースがあり、地域で生産された飲み物や食べ物の試供品を自由にもらってその場で飲食できるので、これを目当てに来る客も多い。樹堂は地域にも貢献している。人間にも、もののけにもやさしい街づくりを目指しているのだ。
「ありがとうございましたー」
那胡の声が店内に響く。えんじ色の作務衣姿が新鮮だ。年末年始はたいてい樹堂と七緒の手伝いをすることになっている。
あの夜以来、流には会っていない。
あれからずっと那胡は何かを思い出せそうなそんなザワザワ感を抱えたままだ。あの懐中時計が流のものということは、那胡が桜杜の中でひとりぼっちで座っていたあの場所に関係あるはずなのだ。…でも思い出せなかった。もう十六年も前のことだから仕方ないことなのかもしれないけれどどうしても気になる。
「パパ」
すぐ近くで品出しをしていたイツキに那胡が話しかけた。
「流って男の人知ってる?」
イツキは作業を止めずに答えた。
「ああ。仕事を…提携しているよ。なんで流を知っているんだ?」
「この前、この店に来ててそれで…ちょっとだけ話したの」
「…話せたのか?流は標準語が苦手なんだよ」
そういえば、途切れ途切れ話していたことを那胡は思い出した。
「そういえば…なんか上手に話せない感じだったね」
「標準語じゃなければ、普通に話せるよ…」
イツキはそのままレジの奥の倉庫へ行ってしまった。
「…関西弁とかなのかな?」
那胡は頬杖をついて外を眺めた。
色の薄い青空に筆でしゅっと描いた鳥の羽みたいな雲が見えた。冬の空はいつだって色が薄く見える。それなのに道路の向こうに見える杉の森はいつだって色が濃い。深緑の森だ。
いつもと変わらない年末の風景だった。
そこへ客がやって来た。桜杜まんじゅうを二箱レジに置いた。
「いらっしゃいませ」
白髪交じりの四十代くらいの男だった。
「…この店にイツキさんという方はいらっしゃいますか?」
「…はい。おりますが、呼びますか?」
「…いや、呼ばなくても大丈夫ですよ。元気にしておられるかなと思っただけなんで」
男はにこやかに話した。
「そういえばイツキさんはおいくつになられましたか…」
「…えーと四十二才くらいだと…思います」
那胡は必死で頭の中で計算した。算数はあまり得意ではない。
「…厄年ですね」
親の年齢を思い出せない恥ずかしさから、那胡はどうでもいい情報を伝えた。
「…厄年ですか…」
男はありがとうと言って、会計を終えると店を出て行った。
那胡はなんとなく気になって倉庫にいるイツキに声をかけに行った。
「パパ…いる?」
だが、イツキはいなかった。
「あれ?いないの?…」
店の奥はどこかへ出られる出口はない。レジの前を通らないと外へは出れない。那胡はレジにずっといたので、イツキが店の奥から出てきたらどうしても気が付くはずだ。なのに、イツキが通った姿は見ていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
