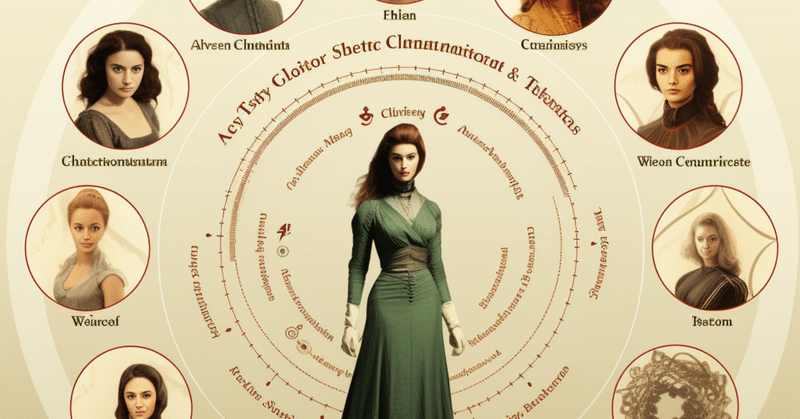
これからは"女性性"優位な時代〜今後予想される社会の変容について考察〜
皆さんこんにちは♪
※今日の話は、もしかしたら気分を害す方がいるかもしれませんが、読むのは自己責任でお願いします^ ^
誰しも"男性性"と"女性性"を兼ね備えていますが、勿論、女性の方が女性性は強いです。
このような話を考える時は100:0で考えるのではなく、あくまでも"傾向"や"全体のバランス"を踏まえて考えないといけません。
そして、どちらが良い・悪いという話でもありませんのでお気を付けください。
女性性優位の社会の特徴は以下の通りです。
・受容
・調和
・感謝
・共有、シェア
・隣人愛
・協調
・情熱、興味
・ポジティブ
・明るい
・内側への意識
・個々より全体
・依存ではなく自立
・興味、関心
・循環型
人類は何千年もの間、"男性性"優位の時代を生きてきました。
その代表例が「宗教」。
現在の宗教が確立されたのは、宗教が本格的に権威化された約3,000年くらい前。
キリスト教カトリック主義の総本山である、
ローマ・バチカンでは、祭祀は「男性しかなれない」という絶対的なルールがあります。
祭祀は「神の声を聞く」役割がありますが、なにもこれまで女性に優れた人がいなかったからではなく、そのようなルールがあるからずっと男性がその地位を独占していたのです。
そのようなルールを作ったということは、裏を返せば、女性は本来、"神秘的な力や感覚を持ち合わせていることを知っていたから"です。
「神」という外側のものに依存する、答えを求める姿勢が人間の根っこに植え付けられ、
政治や経済、社会などはこのような「依存」の価値観を基に動いてきたと言っても過言ではありません。
これには「支配」も含まれています。
世の中の多くのは会社はどのような構造になっていますか?

こんな感じですよね。
上下の関係性で、下の者は上を見て、上の者は下を見ています。
政治の世界や、昨今スキャンダルが多い芸能界も構造は同じ。なんなら、もっとガチガチのピラミッド型になっています。
私たちは学校教育で"平均点"を求められ、枠からはみ出す者は煙たがられます。
子供の時から「受験」という形で、どれだけ良い大学に行くか、という競争を子供たちは無意識にさせられているのですが、
このような構造が多くの人間にコンプレックスを抱かせるのは明らか。
そして、長い学校教育を無事に終えて社会出ると、また、「競争」の世界が待っています。
「お金のために出世をするぞ!」と、殆どの人がお金に目が眩み、生活や時間を惜しまず犠牲にします。
何故なら、お金を沢山稼げれば、
沢山の家や車、モノを「所有」でき、良い女性と結婚ができ、優雅な暮らしを送れるから。
"自分が大きくなる"感覚を味わえるので、お金を稼ぐ目的が大抵はこんな感じ。
ですが、そのためには出世をしないといけません。どんなに辛くても、理不尽でも我慢しなくてはなりません。
時には他人を蹴落としてでも、上に上がろうとすることも…!
"成功者と敗者"を生み出す仕組みで成り立っていたのが、これまでの世の中全体でした。
そして、この競争に必死になる人の多くは「男性」なんです。
支配欲や所有欲、権力欲、成功欲、自己顕示欲が強く、
怒り・コンプレックスをバネに、なにくそ精神で競争・対立する。
男性性はこのような特徴を持っています。
さて、前置きが長くなってしまいました。
今後、社会の女性性が強くなるのは、男性性を軸とした社会はもう時代に合わないからです。
ここまで男性性批判をしてしまったため、ここで少しだけ良い面も話します。
競争が激しい世界では、成功者が世に素晴らしい技術や製品を生み出してくれます。
成功・やる気というのはエネルギーの流動が活発なので、社会全体もそのように激しく流動していました。
そのおかげで、産業革命が起きてからの200年くらいは私たちの生活は豊かになったし、
その活発なエネルギーが原動力となって、世界を突き動かしていたわけです。
以前、以下のような記事を書きました。
地球は"生き物"であり、私たちと同じように覚醒期(起きている時間)があれば睡眠期もあり、明るくなることもあれば暗くなることもあるように、地球にも大きな"流れ"があるのです。
私たちの目には、「時代」の変化として捉えることができます。
ポジティブな言い方をすると、地球が次の段階に"成長"しているのでしょう。
今後、社会が女性性が強くなると、どのような変化が予想できるでしょうか?
まず間違いないのが、「組織の在り方」です。
完全に無くなりはしないでしょうが、これまでのピラミッド型の組織は少数になり、
一部の人たちだけが、旧来型の価値観で生きていくことを選ぶのでしょう。
(もう一度言いますが、どちらかが良い・悪いという話をしているのではありません。どちらを選ぶかは自由です)
縦の繋がりから横のつながりが強くなり、中央集権的な要素をできるだけ排除するのではないでしょうか。
次に「人間関係」。
従来の人間関係は家族、地元、学校、会社で出会う人たちとの繋がりがほとんどでした。
外の世界の人と繋がる機会は、自発的に何かを変えない限りはなかったし、今後もそれは変わらないと思います。
SNSが普及して、少しは外の世界との壁は薄くなりましたが、まだ、多くの人は既にある人間関係との繋がりだけに留まっています。
今後は、価値観とか生き方で繋がるようにもなっていくのではないでしょうか。
価値観が全然合わないガラパゴス化してしまった人間関係に、うんざりしてしまっている人もいるので、そのような方たちは自発的に行動すれば今後、より充実した人間関係が育まれると思います。
最後は「仕事」。
男性性優位な社会では、「競争」などの価値観が根幹にあると書きました。
女性性優位の時代には何が根幹になるのかと言えば、
「共有・感謝・共栄・循環・多様化」だと思います。
まずは共有です。
お金稼ぎに対する考え方、独占欲が薄くなるでしょう。
自分が持っているものを周りの人にシェアして、皆んなでそこから生まれる恩恵や幸せを共有する、みたいなイメージです。
自然も大切にして、自然と人間が共存・共栄していく仕組みが基礎になると思います。
多様化については、
「出る杭は打たれる」から「出る杭になれ」かもしれません。
色々な価値観が同時に存在して、これまでとは違い、お互いが互いの違いを理解する、受け入れる姿勢があるでしょう。排除はしません。
そして、最も大切なのが「感謝」。
他者に喜んでもらえることを軸とする生き方です。
これまでは自分の幸せを追求していたし、「自分の幸せは自分である程度勝ち取るもの」という、ある種の自己責任のような風潮もあったと思います。
勿論、これまでも他人や社会を豊かにするため、人を喜ばせるために様々な仕事が存在していたのは確かです。
ですが、その仕事によって喜んでくれる人は誰なのか、お互いが顔も合わせたこともなければ、やり取りをしたこともない状況でした。
また、自己犠牲も孕んでいた仕事が多いです。
他人を幸せにするにはまずは、自分のことに感謝を出来るようにならないといけません。
自分の人生・生命に感謝を出来ると、他人や外側のあらゆるものに感謝を出来るようになり、心の底から世の中のため、人のために何かをしようという気持ちが自然と湧いて来ます。
使命感や義務感、罪悪感による「仕事」ではなく、
そうした「感謝」の気持ちが前提となった働き方が浸透すると思いますし、そのような社会はとても「受容的で寛容」です。
(記事の最後に、考え方のヒントとなる翻訳した記事を載せておきます)
ここまで女性性優位の社会を予想してきました。
女性性が強くない人でも別に、私の考えに賛同する必要はなく、あくまでも個人の自由です。
自分が生きやすい方を選んで、楽しく生きればいいわけなので♪
ココに正解・不正解はありません。
因みに私は元々、男性性的な要素が他の男性と比べて薄いなと感じていて、女性と一緒に居たり話したりする方が心地良いなと思う人間です。
どうも私には普通の人が持っているなにくそ精神は薄く、「競争」の世界とは無縁ですし、出来れば対立なども避けたい。笑
女性性優位の社会の方が生きやすいと思うので、私は時代の流れに合わせて生きていきます♪
以下は、記事の翻訳です。deeplで訳してます。
『私が効果的なヘドニストを目指す理由』
あなたが自分を快楽主義者だとは思っていないでしょう。しかし、私と同じように、あなたも自分を自己犠牲の精神に駆られた人間だとは思っていないのではないだろうか。だから「利他主義」という言葉は、EA(Effective Altruist:効果的利他主義者)運動と関係があるにもかかわらず、私の心に響いたことがないのだ。心理学者として、利他主義は私たちの動機を理解する良い方法だとは思わない。利他的であろうと努力する人はほとんどいないが、人が良いことをすると良い気分になるという証拠は豊富にあり、2017年の「良いことをする科学に関する7つの事実」という記事や、行動科学者のエリザベス・ダンとマイケル・ノートンが2013年に出版した『ハッピー・マネー』に要約されている:The Science of Happier Spending)にまとめられている。
[time-brightcove not-tgx="true"].
個人的な犠牲を払うのは好きではない。しかし、私は自分自身を憧れのような人間として見ることができるように振る舞いたいのです。快楽を求め、かつ善人であるためには、ある種の錬金術が必要なのだろうか?だから、私は効果的な快楽主義者を目指しているのだ。
私が「効果的な」快楽主義という言葉を使うのは、純粋な快楽主義はしばしば自己破壊や他者への危害につながるからだ。私たちは皆、今気持ちのいいことをしたい。私たちの自動的な反応は、自分にとって何が最善なのか、あるいは自分の核となる価値観とは矛盾していることが多い。幸いなことに、私たちの大脳皮質は、認知を使って本能や社会性を上書きし、自分の行動を目標や価値観と一致させることができる。したがって、私たちは機能不全に陥った快楽的な決断、つまり私たちのウェルビーイングを最大化しない決断を避けることができる。
私たちのほとんどは、目先の快楽を求めたり、自分にとって良いとわかっていることを犠牲にして都合の良いことを求めたりしている。おそらくさらに破壊的なことに、私たちの多くは満足感や価値観を最大化しない人生の道を歩んでいる。しかし、効果的な快楽主義者は、良い気分と良いことをすることの間に二項対立を見出さない。実際、それは幼い頃から見られる。子育てコーチのフェイス・コリンズは、『Joyful Toddlers and Preschoolers』の中で、幼児ほどの「人」は、「自分よりも大きな何かに貢献しているとき、活力と根拠の両方を感じる」という考えを裏付ける研究結果があると書いている。
では、どうすれば効果的な快楽主義者になれるのだろうか?
まず、罪悪感を捨てることだ。そうすることで自分が悪者になってしまうことを恐れて、そんなことは不可能だと思うかもしれない。しかし私は、「やってごらん。罪悪感は長期的なモチベーションにはならない。2個目のケーキを食べたり、子供に不適切に怒ったり、チャリティーにもっとお金を寄付しなかったりすることに罪悪感を感じるかもしれない。しかし、その罪悪感が自分を変える助けになるでしょうか?たとえ罪悪感が前向きな行動を促すことがあったとしても、それは腐食性であり、楽しい生活の邪魔になる。
続きを読む恩返しは生まれながらの権利
効果的な快楽主義のもうひとつの鍵は、より意図的になることにある。より意図的になるには、自分の価値観を常に意識の中心に置いておく必要がある。なぜか?なぜなら、その瞬間に意識していないと、本能や社会性に頼ってしまい、自分にとって最も大切なものから外れてしまうことが多いからだ。私たちは「快楽の踏み車」に乗ってしまうかもしれない。物質的な快楽を追い求め、それが私たちの幸福を最大化する限度を超えてしまうからだ。あるいは、お金や地位のために好きでもない仕事に就いて「出世」しようとする。そもそもやるべきではない仕事に一生懸命になりすぎて、事態を悪化させる。
より意図的になる方法について、私は2つの提案をしている。一つ目は、"マインドフルネス瞑想 "を通して、一瞬一瞬の気づきを高めることだ。これは日常生活を営みながらでもできる。例えば、自分の呼吸に注意を払いながら、ゆっくりと息を吸ったり吐いたりするだけでも、落ち着きを取り戻し、周囲の状況をよりよく認識するための簡単で非常に有効な方法です。皿洗い、散歩、話し相手の話を注意深く聞くなど、日常的な作業に注意を集中することで、注意散漫と自覚の違いを学ぶことができる。意識することは、意図的な行動への重要なステップなのだ。
つ目の提案は、定期的に価値観を明確にする練習をすることだ。自分にとって何が一番大切か?私の現在の行動は、私の核となる目標に合致しているだろうか?もしそうでないなら、何を変えるべきか?私は、一度に多くのことを変えるのではなく、"自己ベスト "を目指して努力することを勧める。つまり、無理はするが達成可能な目標を設定することだ。達成したら、少し難しい目標を新たに設定し、常に "自己ベスト "を目指すのだ。
私にとって、何が自分に喜びを与え、自分が目指す人物像により近づく助けとなるかを理解することは、他人の幸福を最大化するために自分の経済的資源を使うという、効果的な寄付をすることに根ざしていた。利他主義者は、寄付を道徳的義務、他者の利益のための犠牲とみなす。効果的な快楽主義者を目指す私としては、寄付を最大化することは、良い気分になり、よりなりたい自分になるための機会であると考えたい。
私は他の人々の生活を何よりも大切にすると言っているが、最近までその価値観を実践することはほとんどなかった。19歳のときからの価値観の中核は、あらゆる形の不平等を減らす役割を果たすことだった。しかし、私は心理学者としてのキャリアに引き込まれ、その後、地位と金銭の両方に過度に焦点を当てたと今では思えるような企業経営者になった。もっと目を覚まし、もっと意図的に行動していれば、自分の価値観に合致するだけでなく、全体的な幸福感や喜びを高めるような、まったく異なる選択をしていただろう。
義務ではなく、個人的な機会を中心に据えた別のアプローチをとれば、インパクトが大きく、費用対効果の高い慈善活動や、不平等を是正するその他の活動を、より多くの人々に関連性のあるものにできると私は主張する。私は喜びを真摯に受け止めており、楽しい人生を送ることと世界をより良い場所にすることは、相互に排他的である必要はない。不平等を是正することで世界をより良い場所にするという価値を実現するためには、利他主義が必要なのではなく、むしろ効果的な快楽主義が少しは必要なのではないかという考えを、私は人々に検討し、行動するよう促す。
以上です。
読んで頂きありがとうございました♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
