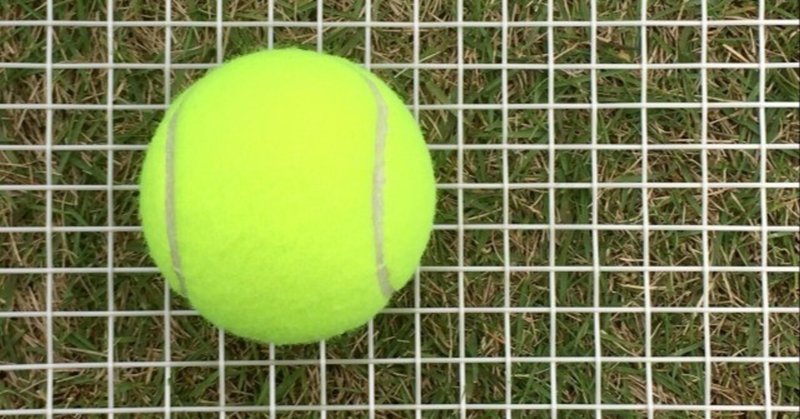
新・ボールの見方~「恐れのメガネ」を外して、ありのままに見る技術~
▶テニス上達の「本質」は、ボールが見えていること
質問します。
目隠しをして、上手くテニスをプレーできるでしょうか?
おそらく(間違えなく)、答えは「ノー」ですよね。
いえ、目隠しとは言わずとも、夕暮れ時などの薄暗い環境のなかで、テニスを、普段どおりに上手くプレーできるでしょうか?
やっぱり、明るいところで普通にプレーするのに比較して、難しいと思います。
その理由は単純で、「ボールがハッキリ見えない」からでしょう。
これはあなたに限らず、テニスの上手なプロテニスプレーヤーであっても、基本的には同じ条件です(※)。
だれであってもボールがハッキリ見えないと、テニスを上手くプレーする難易度は高くなる。
換言すれば、ボールがよりハッキリ見えるほど、テニスを上手くプレーする難易度は低くなる。
つまり、ボールがハッキリ見える条件は、上手くテニスをプレーするうえでの、何より優先される「本質」といえます。
ちなみに、ヒザを曲げるとか曲げないとか、体重移動をするとかしないとか、スタンスはオープンだとかスクエアだとかの「フォーム」は、常識的なテニス指導では散々教えられる内容ですが、果たしてそれらはテニスが上達する「本質」でしょうか?
いえ、全然本質ではありませんね。
まったく違うのです。
なぜなら、ヒザを伸ばしたままで、上手くいく人もいれば、体重移動をしても、上手く打てないシチュエーションもあるからです。
本質というのは基本的に、「例外」を認めません。
「普遍的かつ不変的」です。
ですから状況などによっていくらでも変化する「フォーム」は、テニス上達の本質ではまったくありません。
「オープンスタンスだったから、ミスしたんだ!」
「ちゃんと足を踏み込むスクエアスタンスだったら、成功したのに!」
そんなの「後づけ」です。
ショットが、オープンスタンスで上手くいく場合もあれば、スクエアスタンスでも失敗するシチュエーションもあります。
フォームというのは、プレーヤー自身が意識して形作るわけではなくて、第三者が外から見て、「ああなっている」「こうなっていた」などと表面的な見た目を説明するだけの、「後づけ」にすぎないのです。
にも関わらず、テニススクールやテニス雑誌、テニス実用書などでは、「こればかり」を教えています。
いえ、テニスに限らず、ゴルフも、野球も、卓球も、バドミントンも、日本のスポーツ指導といえば、見た目に分かりやすいフォーム矯正に腐心してばかり。
それが証拠に「清原和博はドアスイング」だの、石川遼は「手首がコッキングしすぎてシャフトがクロスするだの」、根尾昂は「グリップが体の後ろ側に入りすぎる」だの、表面的な指摘に終始する。
繰り返しになりますが「本質」とは、テニスを上手くプレーするうえで、ボールが見えるとか見えないとかの、人や状況によらず例外を認めない条件。
ボールが見えにくくなればなるほど、プレーヤーが遂行できるプレーの質は下がります。
つまりテニス上達の本質は、ボールがより、ハッキリ見える視野の確保。
ではこの「当たり前すぎる本質」を見直して、テニスのドラスティックなレベルアップを図ろうとするのが、本テキスト『新・ボールの見方』の眼目です。
※ボールに内蔵された鈴のバウンド音を頼りにプレーする、目に視覚障害のあるブラインドテニスプレーヤーを除く。
▶あなたのテニス、伸びしろしかない!
プロの試合をテレビで見ていると、行き交うラリーのボールスピードが、普段自分が趣味でテニスをプレーするときに比しても、「あれ、そんなに速くないな」と感じた経験は、ないでしょうか?
それはもちろん、身長2メートル以上のジョン・イズナーが放つ、時速200キロメートルを超えるスピードのサーブならば、テレビで見ていても「速いッ!」と感じるかもしれません。
しかしベースライン同士で打ち合うストロークのラリーボールなら、「案外、速くないな」「自分でも打ち返せるんじゃないか?」などと思えた経験があるのではないでしょうか?
もしそうだとしたら、あなたには、テニスでレベルアップする「伸びしろ」が、たっぷりと残されている証左と言えます。
▶では、友人が打つテニスボールは、なぜあんなに速いの?
しかしところがどっこい、いざ自分がテニスコート上に立つと、どうでしょうか?
プロテニスプレーヤーに比して、さほどテニスが上手いとか強いとか、決して言えないスクールのクラスメイト、あるいはサークル仲間などの友人から打たれるボールなのに、「速くてびっくりした!」という経験はないでしょうか?
人によっては、友人から打たれた瞬間にボールが自分の足元へ、すぐさま到達してくるかのような「速さの錯覚」すら、覚えるといいます。
あたかもボールが、「テレポーテーション」してきたかのような印象。
だけど、そんなわけはありませんね。
テニスは必ず、物理の法則に則ってプレーされるからです。
だとすればそう感じるのは、すなわち、相手コート側から打たれて、時間をかけながら自コート側へ飛んでくるまでのボールの過程が、「全然見えていない」からなのですね。
それで「上手くボールを打ち返せ」というほうが、「無理筋」なのです。
「時間をかけながら自コート側へ飛んでくるまでのボールの過程が、全然見えていない」。
一体なぜ、そんな不利な見え方に、なってしまうのでしょうか?
▶「恐れのメガネ」を外して、ありのままに見る技術
『新・ボールの見方』本編でも詳しく触れますが、私たちが認識できる対象は、「一時にひとつ」が原理原則です。
それが証拠に、今、これを読んでいる最中にも「空調の音」が鳴っていたかもしれないけれど、読んでいる最中だったから、聞こえなかったはず。
だけどこうして指摘されると、聞こえてきましたね。
空調の音を聞きながら、今度はこの文章を、読み進められなくなるはずです。
認識に関する「一時にひとつ」の原理原則が働くからです。
つまり、考えながら、ボールを見る両立は、かないません。
ここに、ボールを見られなくなるヒントを見出せそうです。
「上手く打てなかったらどうしよう……」
「ちゃんと入るか不安だ……」
「速いボールを打ち込まれるのが怖い……」
逆に「上手く打ちたい!」などという思いも、「上手く打てなかったらどうしよう」といった心理の裏返しで、思考による曇ったレンズを通して、ボールを見ていると言えます。
言い換えれば、入るか入らないかの結果や、相手ボールの速さ・強さなどを不安視する「怖れのメガネ」をかけて、ボールを見てしまっている。
だから、よく見えない。
▶お化け屋敷は、なぜ怖いのか?
見えないと、「怖い」のです。
お化け屋敷がなぜ怖いか、ご存知でしょうか?
真っ暗闇だからです。
まったく同じシチュエーションであっても、白日のもとにさらせば、丸見えだから全然怖くない。
ジェットコースターでも、怖いからといって目をつぶって乗れば、その怖さは半端ではありません。
ところがいざ目を開けて行き先を直視すると、怖くなくなるのです。
テニスでは、ボールを打つのが「怖い」という人がいます。
それは、ボールがハッキリ見えないから、お化け屋敷効果で、おっかなびっくりになるからです。
夜、こちらへ向かってくる車のヘッドライトが消灯していたら、怖くないですか?
ハッキリ見えないからです。
その恐怖心のせいで、体がすくんでしまう。
またハッキリ見えないと、輪郭がぼやけて背景に溶け込むから、小さく感じたりするのもプレー上のマイナス。
言い換えればハッキリ見えると、輪郭が背景から浮かび上がって映るから、ボールも大きく感じらたりするのです。
このくだりは本編でじっくり解説しますので、このまま読み進めてください。
▶ボールを客観的に見るか、主観的に見るか
結論をいってしまえば、ボールを、客観的に見られているか、主観的に見てしまっているか、の違いです。
それは、視力の強弱というよりも、集中力の使い方の巧拙。
くだんの、プロの試合の観戦例では、テレビで、あるいはコートサイドから、行き交うボールを「客観的に」見る視点に立てていたのでした。
一方、ご自身がテニスコート上に立って、スクールのクラスメイトや、サークルの仲間から打たれた飛んでくるボールを受けるときには、「主観的な」ボールの見方に、なってしまっている。
言い換えれば、客観的に見られると、現実の速度として速いはずのボールなのに、ゆっくりと感じられる一方、主観的に見てしまうと、実際にはもっと遅い速度のボールであったとしても、速く感じられてしまうという逆転現象が生じるわけなのです。
これは感覚の話ですから、だれしも経験のある、よくある「時間の経ち方問題」と、まったく同じと言えます。
すなわち同じ1分間でも、「アッという間」というほど速く感じるときもあるのに対し、なかなか時間が経たずに「まだかまだか」と待ち遠しく感じられるときもあるでしょう。
言い変えれば、同じ時間的な感覚の話ですから、テニスコート上で飛び交うボールも、待ち遠しいくらいに、ゆっくり感じられる「可能性もある」という理屈になるのですね。
その「可能性」を、手軽に手に入れていただきたいのです。
それが証拠に『新・ボールの見方』本編でも取り上げますが、野球選手のバッターがホームランを打ったとき、「相手ピッチャーの投げたボールが止まって見えた」と顧みる事例を、見聞きしたエピソードが、きっとあるかと思います。
同じ感覚つながりでいえば、究極の集中状態である「ゾーン(あるいはフローとも呼ばれる変性意識)」に入ったゴルファーは、「カップがバケツ大に見えた」とか、バスケットボールプレーヤーは、「リングがフラフープ大に見えた」とかいう、見え方の変化に由来する圧倒的な感覚変化を伝えています。
それがパフォーマンスの向上につながらないはずがありません。
このテキストは、以下のような人に向けて書きました。
■テニス上達の「本質」を知りたい人。
■頭で知るだけではなく、体で覚えて、「圧倒的なレベルアップ」を叶えたい人。
■究極の集中状態と言われる「ゾーン」、あるいは「フロー」を体験してみたい人。
■「ボールを止めてみる?」高速負荷トレーニングで、すでに備わってはいるものの、今までは使えていなかった「潜在能力」を開花させたい人。
おもしろくなってきましたね!
そういったワクワク状態の脳(アルファ波支配)で学習すると、能率は非常に高まります。
では、いよいよ本編を読み進めていきましょう。
▶noteの規約に基づく「全額返金制度」適用アリ!
本編に入るその前に。
もしもこの『新・ボールの見方』を読んでも、「テニス上達の効果をあまり見込めそうにない……」と判断された場合には、ご遠慮なくnoteが定める規約に基づいた「返金制度」が適用されます。
先に申請の手続きについて知っておけば、安心してお求めいただけると思います。
申請の手続きはこちら。
テニススクールのレッスンに、「月謝」として、いくらを費やしていますか?
対費用効果を踏まえれば、『新・ボールの見方』ならすぐに回収できて、なおかつレベルアップの度合いは、比較になりません。
試そうかどうか悩んでいて、ためらうならば、こう考えてみてはいかがでしょうか。
私自身は、ためらう時間と労力がムダだから、迷うようなら「まずやってみる」と、つねに自分に言い聞かせています。
「完璧に分かってから」を待っているのが、いつまでたっても行動に踏み出せない理由になりがちだからです。
たとえば料理や楽器演奏、投資をこれから始めるといっても、「完璧に理解してから」を待っていると、いつまで経っても絶対に始められない。
考えるよりも前に、まずやり始める。
やってみないことには分からないこともあるし、やってみて初めて分かってくることもあるから、「まずやってみる」のが出発点。
つまり、やってみないことには、スタートラインにも立てない。
時間は有限ですからね。
購入するかどうか、行ったり来たりして、迷っている時間すら、それこそ「ムダ」なのではないでしょうか?
迷う行為自体、メンタルが削られますからね。
能書きはこのくらいにしておきます。
いよいよ本編を、とうぞお楽しみください!
ここから先は
¥ 9,800
スポーツ教育にはびこる「フォーム指導」のあり方を是正し、「イメージ」と「集中力」を以ってドラマチックな上達を図る情報提供。従来のウェブ版を改め、最新の研究成果を大幅に加筆した「note版アップデートエディション」です 。https://twitter.com/tenniszero
