
母が作ったお弁当を、毎日家で食べていた頃の話 〜「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」を読んで〜
作家の岸田奈美さんのことは、タイムラインに度々流れてくるリツイートで知った。自分とほぼ同い年で、こんなに面白い書き手がいることに衝撃を受けた。
ツイッターランドの住人なら、読んだことがある人も多いだろう。
わたしもこんな文章書きた〜〜〜〜い!!!!と前のめりでnoteに登録してみたものの、気づけば1度も投稿しないまま3ヶ月が過ぎ、デスクトップの上で埃をかぶっていた。
書きたいことはたくさんあるのに、いざ書き出してみると、ちっとも面白くない。そのうち、ほんとうに書きたいことだったのか、わからなくなってくる。
わたしはもともと、書くことが好きだった。一昨年から脚本の勉強を始めて、応募した脚本がコンクールでいいところまで残ったりしたのだけど、受賞しなければ、それは日の目を見ることがない。すべて私の脳内上映で終わる。
昔、なにかのテレビ番組で、出荷されたパセリの大半が残されて捨てられるという話を聞かされたパセリ農家の方が、「おいしくできたと思ったんですけどね……」と寂しそうに俯いていたことを思い出した。
捨てられたわたしの脚本もまた、一生懸命作り、おいしくできたと思ったのだ。どこかに息を潜めるパセリを好む者に届いて欲しい!!!!
そんな経緯で、わたしは自主映画を撮って、YouTubeに載せ始めた。
監督・脚本・編集はすべてわたし。ついでにコスト削減のため、出演も半分くらいわたしだ。
しかし、YouTubeというのは海にボトルメールを流すようなもので、ただの自己満足である。その実、再生回数は引くほど伸びなかった。
わたしが電子の大海に、お手製のボトルメールをせっせと流し続けていた頃、岸田さんは今年の3月に会社をやめ、作家として独立された。
noteに記事を公開し始めてから、たった1年で独立し、著書を出版。
いや、展開早すぎるでしょ……和牛の漫才か。水田さんに振り回される川西さんの気持ちが、今なら少しわかる。
「どんな人生送ってきたらこんな文章書けるの……」
わたしは岸田さんのnoteを読むたび、そう思っていた。この力強くて面白くて優しい言葉たちは、どこから生まれるのか知りたかった。生まれながらのポジティブモンスターなのか。
年間365日のうち、300日以上はメンタルが終わってるわたしには、岸田さんが眩しかった。岸田さんのエッセイには、今のわたしに必要な言葉が書かれているのではないかと、直感的に思った。
結論からいうと、わたしは岸田さんのことを誤解していた。
岸田さんの強さは、たくさん傷ついて、たくさん悩んできた人だからこそ行き着いた、優しさから生まれたものだった。
読み終わってすぐに、わたしは母に電話した。この感情を忘れないうちに、言葉にしておこうと思ったのだ。
でも、すぐに後悔した。そんな涙腺ヨワヨワの時に、電話するんじゃなかった。母と話していたら泣きそうになってしまって、私は慌てて「今読んでた本、面白かったから、みーぬにも読んで欲しいんやけど」と話題を変えた。ちなみに私は、母をみーぬと呼んでいる。
「ちょっと待って、なんて本?忘れるからメモしなきゃ」
電話口で、みーぬがペンを探す音が聞こえる。
泣いているのがバレないように、わたしは豪快に鼻をかんでから言った。
「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」だよ。
読書感想文とは、好きな本の感想をしたためたものだ。つまり、好きなもののどこが好きなのか、言葉を尽くすということだ。
それなら書ける気がしてきた。だって、わたしは岸田さんの本が好きなのだ。読み終わったら真っ先に、母に電話したくなるくらいに。
「自信過剰」と「自意識過剰」の違い
岸田さんの半生は、波乱に満ちていた。
岸田さんのお父さんは、岸田さんが中学二年生の時に、急逝された。その頃の岸田さんのショックを思うと、胸が苦しくなる。車椅子のお母さんと、生まれつき知的障害のある弟の良太くんを、自分が支えていかなくてはと、幼いながらに思ったのではないか。
けれど、このエッセイはそういった深い悲しみに暮れたものではない。
むしろ、漫談を聞いているかのように、優しい笑いに満ちている。すごいことだ。
脚本学校に通っているとき、「シリアスな物語ほど笑いで包め、悲劇は喜劇にしろ」と散々叩き込まれてきたものの、現実で、辛いことがあったときにユーモラスに語れる人なんてそうそういない。
エッセイには、岸田さんが「どん底まで落ちた」ときの話が書かれていた。
大学生のときから、10年ずっと勤めていた会社を、はじめて休職した。
休職したかったわけではない。
でも、会社が入っているビルのエレベーターに乗り込んだ瞬間、気づいたら床に座り込んで、息ができなくなっていた。
(中略)
そしてわたしは働くことが出来なくなった。
P135
うつ状態になった岸田さんは、2ヶ月間休職することになった。読んでいると、岸田さんが人一倍真面目で、繊細な人なのだと分かる。わたしのなかの岸田さん像が、グラデーションのように変化していく。
わたしは、とにかく自分を責めていた。
「あの人が心ないことをいったのは、わたしの仕事の能力が低かったからだ」
「自分だけ休んで、みんなに迷惑かけて、わたしは本当にダメだ」
毎日、毎日、寝ても覚めても、そんなことを考えていた。
(中略)
それからわたしは、ひまさえあれば、いかに自分がダメな人間かを考えはじめた。
そうすることで、落ち込んでいる自分を正当化したかったのかもしれない。
P39
この描写に既視感を覚え、胸がざわざわした。学生時代、不登校だったときの私も、まったく同じ精神状態だったからだ。
電車で女子高生たちが集まってヒソヒソ話したり、笑ったりしているのを見ると、いまだに冷や汗をかいたり、胃が絞り込まれるような気持ちになる。わたしのことなんて、誰も気にしていないのに。
岸田さんは自分を責め続け、「みんなが当たり前にできることができない」「どうにかがんばってみても、失敗ばかり」と、みるみる自信をなくしていく。つらい。
弟の良太くんは、そんな岸田さんを旅行に誘った。きっと、弱りきった岸田さんが発しているSOSを感じとったのだろう。
しかし、旅行先に向かうバス停で事件は起きる。係員さんに「両替ができませんので、小銭のご用意を」と言われ、焦る岸田さん。小銭を持っていなかったのだ。バスにはなんとしても乗り遅れたくない。
小さな出来事かもしれないが、うつ状態のときは「物事が思った通りに進まない」というだけで、パニックになったり、必要以上に落ち込んだりしてしまうものだ。自分がそうだったので、読みながらにわかに緊張してきた。
岸田さんは良太くんに1000円札を握らせ、インフォメーションでくずしてもらうようにお願いする。良太くんの背中を見送りながら、岸田さんは即座に後悔する。
“間違えた。良太が列にならんで、わたしがくずしてきた方が、よかった。そもそも良太に、札をくずす、という言葉が伝わるのだろうか”と。
しかし、良太くんは堂々と戻ってきた。左手に小銭を、右手にコカコーラのペットボトルを持って。
なぜ良太は、やったこともない両替をやってのけたのか。
たぶん、こんな感じのことを考えたんだと思う。
「姉ちゃんが丸いお金を欲しがってる」
「そういえば、自動販売機に紙のお金を入れてジュースを買ったら、丸いお金が出てきたはず」
「どうせなら、ぼくが好きなコーラを買っとこう」
(中略)
良太は、これまでの人生で得てきたなんとなくの経験値と、まわりの大人のみようみまねで、わたしの窮地を救ってくれたのだった。
P47
岸田さんはそんな良太くんを見て、「もしかして、助けてあげなければいけないどころか、良太はわたしよりたくましい存在かもしれない」と思ったらしい。
岸田さんはこの出来事を機に、目が覚めたという。
人と同じようにできない自分を、迷惑をかけている自分を、恥ずかしく思ったり、情けなく思ったりしていたのは、だれでもない、自分だった。
(中略)
でも良太を見てみろ。当たり前のことをうまくやれなくたって、彼の人生はうまくいってる。〜楽しくやらない方が、損なのだ。両替するために、コーラだって飲んでいいのだ。
P48
わたしはこのエピソードが大好きだ。落ち込んでいるときは、元気づけようと下手に言葉をかけられるより、「ひとりじゃないよ」とそばにいてくれる方が慰められるということが、往々にしてある。良太くんのコーラは、思いがけず姉の窮地を救ったようだ。
めちゃくちゃいい話だし、コカコーラははやくこの実話をもとにしたCMを撮ったらいい。
わたしはふと、学生の時、ある先生が言ってくれた言葉を思い出していた。
わたしが鏡を覗き込んでいたとき、先生は笑って「大丈夫、可愛いよ」と言ってくれた。恥ずかしくなったわたしは、「可愛いから見てるわけじゃない」と慌てた。
「あなたは自分が好きなわけじゃなくて、自分のことが気になって仕方ないだけだよ。それは自意識過剰ではあるけれど、自信過剰とはちがうから、大丈夫」
先生は、たしかそう言った。
「女が鏡に映して自分を見るのは、自分の姿をみるためでなく、自分がどんなふうに他人に見られるかを確かめるためだ」と言ったのはアンリドレニエだが、今ならその意味が分かる。ナルシズムと自己嫌悪は紙一重だ。わたしは自分に自信がなくて、自分が嫌で、人にどう思われているのか、いつも怯えていた。自分の価値や評価をすべて他人に委ねているうちは、どうしたってしんどかった。
あのときの先生の言葉が、わたしのなかに澱のように沈んでいた石を、少しだけ取り除いてくれた気がする。傷つけることもあれば、羅針盤のように導いてくれることもあるのだから、言葉というのは不思議な魔力を持っている。
この旅行を終えた岸田さんは、なんとなく「ああ、もう大丈夫だな」と思え、しばらくして会社に復帰出来たそうだ。
そんな岸田さんが作家になったいきさつには、お母さんの影響が大きいようだった。
「死にたいなら死んでもいいよ」と言える2億パーセントの自信
岸田さんが高校1年生のとき、お母さんが倒れ、車いすでの生活を余儀なくされた。
いつも気丈に振る舞うお母さんが人知れず泣いているところを見てしまった岸田さんは、ひどくショックを受けた。
ようやく外出許可の降りたお母さんと出かける岸田さん。しかし、エレベーターがなかったり、通路が狭かったりと、車いすで生活することの不便さを目の当たりにした。楽しみにしていたお店にも車いすでは入ることはできず、疲れ果てたお母さんは泣き出してしまったという。
「あのね、ママね、ずっと奈美ちゃんにいえなかったことがあるねん」
なんとなく、いいたいことはわかっていた。
「ほんまは生きてることがつらい。ずっと死にたいって思ってた」
(中略)
「そんなこといわないで」「死なないで」そういう言葉は、ひとつも口をついて出てこなかった。わかっていた。そんな言葉がなんの力にもならないほど、母が絶望していることを。
P59
しかし、岸田さんは言った。
「ママ、死にたいなら、死んでもいいよ」と。
そしてこう続ける。
「もう少しだけわたしに時間をちょうだい。ママが、生きててよかったと思えるように、なんとかするから」「2億パーセント、大丈夫!」
背中に冷たいナイフを当てられたようだった。
もしも私が母に「死にたい」と言われたら、「死んでもいいよ」なんて言えるだろうか。「2億パーセント大丈夫」と、笑い飛ばせる強さはあるだろうか。きっと、「そんなこと言わないで」と一緒に泣いてしまうに違いない。
彼女の強さは、どこからくるのだろうか。
岸田さんはビジネスチャンスに出会ったとき、「ちょっとだけデザインができます!」と言ってのけたり、ちょいちょいハッタリ(失礼)をぶちかましているのだが、彼女は根底に、「絶対なんとかなる、ていうかする!」という自信がある。
そうして岸田さんは、お母さんが生きててよかったと思える社会をつくるため、福祉と経営を一緒に学べる日本にひとつしかない大学に進学し、そこで出会った仲間と会社を立ち上げ、3年後にお母さんを雇用したのだ。
もちろんデザインも、後日デザイン本を購入し、ちゃんとできるようになってしまう。
「2億パーセント大丈夫!」
まるで言霊のように、岸田さんの言葉は現実になっていく。
なんだこのとんでもない行動力は……。
鬼滅の刃で、主人公・炭治郎が序盤からいきなり巨大な岩を真っ二つにしたときは「そんな強かったん……?」と動揺したが、その炭治郎に匹敵する成長スピードである。
先の分からない未来を切り開いていくのに必要なのは、この「なんとかなる」という根拠のない自信なのかもしれない。行動は、あとからいくらでもついてくる。岸田さんの行動力の源泉はいつも、「家族のため」という純粋な熱情だった。
読み進めるほどに、感嘆と共感がないまぜになって押し寄せてくる。
同時に、自分のなかにあった迷いが、ゆっくり溶けていくのを感じた。わたしはずっと、自分なんかが岸田さんに「共感した」と言っていいのだろうか、と思っていた。
母が作ったお弁当を、毎日家で食べていた
岸田さんはお母さんと良太くんを支え続けてきたけれど、わたしはこれまで家族に対して圧倒的迷惑をかけ続け、なにもできていない。比べるのはおこがましいのではないか。
しかし、岸田さんの言葉に触れていると、そんな自意識過剰な迷いが薄れていく。岸田さんの言葉は、誰も傷つけない。まるごと抱きしめてくれる。
わたしは中学、高校と学校に行けなかった。不登校というと部屋から1歩も出ないさまを想像されるが、実際は、少し行ってはまた行けなくなるということをループしていた。
学校に行かない間なにをしてたかというと、毎日明け方まで本を読み、昼過ぎまで寝て、規則正しく精密に引きこもっていた。母が部屋まで運んでくれるご飯をもそもそ食べ、また本を読んだり、父のギターを弾いたり、時折思い出したように勉強したりした。
目が覚めると、枕元には毎日、母の作ったお弁当が置いてあった。天てれを見ながらそのお弁当を食べるのが、わたしの日課だった。
「どうせ行かんから作らんといて」と何度言っても、母は3年間、毎日作り続けた。
「もしかしたら、今日は行きたくなるかもしれないと思って」と言って聞かなかった。いらんって言っとんのになんで作るんや、と、わたしは内心不服だった。
ひどいことを言ったり、怒って口をきかなかったりした次の日も、目が覚めると必ずお弁当が置いてあった。素直に食べるのが癪な日もあったが、悲しくても怒ってもおなかは空くので、残さず食べた。
この本を読み終わってから母に電話したとき、「今まででいちばん悲しかったことってなに?」と聞いてみた。母にそんな質問をしたのは、初めてのことだった。
母はしばらく考えていたが、「あなたが学校に行けなくて、毎日部屋にひとりでぽつんとしていたのは、かわいそうで仕方なかった」と言った。
あのとき「学校に行きなさい」と言われることは、どうにも苦痛だった。
はじめのうちは口うるさく言っていた両親も、次第に諦めてなにも言わなくなった。
その代わりに、母は毎朝お弁当を作った。「いつか行きたくなったときに、お弁当なかったら困るでしょ」と笑いながら、来る日も来る日も作ってくれた。
あれは母なりのエールだったのだと今になって気づいて、冒頭に書いた通り、思わず泣いてしまった。
ここまで読んでくださった方はお察しと思うが、わたしの母親は過保護だ。
よくある普通の過保護ではなく、筋金入りの過保護なのだ。
中学のとき、わたしには好きな男の子がいた。勝地涼さんに似ていたので、仮に勝地と呼ばせてもらう。勝地くんとはほとんど喋ったことはなかったが、ひとりでグラウンドを走っているところを見て、なんかいいなと思っていた。
そんな話を母にしたら、わたしのためにひと肌脱ごうと思ったのだろう。
勝手に学校に乗り込み、自転車置き場で勝地くんの写真を撮ってきてしまった。
あろうことか「勝地くんいますか?」と生徒たちに聞いて回り撮ったという。
討ち取った敵の首を引っさげ凱旋する戦国武将のごとく、絵にかいたようなドヤ顔をする母に、なんちゅうことしてくれたんや……とわたしはひっくり返った。羞恥という死因があれば、わたしは当時即死だったに違いない。
一応写真をみせてもらうと、引きつった笑顔で控えめにピースした勝地くんが写っていた。どこからどう見ても戸惑っていた。知らないおばさんにいきなり写真を撮られて怖かったよね。ごめんね勝地くん……。
過保護といえば、3年ほど前に「過保護のカホコ」というドラマがあったが、放送を見たわたしは衝撃を受けた。わたしが母から言われてきたこと、されてきたことが、そっくりそのままだったからだ。まかり間違って監修に我が母の名前がないか、クレジットを隈なく探したほどだ。
まぁ厳密にいうとところどころ違いはあって、特に高畑充希さん演じるカホコのようなピュアな心があるかというのが決定的な違いなのだけど。
ふてぶてしい岐阜のカホコは、過保護な母を受け入れられなかった。過剰に甘やかす母に対して、わたしはこれでもかと反発した。
あのときのわたしは、ひとを傷つけるために傷つけている節があった。
小さな子どもが愛情確認をするのに「試し行動」をすることがある。「自分にどれくらい愛情があるのか」「こんなことをしても受け入れてくれるのか」を試すために、わざと困らせることをして大人の反応を伺うのだ。
わたしはまるで小さな子どもだった。どれほどひどいことを言っても、悪いことをしても、変わらず愛してくれるのか確かめずにはいられなかったのだと思う。
母との関係が良くなったのは、というより、わたしが母にきちんと向き合えるようになったのは、大学に行って、はじめて親友ができて、お豆腐メンタルが回復してからだった。
上京したわたしは魔女の宅急便よろしく、人間関係を模索しながら立派に自立していく手筈だったが、あまり両親が喜ぶような仕事をしてこなかったので、来るのは心配のLINEばかりで、到底キキにはなれなかった。
おちこんだりもしたけれど、わたしはげんきです……。

学校も会社も、それが世界のすべてではない
几帳面で活発な母と、ルーズでインドアなわたしは正反対だが、わたしはどちらかというと父に似ている。父はとても変わっていて、「いらんことしい」で、よくある『B型あるある』みたいなのがすべて当てはまる面白おじさんだ。
わたしは自分のこれまでの選択の節々に、父の存在を感じることがある。父ならきっとこうするのではないかと、不思議とそう思うのだ。
自分の話ばかりになってしまったが、岸田さんも、どうやらお父さんに似ているらしい。お父さんとのエピソードを読んでいると、岸田さんの類稀なる才能は、お父さん譲りのものなのだとよく分かる。
岸田さんのお父さんは新しいものが好きで、先見の明があり、爆発的な人気だったファービーを始め、当時珍しかったiMacを買ってくれたそうだ。
ある日、学校に居心地の悪さを感じ、家でしょんぼりしていた岸田さんに、お父さんは言う。
「お前の友だちなんか、パソコンの向こうにいくらでもおる」
P97
その言葉どおり、岸田さんはインターネットを通して、たくさんの友だちに出会った。チャットで、知らない人たちと、好きなアニメや漫画の話をした。
学校にいるときは教室が世界のすべてだと錯覚してしまうからしんどくなる。
お父さんの言葉は、どれほど岸田さんを救っただろう。
大丈夫。学校がすべてじゃない。会社がすべてじゃない。
誰かが何気なく言ってくれたそんな言葉が、まるでお守りみたいに、自分を支えてくれることがある。わたしの父もかつてわたしに、「学校がすべてじゃない」と言ってくれた。
わたしはやることなすことすべてが異常に遅くて、みんなと歩幅が合わせられなかった。担任の先生に「あなたはちょっとおかしいじゃない?普通に就職したり生活したりできないと思うから心配」と言われたときは、心底落ち込んだ。実際、普通に就職したりできなかったのだから、先生は正しかったのだけれど。
大人になってようようわかったことだが、わたしは衝動型の発達障害だった。
それまでは、わたしが単にいい加減なだらしのない人間なのだと思っていた。いちばん困るのは、集中しているとき、とくに本を読んでいるときに、周りがまったく見えなくなることだった。過集中というらしい。止められないと、食べるのも寝るのも忘れて30時間Macbookに向かっていたりする。
話しかけられたら、一応適当に返事はしているらしく、「言ったのに」「約束したのに」と怒られることが多かった。まったく覚えていないので、正直不本意だった。
その日も例のごとく、「Aちゃんの家で遊ぶ」という約束に生返事していたらしい。
ホームルームが終わってもポヤポヤしていたわたしが昇降口を出ると、目を三角にしたAちゃんたちが立っていた。約束したのに、待ってたのに、なんでこんなに遅いんだとなじられ、びっくりした。謝っても謝っても許してもらえない。Aちゃんは、「悪いと思ってるならここで土下座してよ」と言った。
Aちゃんに許してもらえる手段はそれしかないように思われたので、わたしはコンクリートに土下座した。砂利や尖った石が多くて痛かったけれど、友だちを失うよりずっといいと思った。
Aちゃんたちは、土下座したわたしを見て、笑いながら帰ってしまった。
わたしはひとりでとぼとぼ帰りながら、Aちゃんはあれで許してくれたのかなあと考えていた。なんだか、急に悲しくなった。
わんわん泣きながら帰ってきたわたしから事情聴取した母は、青ざめて学校に電話をかけはじめた。父はというと、なぜかわたしに怒りはじめた。この状況で怒るなんて鬼かよと思ったけれど、わたしは今でも父の言葉を覚えている。
「ほんとうに悪いと思ったとき以外、土下座なんてするな」と父は言った。
「情けない」「もっとプライドを持て」と。
わたしにとっては、「立て!立つんだジョー!」に勝るとも劣らない名言であった。割れんばかりの歓声を浴びながら、わたしはよろよろと立ち上がり、拳を高い位置に構えた(ような気がした)。
Aちゃんとはそれきり遊ばなくなり、ジョーは見事に孤立したが、今となってみればそれでよかったと思う。
わたしが良くも悪くもプライドが高く見栄っ張りなのは、父の教育によるものだと確信している。おかげでわたしは、わたしを傷つける人からは、光のはやさで離れるようになった。たとえ冗談でも嫌なことを言われたら空気を読まずに帰るし、毎度毎度土下座する半沢直樹を見ては、正気の沙汰じゃねえと思っている。
岸田さんのお父さんが岸田さんに残したものは、知らず知らずのうちに刻印のように浮かび上がり、きっと今も、彼女のなかに息づいている。そうして時折、岸田さんの背中を押したり、喝を入れたりしてくれているのだろう。
傷を愛せるか
つらい日々を過ごしてきた岸田さんは、自分を守る術を身につけた。
よくまわりの人から「つらいことばかりの人生を、よくがんばってきたね」とほめてもらえることがあるが、恐れ多くて仕方がない。
わたしにとって生きるというのは、がんばることではなかった。ただ毎日「死なない」という選択を繰り返してきただけの結果だ。
(中略)
その代わり、忘れることにした。楽しい思い出も、悲しい死に様も、心の隅に追いやった。そしたら、つらくないことに、気がついた。
父が死んだら、父のことを考えないようにした。母が倒れたら、母のことを考えないようにした。
P115
嵐の夜を幾度も乗り越えてきた岸田さんは、自分には「忘れる才能」があったという。
つらいこと、いやなことは、無理して乗り越えなくていい。逃げたって忘れたっていい。そうして生きのびているうちに、いつか、忘れるのがもったいないような瞬間に出会うことがあるかもしれない。
ある時、実家に帰省した岸田さんは、お母さんと弟とおばあちゃんで回転寿司に行った。
「あんたもっと食べえな!しゃべってばっかおらんと」と怒りながら笑うおばあちゃん。
せっせとお茶をいれてくれたが、粉末の抹茶と生わさびの容器を間違えている弟。
「これはワサビや!ドリフかあんたは!」と泣き、喜ぶ岸田さん。
我先にとオニオンサーモンを集めるお母さん。
笑っていたり泣いていたり、騒がしくて愉快な家族だ。
岸田さんがなぜこれほど鮮明に描写できたのかというと、スマホのメモ帳に書き留めていたからだという。ほとんど衝動に近いその行動に、わたしは「愛おしい」ってこういうことなのかと膝を打った。
わたしは忘れるから、書こうとするのだ。
後から、情景も、感動も、においすらも、思い出せるように。
つらいことがあったら、心置きなく、忘れてもいいように。父のときみたいに、もう忘れたりしないように。
P117
岸田さんのエッセイは、ロードムービーのようだ。監督は岸田さん。出演者はもちろん、岸田家の皆さんだ。「大切な瞬間を残しておきたい」という純粋な衝動でカメラを構える岸田監督は、最高のキャスト陣と、筋書きのない物語を紡いでいる。岸田さんのフィルターを通して切り取った世界は、ユーモアと愛で彩られている。
わたしが初めて撮った映像は、なにを隠そう母だ。天然な母は言動がいちいち面白いので、いつもこっそりカメラを回している。まったく映画と呼べるような代物ではないけれど、今でもたまに見返してはニヤニヤしている。

わたしはきっと、いまを忘れるだろうけど。
だから、今年も書いていきたい。知らない誰かが、笑ってわたしの過去を、思い出してくれるように。重い人生だから、せめて足どりくらいは軽くいたいんだ。
P120
ハートを傷つけたら、あなたも傷ついちゃう
わたしは今まで、誰かに言われた言葉を反芻しては、自分で自分に呪いをかけていた。昔のことも、人に話すようなことではない、つらいだけの話だと思っていた。
でも、どこに目を向けるかで、その物語の持つ意味は変わってくる。同じ物語なら、楽しんだほうがいいに決まってる。
稀代の喜劇王・チャップリンが演じれば、盲目のヒロインとの悲恋も喜劇になる。
岸田奈美が書けば、悲しい記憶も、何気ない風景や日常も、いつだって喜劇になり得るのだ。
少し話は戻るが、相手が自分にどれくらい愛情があるのかを探ってしまう、「試し行動」。
恥ずかしい話だけど、わたしは大人になった今でも、この癖が直らなかった。無意識に家族や周りの人を傷つけて、自己嫌悪に陥ることを繰り返している。
そんな悩みを友だちに話したとき、どうしてそんなことするの?と平然と言われた。
「家族も恋人も、あなたのハートのなかにいる人でしょう?ハートを傷つけたら、あなたも一緒に傷ついちゃう」
思わず言葉を失った。メルヘンな表現だが、彼女の言うとおりだった。
ひどいことを言ったりしたりすると、傷つく相手を見て安心する反面、同じくらい自分も傷ついていた。ずいぶん凶暴な、ヤマアラシのジレンマだった。
逆をいえば、誰かを大切にできているときは、心が凪のときだった。
人は、自分を投影した誰かや何かを愛することで、自然と自分を愛し、許せるようになるのではないかと思う。わたしにとって、そしてきっと岸田さんにとっても、それが家族なのだろう。
愛がもし目に見えるなら、それはたとえば、岸田さんの言葉だ。岸田さんが物事を面白く捉える才能に溢れているのは、岸田奈美を岸田奈美たらしめた、家族からのギフトだ。
わたしもいつか、家族のことを話して、誰かに笑ってほしい。
そんな衝動に任せて、こんな「誰が読むねん、暇ちゃうぞ」みたいな長文(狂気の1万2000字越え)を書いてしまった。でも、誰も読んでくれなくても、家族が読んで、そんなこともあったねと笑ってくれたら、それでオッケーだ。
実は、母に電話したとき、最後に「今まででいちばん幸せだったことは?」と聞いてみた。母は即座に答えてくれた。
「そんなのいっぱいあるよ。東寺でお花見したのも楽しかったし、〇〇でお食事したのも楽しかったし……」
母の羅列する幸せには、すべてわたしがいた。色々あったけど、母は楽しかった記憶だけを切り取り、「いろいろあったけど幸せだった」と言ってくれた。喜劇王3人目の刺客は、母だった。まさかのダークホースである。
こんな家族と一緒なら、この先の物語だって、面白可笑しく作っていける気がした。筋書きはとくにないけれど、ハッピーエンドってことだけは決めている。
ボトルメールはインドネシアにたどり着いた
後日談のようになるが、のんびりやっていたわたしのYouTubeにも異変が起きた。
短編映画のひとつ、「美味しい彼女」が、突如として1日に10万回ずつ再生され始め、再生回数が1300万回を超えたのだ。
3000件以上届いたコメントは、あらゆる国の言語だった。突然の出来事に、嬉しいよりも「Why……?」という戸惑いのほうが大きかった。
だってこれ、「いちご大福がいかにセクシーな食べ物か知らしめたい」というわたしの妄言を映像化した、トチ狂った内容なのだ。
しかし、何はともあれ、浮いたり沈んだりしながら漂っていたわたしのボトルメールが、海の向こうまで届いたことだけはたしかだ。
(コメントが気になって片っ端から翻訳にかけていたのだが、「Is this YouTube?」というコメントがあって笑った。Pornhubじゃなくてごめん……成人向けなので、くれぐれも会社や電車内で開かないように注意してほしい。)
この短編は、公開してすぐは身内から否定的な意見もあって、これが面白いって思ってるの世界でわたしだけなんかな……とナーバスになっていたけれど、こうして「誰かに届いた」ということが、続ける自信に繋がった。大丈夫、わたしは少しずつ、確実に前を向いている。
「つらくなったらいつでも話を聞くよ」「ひとりじゃないよ」ということが、言葉でも、態度でも伝われば、ただそれだけで。
岸田さんの言葉はこれからのわたしを守ってくれる気がして、栞を挟むかわりに、こうして書き残しておいた。頑張れなくなったら、何度でもこのnoteを読み返したらいい。

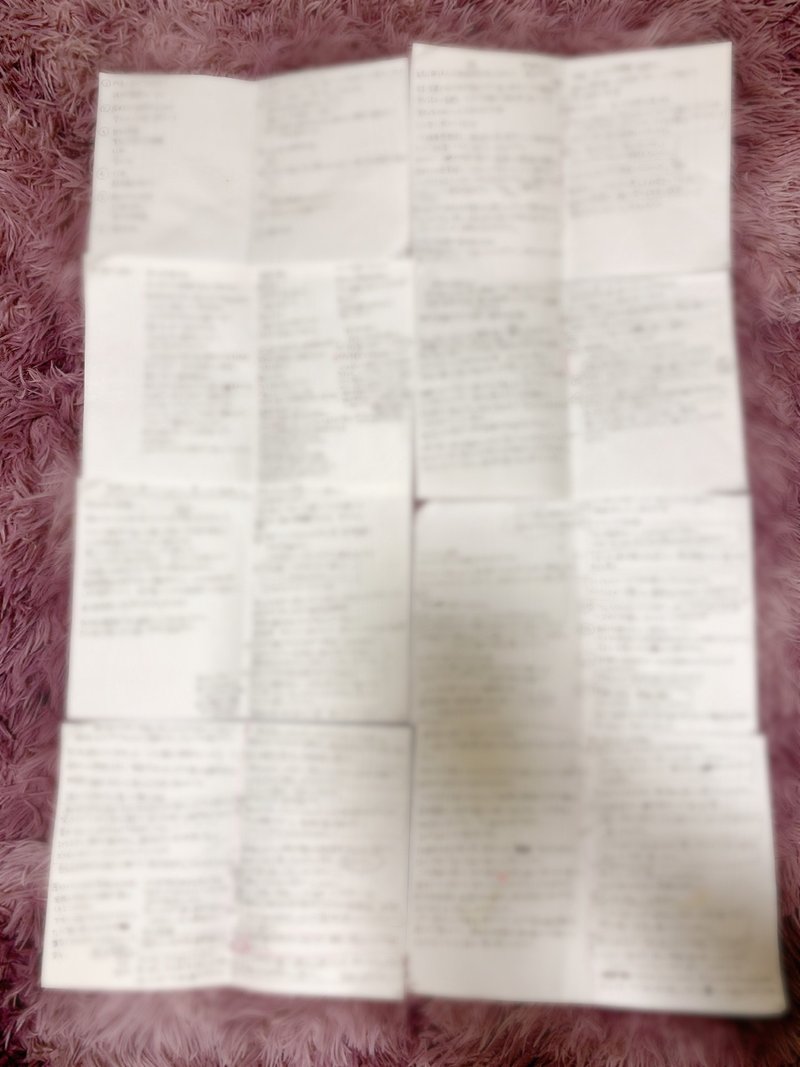
夢中でメモを取りながら書いていたら、すごい量になってしまった。
この記事の下書きを家族に見せたところ、「熱量が卒論やん……」とドン引かれた。この感想文を持って、わたしも「わたしなんて」から、少しずつ卒業したい。
いただいたサポートは、すてきな記事を書くために使わせていただきます。「スキ」を押していただくと、わたしの好きなムーミン谷の名言が出てきます。
