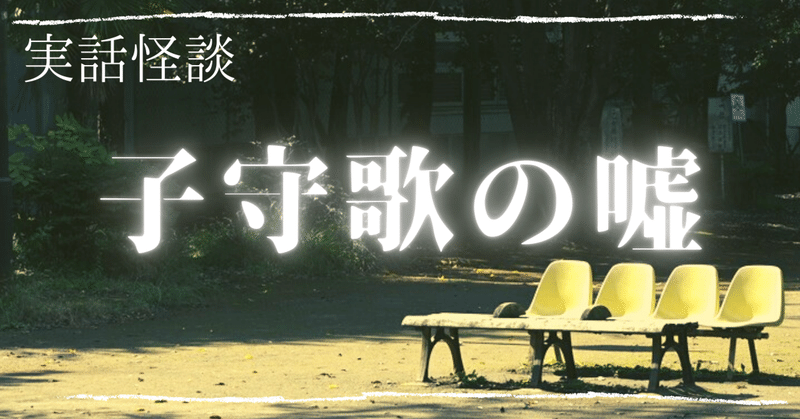
子守歌の嘘
新宿区のはずれに小さい公園がある。
トイレとゴミ箱、それに地域の備品を置く物置があるだけ。
大学や専門学校が近いこともあり、そこで酒盛りをする学生がいた。
新田さんの先輩である斎藤さんもその1人だったそうだ。
夏の盛り。学校は夏休み中だった。
偶然、街で斎藤さんに会った。
久しぶりに見る彼は、見てわかるほど痩せていた。
「なぁ新田。あの公園、出るんだよ」
「何がですか」
「オバケ」
斎藤さんの真剣な表情に、新田さんは怯んだ。
少しせり出た眼球がこちらを睨む。
「だから、近寄るなよ」
それだけ言うと斉藤さんはその場を去った。
そう言われても、無茶な話だった。
なぜなら新田さんの住まう学生会館は、その公園を横切るほかないのだ。
その夜、恐る恐る例の公園を横切った。
珍しく学生らはおらず、無人だった。
ねーむれ ねーむれ ははのむねに……
新田さんが通り過ぎる直前。
子守歌が聞こえた。
同時に、後頭部にぞわりとした悪寒が走る。
耳の産毛までが粟立つような感覚。
生まれて初めてのことだった。
ーーこれは、聞いて大丈夫な歌なのだろうか。
見通しのいい公園。
無人には間違いなかった。
悪寒は酷くなり、全身の毛穴から汗が吹き出す。
斎藤さんの言うオバケとはこの歌の主ではないだろうか。
しかし、見渡して確認する勇気は持てなかった。
新田さんは即座に走った。
そして家に着くなり布団に潜り込み、斎藤さんに電話した。
「先輩、昼間の話なんですが」
「あぁ、オバケ?」
電話の向こうは宴会の雰囲気が漂っていた。
「あれウソ! 最近、公園で酒盛りすんなって学校から連絡きてさ。ただ注意してまわるよりは面白いかなーって」
「ウソ……? 子守歌は?」
「お前に子守歌が聞こえるって話したっけ? 確かにそういう設定だけど。あぁ、誰かから聞いたんだろ?」
何と答えればいいのか、言い淀んだ。
そして、次の瞬間、耳を疑った。
ねーむれ ねーむれ ははのむねに……
宴会のざわめきに混ざり、あの子守歌が確かに聞こえたのだ。
「おい。どうした? なぁ、お前もここに来いよ。飲もうぜ」
「す、すみません。今日はやめときます……」
通話を切ると、今度は窓の外から子守歌が聞こえた。
――ウソのはずだろ?
イヤホンを耳にねじ込み、大音量で音楽を流した。
うっかり子守歌が聞こえることがないようにだ。
結局そのまま眠れず、朝になった。
公園を横切ったが、拍子抜けするほど何も無かった。
それ以降、夕方や夜、どのような時間だとしても歌声らしいものは聞こえなかった。
やはりウソで、自分の思い込みから幻聴が聞こえてしまったのだろう。そう思った。
学校が始まり、斎藤さんに文句ひとつでも言おうとしたが見つからない。
電話も繋がらず、人に尋ねても誰もが同じ状態だった。
斎藤さんが交通事故で亡くなっていたと知ったのは、だいぶ後の事だった。
葬式は桜散る頃だったそうだ。
夏には、この世の人ではなかったという。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
