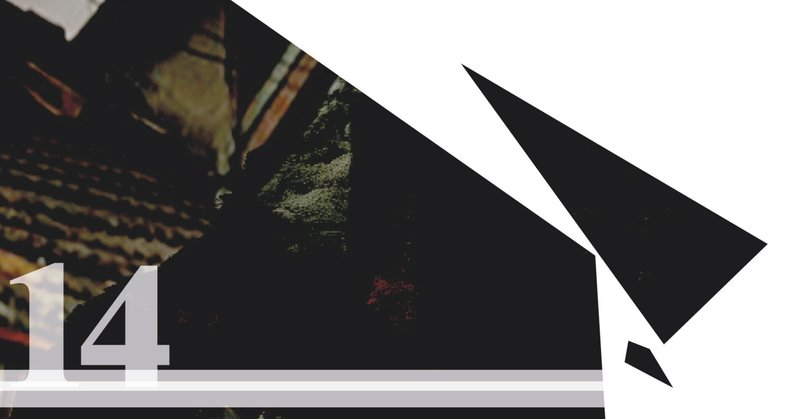
14. ぶどうからコマドリ
ある冬の日の午後、お茶請けに出したぶどうの中に、呪いを見つけた。
スーパーで買ったパック果物だったので、少し驚いた。そういえば、昨日は急いでいて、あまり中身を確かめずにカゴにいれたのだった。こういうこともあるから、なんでもおざなりにしてはいけない。
他の房をつまんで見ても、呪いはそこにしかついていなかった。
小さな、未成熟の実である。固くて青い。誰も食べそうにないぶどうに呪いをかける意味がない。恐らく、意図して付けたものではなく、天然発生した呪いなのだろう。
「おじいさま、どうしましたか」
グリーンルームに備え付けたテーブルの、向かいの席に座ってお茶を飲んでいた孫娘が、不審な顔でわたしを見ている。差し出された手のひらにそれを乗せてやり、「呪いがあったんだよ」と説明した。
孫は目を輝かせて、
「じいじ、これをください」
と言い、懇願しながらも手はひったくった呪いを握りしめて、絶対に譲らない姿勢をみせている。
甘えるとつい、じいじ呼びが出てしまうのは困ったものだ。
孫娘は六歳になるのだが、予定していた学校に行けなくなってしまったので、とりあえず我が家で預かった。
どうせ妻は出張が多くてほどんと家にいないし、生活に張りがでて良いと引き受けたのだ。けれど、孫娘にとって二人の暮らしは少しのんびりしすぎているらしく、文句こそ言わないが、暇を持て余しているのは火を見るよりも明らかだった。
ちゃんと面倒をみるのなら、という条件を付けて許す。孫娘は喜んでイスから飛び降り、嵐のようなキスを一つして、ぶどうを持って行ってしまった。お茶は半分も飲んでいない。あとでおなかがすいたと騒がなければよいのだが、とわたしはため息をつく。
十中八九、管理しきれないだろう。
弱弱しく、今にも消えてしまいそうな呪いなのである。しかしまあ、しばらく忙しくすごして、結果が思わしくなかったとしても、それはそれで良い経験になるのではないか、と思ったのだ。
案の定、夕飯の後自室に戻った孫は、階段を転がるように降りてきた。
「大変、呪いがしにそう」
手にしていた食器を食洗器に並べ、スタートボタンを押してから、わたしは孫娘に向き直る。キッチンの入り口から、やきもきしている顔が覗いていた。台所は危ないものが多いので、むやみに入らない約束なのだ。
小さなぶどうは芯についたまま、それ以外を取り除かれて、小さな紙箱の中、更に綿に包まれてちょこんと孫娘の手の上に乗っている。表面から漏れる黒いもやは、か細く震えていた。
「どこに置いていたんだね」
「ヒーターの上」
それはだめだろう、とわたしは顔を顰める。
ぶどうに発生した呪いなのだから、その育成に適した環境が必要なはずだ。まして、すでに手折られた房である。急な温度変化に対応できるはずがない。
わたしはとりあえず冷水に実を浸し、妻が作り置きしていった薬をほんの少し振りかけた。
孫は尊敬の目で作業を見ているが、ここだけの話、わたしは魔術に詳しくない。長年連れ添った妻の入れ知恵で何とか対応しているが、内心では冷や冷やし通しだった。
幸い、それで呪いは持ち直したが、あまりにか弱い気配に、しばらく冷蔵庫で寝かせておかなければならなかった。
翌日、朝食の間、孫娘は始終黙って何か考えていた。
起きてすぐ冷蔵庫の中で呪いが生きているのを確かめ、食後もまた一瞥して、片づけもそこそこにどこかへ行ってしまった。
庭仕事の前に姿を探すと、孫娘は書斎で何やら本を広げていた。
カウチに埋もれるように座って、真剣にページを繰っている。多分呪いを調べているのだろうが、果たしてうまくできるだろうか、と心配になる。が、あまり構いすぎるのも良くないと、ぐっと堪えて庭へ出た。
草を毟りながら、時々窓を見る。孫は本を戻したり、ノートに手を伸ばしたり、忙しそうにしていた。今日の家庭学習と思えば良いか、と好きなようにさせておく。
その後、昼食を作っていたら、しょげかえった孫娘がやってきて「わからない」と言う。
呪いを助ける方法が調べたけどわからなかった、という意味だろう。まだろくに単語も知らないのだから、当たり前の話ではある。
昨晩の電話で、こっそり妻に助言を求めておいてよかった、と感謝した。
「こまどりを捕ってきなさい」
とわたしが言うが早いか、孫娘はすぐさま庭から、一羽の小鳥を捕まえてきた。
そういうところは、年齢不相応なのである。普通、動物を捕獲するのは大人だって難しい。それに、恐らく何に使うか気が付いているだろうに、それに対する躊躇を見せないのも、一般的ではないだろう。
やっぱり学校へ行かせなくて正解だった。
思ったが、口には出さない。それは孫娘が聞くべきではない。
「呪いを食べさせればいいんですか?」
孫娘はすぐにでも冷蔵庫からぶどうを取り出して、手の中のコマドリの口に押し込みかねない勢いである。焦る彼女を宥め、落ち着かせる。
わたしたちはコマドリを空き箱へ、小鳥の口には大きすぎるぶどうを小さな細切れにして、一緒にそこへ入れた。
落ち着いたら勝手に食べるだろうから放っておけと言ったのに、孫娘は午後ずっと、居間の隅で鳥が呪いを飲み込むのを、今か今かと観察し続けていた。夕飯の直前にやっと全ての果肉を食べきったコマドリは、けれどすぐさま劇的な変化があるというわけでもなく、孫娘をソワソワさせた。
呪いが小鳥に定着したのは、三日後のことである。
羽の先が黒くなった以外、視覚的にはほとんど変化はなく、元気に鳴く。目が少し濁った色になったが、命には関わらないだろう。
孫娘は狂喜乱舞して、コマドリにほおずりをした。
「けれど、これで終わりではないからね。供物を与えたり、呪文を唱えてあげたり、育ててやらないとすぐまた死んでしまうよ。もちろん、鳥本体の世話もみなければ」
どのアドバイスに対しても、孫娘は大きな声で「はい」と返事をするのだった。
甘いな、と自覚しつつ、町へ一緒に出かけて、鳥籠を買ってやる。それから餌と粟穂、呪いの構造教本と練習問題集。
やらなければならない学習が増えたというのに、孫は嬉しそうだった。
すぐに文字を覚えて問題集を埋め尽くしてしまい、次のレベルの本を購入することになった。着々とコマドリが育つのをやりがいに、一年も経たずして、孫娘は呪術生成を会得し、わたしを驚かせた。
しかし、小鳥本体の寿命は短いのである。
ほぼ一日中巣の中でうずくまっているようになった老コマドリを見て、孫娘はある日「フクロウか、タカを捕るにはどこへ行けばいいですか」とわたしに尋ねた。
「待ちなさい」
わたしは少し慌てた。
「まだ生きているうちにロビンをフクロウに食べさせる、という案なら、賛成できない」
「なぜですか」
孫娘はきょとんとして、首を傾げた。
ホームスクーリングの続行が決定した瞬間である。ひとつの悩みは解決したが、責任は重大だ。これから孫娘に正しい方向へ、教育を施していかなければならない。
「それは、もうやったからだ」
「なるほど」
すでに成功した同じことを繰り返しても、学びはない。
ところが、わたしには次の手の見当がつかなかった。孫娘の献身によって呪いは確実に成長したが、受肉せずに存在できるかまでは怪しい。孫娘と共に教本を読み込んではいても、わたしもしょせん素人なのである。
悩んだ結果、「おばあさまに連絡をとろう」ということになった。
餅は餅屋に任せるのが良い。午後のお茶を飲みながら草稿を練り、すぐにでも小鳥は死んでしまうかもしれない状況であることを強調して、わたしたちは手紙を書き上げた。
孫娘ができると言ってきかなかったので、便箋は彼女が送った。バラ柄の封筒は多少ふらふらしながら、けれど結構な速度で窓から飛んで行って、すぐに見えなくなった。この一年の、勉強の成果が目に見えたのも良い機会だった、と満足だった。
その後の妻からの返事を元に、使い魔を造ることにした。
中身なしの使い魔なら練習次第ですぐ出来るようになるだろうから、それに呪いを食わせて併合するのが良かろう、ということだった。
やっぱり食べさせるのか、と二人でひとしきり笑いあった後、孫娘はすぐに練習にとりかかった。
使い魔の身体から作り上げるのは、基礎を終えて専門へ進んでからのはずだ。まだ幼い孫娘には難しく、時間もないので、数日は寝るのも惜しんで修練していた。
なんとか形にできるようになった夜、コマドリが息を引き取ったので、慌ただしく造り上げたのが、ロビンである。
孫娘はコマドリをそのままロビンと呼んでおり、後に何度か形が変わっても、相変わらずロビンと呼び続けたのだ。
それははただの黒くて丸い塊で、目も口もなかった代わりに、魔力が凝縮されていかにも丈夫そうだった。
黒塊が呪いの小鳥を取り込み、晴れて呪いはロビンとなった。
それから後の数年間は、わたしたちの生活の中心にはロビンがあった。
孫娘の教材となり、学力向上がそのままロビンの強化に繋がることでやる気に繋がり、外出理由にもなった。ロビンの進化のために自然史博物館へ行き、生きた動物を見るために動物園へ行き、社交性を学ばせるために散歩もさせてみた(これは数回目に公園のリスを食べてしまったので、途中で止めた)。
ロビンは自然発生した呪いであるためか、使い魔となっても半分は野生で、言うことを聞かないこともしばしばあった。
しかしそれは、孫娘にとって幸運なことだった。ろくに友人を持たない孫娘にケンカする相手が出来て、わたしは素直に喜んだ。恐らくロビン側からしても、特殊な使い魔では仲間を作るのが難しいだろうから、良いことであったのだろうと思う。
わたしも妻も孫娘を支えていくつもりはあるが、いつまでもいられるわけではない。盲従するのではなく、対等の相棒を持つのは、人生において重要だ。
そして、一時の別離を知るのも、悪いことではないはずだ。
わたしは午後のお茶を啜って、そんなことを考える。
かつて孫娘と休憩したこのグリーンルームで、わたしはロビンと午後のお茶を飲む。
わたしはミルク入りの紅茶だが、ロビンには魔素強化剤入りまたたびを与える。主が近くにいないので、使い魔に必要な魔力の補充ができず、投薬は必須だ。
現在はほぼ二人暮らしである。
妻は相変わらず出張で、孫娘はこの秋から、学校に通っている。なんとか基礎教育は終わり、これから誰かに弟子入りなりして学問を極めて行けば良いと思っていたら、「やっぱり社会を知っておいた方が良いと思うの」と本人が希望したのだ。専門学校とはいえ入学だ、八年来の悲願達成である。
しばらくぶりに戻った両親の家でも、それなりにうまくやっているらしい。いつのまにか離婚して母親が変わっていたけれど、腹違いの妹とも、仲が良いと聞いている。
しかし、ロビンは連れていけなかった。
家庭学習とはいえ、専門家の妻から直々に教わった使い魔なので、同級生たちのそれと、レベルが違いすぎるからだった。半野生であること、かなり大型であることもあって、もちろん実家に置いておくわけにもいかない。
それで卒業まで、わたしが預かることになっている。
ロビンはもう、全長二メートルほどになるだろうか。
基本的には猫類の身体に、ずんぐりした嘴がついていて、ちょっと人前に出せない姿をしている。そのくせ性質は孫娘に似て甘えん坊の寂しがり屋で、一日中わたしについて回り、時々こっそり古巣の鳥籠に頭を突っ込んでいることもある。
次の休暇には、孫娘が帰ってくる予定だ。
わたしたちはそれを、心から楽しみにしている。わたしはクリスマス・ランチのロースト用に、庭でパースニップを育てていて、孫娘の好物のそれが虫やウサギに食われてしまわないよう、見張るのはロビンの仕事だ。
読んでくださってありがとうございました。少しでも楽しんで頂けたらうれしいです。
