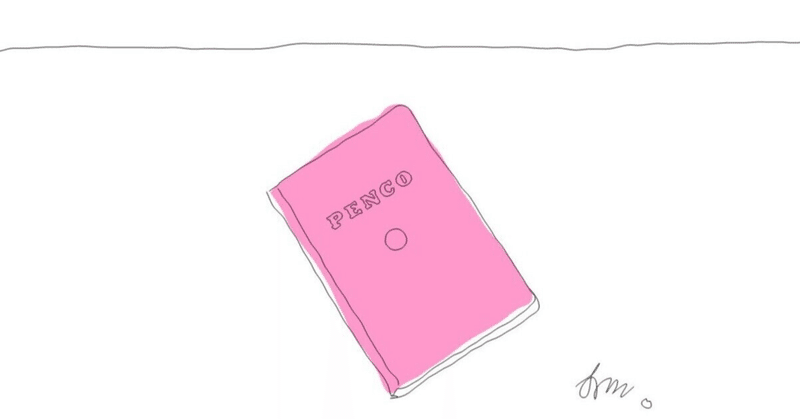
介護関連ニュースのまとめ読み。
昨夜は創業計画書と資金繰り表の見直し作業など集中して行っていたので、気が付いたら23時を過ぎていました。
いつもは22時には布団に入って睡眠モードになっているのですが、昨日はそんな感じで頭が冴えてしまってなかなか寝付けませんでした。
いつの間にか眠っていましたが、やはり朝の寝たりなさ感は強く、だらだらとした起床になりました。
10月月初ですので、人事関連の作業と請求業務を処理する日々ですので、ほんとうにデスクに座ってパソコンをカタカタしている1日です。
精神衛生上よくないので、各作業細かく区切りながら、必要な書類を、本来なら一度に持って回れば効率がいいのですが、こういう時期は、細かく持って行くようにしています。その方が座りっぱなしよりも集中力が持続します。
とはいっても目が疲れるので、相変わらず肩も首も頭も痛くなってきました。
最近は介護関連のニュースを確認するのも忘れていたなぁ・・・と思ったので、ちょっとまとめて読んでいこうと思います。
こちらは9月23日の記事です。
居宅介護支援の昨年度の利用者数は379万900人。高齢化の進展を背景として、前年度から3.2%(約12万人)増加した。利用者数、費用額は今後も引き続き増えていく見通しだ。
これ、ケアマネの数って間に合ってるんでしょうか・・・。
現場も人手不足ですけど、ケアマネ不足も深刻ですので本当にどうするんでしょうね、これから先の介護保険制度。
ケアプランを含めた書類作成に関するICT活用の効率化のアプローチが遅いとしか言いようがないなぁ・・・という感じです。
ケアマネも現場経験を積んで資格を取るので、ケアマネが増える=現場のベテランが現場から消える、という構造も一定でありますので、今後どうなっていくかは本当に不安です。
政府は現在、2024年度に控える次の介護保険制度改正を念頭に、居宅介護支援でも新たに利用者負担を徴収する案を俎上に載せている。仮に1割負担が導入された場合、単純計算でおよそ500億円強の給付費を抑制できることになる。
ただし、現場の関係者の間ではこの案への慎重論が根強い。「利用者の希望が優先され、必ずしも自立支援につながらないケアプランが増える」「かえって費用額の膨張が加速する」などの懸念の声が出ている。
ケアプランの有料化ですね。
1割負担にしてまかなえる金額と、記事で指摘があるようなリスクを考えると、あまり費用対効果がよいとは思えないです。
まぁ真に公平中立の立場でケアプランを立てているケアマネさんって本当に限られた少数だと思いますが、介護保険制度の根幹をなすケアプランに対して、利用料が発生してしまうというのは非常に大きな問題だとは思います。
いずれにしても、1割負担になろうがなるまいが、全てのケアマネが専門性を発揮して、本当に適切なサービス導入をきちんと本人・家族が納得できる形で説明し説得する力量が求められているのだと思います。
これが、何でも言われた通りに作りますよ、みたいなケアマネが一人でも居ると成立しないので、ケアマネ集団として専門性を高めて取り組んで頂きたいと思います。
そうでなければ、利用者の希望が優先され必ずしも自立支援につながらないケアプランが増える・・・などという意見は出てこないはずですから。
個人的には、ケアプランの1割負担で介護サービスの利用料の総量が増えれば、デイサービスやヘルパーの支援を減らして捻出するようなケースが増えるように思います。
それは、結果として重度化を予防できず、医療費などの社会保障費用の増大を招くと思います。
こちらは9月27日の記事ですね。
「先人たちの努力を踏みにじる改革」「粗雑な審議はやめて欲しい」。
26日に開催された社会保障審議会・介護保険部会。介護現場の関係者から、要介護1、2の高齢者に対する訪問介護と通所介護を市町村の総合事業へ移す案について、こうした厳しい批判が相次いだ。
ごもっとも意見だと思います。
要介護1・2を総合事業へ移す意味が分かりません。
総合事業は、市町村が独自に実施する介護保険サービスで、既に要支援1・2の方が対象になっています。
国の定めた報酬額を上限に、各自治体が独自に報酬を設定できる事と、要支援1・2の方の利用料は、要介護1~5の方の1回ごとの利用実績ではなくて、月額の支払いになっています。
なので、事業者側とすると、収益を上げにくいサービスなんですよね。
逆にいうと、社会保障費用を抑えられるという事になるんだと思います。
現状では、要支援1・2の方は、ほぼ自立した生活が送れる方(という事になっている)ですので、そこまで頻回なサービス利用はないのですが、やはり要介護1~5の方へのサービスと比べると、収益も低くなってしまいます。
その上で自治体ごとにある程度報酬を決めれるので、上限の90%や80%の単位を設定している自治体もあると聞いています。
そうなると、同じサービスを受けるにしても、ある町では1000円なのが、別の町では900円とかいう矛盾も生まれています。
要介護1・2が総合事業になる場合も、やはりそのようにして現状よりも低い報酬になるだろう、というのは容易に想像できます。
総合事業の特徴は自由度の高さ。全国一律のルールに基づく介護給付と異なり、運営する市町村が地域の実情に応じてサービスの運営基準、報酬などを独自に決められる。例えば、地域の住民やボランティアを担い手とするなど人員配置を緩和したうえで、それに合わせて低めの報酬を設定することも可能だ。現在は要支援者の訪問介護、通所介護などが総合事業で運営されている。もっとも、見返りが少ないこともあってこうした住民主体の弾力的なサービスは十分に普及していない。
住民主体の総合事業もあるにはあるのですが、ほとんどの自治体でうまくいっていないように見ています。
その上で要介護1と2の方をそのような形で総合事業にしたとして、うまくいくようには思えません。
そもそもですが、人口がこうなって高齢者が増えてこうなっていく事はわかりきっていた事なのに、何を今更・・・という感じです。
政府としては対応してきた、と説明するつもりの実績づくりなのでしょうか。
介護保険制度の大きな間違いは、制度をコロコロと変えてきた事だと思います。
もともと介護保険制度の要支援1・2はありませんでしたし、総合事業もありませんでした。
介護予防をもっと頑張ろう、みたいな形で要支援1・2が出来ましたが、介護予防だってうまくいってないと思いますよ。
そんな状況で要介護1・2の人を総合事業にしても意味がないどころか悪影響しかないと思います。
こちらは10月1日の記事です。
要介護1と2の高齢者に対する訪問介護、通所介護のサービスを、現行の介護給付から市町村の「総合事業」の枠組みへと移管する構想をめぐり、「認知症の人と家族の会」による反対のオンライン署名運動に支持が集まっている。1日16時の時点で2万9065人が賛同。Twitterでは一時、「#要介護1と2の保険外し」がトレンド入りした。
これは凄いですね。
僕も時間のある時に署名しときましたが、その時点で3万9523人の署名が集まっていました。
認知症の人と家族の会の取り組みは素晴らしいですね。
報酬の低さもあって請け負う担い手が十分に存在しないこと、サービスの質が低下しやすいことなどを指摘する声が多く、地域による多少の違いはあれど、総じてまだまだ発展途上と認識されているのが実情だ。このため介護関係者の間では、この総合事業を要介護1と2の訪問介護、通所介護にも拡大する構想への慎重論が大勢を占めている。
現場でこれまで要支援1・2の人へのサービスを提供してきましたが、月額報酬なので、必要なだけ必要なサービスを提供できたりするんですけど、定員や派遣できる人員が限られている中で、総合事業を増やすより要介護の人のサービスを増やした方が経営的なメリットが大きいので、本当にご本人次第の介護予防になっています。
※ 家族の会はこのほか、介護の利用者負担の引き上げを見送ることもあわせて主張している。
お金のあるなしで使えるサービス量が変わってくるのは本当にあります。
1割負担でもお金がないから必要なサービスを使えない。
そんな制度だから介護が必要な高齢者を増やしてしまっているような気もします。
お金が少ないので、ちゃんとした栄養バランスのとれた食事だってほとんど食べれていない状況ですので、そりゃ足腰が弱くなって歩けなくなるよ・・・というケースも多いです。
ケアプラン有料化より、全ての利用者負担をゼロにした方がもしかしたら介護予防や重度化防止の効果はあるのではないかと思います。
財源は、そのための消費税なんでしょうし、消費税をちゃんと使いましょう。
こちらは10月3日の記事です。
経済再生を最優先の課題と位置付け、「物価高・円安への対応」「構造的な賃上げ」「成長のための投資と改革」の3点を重点分野に掲げた。賃上げについては、介護職の処遇改善や業務の効率化を進めると改めて明言した。
この国のこれからの政策の方向性が示されました。
本当に目先の対応しかないんだなぁ・・・という正直な感想です。
人口減少をなんとか食い止めようとか思わないのでしょうか。
人材不足の介護現場と同じで、働く環境やチーム環境を改善しないで新人をどんどん入れても定着せずに辞めてしまうような事を、経済さえよくなれば何でもうまくいく、なんて思ってやっているのかなぁ・・・なんて思います。
介護職の処遇改善はありがたい話ですが、他の中小企業のお給料だって上げないとダメじゃないかと思います。
大企業はたぶん体力あるから自前で処遇改善できるでしょうけど、処遇上げたくてもあげれない企業への援助もすべきと思います。
岸田首相はこう語り、官民で連動する賃上げの実現を主導すると強調した。そのうえで、「公的価格についても、制度に応じて、民間給与の伸びを踏まえた改善を図る」と説明。「看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める」と述べた。
業務の効率化は本当にすぐにでもやってほしいですね。
現場の負担があまりにも多すぎますよ、書類関係。
こちらは10月4日の記事です。
介護事業所の指定申請や報酬請求などに伴う事務、自治体との手続きの効率化を前へ進めるため、厚生労働省は現場の要望を直接受け付ける専用フォームを先月末に開設した。9月29日に局長通知を発出。全国の自治体に事業者への周知を要請した。
凄いですね、現場の要望を直接伝えるチャンスです。
こちらが専用窓口のある厚労省のページです。
ここから窓口にアクセスして下さい。
事業所名と名前とか事業所の電話番号まで記載しないといけないんで、ちょっと気軽に・・・という感じではありませんが、僕も意見は提出させていただきました。
行政に対する変更届等、各自治体や行政区によって独自の書式などがあり必要時のみの作業とはいえ煩雑となっております。情報の公表やLIFEといったデータベースと相互共有できるようなシステムの構築をお願いしたい。また、書式フォーマットをダウンロードするのではなく、システム上で入力したものが直接クラウド上のシステムに反映され、変更・更新などあった場合に、各行政区に通知が行き確認が行われるようなシステムの方が行政側も事業者側も作業が簡素化できるし、同じ内容を何度も入力(コピペするなど)する必要もなくなる。また、このようなシステムが構築できれば、運営指導についてもより作業が効率化できる上、全国で同一のシステム・様式となるので、行政担当や事業所管理者らが別の行政区に異動したとしても、独自ルールがないので対応しやすい上、後継者育成・指導も行いやすい。特に、法令上定期的な更新管理が必要な書類については、このような管理を行う事で運営指導で必要な書類については、更新遅れなどある場合はアラートを鳴らす等で注意喚起し、法令順守をより確実に実施できるようになると思う。ケアプラン連携システムの導入を契機に、介護保険制度全体で統一されたシステムを各事業所が運用するようにすれば、様々な面での効率化が進むと思われるので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
入力欄は小さかったですが、このボリュームの内容でも提出できました。
内容が指定申請や変更関連の行政手続きのみのシステムのようだったので、どうせなら他の書類業務もそのシステムでやってほしいな、という感じの内容です。
直接国に提案できるいい機会なので、事業者の皆さんはいろいろアイデアを届けるとよいかもしれません。
10月5日の記事です。
厚労省はこれまで、介護現場の事務負担の軽減やデジタル化などを前進させる施策の一環として、事業所の指定申請、報酬請求などの書類から押印欄をなくすよう求めてきた経緯がある。
今回の通知では、「実際の取り組みの詳細を確認したところ、押印を不要とした書類が一部のみの事例が散見される」と指摘。「全ての指定申請書類などについて、押印、または署名を求めることがないよう様式の再確認を」と改めて要請した。
電子申請になれば押印なんてできませんし、足かせにしかなりませんものね。
現場でも契約書等には押印が必要という流れがまだ根強く残っているので、こういう書類にも押印は不要ですよ、という指導をしてほしいなぁと思います。
会社の仕事でもテレワークなのに押印するために出社した、なんてニュースもありましたね。
全ての申請書類で、署名も押印も不要になっています。
本日(10月6日)の記事です。
日本経団連の十倉雅和会長ら4人の民間議員は、「賃金の継続的な上昇」を目玉の1つとするよう要請。「看護・介護・保育の現場で働く人の処遇改善に向けた取り組みなどを通じ、賃金の底上げを進めるべき」と提言した。岸田文雄首相も介護職の処遇改善を図る意向を表明しており、関係者からは思い切った施策の立案を求める声が強まっている。
経団連からこのように介護職等への賃上げを要請するような事って今までなかったように思います。
他産業よりも低賃金と言われている職種の賃金を上げる事で経済効果も期待できるのかもしれませんね。
ただ、貯蓄に回るような気もしますけど。
日本全体で賃金が上がれば一番いいんですけど。
そこはどうなんでしょうか。
「医療・介護、ヘルスケアなど公的部門の規制・制度改革を徹底して民間の投資、人材、スタートアップを呼び込み、賃金・所得の増加につなげるべき」とも提案した。
介護業界でも若い人がベンチャーや新規創業で元気な現場を作ってくれると業界も明るくなりそうですよね。
岸田首相は会合で、「物価上昇に負けない継続的な賃上げを実現する」と強調。
本当に食材費や燃料・電気代の値上げによる経営的なダメージは大きくて深刻ですので、体力の弱い中小の企業に対してもそれ相応の対応は必要と思います。
言ったからには頑張ってやり遂げてもらいたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
