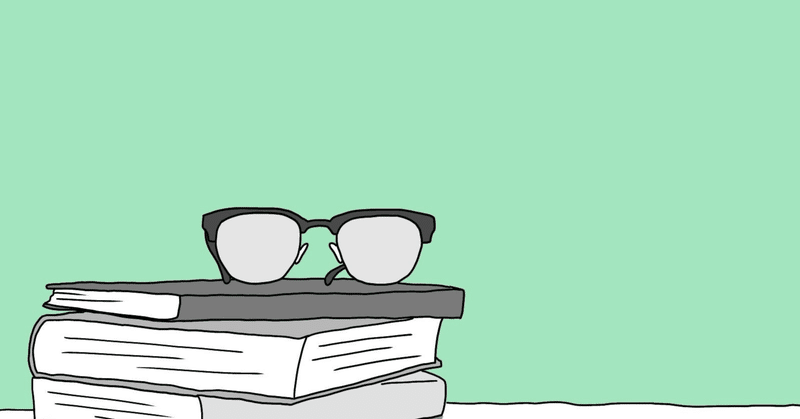
【小濱道博】介護保険改正、自己負担増でサービスの利用控えが起きる 事業者は危機感を持って原点に立ち返れ・・・という記事の紹介。
介護保険改正に向けた情報がいろいろと出てきますね。
2024年度の改正です。
2023年度中にいろいろと準備や対応を進めておく必要はあるので、こういう改正の流れの情報については把握しておく事にこしたことはないとは思います。
また、改正直前になって加算要件などの情報が出てきたりするのでしょうか・・・。
どうも年々そういう説明のタイミングが遅くなってきている気がするのは機能性でしょうかね。前回はコロナの影響もありましたもんね。
今度の改正は、しっかりと厚労省には事前に情報を発信してもらいたいものです。
自己負担が1割から2割となった場合、病院の窓口で支払う金額が倍額となる。9月まで1万円を支払っていた場合、10月から2万円を支払うこととなる。しかし、受給される年金は同じ額しか振り込まれない。
そうすると、必然的にやり繰りが生じる。これまで買っていた物を買わなくなる。使っていたものを使わなくなる。そのやり繰りの対象として、介護保険サービスも例外では無いということだ。
今後、自己負担を2割にしていく流れは健在で、各団体が反対をしていますが、この記事で指摘があるように、確実に介護サービスの利用控えが発生します。
たとえば元々は利用者負担は1割でした。
これが2割負担になった時に何が起こったかというと、利用控えです。
これまで月1万円だったサービス利用料が、1万円から2万円になりました。
中には3割負担に該当した方もいて、その方は1万円が3万円になるという状況です。
当然、収入が増える見込みがない高齢者ですので、年金などのやりくりで工夫するしかありません。
デイサービスの回数を減らしたり、ヘルパーさんを減らしたりが実際にありました。
そして何が起こったか・・・。
現場の僕らや担当ケアマネも心配していましたが、やはり活動量の低下や他者とのコミュニケーション・社会とのつながりの低下・断絶などが発生し、一気に重度化し入院し、そのまま在宅復帰できず入所・・・という事が結構な頻度で起こりました。
介護予防にシフトして、できるだけ要介護度があがらないようにしないとならない時期に、更に利用者負担を高くする施策なので、本当に大丈夫だろうかと思います。
地域包括ケアシステムの整備が進んでいればいいのですが、実態はそうでもない地域も多く、地域での担い手が不足している状況もあります。
コロナ禍が起こってから3年目となっている。この3年間で、多くの利用者は介護サービスを使わなくてもいいことを知ってしまった。特に休業を余儀なくされたデイサービスなどにおいては、未だに利用者数が元に戻らない事業所も多い。そのため、経営体力の弱い小規模事業所を中心に厳しい経営状況が続いている。
ここの部分については、僕としては少々疑問です。
確かに感染リスクはありますが、基本的にケアプランに位置づけられたサービスがなければ自立した生活が困難なはずなんです。
なので、コロナが拡大していた初期時の時期から、必要なサービスなんだから感染対策を徹底して利用する際の不安感を払しょくして提供するか、それでも困難なら訪問してサービスを提供せよ、と現場に指示を出したり、別の拠点では実際に訪問にいったりして陣頭指揮を執ってきました。
ただ、やはりコロナでサービス控えをする利用者は多く、実態として利用再開した際に日常生活動作の機能が低下していたり、認知症が進行していたりしたケースも多かったです。
ですので、介護サービスを使わなくてもよい、という事ではなく、不安があり多少なり我慢して利用を控えた結果、身体機能や認知機能が低下してしまった、という事も合わせて理解しておく必要があると思います。
本当に必要がないサービスであれば、そもそもケアプランに位置づけられる事にはならないので、使いたいサービスをコロナ禍で我慢した、という事だと思います。
ただ、経営的な面で見ると、そうは言っても利用者さんを確保して収益を高めないといけないので、利用中断しているならコロナ禍でも必要としている方にサービスを届けるよう経営努力をするのは当然ですので、一方でそういう経営努力もあり、コロナ禍でも経営的には向上している事業所もあります。
実際、コロナの前後の介護給付費については、ほとんど横ばいが微増傾向だったはずなので、コロナ禍で減らした事業所もあれば、増やした事業所もあるという事には間違いないと思います。
今一度、“自身が営んでいる介護サービスとは何か”という原点に立ち返らないといけない。まず経営者は、自分自身を利用者の立ち位置に置き換えて、自分が営んでいる介護サービスを支払い金額が倍になっても使うかを考えて欲しい。そこから、どうすれば良いかを考えることから、解決策が見いだせるはずだ。
いろいろな視点はあるとは思いますが、人材不足や物価高騰など課題が山積する中でも利用者負担増や様々な制度改正が行われますので、そういう事に柔軟に対応していけないと生き残りは確かに難しいかと思いした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
