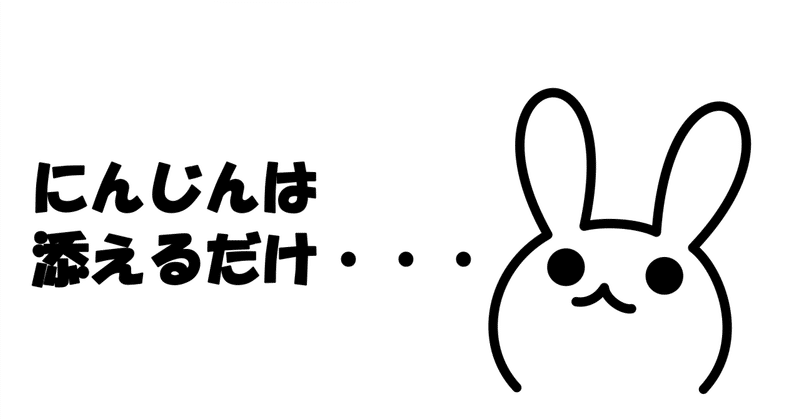
【ソーシャルワークとは?】定義や原則、日本での歴史的変遷をわかりやすく解説・・・という記事の紹介です。【研修準備】
今日も研修の準備です。
介護の仕事の基本ともいえるソーシャルワークについて、学び直していきたいと思います。
ソーシャルワークとは何か?
ソーシャルワークとは、困っている人の生活や人生を社会の相互関係に注目して、人と環境の両方にアプローチして支援していく実践的な専門職であり学問のことです。
日本では生活面の相談に乗る仕事をソーシャルワーカーと呼ぶことがあります。また狭義には国家資格である「社会福祉士」「精神保健福祉士」の有資格者を「ソーシャルワーカー」と呼ぶこともあります。明確な言葉の定義があるわけではありません。
ソーシャルワークは、支援をして実践していく専門職の総称だと思いますが、なんとなく相談員っぽいイメージが強いですね。
この記事ではケアマネの資格名がありませんが、ケアマネジャーもソーシャルワーカーだと思います。まぁ、困っている人の生活や人生を支援していく人はソーシャルワーカーと言って差し支えないとは思います。
「ソーシャルワーク」のグローバル定義
ソーシャルワークは、社会変革と社会開発、社会的結束、および人々のエンパワメントと会報を促進する、実践に基づいた専門職であり学問。社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重の諸元りは、ソーシャルワークの中核をなす。ソーシャルワークの理論、社会科学、人文学、および地域・民族固有の知を基盤として、ソーシャルワークは生活課題に取り組みウェルビーイングを高めるよう、人々や様々な構造に働きかける。
(国際ソーシャルワーカー連盟と国際ソーシャルワーク教育学校連盟が採択した「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年7月))
定義は何だか難しいですね。
生活課題にとりくんで幸福度をたかめていくために地域の人々や地域資源を活用する、そういう感じでしょうね。
日本学術会議がまとめた「ソーシャルワーク」の定義
ソーシャルワークとは社会福祉援助のことであり、人々が生活していく上での問題を解決なり緩和することで、質の高い生活(QOL)を支援し、個人のウェルビーイングの状態を高めることを目指していくことである。
日本なので、とりあえずこちらの定義の理解は必要とは思います。
世界的な定義では、その人以外の人々や周囲の環境や社会資源に働きかけるのが役割でしたが、日本で定義されている所のソーシャルワークでは、個人の幸福度を高めていくのが役割となっています。
たぶん同じ内容を言っているのだろうとは思うのですが、周囲にも働きかけるのが役割であると明記されていた方がよさそうな気もしますが、個人のQOLを高めるのだから周囲も巻き込んでいくのは当然、と考えるとそこまで言わなくてもわかるだろう、という意図があるのかもしれません。
ソーシャルワークの目的は、グローバル定義や日本学術会議の定義にも示されている通り「ウェルビーイング」を高めることです。ウェルビーイングとは、本人にとって良い状態です。
また、ソーシャルワークは個人に対する支援だけを指すわけではなく、個人と社会の相互関係にアプローチすることが特徴です。組織や社会をより良い環境にすることも目的の1つとなります。
ここの所が重要ですね。
”ソーシャルワークは個人に対する支援だけを指すわけではなく、個人と社会の相互関係にアプローチすることが特徴です。組織や社会をより良い環境にすることも目的の1つとなります”
ソーシャルワークの基本原則として有名なものに、アメリカの社会福祉学者バイステックが1957年に「ケースワークの原則」という書籍で体系化したものがあります。
① 個別化(同じ問題は存在しない)
② 意図的な感情表現(利用者の感情表現の自由を認める)
③ 統制された情緒関与(冷静に自分の感情をコントロールする)
④ 受容(利用者の考え・価値観を否定せずに受け止める)
⑤ 非審判的態度(良い・悪いの判断はしない)
⑥ 自己決定(利用者自身が決める)
⑦ 秘密保持
これはもうどんな介護職でも知っているはずの原則です。
特に有資格者や介護の研修を受けた人は必ず聞いているか資料に掲載されている内容です。
しかし、この原則をしっかり守れて支援していれば、まず虐待などは発生しないのですが、実際は虐待の件数は年々増加傾向にあります。
人手不足や業務過多という理由で虐待が発生しているような状況もあるようですが、忙しいからといって他人の人権を侵害できる道理はありませんので、今後更に人手不足が確実と思われる介護業界では、改めて基本中の基本であるこの原則をしっかり腹に落としておく必要があると思います。
ソーシャルワークの流れは以下の通りです。実際にはもっと複雑なこともありますが、まずは困っている人に気付き、課題を整理して、支援し、その結果を評価して改善していくことの繰り返しが基本となります。
① ケース発見とインテーク
② 課題分析(アセスメント)
③ 支援計画の作成(プランニング)
④ 支援の実施(インターベンション)
⑤ 経過観察(モニタリング)
⑥ 効果測定・支援計画の評価
⑦ 終結・アフターケア
PDCAサイクルですよね。
そしてこの流れは介護現場で計画作成や記録等を担当した事がある人なら馴染みの介護過程の展開ですが、そっか、ソーシャルワークの流れがそのままあてはめられている感じだったんですね。勉強になります。
ちなみに、介護現場では、これら①~⑦の内容については、それぞれ記録を残した上で根拠となる記録や関連する記録もしっかりと記録として残しておかないと指定取り消しや報酬の返還等のペナルティが発生します。
上記の①~⑦についての書類は、利用者さん全員分が必要であり、そして時系列でそれぞれの書類に整合性がなければいけませんので非常に煩雑な業務になっており、介護職員が現場で利用者さんの対応に注力できない原因の一つでもあります。
たとえば記録の日付一つとっても、他の書類との整合性がとれていないと行政から指導が入ります。
ペナルティがあると経営的にも事業継続的にも死活問題になるので、どうしても現場の目の前の利用者さんのケアよりも優先度が高い仕事になりがちですが、ソーシャルワークの視点や本来の介護の仕事とはなんぞや、という視点で考えると本末転倒なんですよね。
①~⑦のPDCAサイクルを適切に回す事で、利用者さんのQOLを少しずつ高めていくのが目的なのに、書類作成が優先されてしまって現場での対応が手薄るになる事で必要なケアを提供できない可能性が発生しています。
社会保障費用を抑制したいのであれば、現場の専門職がしっかり現場での役割を全うできるような仕組みが必要ですが、国や厚労省はそういう頭がないので制度が変わる度にいろんな書類を増やしてきました。
裏金問題で記憶にないと言っていれば責任問題にも問われない議員の話を聞いていると、俺たちは何の仕事をこんなに一生懸命やってんだろう・・・なんて愚痴も言いたくなりますが、多くの現場で残業が減らない原因の一つがこの書類整理であり、介護をしたくて介護職になった人がバーンアウトしてしまう原因でもあると思います。
ICT化によりかなり簡略化は出来るようになってきましたが、介護現場のDXを進める上で、これら書類をどこまで簡略化するかというのは本当に重要な課題ですし、それこそ行政毎に書類のローカルルールもあって、A市では不要な書類がB市では必要、なんて事もあるので、早く統一したシステムで介護業界全体が回るようになればいいのですが、それももうここまで続いてきた制度ですから、今更は不可能な気がします。
ソーシャルワーク理論の起源と歴史
ソーシャルワークという言葉は、19世紀末から20世紀初頭にかけて、欧米で生まれた概念です。日本では、明治時代から大正時代にかけて、社会事業や社会改良運動という言葉が使われました。
大きな変遷としては、疾患を個人の問題と捉える「診断主義(治療モデル)」から、社会の問題と捉える「機能主義(生活モデル・社会モデル)」へと変化しています。
特に大きな影響を与えたのが、1945年に提唱された「一般システム理論」です。直線的因果律から円観的因果律への変化し、焦点は個人から社会にシフトし、個人と環境の相互作用にアプローチする視点が浸透してきました。
今でも疾患を個人の問題として考えている人って日本では多いような気がします。
糖尿病にしても単に食べすぎているとかそういう問題ではなく、健康によいとされる食材は総じて高価なので、貧困や格差が原因とも言えますので、単純に個人の問題とは言えません。
ウェルビーイングを高める為の課題は、社会問題であるという事にも繋がるわけですので、そういう意味でもソーシャルワーカーは社会に働きかける役割が重要になっているとも言えると思います。
1922年:
ソーシャル・ケース・ワークとは何か(メアリー・リッチモンド)
リッチモンドは「ケースワークの母」とも呼ばれます。ソーシャルワークの基本的考え方の土台を作り上げました。
・ 人間は社会環境と相互に関係しているので、環境を変えることで人間も変わることができる。
・ 人間は自分の人格を発達させることができるので、可能性を引き出すことが大切である。
・ 人間は自分の問題に対して解決策を見つけることができるので、その能力を支援することが必要である。
1945年:
一般システム理論(ベルタンランフィ)
人間は社会や環境とも関わっており、自身が成長・変化したり、環境を調整したりすることができます。細胞レベルで人間を捉えては本質を見失ってしまい、もっと広く全体の性質や振る舞いをシステムとして捉えることが重要です。
1954年:
リッチモンドへ返れ(マイルズ)
この時期は、診断主義(治療モデル)と機能主義の論争が激しく対立し、本来支援の中心であるはずのクラウエントが置き去りになっていました。その状況を批判して、マイルズはケース・ワークの母であるリッチモンドに帰れと言ったとされています。
この頃の状態が今の日本の状態なのかもしれませんね。
実際、介護保険制度の現場でも利用者さんが置き去りの状況はよく見てきました。リッチモンドの理念を改めて現場に落としていく必要があるのかもしれません。
1957年:
The Casework Relationship(バイステック)
1957年にはケースワークの原則で紹介したバイステックの書籍「ケースワークの原則」が出版されました。バイステックはアメリカの社会福祉学者で、カトリック教会の司祭でもありました。
リッチモンドに帰れ!という時期を経てバイスティックの7原則が出てくるのも興味深いです。
1967年:
ケースワークは死んだ(パールマン)
1967年にパールマンが「ケースワークは死んだ」という論文で、ケースワークのあり方を批判しました。当時のケースワークが社会改善を忘れて、個人の心理や感情にばかり注目しており、もっと社会的な視点や責任を持って、人々の生活や環境をよくすることに貢献するべきだと主張しています。
個人に焦点があたって社会や環境をどうするという事が抜け落ちてしまっているのも現状の日本の状況に似ているような気もします。
当たり前なんですけど、社会が良くなれば必然的に多くの人々のウェルビーイングも高まります。
リッチモンドがソーシャルワークとは何か、という事を言ってこの時点で45年が経過しています。
1970年:
社会福祉実践の共通基盤(バートレット)
バートレットは著書「社会福祉実践の共通基盤」で社会福祉に共通する基礎や原理を整理しました。
※ 社会福祉実践の本質的要素は「価値」「知識」「介入(調整活動)」の総体から構成される。
・ 「価値」とは、社会福祉実践における目的や方向性を示すもので、人間尊重や自己決定などの基本的な価値観を持つべき。
・ 「知識」とは、社会福祉実践における判断や行動の根拠となるもので、人間や社会に関する科学的な知識や経験的な知識を学ぶべき。
・ 「介入(調整活動)」とは、社会福祉実践における具体的な方法や技術のことで、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークなどの様々な手法を使い分けるべき。
この内容は、介護職員を育成する上で必須の基本的な項目になりますね。
特に、人間尊重や自己決定などの基本的な価値観を持つべきとされていますので、介護職員にはこの価値観がなければいけません。
自己決定は、そのものが自立に直結する内容なので本当に重要です。
・・・ここまでは世界のソーシャルワークの歴史でしたが、次は日本の歴史の説明になります。
明治時代のソーシャルワーク
社会事業や社会改良運動が始まる。政府や宗教団体、民間団体などが貧困や病気、労働問題などに対処する。小石川養生所や人足寄場などの無料の医療施設や自立支援施設が設置される。
米沢藩や会津藩などの藩政で福祉政策が実施される。
1879年に東京府癲狂院が設置され、日本初の公立精神病院となる。
琵琶法師の明石覚一が江戸本所で杉山流鍼治導引稽古所を開設し、視覚障害者教育の先駆けとなる。
リッチモンドより前の時代に無料の医療施設や自立支援施設が日本にもあったというのは意外でした。
大正時代のソーシャルワーク
1912年に日本初の医療ソーシャルワークが恩賜財団済生会芝病院、聖路加国際病院で始まる。
1914年に第一次世界大戦が始まる。
1923年に関東大震災が発生し社会福祉団体やボランティアが救援活動を行う。
1925年に普通選挙法と治安維持法が制定され、男子普通選挙制度と共産主義思想の弾圧制度が施行される。民主主義や社会主義の思想が広まり、労働運動や婦人運動が活発化する。
検校制度が廃止され、視覚障害者の自立支援が進む。
昭和時代のソーシャルワーク
1945年の終戦後、敗戦の混乱や急速な経済成長に伴う都市化・高度化で新たな社会問題が生じる。欧米からソーシャルワークの理論や方法が導入され、日本でも教育や研究が始まる。
1950年代半ばからは、ソーシャルワークの展開期と呼ばれる時代に入り、社会変革を必要とした時代背景が大きく影響する。
1961年に反精神医学運動が始まり、強制入院や電気痙攣療法などの人権侵害や社会統制の側面が批判される。
1969年に「Y問題」という川崎市に住む19歳の浪人生Yが、ソーシャルワーカーによって無診断で精神病院に強制入院させられた事件により、日本の精神科医療やソーシャルワークにおける人権侵害や専門性の問題に対する裁判・社会運動が起こる。
1975年に「ライシャワー事件」で日本の精神科医療の遅れや問題点が国際的に注目される。
1983年に「宇都宮病院事件」が起き、精神保健法の改正や患者の人権保障の強化につながる。
世界では、一般システム理論(ベルタンランフィ)の時代に日本に欧米からソーシャルワークの理論や方法が導入されたそうです。
しかし、そこから約30年後の1975年の時点でソーシャルワークの理解や浸透の遅れが問題になっていますね。
平成時代のソーシャルワーク
1984年10月に東京大学、東京工業大学、慶応義塾大学の3大学を結ぶネットワークJUNETの実験が開始され、日本にもインターネットが誕生。グローバリゼーションや情報化などの社会変動に対応するために、国際的な視野や専門性を高めることが求められるようになる。
バブル崩壊・失われた20年。
先住民族や地域・民族固有の知などの多様性や文化性を尊重することが重視されるようになる。
IFSWやIASSWなどの国際組織がソーシャルワークのグローバル定義や倫理原則などを策定し、ソーシャルワークの共通の基盤や方向性を示す。
1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災など自然災害に対するソーシャルワークの役割が注目される。
令和時代のソーシャルワーク
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、社会や経済に大きな影響が及ぶ。
オンライン化やデジタル化が加速し、働き方や暮らし方が変化する。
人口減少や高齢化が進み、地域間の格差や社会保障の負担が深刻化する。
環境問題や災害対策などの持続可能な社会の実現が求められる。
ソーシャルワークは、感染症対策や在宅支援、地域包括ケア、多文化共生などの分野で重要な役割を果たす。
ソーシャルワークへの今後の期待
ソーシャルワークは、個人と社会の相互作用にアプローチするため、社会環境の変化が激しい時代においては多様な役割が求められます。厚生労働省の「第9回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会」がまとめている「ソーシャルワークに対する期待について」では下記のように「包括的な相談支援体制の構築」と「住民主体の地域課題解決体制」が必要と提言されています。
恐らく地域包括ケアシステムの構築を目指す内容で、地域住民みんながソーシャルワーカーになる、みたいなちょっと何言ってんのかわからないような内容なんですけど、結局は、社会保障費用を抑制したいので、住民は隣近所で助け合ってくださいね(自助互助)、という事なんだろうと思います。

これ、もう間に合うタイミングではないし机上の空論になりそうです。
そもそもこんな事が地域住民でできるようになるのであれば、国という器って本当に必要ですか?という事にもなりかねないので、ある意味で国が担う責任を自分で放棄しちゃっているような形にもなっています。
特に少子高齢化や人口減少が進む地方の地域では、移動の問題をはじめ様々な問題がどんどん顕在化してくると思います。
人手不足、経営不振による公共交通網の減少は、そのまま地域住民の生活の質を悪化させます。
本当なら国や議員にこそソーシャルワークの視点が必要なんですけど、現実はそういう状況でもないのでなんとも言えないですね・・・。
研修資料の準備で調べてみましたが、将来が不安になるような感じなってしまってどうしたものか・・・と悩みます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
