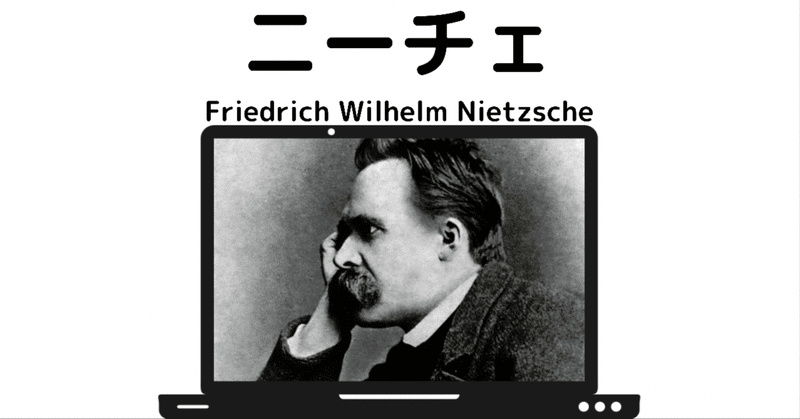
ニーチェについて調べてみました。
先日、こちらの記事の中でニーチェが出てきまして、いつか調べようと思いましたが、きっとそのうち調べる事自体を忘れてしまいそうだったので早めに調べてみました。
本当は何か本なりを買って読んだ方がよいとは思うのですが、ちょっといろいろ時間的な余裕もないのでサクッとネット検索で。
ニーチェはドイツ出身の19世紀の哲学者です。名前はかなり有名で、誰しも一度は聞いたことがあると思います。
名前だけは聞いた事あって、有名な人なんだなぁ・・・くらいで終わっていました。
ニーチェの思想を理解するには、ニーチェの哲学史上の位置づけについて理解する必要があります。
まず、ニーチェが登場する以前と以後の思想では、180°異なります。ニーチェによって大転換が起こったと言って良いでしょう。
うお!めっちゃ凄い人じゃないですか!
業界を180度変えるというのはとんでもない事ですよね。
ニーチェが乗り越えようとした「これまでの哲学」とは何なのでしょうか?
それは、「超自然的原理」(言い換えると形而上学的原理)を立てて、それを媒介にして、自然を観察し、自然と関わるような思考様式のことです。「超自然的原理」はプラトンのもとでは「イデア」、アリストテレスのもとでは「純粋形相」、デカルトのもとでの「理性」など、名前を変えながら継承されています。
つまり、「哲学」という学問体系自体が、「超自然的原理」を用いた思考体系だということです。
ニーチェは、その哲学一般の思想体系を批判し乗り越えようとしました。ニーチェは哲学批判とは実際には言わず「プラトニズムの逆転」と表現していますが、ニーチェ以前の哲学はすべてプラトンの解釈であると言われてますから、哲学批判を試みたと言えるでしょう。
あぁ・・・もう理解が追いつかなくなりつつある状況です。
哲学とかも良く知らないので余計でしょうけど、カタカナの人名がいっぱい出てくると脳が理解しようとするのをやめそうになるんですよね・・・これなんでだろう・・・。中国とか日本の人名だと全然大丈夫なんですけど・・・やはり漢字の威力というか、そういうのがあるのかもしれませんね。
とにかく、ニーチェ以前の哲学というのはプラトンの思想体系だった、という事でしょうか。
哲学という学問自体が”超自然的原理”を用いた思考体系という所でちょっとよくわからないんですけど、”イデア”とか”純粋形相”とかはさっぱり意味不明なんですけど”理性”というのは、人間が持っている理性の事なのかなぁ・・・。そうであれば、それを超自然的原理というのもどうなの?と思ってしまいました。
ただ、ニーチェという人が、そういう事に”なぜ?”と感じて別の角度から考えてみた、というのは昨日アップした記事のラテラルシンキングにも繋がるような感じですよね。
様々な分野で、これまでの学問を批判し乗り越えようとする動きが見られたと言えます。
経済の分野でも同じような事が同時代に起こっていたようです。
歴史を振り返った時に、こうい同時期に同じような考え方で世の中を変えていく人たち、というのは結構出てくる気がするんですよね。
なので、個人の発想というよりかは、時代か何かが個人をそうさせている、というような気もしないではないです。
ニーチェはよく実存主義の哲学に分類されると言われます。実存主義とは大雑把にいうと
哲学の伝統にこだわらずに自分自身との対話の中でものを考える立場
です。しかし、これはちょっと言い過ぎです。
なぜなら、ニーチェは古典文献学者として経歴をスタートし、様々な西洋哲学の伝統をきちんと理解しているからです。
ニーチェという人は、ちゃんと批判する学問をまずは理解した上で批判しているという事ですよね。ちゃんとした人だなぁ、と思いました。

つまり、ニーチェは一見関係のない芸術様式の研究から、ギリシャ以降続く、西洋を覆う思考様式(哲学)について、理解しようと試みたと言えます。
もともとは芸術を研究されていたようで、そこから哲学への考察を深めていったそうです。
まぁ、ちょっと良くわからないんですけどね・・・。
ニーチェの有名な言葉に「神は死せり(神は死んだ)」がありますが、つまり、最高価値と考えていた、超感性的な原理、言い換えれば「神」の価値が揺らいだことを表現した言葉です。
神の価値 = 超自然的原理、という理解でも良さそうですね。

これらが人間を支配するために作られたもの、という考え方自体が凄いというか、そんな事を思うのか、と感心しかないです。
プラトンがイデアを設定し、世界は作られて存在すると考えた背景には政治の腐敗がありました。つまり、ニーチェが考えた、人間を支配するための価値基準が「超感性的なもの」だという批判はその通りだということになります。
もともと存在しない「超感性的なもの」「超自然的なもの(形而上学的なもの)など、無くなって然るべきで、それ自体必要ないものだと考えればニヒリズムを克服できると考えました。
しかし、「超感性的なもの」がなくなったら、何に価値を求めれば良いのでしょうか?お金が価値があると思っていたのに、いきなりお金がない世界を信じろと言われても難しいですよね。
ニヒリズムあるいは虚無主義(きょむしゅぎ、英: Nihilism、独: Nihilismus)とは、今生きている世界、特に過去および現在における人間の存在には意義、目的、理解できるような真理、本質的な価値などがないと主張する哲学的な立場である。名称はラテン語: nihil(無)に由来する。
今まで価値があると思っていた事が、もしかしたら本当は価値がないんじゃないか・・・、これって職場で業務改善や手順とかを変えるときに陥っている心理状態かもしれませんね。
これまで信じてやってきた事が、これから変わる = 価値がないといわれているような感覚・・・、こちらが合理的で正しいと思っていたとしても、そこにはそれを認められない理由があるんですよね。
ニヒリズムという単語が良く出てくるので調べましたが、そうかもしれないけどそれを認めてしまうと何だか悲しいな、と思ってしまいました。
そこでニーチェは、取って代わるような、あらたな価値を設定しようとします。いわばニヒリズムに対する処方箋を施します。
超感性的・超自然的なものが否定された今、残されたものは感性的世界、つまり「自然」しかありません。超自然的な原理が設定されている時は、「自然」は、質料(ヒュレー/マテーリア)、つまり死せる物質(マテリアル)でしかありませんでした。
しかし、超自然的な原理が否定され、自然は再び生命力を取り戻すことになります。つまり、自ずから生き生きと生成するという自然観です。プラトン以前の思想家たちの考え方です。
それをニーチェは「生(レーベン)」という概念で説明していますが、生(レーベン)の本質とは「力への意思」であると説明しています。つまり、今あるものより大きくなろうとする、生き生きと変化するということを「力への意思」という妙な言葉で表現しています。
生き生きと変化すること。
今あるものより大きくなろうとする事。
成長という言葉がぴったりはまりそうですけど、そんな進化したり発展する事が新しい価値になって現代に繋がっているという事なんでしょうか。
うーん、やっぱりよくわからんというか、もうちょっと僕にもなんとなくでもわかったかも?と思えるような記事はないかと探してみました。
1883年から1885年にかけてニーチェが発表した『ツァラトゥストラはかく語りき』では、「超人」の思想が展開されています。「超人」は、恨みや妬みの感情をもたず、嫌な出来事はすぐに忘れ、従来の価値観にとらわれることなく常に創造力がある人間のこと。ニーチェの慣習にとらわれない開放的な考えが読み取れるでしょう。
超人って凄いですね、理想のリーダーっぽいですね。
こんな風になれたらよさそうですけど、さすがに・・・
「目的を忘れることは、愚かな人間にもっともありがちなことだ」
物事に熱中するあまり、目的を見失うことはよくあること。しかし目的を失ったままでは、最終的に自分の思い描いた理想の場所に辿り着くことはできません。何のためにやるのか、目的を明確にすることで、結果を出すことができるのです。
何のために誰のために、というのは本当に重要ですよね。
「樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ」
人間にとって樹木を育てる目的は果実を得るためだと考えるのが普通ですが、樹木が芽を出すにはまず種を植えることが必要不可欠。果実という結果は、種を植える行動がなければ得られません。つい目先のことばかりを考えて身動きがとれなくなりがちですが、まずは行動することが大切だと言っています。
目先の利益だけを考えているとダメですよね。
自然の恵みも見境なしに乱獲すれば無くなってしまいます。
種を植えるという事で考えると、やはり職場の環境改善というのは育成が重要だな、と改めて感じました。
「人が意見に反対するときはだいたいその伝え方が気に食わないときである」
誰かに反対されたり誰かを反対したりする時、意見そのものに反対しているのか、相手の態度を批判しているのか見極める必要があります。意見に反対している場合は考え方の違いをすりあわせることが大切でしょう。また人間は、どれだけ正しいことを言われたとしても、伝え方が悪ければ受け入れられないもの。誰かに意見を伝えたいのであれば、伝え方に気を配る必要があるのです。
物の伝え方とかもありますけど、普段の関係性も重要ですよね。
正しい事だからみんないう事を聞くという事ってほとんどないんですよね。
伝え方に気を配るというのは最低限の大前提ですよね。
「忘却はよりよき前進を生む」
人生では、時に忘れることで前に進めることもあります。経験の積み重ねも大切ですが、悲しみや憎しみなどのネガティブな感情を引きずらないことも重要なのです。
ネガティブな感情は覚えていても仕方ないので一刻も早く忘れた方がいいですよね。忘れようとすると逆に余計にその感情に引っ張られたりするので、別の事に集中したり夢中になれる事に取り組んだり。
僕は、何か映画を観る事が多いかもしれません。
登場人物や映画の世界に入ってしまう事でうまく忘れる事ができる気がします。
ニーチェについて調べましたが、やっぱりというか哲学というのはそれ自体が難しい気がするので、こんなちょっと調べたくらいで何が理解できるという事ではありませんが、なんとなく新しい価値観とかに触れる事ができて成長できた気がします。
気のせいでもそういう実感って重要だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
