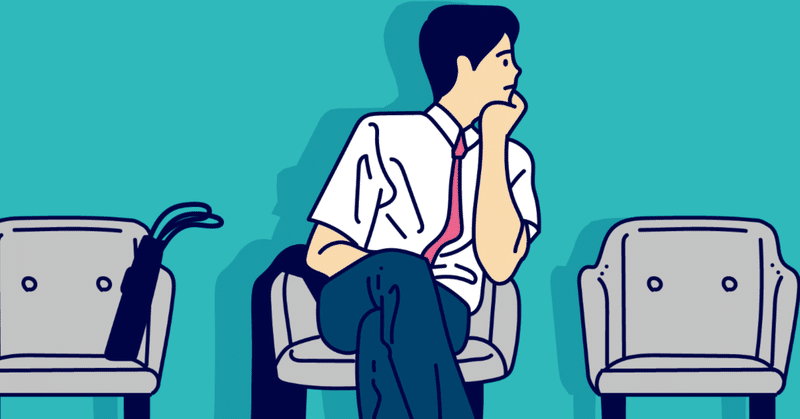
『小説』 あの頃のぼく(2)
( 小さな美術出版社に勤めていたぼくは、あるとき偶然、後藤さんと知りあった。都会の片隅でひっそり生きている姿に何かしら親近感をおぼえるのだった)
「はい。これが注文なされていたピカソとモディリアニ。それから、『構造主義と記号論のあいだで揺れるヌーディスト』ですね。いま、ここにないんですよ。たぶんもう、あちらの方に着いていると思います。すこしここから離れていますけど、ご一緒によろしいでしょうか」
「ええ、大丈夫です」
どうも、すみません。
お手数かけます。
日時的に、
時間的に会社の方に、
もう配達されていると思うんです。
そういいながら顔を下げ、
ていねいに応対していた。
別にそんなに恐縮されるほどのことでもないのに、
ぼく自身、
あまり急いでないのでこちらの方が恐縮してしまう。
むしろ、この時間を楽しんでいた。
後藤さんといるのがいやではなかった。
心地よい気分だった。
なにかしら、心が落ちつくのだ。
また後藤さんのあとをついていくことになった。
後藤さんはぼくの横じゃなくて、
すこし前を先導するかのように歩いていった。
ときおりぼくが歩くのがいやじゃないのか、
疲れないのかと気にしていた。
振り向いて丸くふくらんだ赤いほっぺを見せながら、
もうすぐですから、
どうもすみませんと頭を下げていた。そんなに恐縮しなくてもいいのに、ほんとうにこの人はいい人なんだな、ただ単に腰が低いだけじゃない。
後藤さんはさっき来た渡り廊下を戻って、
もとの大きな建物のなかに入っていった。
本館みたいな建物に入ると、
二階にのぼっていった。
なぜかここにくる本はすべて、二階に上げられていくらしい。
ここでも後藤さんはこちらを振り向き、
赤いほっぺの笑顔を見せながらふたたび、
もうすぐですから、すみませんといっていた。
二階に上がり、
しばらく歩くと右側の扉を開けて、
後藤さんは入っていった。
あとに続いて室内に入った。
そこはさきほどまでいた分室以上に広く、
建物のワンフロアとなっていた。
本がたくさんあるのは分室と変わらない。
ただ機械の音がゴトゴトなり響いていた。
ベルトコンベアでさまざまな本が運びこまれ、
室じゅうがあたかも体の血液循環みたいにまわりこまれていた。大勢の人が本の棚のところで作業をしている。
正社員ばかりじゃなく、
あきらかにアルバイトとわかる若い人たちが働いていた。
本を棚に入れたり、
本をチェックしている。
その多数の本棚や作業員のまわりを囲むようにベルトコンベアがまわっていた。
そのベルトコンベアから本のつまった箱を取りだして、
なかの本を個別的に他の人たちが本棚の方へ運んでいくのだった。
後藤さんとぼくは、
本が運ばれていくベルトコンベアの横を通りすぎていった。
室内のまん中ほどにくると、
後藤さんはひとり、
ベルトコンベアの上にかかっている小さな鉄製の橋を渡っていった。
ゆっくりと足もとを確認しながら、向こう側に渡った。
「あっ、高木くん。ちょうどよかった。この本、届いていない。たぶん届いていると思うんだけど」
ちょうど渡りきったところの本棚に、
担当者の人がいたらしかった。
ここでも、
年下で後輩と思われる人にていねいに声をかけていた。
そうなんだよ、悪いね。
忙しいところ、
お願いしますと頭を下げていた。
ほんとうに、この人は誰に対してもていねいに応対する人なんだ。
やがてぼくの注文した本があったのか、ほっとしたようだ。
「どうも、ありがとう」
こちらまで、
後藤さんの声が聞こえてきた。
後藤さんの安心したような声がぼくの方まで伝わってくるようだった。
こちらまでなんだか、安心したような気持ちになった。
東京生まれのぼくがいうのも変だけど、
都会にもまだこんな人がいるんだ。
なんだか、ほっとしたというか、
なつかしいというか、
まだ若いぼくは思うのだった。
逸材を見つけたという感じだった。
それから用事を見つけては、
取次所に行くようになった。
そのたびごとに後藤さんと会うようになった。
専門の担当になったようだった。
前に何度か行った時は一度も会わなかったのに、
会うようになるといつも会うようになった。
そんな何度目かの時、
後藤さんから誘いを受けた。
上の階、
食堂の横に小さな喫茶室がありますから行きませんか、
とお茶を誘われた。
もちろん、
さし急いで用事がある訳じゃない。
喜んで招待を受けることにした。
すこし後藤さんにも興味があったので、話してみたかった。
テーブルに向かいあって座った。
なんだかにこにこして楽しそうだ。
ぼくみたいな若い人とあまり話したことがないように、
あらためて話をするのがうれしそうだった。
若い人ばかりでなく、
社内でも他の人たちとうちとけて話をしているようにもみえない。
浮いているというのでなく、
また疎外されているようでもない。
なんとなくひとり淡々としているようにみられた。
思いちがいかもしれない。
まわりにいる社員と空気がちがうように感じられた。
ぼくが最初に出会ったのがあの電車のなかだったから、
なおさらそんな印象を受けた。
そうでないとうれしいのだけど。
コーヒーがふたつ、
運ばれてきた。
痩せて黒ぶちの眼鏡をした女性がテーブルの上に置いた。
ウェイトレスをするには歳を取りすぎている。
三十半ばすぎ。
社員とも思えない。
にこっと笑顔をつくって離れていった。
どうも後藤さんとは懇意らしい。
たぶんここにはよく来るのだろう。
あれ、
テーブルの上を見ると、
コーヒーの他にショートケーキがふたつ添えられている。
ぼくはたのんでいないのに。
「ここのショートケーキ、うまいんですよ。いかがですか。わたしのおごりということで」
「ありがとうございます」
礼をいって、
なにげなくショートケーキを見ていた。
白いクリームケーキの上にちょこんとのっている、
赤いイチゴ。
とてもおいしそう。
ぼくはおもわず指でつまんで、
ぽいっと口のなかに入れた。
とてもジューシーでおいしかった。
またおもわず、ぼくの顔はほころんだ。
後藤さんも、
小さなフォークを使ってケーキを食べている。
とてもうれしそう。
甘党なんだ、後藤さん。
この時が、
いちばん好きなんだといいたげに食べている。
なぜか白いケーキをさきに食べ、
てっぺんの赤いイチゴは残っている。
最後にクリームとケーキの山が崩れる時に食べるんだろうか。
すこし気になった。
その半面、
ぼくのケーキにはもうイチゴがない。
赤いイチゴがない。
白いクリームでおおわれたショートケーキのてっぺんには、
赤いイチゴがあったらしい跡がさびしく窪んでいた。
なんだか、悲しくなった。
わからない。
取り残された残骸みたい。
ひとりぼっちのケーキ。
ひとつ、ぽつんと。
ケーキから目をはずして顔を上げたら、
後藤さんと目が合った。
おもわず、
後藤さんとぼくは笑ってしまった。
いやあ、どうも。
ぼくは恥ずかしくなって顔が赤くなった。
後藤さんほどなくても、
その時はすこし赤らんでいたんじゃないかな。
「じつは、いつも会っているのに自己紹介もしていなくて、後藤といいます。よろしく」
「山形美術出版事務所の田中です。よろしくお願いします」
おもえば、
ちゃんと向かいあって話をするのは初めてだった。
それまでは形式的な話ばかりでうちとけて話したことがなかった。
単に仕事的に相対していた。
「後藤さん、お子さん、いらっしゃるんですか」
「ええ、ふたり。上が小学三年生、下がもうすぐ五つですかね」
「ふたりとも男の子ですか」
「いえ。上が女の子で、下が男の子です」
「いまがいちばんいいんじゃないですか。かわいいざかりで」
「さあ、どうですか。まあ、元気であってくれればいいと思っています。こればかりは親の気持ちだけではうまくいきません。田中さんの方はいかがですか。ご結婚なさっているんですか」
「いや。相手がいるにはいるんですけど、生活していける自信もありません。向こうもその気があるかどうかもわかりません。まだ歳も若いし、ぼちぼちやっていきます」
じっさい、
結婚どころじゃなかった。
就職して半年ばかり。
生活するので精いっぱい。
とてもとても結婚なんて。
それに、
まだ大学受験の失敗の後遺症も残っている。
いまだにどこかにくすぶっている。
まだ、
すっきりした気持ちで世の中に存在している気分になれない。
そんな時に、
小市民的といっては悪いけど、
後藤さんの顔を見ると、
とても心が和らげる。
会話をすると安心する。
後藤さんより、
どこかしらましなんだ。
がまんして社会に適応している人がいると思えば、
そんなに贅沢をいっていられない。
上を見ればきりがない。
下を見れば後がないという言葉があるように、
そんなふうにがんばっている人を見れば、
いくらか気持ちが落ちついた。
ほんとうはそんなことではいけないんだけど、
なぐさめられる思いで対応していたかもしれなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
