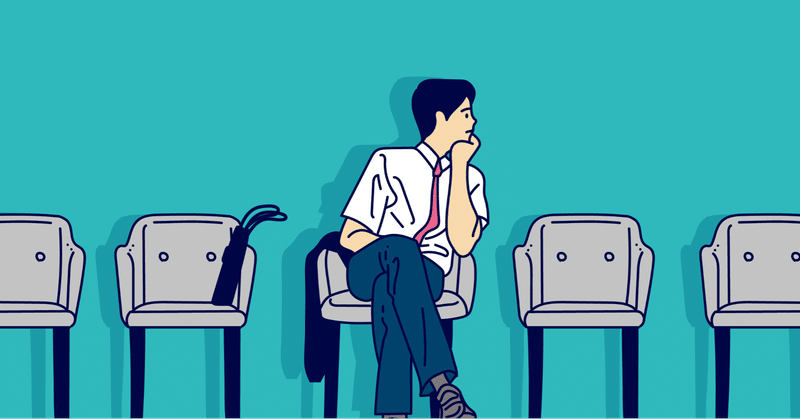
『小説』 あの頃のぼく(5) 完
( 半年たったある日、街で偶然に後藤さんと出会った。そこでぼくは後藤さんの意外な一面を知ることになった )
週末、
ここは若い人が多い居酒屋ふうのカウンター。
ぼくはウイスキーを飲んでいた。
となりで、ぼくの彼女、
ひろみはカクテルを飲んでいる。
いいたくないけど、
カクテルにはいやな思い出があった。
以前彼女にあわせて、
いろんなカクテルを飲んでいた。
ところがどういうわけか、急に気持ちが悪くなってしまった。
それ以来、カクテルは飲まないようにしている。
よほど合わなかったのか。
ぼくには合わないのか。
それともつくったものがいけなかったのか。
こりごりしてしまった経験がある。
そんなことを思いだしていた。
ふと、ひろみが前かがみになった。
胸元からブラジャが見える。
ピンク色。
色っぽい。
ぼくはまだ彼女を知らなかった。
抱いていない。
裸も知らない。
どんなからだをしているのかもわからない。
だけど抱きしめたことはある。
もちろん服の上からだった。
一度だけあった。
女のからだって、柔らかいと思った。
胸がこんなに柔らかいなんて、
まるでマシュマロみたいな感触をぼくの胸に感じた。
もっと他にたとえれば、
丸い軟球のテニスボールを大きく柔らかくしたみたいな感じかな。
おもわずひろみがぼくを見て、目が合った。
いっしゅん考えていることをさとられたかなと思って、どっきりした。
なぜか、その日に限って潤んでみえる彼女の目がぼくをどぎまぎさせる。
言葉がつまってしまった。
「それから、どうしたの」
「それからって」
「おじさん」
「あっ、おじさんね」
なに、どうしたの、
急にどたばたして。
そんなふうにひろみには見えているだろう。
彼女はおもしろそうに聞いている。
事の顛末をおもしろがっている。
興味深そうに。
「男のぼくが見てもそうなんだから、君みたいな女性だってきっとだまされると思う。でもきっとだまそうと思って、だましているんじゃない。成り行きというか。どんな成り行きが知らない。けっして意図して、だましつづけて関係を持っていたのじゃないと思う」
「あなたも、そういうふうにやりたいわけ」
「そうじゃない。驚きと脱帽。それだけ。ぼくって、世の中を知らない。世間を知らないと思ったわけ。だから人生をよく生きるためにも、人をよく知るためにも、見抜く力をつけないといけないと思ってさ」
「つけて、どうするの」
「いや、そのう、つけていろいろと今後のためにも役立つだろうから」
「いいよ。そんなもの、つけなくたって」
「そうかな」
〈ふと、天井を見あげてみる。そんな
会話もいまは昔。いまいるこの空間は
明るく晴れやかな色に包まれていた。
壁にも欧米の絵画が貼ってあった。た
ぶんこれもイタリアンレストランだか
らだろう。何十年か前、ひろみと語っ
ていた居酒屋バーは様変わっていた。
そう、ここで一緒に座っていたカウ
ンターもない。残っているのは室内の
大きさと天井の高さぐらい。時は変わ
っても、客の年齢層は同じ、若い人。
雰囲気はちがっていた。空気ばかりで
なかった。人の感受性がちがっていた。
昔、ぼくより年輩がたぶん感じていた
ようにいまのぼくが感じ始めているも
のがあった。
あのときの座っていたカウンターは
あそこの辺だった。壁の造り具合から
して入り口から入って左に曲がったと
ころだった。いつも口にスパゲッティ
をくわえながら、そうそう、あそこら
辺。同じようにいまでは、ぼくの子供
がスパゲッティにかぶりついている。
スパゲッティをこぼさないよう、ほ
らほらあごを突きだして。子供が楽し
そうに、ぼくの口にスパゲッティを与
えようとする。ぼくはそれに答えよう
と必死になって食べている。子供はに
こにこしてはしゃいでいる。ぼくはす
こしばかり感傷的になって思う。時代
が変わっても場面が変わっても、たし
かにあのときぼくとひろみは時代を生
きていたのだ。平凡だけど一市民とし
て。政治家でも革命家でも偉大な芸術
家でなくても、一個人として生きてい
た。
まわりを見ても、世の中を見ても、
ひとつも変化していないように見えた。
もしかして、あの時わからなかっただ
け。世の中を見る目がなかった、仕組
みとか暗躍しているものがわからなか
った、それだけだったかもしれない。
同じ世界なのに、同じ現象なのに、い
まは見えるものが以前と変わってみえ
る。大人になったのだろうか。もちろ
ん、見た目の建物などは変わっている
はずなのに根本的なものはそう変わっ
ていない。
ぼんやり思いだす、あの時のこと。
美大生のひろみはぼくの話を聞いてい
たと思ったら、気づくとぼくの似顔を
描いていた。手もとにあった白い紙に、
鉛筆でぼくの顔を描いていた。手がひ
まだと、なにか絵を描きたい習性みた
いだった。描いていると安心。気がつ
いたら描いている。そんなひろみを、
ぼくはよく見ていた。
マンガみたいに単純な線でなく、パ
サパサと輪郭をつけたようなデッサン
ふう。ぼくの顔を、ちらちらと彼女の
大きな目で見ていた。ぱっと見てすぐ
に下に目をやり、紙に鉛筆でデッサン
する。似顔絵を描く。描いていた。
後藤さんも、あの時 〉
たしか、
あれは半年ばかりたった、
ある日だった。
ばったり街中で後藤さんと出会った。
休日の繁華街。
人の激しい通りで出会った。
こんなところで会うのも意外だった。
後藤さんのカジュアルな服装な服装を見て、
また意外に感じた。
春なのか、
ワイシャツ姿の軽やかさで、
なんだか以前とちがって明るかった。
とても解放されたような雰囲気をあたえた。
前より、ほがらかに元気になっている様子だった。
ぼくはあいさつをした。
「こんにちは」
「おっ、田中くんでしたっけ。ひさしぶり」
ぼくを見た時は、
一瞬驚いたようだった。
だけどすぐに、
昔のフレンドリーな関係にもどった。
形だけのあいさつをして、しばらく日常的な話をしていた
向こうもなつかしかったのか。
どう、行きつけの店があるんだけど行かないというわけで、
大人の後藤さんの行きつけの店にお誘いを受けた。
別に、こちらに急ぐ用事もなかったし、
後藤さんの現況を聞きたかった。
それに、あの借金の問題。
三人の女性の関係もあったので、興味をもってあとに従ったしだいだった。
行きつけのお店だというので、
まるっきりお酒を飲むところだと思っていた。
なんのことはない、喫茶店。
おいしそうなケーキがたくさん並んでいる。
奥ばったところにテーブル席があった。
そこに導かれるようにしていった。
ほんと、行きつけの常連みたいにスムーズに軽やかに通されていった。
テーブルにつくと、いつものにこにこした顔にもどって、
ぼくの顔をしげしげと眺めた。
注文にも慣れたふうに、
いつものふたつ、お願い、と来た。
よほど気にいった店みたいだ。
「どう、いいところでしょう。静かで。いいお店って、なんでも通りの間の小さな路地にあるから不思議ですよね。ここのケーキもおいしいけど、じつはお茶がものすごくおいしんですよ。お茶なんかタダで飲めるから、別にお金を払って注文しなくてもいいですよと思うでしょう。
じっさい、私もそう思っていました。ところがショートケーキよりも高いので、なんだかなと思っていたんですが、ものの試しに飲んでみたんです。びっくり。お茶の香りが口いっぱいに広がって。それからは必ずここに来ると、ケーキと一緒に注文するんです。ケーキには合わないと思っていたのに。ミスマッチみたいで」
後藤さんは饒舌だった。
そういえば、
いつか後藤さんの会社で会った時もケーキを一緒に食べたんだ。甘党なんだ、後藤さん。
あのときも、うれしそうに食べていたもの。
それにしても、
どうやって切りだしていいものやら。
別に聞かなくてもいいけど、なにか心配。
うまくいっているんだろうか。
大丈夫かな、借金。
そのことが気になって、
あまり気持ちが前に進まない。
聞いていいのかどうかわからない。
それに変に後藤さん、にこやかで元気そうだし。
もしかして、いいことがあった。
借金が返せそうとか、
返したとか、
見通しがついているのかもしれない。
そうでなければ、こんなに明るくふるまえないもの。
たぶん、そうだろう。
ところが話を聞いていくにしたがって、
驚くことばかり。
後藤さんはいままでの体験というか、
思いのたけを話し始めた。
どうして、私がこんなにおとなしくなったのか。
世の中に埋もれたような生活をしているのかを話し始めた。
「あの会社では、自分を出してみても虚しいんですよ。別に本心を隠しているわけではないけど、その方が楽なんです。みんなに合わせているのが、いろいろな意味で」
指紋を取られたことありますか。
指の第二関節まで墨をぬられて、
相手の指でこうやって押さえつけられて、
両手の指を一本ずつすべて取られるんですよといって、
後藤さんは実演してみせた。
田中さん、あります。
軽い交通事故ぐらいだったら、取りませんよね。
最近は取るのかな。
意外と交通マナーは守っているんですよ。
丸く赤いほっぺをほてらせながら、明るく、なぜか楽しく話していた。
なんと、後藤さん。
大学時代、政治活動していたんだとか。
それで警察から取り調べられた時のことなんかを語った。
それもいとも簡単に話している。
みんな、その当時そんなものだった。
本人も振りかえってみれば、大変そうに見えるそうだ。
他人ごとみたいだった。
当時は、そんなに深刻には思っていなかった。
まあ、時代がそうだったから、
なんとなく激しくなったかなといった。
過去の出来事が楽しく、
過去はすでに終わったことなのでなつかしく思っているかのようだった。
その反面、失ったものも多かったようだ。
話の内容があまりにも
取次所に勤めていた時の後藤さんとはちがっていたので、
とまどってしまう。
どう対応すればいいのかわからない。
印象がまるで正反対というような言葉があるように、
性格も以前とまるでうって変わってみえる。
過激派とも関係していたなんて、いとも簡単に怖いことを語った。
後藤さんにとって、これはあたりまえ。
ほんとうの姿といわんばかりにしゃべりつづけている。
いままでためていたものがとり放たれたかのようだった。
心が蝶のように心地よくはばたいて
飛んでいる感を受けたようだという言葉は、
まさにこの時使われるにふさわしかった。
後藤さんの話は本人のことばかりでなかった。
いままでのぼくが持っていた考えや物事のとらえ方も、
いつしか変えていったと後になって思う。
後藤さんの思春期。
大学生時代の活動とその感情など。
名前だけは聞いたことがあるマルクス。
初めて聞くバクーニン。
あの時は、すでに政治の季節は終わっていた。
あたかも第二次世界大戦の状態を聞いているかのごとく響いていた。
話している後藤さんは懐かしがっているようにみえた。
それでもまだ引きずっている問題でもあったようだ。
後藤さんの年齢がちょうど思い起される時期なのか。
青春に結論がいる時期なのだ。
なんでもいいからこれを一段落しなければ、
なにか欠けているような、
前に進めないといった格好だった。
まるで後藤さんがじぶんの親から戦争のことを聞いていたように、
ぼくも肉親じゃないけど後藤さんの活動体験を聞いていた。
後藤さんの子供はまだ小さいのでぼくに話しているのだ。
話すことでなにかを清算したかのようにじぶん自身に話していた。
ぼくはニュースで知った事件を後藤さんの個人体験で聞いていた。
たとえば三島由紀夫の事件。
あのときはテレビを見てびっくり、
大学生の時で、昼間眠気まなこでニュースを見たという。
浅間山荘事件の時は京都の旅館にいたそうだ。
旅館のテレビを見ていたそばでは若い男が腕を振りあげて、
やれっ、やれっ、
もっとやれとあたかもプロレス観戦のようにはしゃいでいた。
向こうでは同じ年頃の青年たちが血を流し、
銃で応戦していた。
犯罪集団のように映しだされていたという。
考えればいまでも立場はちがっても、中東では同じことがくり返されている。
アメリカの貧しい青年や、
奨学金をあてにしなければ学生生活を送れない青年が戦場に行って、
互いに血を流しあって殺しあっている。
その一方で、
以前テレビで、
イラク戦争を観戦していたアメリカの同じ年頃の若者たちが、
ビールを飲みながらパブではしゃいでいた。
徴兵制度がなくなった米国では昔の反戦デモはうそのように消えた。
少なくなった。
聞こえてこない。
いま欧米の偽善さを知ってか知らずか、
アラブの反撃が始まっている。
まるで、百年前の中国を見ているようだ。
後藤さんのその時の気持ち、
じつをいうと聞いていてもよくわからなかった。
気持ちの方はわかるといいたい。
でも、やっぱり気持ちもよくわからない。
なぜこんなことをぼくに話すのかさえわからない。
わからないと思ってしゃべっているような気持ちもみえる。
ただしゃべりたい。
ぼくになにかいいたい気持ち。
いま話したいというような、
なにかそうさせる感情というか、
気持ちがわいているのだろう。
それもぼくみたいに
政治、社会にすこしばかりうとい男だからこそ、話しやすい感じだった。
もしかしてぼくにメッセージをしている。
じぶんにできなかったものを託してしるとか。
そんな大そうなことじゃないだろう。
ただ話している。
気分をはらすためだけかも。
そのあと、後藤さんはどんな話をしたのかよくおぼえていない。このようなこと話していたことを漠然と記憶している。
これだけでもおぼえていたのも、
あまりに変わった様子に戸惑いと驚きがあったからだ。
とうとう別れぎわになってもいえなかった。
借金のこと。
女性のことなど。
聞いたところでいったい、なんになる。
結末がわかってもどうってことない。
ぼくの心が安心するだけ、オチがつくということだけだ。
そんなものなんて。
ただ最後に、ぽつんと後藤さんはいった。
大学紛争の闘いはうまくいかなかったのに、
女性関係のことだけ、大杉栄のまねをしちゃった。
大杉の名前を聞いたのもこれが初めてだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
