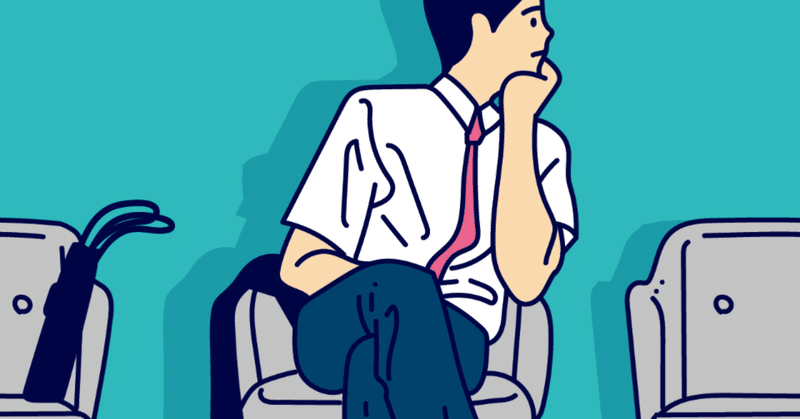
『小説 』 あの頃のぼく(1)
明日より今日を視れば
猶ほ今の昔を視るがごとくならん
元政、江戸時代初期の文人
* 同じ時間の読書でも、義務感やおもしろくなかったらとても長く感じるのに、おもしろい本はゆっくり読んでも、アッという間に過ぎるからなんて不思議な感じ。たとえばこの短編が興味深く読まれることを期待しつつ 。
ぼくはこういう者ですと直接言うよりも、絵画とか音楽を創造したものから深く感じとられ、文学でも虚構(フィクション)を描くことによって、気づかないじぶん自身が見つけられ、文章を書きながらじぶん自身が創られていくにはいい手段のようだった。
この物語では時をあい前後して、じっさいに美術雑誌出版社に勤めていたことを除いて、フィクションを通して、あの頃のぼくの心のあり方をのぞいてみたかった。
物語の主人公と同じく、ぼくは大学受験に失敗して鬱屈した日々を送っていた。 全5回
朝、
今日も、
通勤はラッシュアワー。
おもえば、
通勤も一時間もかからない。
歩行、電車を入れてだから東京の会社暮らしではめぐまれている。
一時間以上はざらだもん。
それに電車も一本道。
乗り換えなし。
東京に実家があるのに親もと離れてのひとり暮らし。
便利なアパートを見つけたというわけ。
みんな、えらいな、
こんなラッシュアワーのなかをいつも通勤するなんて。
ぼくなんて、
一日でグロッキーになっちゃった。
それも半年もつづけているのでじぶん自身がえらいと思っているのに、
他の乗客のサラリーマンはもっとえらいと思ってしまう。
いままでも、
これからさきもやっていくんだろう。
大変だ。
すわっている人はともかく、立っている人はなおさらだった。
特に、
乗客口のドア近くにいる中年のおじさんはとても大変そうにみえる。
すこし頭が禿げかかって小太りのおじさん。
とても顔のほっぺたが赤い。
あんパンみたいに丸く赤ら顔。
どこにでもいるような人だ。
乗り降りする人が出入りするたびに接触するのか、
「ごめんなさい」、
「ごめんなさい」
といっている。
なかの方につめようにも行けないでいる。
それで電車が止まって、
乗客が出入りするたびに立ち往生して困惑しているのだ。
このさき、
あのおじさんが下車するまで大変。
とてもそれまで乗客は減りそうもなかった。
ぼくはこれからさきのことを考えて、おもわずため息をついてしまった。こうやって、ずっと同じような生活をしていくんだろうか、箱づめのなかに閉じこめられて運ばれていく。乗っているのは地下鉄だった、ときに地上にあがる区間もある、だからといって深い意味もなかった。
その日の午後。
ぼくは本の取次所に行った。
注文していた本を取りに行った。
別に取りにいかないで、
先方から持ってきてもらってもよかった。
店は近くにあったので、
手っ取り早いということでもない。
ただ取りに行くぼくの方も社内いるばかりで、
ちょうど気分転換によかった。
三十分もかからない。
いつものように玄関に入り、
受付に用事をいって目的の場所に行った。
部署は見慣れたところにあって、
担当の人も同じテーブルのところにすわっていた。
その部署の責任担当者のところに、
一応顔を出すことになっていた。
責任担当者はいつもせわしく動いていた。
誰かれとなく、
いつも指示をとばしていた。
やせて細い顔をした彼は、
鼻も細くとがっていた。
テーブルのついたては係長となっていた。
ぼくはあいさつをして、
注文した本を取りにきたことをいった。
係長はいっしゅん驚いた顔をしていた。
えっ、そうなの。
別に取りにこなくてもという風に、右手で黒い丸ぶちの眼鏡を持って、こちらを見なおした。
「じゃそうだね、今日は他の人。あっそうそう、後藤さんにたのもう」
係長は、まわりをキョロキョロ。
「あっ、後藤さん。後藤さん、ちょっと、こちらに来てくれないかな」
係長が呼びこんでいるさきを見た。
後藤さんらしきひとが、
ゆっくり、
ぴょこたんぴょこたんというふうにやってきた。
いかにも善良そうでおだやかそうで、
あれっ、
朝の中年のおじさん。
「ごめんなさい」、
「ごめんなさい」
の小太りの赤ら顔で、頭の禿げたおじさん。
「今日はこの人にたのむから、よろしく」
係長から紹介された後藤さんは、
にこにこしながらぼくにあいさつをした。
「じゃ、こちらへ。案内しますのでついてきてください」
どうも、よろしく。ぼくはあとについて行くことになった。
そうか。
後藤さんというのか。
前に二、三度来たときはいなかったのに、
あの部署にいるようにもみえなかった。
見えなかっただけかな。
ただ漠然として見ていたらわからない存在だし、
目立つようなふうでもない。
そんな感じだった。
前を歩く後藤さんは、
ときおりうしろのぼくを振りむきながら、
もうすこしですからと恐縮そうに言葉をかけていた。
赤いほっぺたをさらに赤らめながら、
笑顔をふりまいていた。
ええ、どうぞおかまいなく。
ぼくは言葉を返した。
あまり意味もない、
脈絡もない交わし方をした。
そんなふうに変なぎこちなさを感じながら、あとをついていった。
そこはもうひとつの棟で、
離れたところにあった。
渡り廊下を通っていった。
歩きながら、
ふと高校時代の校舎を思いだした。
教室のある校舎から、
図書室のある分室へ通じる渡り廊下を思いださせた。
そんな思いで、
なつかしい感じがした。
偶然にも、建物の入り口に第一分室と書いてある。
分室にしては、大きな建物だった。ドアを開けると、体育館みたいに天井が高く左右に広がり倉庫みたいで、手前の左右には大きな窓があった。昼間でもシャッターがおりていて、開けるとパアッと光がさすだろうと思われて、さすがに、奥に行くほどに光はさえぎられているようだ。
手前にカウンターがあった。
そばにテーブルがふたつ。
椅子もそれぞれにふたつずつついてあった。
「しばらく、こちらでお待ちください」
後藤さんはそういって、
カウンターの奥の方へ行った。
カウンターの向こうは、
本のずっしりつまった棚が何列にも室内に並べられていた。
倉庫そのものが本の図書館書庫みたいだった。
棚のなかにはいろんな本が積み重ねられ、
あいだから注文書みたいな紙がのぞいていた。
その本のなかを後藤さんはあちこち見渡しながら、
たぶんぼくの注文した本をさがしていた。
ぼくはしばらく椅子にすわって、目の前の窓の方を見ていて
それから顔を上にあげて、天井をなんともなしに見つめていた。
なんとまあ、
静かな空間。
都会のなかにいるのに、
どこか人里離れたところにいるような、
それでいてかすかに車の音も聞こえてくるようで、
ひとりぼっち。
なんて落ちつく場所なんだ。
まわりに人がいるのに、
いないように感じてしまう不思議な空間、
昔の子供に戻ってしまう。
自由な時間、
誰からも束縛されないで、
気ままに気持ちをはせられる思い、
元気な思いはひさしぶりだった。
学校を卒業して以来かもしれない。
卒業してからも勉強なんかで時間に追われていた。
浪人していたから、
なおさらだった。
こんなに静かに、
ひとり落ちついて物ごとを考えていたことはなかったもの。
一浪でも大学に受からなくて、
挫折とか落胆とか、
もうどうしようもない気持ちでいっぱいで、
まともにじぶんに向かって考えたこともなかった。
ひさしぶりに訪れた情緒だった。
情緒というにはすこしもったいぶった言葉だけど、
なんともいえない静寂な気持ちがぼくの心をいくぶん和らげていた。
そこへ急ぎ足みたいで、
だけどゆっくりこちらに後藤さんは、
本を携えながらやってきた。
ハンカチで丸い顔の額をぬぐい、
どうも遅くなりましたといっていた。
たしかもう夏は過ぎたはずなのに、後藤さんの体には暑さは続いているみたいだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
