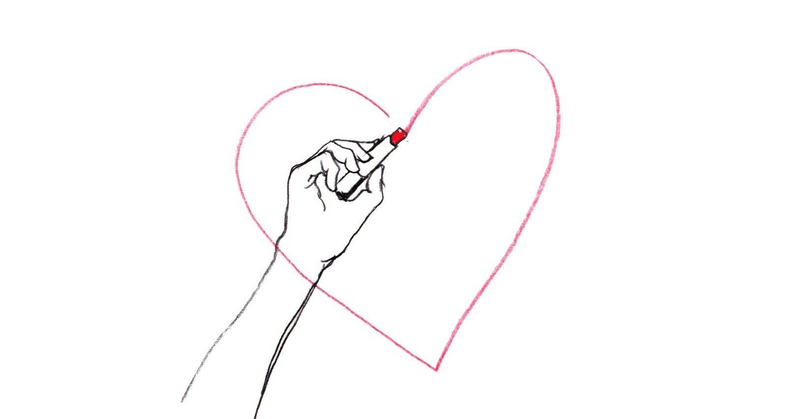
愛のかたちー認知症のおばあちゃんと私ー
おばあちゃんの訃報を聞いた時、
ああ、そろそろだったろうな。と冷静に受け止めた。
老人ホームに入って6年。
認知症が始まったのは15年以上前のこと。
お正月に顔見せに行った時は、もうほとんど骨と皮で。ただほのかな温もりと血の巡りが生きながらえていることを緩やかに証明していた。
○月×日、お通夜あるからね。
あなたスーツ着ていきなさいね。就活で着たのあるでしょ。
淡々と時は進み、
あっという間にその日は来た。
小さな家族葬。
親類は少なく付き合いも浅い。
手短に挨拶を済ませると小さな部屋に入り、葬儀の始まりを待った。
お焼香はくるくると周り、しんとした空間にお経だけが響く。
ただ数珠を手に挟み、冥福を祈り続ける。
当家のお坊さんは愛想なしお経読むのも苦手っぽいと親族内で評判なのだけど、そっと目を閉じると脈々と続く音のなかで在りし日の思い出が、頭の中にたくさん浮かんできたのだ。
それは初めてお料理をした日。
私が料理をするようになったのは、おばあちゃんがきっかけ。
小さい頃、ちょうど母が弟を妊娠していた時、よくおばあちゃんの家に預けられていた。毎度のように「おりょうりつくるの!」と繰り返していたのを覚えている。
まだ幼稚園児。家では火も包丁も触らせてもらえなかった。
「じゃあ卵つくってみようか」
「たまご?ひな、すくらんぶるえっぐがいい!」
菜箸もグーで持つような私に卵の殻が入りまくって涙ぐむ私に、
「ひなちゃん上手ねえ」
「ひなは優しいし何でもできるのね」
「こんなのひょひょいって取れちゃうわよ。大丈夫」
「おばあちゃんーこげちゃったあ」
「あらまあ。炒りたまごにしましょうね。
おばあちゃんはね、これもとっても大好きなのよ」
幼い頃の記憶がほとんどない私だけれど、初めて食べた炒りたまごの味は鮮明に覚えている。ほんのり醤油が香って少し焦げた味。
卵ひとつ分のちいさなちいさな炒りたまごを、和風な豆皿に少しずつ載せていたことも、豆皿の柄も、私の記憶にしっかり刻まれている。
「おいしい!」
「そうでしょう、そうでしょう。だってひなちゃんが作ったのよ?なんでも美味しいに決まってるわ」
仏様のように優しい顔を綻ばせて、私以上に嬉しそうにはしゃぐおばあちゃんに、私は確かに愛を感じていた。
幾年かすぎて、弟が幼稚園児になった頃。
はじめておばあちゃんの家に弟と2人で預けられた時のこと。
「ひながね、弟くんにおりょうりを作ってあげる!」
おばあちゃんは弟を抱き上げて
「お姉ちゃんとっても上手なのよー!弟くん見ててごらん?」
と、今度はノータッチ。
「ちょっとマヨネーズ入れると美味しいの」
何回も何回も作って、火加減も隠し味もかんぺき。
ふわふわでほかほかのおばあちゃん仕込みのスクランブルエッグ。
「おねーちゃん、おいしい!」
その時の弟のまるまるした白いほっぺたも、まんまるできらきらした目を見開いていたことも、天使のような笑顔も、私は覚えている。
「そうでしょ!おねーちゃんはすごいのよ!」
私も嬉しくてくるくる回って、おばあちゃんが「危ないわよ、まだフライパン熱いからね」とにこにこ笑いながらちょっと注意してきたことも、全部。
不思議なのは、弟もその記憶をしっかり持っていること。後々、「おねーちゃんの料理食べるの初めてじゃないよ。ばーちゃん家で食った。」「いまだにおねーちゃんより上手くクランブルエッグはできないんだよね」とかとか。
愛が溢れた時間の記憶。
それは、きっといつまでも残り続けるもの。
弟にしばらく手がかかっていた時、
歩いて20分はかかる自然公園につれっていってくれたり、一緒にお人形遊びをしてくれたり、私がひとりで寂しいと思う間もないくらい可愛がってくれた。
たくさんたくさんおばあちゃんの記憶も私に流れている。
私はたくさん外国のことを教えてもらった。
「これはギリシャよ。おじいちゃんにもこの景色、見せたかったわ。」
「これはオーストラリア。コアラを抱っこしたのよ。」
「おばあちゃんはね、このおじいちゃんの写真が入ったロケットを持って、色々なところに行ったわ。本当は一緒に行きたかったのだけどね….」
もういなかったけど、おじいちゃんの分の愛情もたくさんもらった。
「おじいちゃんがいたら、ひなちゃんのこと、それはもう可愛がっていたでしょうね。子どもが大好きだったのよ。」
「おじいちゃんも、いつだってひなのことを見守ってるわ。ほら、ひなちゃんがご挨拶したから、おじいちゃんいつもより笑ってるわ。」
だけど。私が10歳を過ぎた頃から異変は始まった。
「ねえ義母さん、また納豆買ってるの?」
「おはぎ20個も買ってきて….どうするのこれ」
物忘れがぽつぽつとインクの染みのようにじわじわと広がっていって。
「昨日母さんが、徘徊してたらしいんだ。」
「また? この前も警察から電話があったわ。」
私が話しかけても、前までのように返事が返ってこなくなって。
見た目は変わらないのに、どんどん私の知っているおばあちゃんはいなくなった。
その折、私は陰湿ないじめに遭い心を壊しかけていて、遠くに引っ越しをした。そして、母が入退院を繰り返しはじめたのもあり、おばあちゃんの家から足が遠のいていった。
さらに反抗期真っ盛りの時、渋々会いに行くも、しばらく会っていなかった故に会話もぎこちなく、おばあちゃんはひたすら若き日の記憶を壊れたラジオのように繰り返すばかりだった。
この時、すでに私の中でおばあちゃんは死んでいた。
私の大好きだったおばあちゃんは見る影もなく、あんなに清潔好きだったのにお風呂に全然入らなくなり、笑顔も消え、周りに小言ばかり。
もう知らないナニカだった。
しばらくして、おばあちゃんは老人ホームに入居した。時を同じくして、隠されていた軋轢を知ってしまった。
母はおばあちゃんにしつこい嫁いびりを受けていて、父も伯父もおばあちゃんと不仲だった。
余計に、おばあちゃんに得体の知れない不気味さを覚えた。
常に朦朧としている意識、会いに行くたび私を家族を認識できなくなっていく。
毎年お正月、老人ホームへの行き帰り。私たち家族は同じような会話を繰り返す。
「幸せ、じゃないよね。」
「じゃないでしょ。俺ならスイス行って安楽死したいレベル。」
「こら。死ぬタイミングは選べないのよ。おばあちゃんだって、なりたくてああなってるわけじゃないの。」
「まあ、パパは認知症初期からホームっぽいとこ入って、みんなに迷惑かけないようにするわ。」
そんな過程を経たけど。もうとっくに私の中にはいなくなっていたけど。
私に似て、少しわがままで自分勝手だったかもしれない。
そのせいで、ママにもパパにも嫌な思いをさせてしまっていたのかもしれないけど。
それでも、私はたくさん愛されていたんだ。
どうしてあの時もっといっしょにおしゃべりしなかったんだろう。
ちょっとでもおばあちゃんに幸せって思える時間をあげられたらよかったのに。
わたしは、わたしは。何もお返しができなかった。
「ねえ、何でおねーちゃん泣いてたの?」
「静かに。ひなは小さい頃から一緒にいたからね。」
弟は、あのスクランブルエッグの味を覚えていても、優しい記憶は覚えていなかったのだ。物心ついたころには、もう変わり果てたおばあちゃんになってしまっていた。
家族の前で泣けない私は、その後当時の彼氏にわんわん泣きながら、取り留めもなく感情のままに話つづけた。
「私、おばあちゃんにいっぱい色々してもらっていたの。
あのね、愛されてたのよ。なのに、わたしわたし…….だからどうか彼くんはおばあちゃんおじいちゃんを大切にね。」
「ひなちゃん、今いる人をおばあちゃんにできなかった分まで大切にすればいいよ。
きっとおばあちゃんも見ててくれるから。」
まだまだ涙なしには仏壇に手を合わせられないけど。
私も大切な人たちをたくさん愛していきたい。
そして、おばあちゃんのように幸せに生きられる瞬間をこれからも増やしていく。胸を張って、私は幸せですって言えるように。
だから、見ててね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
