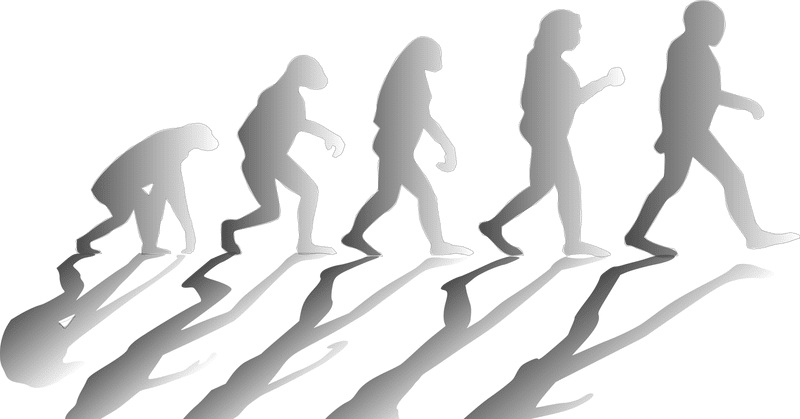
自然選択説の反証可能性
「利他学」(小田亮、新潮新書、2011年)P25-より
「利他学」の中では、養老孟司の『バカの壁』(新潮新書)の自然選択(自然淘汰)についての記述に誤りがあると指摘している。養老によれば、「進化論を例に取れば、『自然選択説』の危ういところも、反証ができないところです。『生き残った者が適者だ』と言っても、反証のしようがない」のだそうだ。この記述の背景には、反証主義という考え方がある。反証主義とは、ある理論や仮説が科学的であるかどうかは、それに反証可能性があるかどうかによるという考え方だ。また、厳しい反証テストを耐え抜いた仮説ほど信頼性が高いとみなされる。
反証可能性とは、その仮説が何らかの客観的なデータによって反証されうることを意味している。注意しなければならないのは、実際に反証されたかどうか、ということではなく、あるまでもその仮説が反証可能な形になっているかどうかという点だ。例えば、「すべてのカラスは黒い」という仮説がったとする。これは反証可能な仮説だ。なぜなら、一羽でも白いカラスが見つかればこの仮説は反証されてしまうからである。一方、「白いカラスがいる」という仮説は反証できない。白いカラスがいない、ということを証明することはまず不可能だからだ。
ちなみに、現在の生物はすべて神のような超自然的存在が創造した、という創造説やインテリジェント・デザイン説というものがある。これらは科学的な仮説ではない。なぜなら、神によって創造されていない、ということを証明するのが不可能だからである。
では、自然選択説には反証可能性があるのだろうか。別の言い方をすると、どのような事実が見つかれば、自然選択説は反証されるのだろうか。この問いに対する最も多い(誤った)答えは、環境が変動しているにも関らず進化しない種が発見されればいい、というものらしい。これは反証ではない。環境の変動が次世代に残る遺伝子の頻度に影響を与えれば自然選択は起こるが、影響しない場合には当然起こらないだろう。これは進化が必ずしも自然選択によるものではない、ということを言っているだけであり、自然選択説そのものを反証しているわけではない。
正しい答えの一つは、言語学者スティーブン・ピンカーが『言語を生み出す本能』(NHKブックス)の中に書いている。それは、自分の子どもを食べてしまうような種が見つかればいい、というものだ。自然選択は起こったり起こらなかったりするし、その強さもまちまちである。しかし、自然選択が起これば必ず適応が生じる。わざわざ自分の適応度を下げてしまうような行動は見られないはずだ。もし、積極的に自分の適応度を下げるような種が見つかれば、自然選択説は間違いだった、ということになるだろう。今のところそんな種は見つかっていないので、自然選択説は正しいであろう説とされている。
自然選択によって、その時々の環境において最も効率よく遺伝子を複製できるような特徴が残っていくので、結果として生物の特徴は機能的なものになる。自然選択が働くと、あたかも誰かが設計したかのように非常に洗練されたものになっていくので、超自然的な存在が設計した、と考えてしまうのも仕方ないのかも知れない。
余談
ピンカーの「自分の子どもを食べてしまうような種」という記述に関しては、≒適応度を下げるような種が見つかれば反証となる、ということだが、自分の子どもを食べてしまう動物は存在する。
ヘルシンキ大学(フィンランド)の進化生物学者であるホープ・クルッグ氏は、ハゼの仲間を使って親が我が子を食べる理由を探っている。
それは、雄が卵の世話をするハゼを研究したものだ。父親が卵の世話をする習性があるものの、卵の1/3ほどを食べてしまう。研究チームは、ハゼが大きな卵を好んで食べること、大きな卵ほど孵化するのに時間が多くかかることから、子供を世話をする時間を短縮させ、次の交尾にそなえるためではないかと推測した。
このハゼのオスは何千もの卵の世話をしなければならない。しかも卵が孵化するまで1~2週間かかり、その間オスは他のメスと交尾することはできない。オスは育ちにくい卵を食べ、その短縮した時間で交尾をする。トータルでみると結果的に自分の子どもを増やせるのではないかと、研究チームは考えた。
クラッグ博士はこの研究により、動物で親と子の間に存在する潜在的な競合について分かるかもしれないと考えた。——人間から見れば、自分達の子どもの世話をするということは、愛ある行動だと思いがちだ。しかもそれに多くの時間をかけるものだと思っている——
――しかし、動物界においては人間の価値観とは相反するものが存在している。人間から見たらそれが暗黒面のように見えるかもしれない――クラッグ博士は、動物の親が子を食べるのには他にもいくつか理由があり、それらすべて必然性のあるものだと考えている(例:弱った子供を親が間引く、単なる空腹)。
この事を考えると「親が子供を食べる≒適応度が下がる」とは、必ずしも言えないように思える。「親が子を殆どすべて食べてしまう」のであれば、適応度は下がるだろう。
親子関係ではないが、チンパンジーが他の群れの子猿(と大人の猿)を食べる話も有名だろう。殺した小猿を食べるのが理解できないことはなく、無駄な殺生で終えるより、食料として体に取り込んでいくことになる。
もしサポートをいただけた暁には、私の生活が豊かになります。
