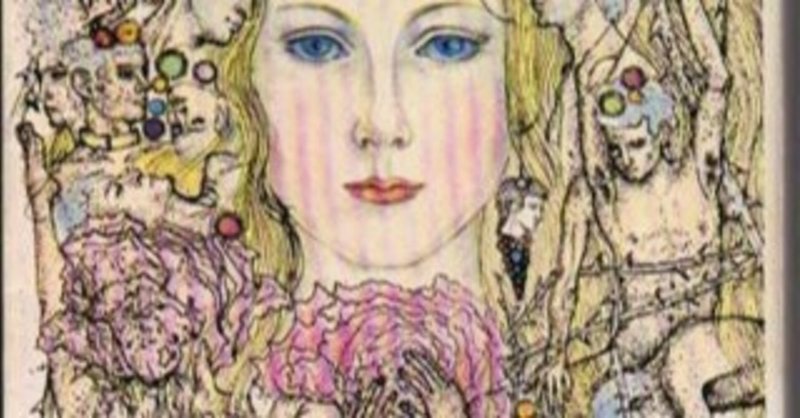
題:沼正三著 「家畜人ヤプー」を読んで
ずっと以前に読んだ本である。とてもよかったと記憶している。ただ、内容は殆ど忘れている。サドやマゾッホの作品を読んでいるために、もう一度読んで内容を確かめたかった。結論から述べると、やはり良い本である。ただ、良いのは前半で後半は少し緩慢である。それは日本人瀬部麟一郎がマゾ化し、婚約者たるドイツ人クララがサド化していく過程が描かれるというより、彼らが連れ込まれた40世紀のイース宇宙帝国について、オロチなど古事記の内容の言い換えや20世紀以降の世界の状況を参考にして描かれて、もはや、彼らのサド・マゾ化していく心理過程が希薄化しているためである。
著者によると本書は「地球編」の半ばであり、この続編が彼らの相互の心理や隷属・主人関係を克明に記述しているとのこと。でも、この続編はどうも沼正三ではない、もう別人が書いている。角川文庫発刊の本書のみが沼正三が書いているらしい。従って、本書以外の作品はもう読まないことにしている。著者は文学のみならず物理化学にも通じている相当の博識である。文章もゆったりと穏やかで上手である。サドの作品のように凄惨な場面はない。それは文章のゆったりとした穏やかさと、悪徳や殺伐な場面が単にただ説明的に書いているためであろう。本書は奇譚小説であり、冒険小説であり、推理小説であり、心理小説であり、幻想小説であり、風刺小説であり、人情小説であり、通俗小説である。
簡単に内容を紹介したい。日本人瀬部麟一郎と婚約者たるドイツ人クララは、40世紀のイース宇宙帝国からやって来て、20世紀に遭難した円盤艇に偶然遭遇する。そこに乗っていたイース宇宙帝国の高級貴族ポーリンと一緒に彼らはイース帝国に行くことになる。イース帝国は白人が上位であり、その白人も貴族と平民に分けられる。黒人は半奴隷であり、その下に先祖が日本人なる家畜人たるヤプーがいる。ヤプーは白人のための便器や椅子などに改造される人間家具である。こうして麟一郎はリンと称されて、もはや貴族なるクララの家畜人として仕えるようになっていくのである。
婚約者として麟一郎を愛していたクララも次第に家畜人ヤプーの女主人として振る舞うようになり、麟一郎もリンとなりクララを女主人として敬い崇拝の対象とする、家畜人として改造されていくのである。そのマゾ化していくともいえる過程の心理は簡単に記述されているが読み応えがある。なお、イース帝国は女上位の社会であり、男は今の社会とは逆になるのか女に奉仕する、貞操帯を嵌められることもある。この白人・女性優位の社会でクララはリンをもはや家畜とみなして、ポーリンの弟なるウィリアムズと結婚する。本書の大部分はこのヤプーの人間家具なるもへの改造やその機能・役割を詳細に描いていて、後半になるとより一層多くなり読むのに疲れてくる。これも、本書の冗長な原因の一つである。ただ、日本の未来の予測も記述されていて、ここでは述べないが、なかなか面白くて、鋭い所がある。
この小説をどう評価すれば良いのか、ドゥルーズのサド・マゾ論に従って、超自我と自我の関係からすると、白人には自我のみがある。超自我たるものはもはや自我の内に埋め尽くされていて、むしろ白人貴族同士は人情に満ちている、人間的に交流する暖かな、もしくは競い合い敵意を持つ人間関係を持っている。彼らは純粋理性を否定も肯定もしない、思いのままに行動するだけである。そして、法はイース帝国に絶対的に支配しているけれども、ポーリンのように高級貴族は時には原住民たるヤプーを持ち帰りクララを高級貴族とするなど逸脱が可能である。
だが、この逸脱がそれほど問題になるわけではない。快楽は自然に欲求のままに行われる、イド(もしくはエス)さえ自我の内の埋め込まれていると思われる。ただ、家畜人ヤプーに自我や超自我はなく、むしろ主人のオシッコを飲むと感嘆する無意識に本能的なイドにのみに支配されている。本書が問題にするのは、もはや物化したこの家畜人ではない。リンおよび日本人が物化していく過程そのものを類まれな風刺として捕らえていて、さまざまに物化していく人間と社会を考慮していくことを、暗に要求している。それはこの現実世界おける現実そのものである。そして物化すれば、まさにサドが大衆の肉体を消尽することと同じことと言えよう、ただ本書では日本人のみが消尽の対象となっているだけである。
ここまで記述すると言いたいことの大部分は記述されている。この後は、簡単に箇条書きにてまとめたい。
1) この奇妙な幻想社会は読み進むにつれて読者の心の内にへばりついて、通常の社会構造とも受け止めることができる。すると、それほど恐ろしいものではない。仮想の世界でありながら、もはやこの現実の世界をリアルに描いているとも受け止めることができるのである。
2) 階級社会では常に消尽する人間を必要とする。この消尽すべき人間は常に増殖して数を増やしておく必要がある。
3) この階級社会は安定的な制度を必要とする。ただ、制度を支える概念は不安定なものであり、絶えず変動するために、法の支配に基づくものであったとしても崩壊することがある。何らかの手立てを加えて、新たな概念によって絶えず法を修正し、社会構造を変革し再修正して、制度を安定的に維持する必要がある。
4) 技術の進歩によって絶えず人間は物化する可能性がある。例えば、AIやタグにナノポッドによってであるが、人間は自らの手によって人間たることを、即ち知・情・意をあっさりと放棄することがあり得る。
5) 人間の心は変わり得る。クララのように貴族なる白人が家畜人から神として奉られることも、リンのように家畜人として自我を喪失して神を称えるだけのイドを持つようになることも、技術によって変身は早いのであり、常日頃その覚悟と対策を持っている必要がある。ただ、対策としてどうすべきかは難問である。果たして持ち得るのだろうか。
6) 家畜人たるヤプーは日本人をマゾ化していながら、単に日本人だけではない、普遍的なマゾ化を行おとしている。マゾ化と言うより人間そのものの物化である。これはサドの消費すべき人間の確保と同じ思想である。マゾッホの観念や契約とは関係がない、マゾッホはまさに人間的な倫理において思考している。マゾッホにおいて人間は宙吊りされ鞭打たれながらも、生きて快楽を感じている。上下関係は契約通じてのみ実現される、仮の関係である。
7) もしやこの小説は人間主義、即ちヒューマニズムを描いているのではないのか。逆説的な批判すべきヒューマニズムである。アンナ・ハーレントが「全体主義の起源」で述べたように孤独な大衆こそが全体主義を生み出す。まさに物化して心を閉ざして崇拝する孤独な人間の姿を、対極的な人間主義の観点から描いているとも言える。もはや自我を持たずに熱狂的に崇拝する人間こそが一番幸福なためである。そして彼らこそが批判されなければならない。すると、クララを含めた貴族は、常にこの物化した人間に崇拝されこそすれ、本来的なヒューマニズムの回復の動きを常に監視し、問題を把握し考慮して必要とあれば処分する必要がある。
何項目かにわたって述べたが、まだ少し考えだけで書き落としている点もあるかもしれない。なお、前回の日記の有島武郎「或る女」で谷崎潤一郎と三島由紀夫の文章を掲載したが、彼らのどちらかが沼正三とも考えた。ただ、本書の文章は谷崎潤一郎に似て穏やかに静かに書いているけれど、やはりリズムがことなり、結局、どちらでも無いようである。作本書の解説に作者と思われる人物が指摘されている。
以上
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
