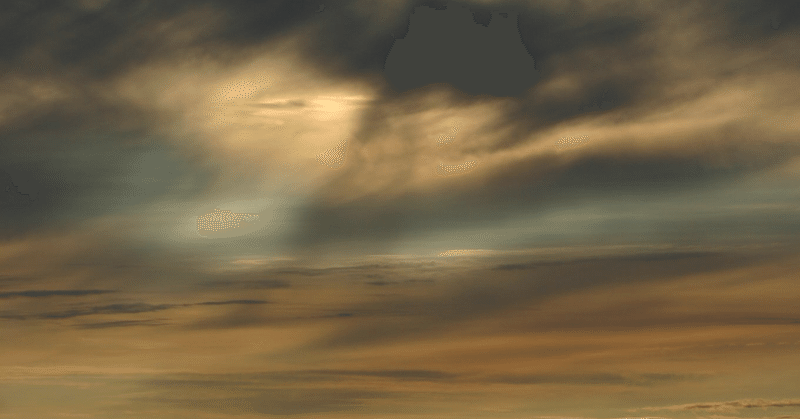
短編小説その17「笑う死刑台」
笑う死刑台
笑うのは死体ではない、死刑台である。この場所に引き連れられて、死刑囚は首根っこを押さえられて、身動きのできないまま跪いている。祈り捧げてはいない、もはや両手を後ろ手に縛られて、天を仰ぎみることさえできない。介添い人の腕力に首を突き出されて、跪くとも押さえつけているために何らの動きもできない。密やかに心の中で祈っている。どうしても祈り捧げざるを得ない。自らの安寧をかつ極楽往生を願うためである。こうした死刑囚の心の中を死刑台は読み解いている。最後の時になって少しも動くことができずに、ただ心の中でしかそっと祈ることしかできない者を嘲笑うのである。死刑囚は呟いているのかもしれない。その声が風に流されて死刑台に聞こえてくることがある。日差しに照らされた首に青い血管の筋が浮いて見えることもある。その流れる血流が透いて見えてくる。誰かが指令を発すると、跪いていた死刑囚は首筋を剥いて台座に寝かし付けられる。死刑囚のときめく鼓動が伝わってくるとも、もはやすべてが死刑台に任せられたからには、心の内を解き明かしたりしない。明かしたとして何の利益になるのであろう。ほんのわずかな楽しみにさえならないことを死刑台は知っている。もはや死刑囚は祈ろうとは思っていない、自らのことも家族のことも、当然こととして憎悪に満ちて殺さざるを得なかった者のことも思ってはいない。死刑囚のの心の内は空虚に近い、真空ポンプで吸い上げられたように心は空っぽである。死刑台はそのことを知っている、解き明かそうとしても無理なのである。もはや心が空っぽになっていて何が起ころうとも驚きはしない。勝手にせよということでもない、純粋に出来事を待ち構えているのでもない、やはり何ら何も思っていないのである。
こうした死刑囚を数え切れない位見ている死刑台はもはや自らの意志に従って死刑を執行する。重く硬く切れ味鋭い刃を垂直に落下させるのである。死刑執行人の指示には基づかないこの死刑執行は突然気ままに実行され、常に笑い声が響いている。嘲笑う死刑台の声であるのか、興味深く眺めている群衆から響いて来る悲しみや怒りを含んだかつ嘲りの笑い声であるのか、死刑台自身にも分からなくなる。まさか死刑執行人が歌を歌っているわけではあるまい、小鳥たちが並んで木々の上から合唱しているはずもない。讃美歌はとうに終わっている。そうした声の源を死刑台は勘繰って探したりはしない。何処からか聞こえていても聞こえていなくとも、どうでも良いことである。飛び散った血の流れが、噴き出た血潮の拡散が声の響きとなって発せられているのかもしれない。死後においてさえまだ未練がましいのではない。死刑囚は何事も心に思っていないのに、その切断された体の内から自然に声を発している。まるで時差を持って成り出す狂ったオルゴールのように、それも笑い声であって、自らや理不尽な仕打ちに抗議しているのではない。自らを慰めるためでもない。何処の誰が発しているか分からないからには、どうとも理解できる。きっと死刑囚ではない。この理解する手の内はおぼろげにあやふやであって、死刑台はそれに論理や感情の解釈も施さない。そもそも死んだ死刑囚が笑うはずなどないのであって、死刑囚の残された心や体が声を発して笑っていようとも、もう死刑囚とは無縁なはずである。いつも常に切断された死体は持ち去られる。邪魔であるからである。何処かに捨てなければならない。死刑執行人の温情が施されれば埋葬されることもある。ただどちらの方法によっても時が経過すれば腐敗して消え去るという同じ運命が待ち構えている。
死刑囚からあふれ出た体液で汚された死刑台は、日差しを浴びながら乾燥するのを待っている。台座の上や鈍重な刃先には幾層もの血が重なって塗られている。ドラキュラよりも圧倒的に多い数の人間の血を噴き出させて吸ったからには、勲章を与えられても良い見事な働きである。稀には死刑執行人の指示に従って清掃されることがある。死刑台は拭かれて汚れを落とすのである、諸々の濡れた布で台座の肌や重くて鋭い刃先などが清い水を流して磨き立てられるのである。この次の死刑の機会には磨かれた綺麗な体を見せつけることができる、多数の群衆に向けて小ざっぱりとした体を披露することができる。でも主役は死刑台ではない、死刑囚なのである。いや死刑囚でもない、死刑執行人や群衆自身や煌めく日の日差しや小鳥たちの囀りも含めたすべての出演者による総合的な舞台芸術が主役である。こうした芸術の生み出す感動は積み重ねられるけどそれ程厚くもないが薄くもない。ただどうしても死刑と定められる者たちは後を絶たずに現れ出てくる。この世界に感動を呼び込むために共演者を待たせないために、審判を下す法廷はこの死刑台へと人間を送り込んでくる。むしろ規則正しいと言った方が良いのかもしれない。罪科に関わらず死刑の判決を下しているのかもしれない。いずれにせよ総合芸術の演じられる周期はほぼ決まっている。感動はまだ忘れないうちに再び感動を味合わなければならない。忘れなければより効果的に、この世界の内にてアブサン以上に酔い痴れることができる。この世界は酔い痴れなければ生きていけない。常に新鮮なもしくは記憶を甦らせるより豊かな芸術的な感動が必要なのである。
もはや誰もが去り居なくなっても死刑台はいつもの場所にある。笑うことも呟くこともなくて所定の場所に居続けている。自らは動くことができない、この性質故に永久に吹き晒されていようとも居続けるすかない。どっしりと構えているように見えて決してそうではない。こうした死刑台の心は死に行く死刑囚の心以上に探るのは止めたい。むしろ何らの心も感情も持っていずに、ただいつもの場所に居て待っているだけである、どうしてその心を知ることができよう。時々少女がやってくる。犬を連れて散歩するのが日課と思われる。きまった道筋を決まった時刻に現れ来る規則正しさは律儀な性格の持ち主である。死刑台にも決まった時刻に犬を連れて少女はやって来る。寄り道をする決まった場所である。少女ではなくて犬の習性である。この台が見えだした途端に、犬が縛り付けた首縄を振り解かないばかりにすり寄って来て台座の上に前足を乗せて、鼻づらを台に擦り付ける。死刑台の匂い、脂切った匂い、死の匂いが好きなのである、犬は長い舌を出して舐めている。少女は犬の成せるままに放置している。飼い主にも飼い犬の習性は間々ならないものである。少女の顔は痩せて青白い、病人のようである。不健康な売春婦の病弱な子供時代の姿を見せつけられているようで、死刑台はこの者どもが不愉快である。さっさと行ってしまえば良いと思う。長く居続ければこの後の規則正しい散歩の時刻にも影響を与えるだろう。この寄り道の長い時間は織り込み済みなのだろうか。死刑台はそうした心配はしない。ただ舐められることなど嫌でさっさと去るが良いと思っているだけである。死刑台は青ざめた少女の顔に薄らと赤みが帯びてくるのを知っている。無関心を装いながら、犬の思うままにまかせながら、少女はこの場所の何かを、何を目的としているか知っていて深く関心を寄せている。
一度でも見たことがあるのだろうか。そのはずである。見たことが無ければこうして、この場所にて無関心を装いながら顔を赤らめ興奮することなどない。犬は飼い主の気持ちに代わってその募る思いを成し遂げている。台座が綺麗に清掃されていて微かな痕跡も残っていない時がある。すると台座に寄り添って嗅いで舐めて涎を滴らすとも、この行為は常には満たされない。羞恥心を起こした少女が急き立てることもある。満たされることなどなくても、犬は執着せずに飼い主の命令に従って離れる。その時少女は青白い面のような顔をそっと死刑台の方に向ける。赤みとは頬紅を塗っていると思われがちな、少女から湧き出た感情の渦である。見たことが無いのに見たと装ってこの場所で行われた出来事への切ない思いを急ぎ消去して、頬紅を塗る感情を消せば青白い顔になる。死刑台に少女の思いなど分かるはずはない。少女は犬を引いて去って行く、まるでこの場所にまだ残って居たいと思うのに逆に犬に連れ去られているとも見える。どちらが真実であるか死刑台には分かるはずもない。ただ素足である少女は小石を踏みながら振り返りつつ名残惜しそうに去っている。朝もやの光の内に少女は消えていくのである。確かに立ち寄った少女と犬とが居たのか定かでなくとも、一向に構いはしない。死刑台には何が起ころうとも本来的には無関係である。こうしてこの場所に居座っているだけである。自らが気ままに死刑執行しているように見えても、他者の意志に従って使用されるだけの器具なのかもしれない。どうしてこの世界の死者を生み出そうとするせわしい動きや少女や犬の思いを知ることができるであろうか、何も知りはしない。
死刑台は日がな一日沈黙している時が多い。壮大な見世物を催さなければ集まってくる人はいない。死人を作り出す華麗な見世物の周期は散歩とは異なった日延べされた長い周期である。少女と犬以外にもやってくる者が稀にいるが、彼らは柵の内側にまで入って来ない。死刑台も静かに笑い声をたてている時がある。それは喜劇的でも悲劇的でもない、自虐的でさえない。青い空から日がな日差しを浴びて、台座の肌が少しばかり反り返って発する音である。誰にも聞き取られない微かな声である。笑い声と言うのは正しくないかもしれない。笑い声として聞こえる確固たる証拠があるわけではない、でも死刑台が光を浴びて肌を乾燥させて音を発するとすれば笑い声であるという確信がある。誰でもが泣き声や叫び声ではなくて笑い声であると言うに違いない。決して斬首された者の悲劇的な声が体内に残されていて、それが逆に笑い声となって伝わってくるのでもない。笑い声と断定せずに、奇妙な声が発せられていると言うこともできる。青い空からの光の呟きや森から届けられる小鳥の囀りに、駆け巡る馬車や犬の鳴き声の混じったこの世界の発する声、誰をも笑うために響かせる声である、奇妙な声なる音である。効果的に笑うべきである。誰もが、死刑台も含めて常に笑わなければならない。死刑台の傍らに犬がやってきて寝ころ返っている、少女なる飼い主から逃げて来たのだろうか。少女の陰気くさい顔など見たくはないが、一緒に居なければ気に掛かるものである。もはや飼われずに放たれたのか。犬は台座の上に気持ちよさそうに横になっている。そのうちに少女が追い駆けてくる。そして死刑台の頑強な刃など気に掛けずに、頬を染めた赤ら顔をして初めて犬とともに台座の上に気持ちよさそうに横たわる。日差しに満ちた青空を少女が首筋を伸ばして見上げると、紅色の雲が流れるに違いないのである。
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
