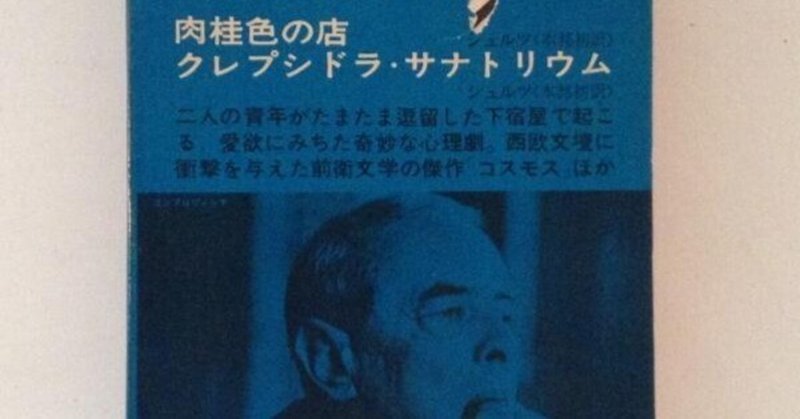
ヴィトルド・ゴンブロヴィッチ著 工藤幸雄訳「東欧の文学Ⅵから コスモス」および「ゴンブロヴィッチ短編集」を読んで
不思議な小説である。不思議というのはシーニュ(意味しているもの)が言語ではなくて首吊りという現象による。そして、シニフィアン(意味されているもの)が、この現象の内に表されていても、その現象の確かな意味、シニフィアンが何かは良く分からない。次から次へと吊るされ死んでいき、不気味さだけがある。固定的ではない、吊るされていく生き物の種類は移り変わっていくのである。ただ、最後に作者の意図が明確になる。読んでいる途中に、フランツ・カフカの「流刑地にて」という小説を思い出したが、拷問し処刑する機械の話である。機械と刑を執行する将校の残酷さは「コスモス」の首吊り以上である。でも、このカフカの短編小説では機械の存続を希望する将校自らが機械に処刑される点である。
ずっと前に読んでいるので、機械が将校に何らかの希望をもたらしていたのか忘れたが、何らかのシーニュは含んでいるはずである。ただ、これも言語ではなくて現象であり機械装置である。この機械に含まれているシーニュは分かるようで分からない。無論、勝手に意味づけはできるが、カフカの真意を推し量ることと同等である。断っておくが、カフカは短編なども含みほぼ全作品を読んでいる。彼の作品には、例えば「掟の門」など意味を推し図らせる作品が多い。一般的には寓意作品と呼ばれている。でも、その寓意が分からないのである。即ち、寓意、シーニュと呼んでも良い、これらはカフカの小作品から謎解きを行うのではなく、これらの作品群を書いたカフカの真意そのものを推し量ることが大切である。でもカフカに真意などあったのか。ただ、精力的に描いた作品群は表層を超えて意味は深くに隠れているのではない、夜通し文字が走り文章となっただけなのかもしれない。カフカに関する多くの作家論を読んでもこうした謎は解けない。さて、ゴンブロヴィッチは、後で詳しく述べるが、シーニュを含まない、現実と幻想を織り交ぜて描く作家であると知る。でも、矛盾しているが意味を求めている作家でもある。
「コスモス」を読み終わった後に、本書の初めに「異端のポーランド文学―非リアリズムの系譜」と題して、工藤幸雄が二十ページにわたり解説しているのを読み、なるほどと思った。ヴィトルド・ゴンブロヴィッチは初めて読む作家で、本書が「東欧の文学」と題しているため東欧の作家というだけを知っていたが、その他の前衛的な作家たち、特にブルーノ・シュルツの「肉桂色の店」など、そしてスタニスソフ・イグナツィ・ヴィトキュヴィッチ(ヴィトカツィというあだ名)の「非飽和」もしくは「満たさざるもの」などの作品とヴィトルド・ゴンブロヴィッチとを含めたその生涯、ナチスとの戦争の惨劇、悲劇的な最後に、サミュエル・ベケットに通じる不条理などについて書かれている。ゴンブロヴィッチは亡命の道をたどったらしい。彼の日記には意味の均衡に触れること、それが意味を所有することであり、外面的な意味を破壊することによって、狂気は、内面の意味、われわれ自体のなかへわれわれを入り込ませる、などと書いていたらしい。つまりゴンブロヴィッチは、異常な外界環境があっても生きる実在の確かさを、その意味を含めて確かめたたったとも言える。その意味とは実在の逃れることのできない欲望なのである。
「コスモス」なる作品の持つ意味を、ゴンブロヴィッチが日記を通じて簡単に紹介していたが、そのまま転載されていたので紹介したい。「コスモス」の主題について彼は次のように語っている。
「コスモス」の主題は、現実を構成するためのある意識の努力だ。その現実は、それが形成されるにつれて壊れて行く。固着したような現実を描くのは、それこそ人為的だし、恣意的なことだ。現実のイマージュは、押し寄せ、そして過ぎ去っていく黒い波だ。人間はその感覚の連想によって、形を生み出す動物だ、しかしそれらの形はいつも不完全なものだ。人間はたえず失敗する。人間はいつも確実ではない。ぼくの小説のなかでは、現実それ自体はない。中心のテーマは、現実を構成する主体の努力ということだ。
などの会話が記述されている。この主体という言葉は、個人に通じる。組織や構造ではなくて、個人こそが主役を演じることができるのである。
ここで「コスモス」のあらすじを示したい。ぼくは友人フスクと共に家を逃げ出し遠くへ出かける。木立の小枝からスズメが針金にぶらさがっている。安い部屋を借りる。女中カタシアの唇が一ミリ引き攣れつり上がっていて、ぼくはぬるぬるとした粘液に導かれるように感じる。カタシアの部屋に通じている、庭や星座が見える廊下に立っていることもある。ぼくはスズメと唇の間にいるのだろうと思う。カタシアは夫を持っている。家主は元銀行支店長ヴォイテス氏とクルカ夫人、それに娘レナがいる。庭を抜けて小道を通り空地に通じることができる。天井に矢のような模様が見えて、その先に向かうと塀の上にぶらさげられた木切れがある。ぼくはカタシアの唇とスズメと木切れとの間に共通するものの可能性を誰かが看過してくれると思っている。カタシアとレナの唇の二重性、スズメと木切れとの二重性もだ。ぼくはカタシアの部屋に忍び込んでカエルを隠すことも、部屋を覗き込むこともできる。
ぼくはレナの猫の首を絞めて殺す。猫は鉤にぶら下がっている。ぼくは猫を通じてレナと共通化することになる。ぼくは彼女の部屋のドアをノックすることができるし、実際にノックする。でも、応答はない。レナにも夫がいる。彼らを密かに覗き見することもできる。クルカ夫人は猫を殺された可哀そうなレナを抱き締める。レナは若い二人の新しい下宿人を非難しているようにみえる。皆で山の中に遠出する。木切れ-スズメ-猫-唇-手等々の体制に新鮮な空気を流し込むのだ。レナの女友達やその夫たちに、部屋の主の夫婦や司祭も同行している多人数である。でも、食事をすると首吊りした木切れ-スズメ-猫のイメージが纏わりついてくる。家主のヴォイテス氏の話では、二十七年前の真夜中に料理女と官能の世界に没入した山の岩にみんなを巡礼させたいとのことである。巡礼ベルグ、ベンベルグの話である。ベルグとはそっと、こっそりと、昼でも夜でも好きな時にベルグすることである。即ち、ベンベルグである。どうも首吊りや矢印はヴォイテス氏の仕業らしい。ぼくは森に巡礼する。山の森の岩と土の間を行こうと思うけれど、立ち往生してしまった。でも、ただ、立っている権利はなく行かなければならないと思う。山の中の在家に近づいた頃には暮れなずんでいる、即ちもはや夕暮である。在家ではカップルの蜜の味がして声がして、ぼくは指に塩をつけて食事をする。司祭と女が嘔吐している。外に出て木立の中を歩くと、レナの夫のルドビックが松の木からぶら下がっている。三つ目の首吊りである。この度の首吊りはレナの番であるとぼくは思っている。
さて、本書の最後に篠田一士が「わたしの作品論」として、「コスモス」の小説の形式と内容とカフカのそれと比較した短論文を掲載している。ポーランド文学については良く分からないが、「コスモス」の作品論、及びF・カフカの小説との比較については、私とほぼ同意見である。「コスモス」は文学的な姿勢を初めから持っているのではなくて、現実世界のさまざま日常性の中に生起する異常さを、いきなり直視するところから小説を書き出していると彼は述べている。ゴンブヴィッチは「コスモス」を探偵小説にたとえ、カオスを組織する試みだと説明している。探偵が解明する世界は彼自身の内面であり、そこに彼の文学的な宇宙が生成する。また、その宇宙は解体することによって生成し、そこでは謎解きが謎を生み出してくるらしい。ただ、私見では探偵小説ではないし、謎が謎を生み出すのでもない。結論は一つでなくとも、どれにも決めることができるのだ。また、決めなくとも一向に差し支えないだろう。私の本小説に関する見解は最後に述べる。
次にカフカについてである。カフカは、読者が言葉を喚起する官能の魅力を味わうこともなく、いきなり「物」として突き出される言葉の存在に畏怖させられる。カフカの言葉は何かを伝達するための機能を著しく弱め、言葉はそれ自体があるものとして突き出される。その問い掛けに答えることが、カフカの作品を読者が読みこなすことになる。そこにカフカの文学の多義性が生まれ、さまざまな解釈が可能になると、篠田一士は述べている。ブルーノ・シュルツとの比較において彼はカフカを述べている。なおシュルツの「肉桂色の店」は短編集で、その中の「肉桂色の店」なる短編を読む限り、シュルツに官能性は見られず、内容もありきたりである。あらすじは劇場で外套を忘れた父の代わりに、私は家に戻ることになる。その途中、私は夕暮れに並ぶ肉桂色の店と呼んでいた魅力ある店々の中の様子を思い浮かべて歩き通る。そして通っているデザイン学校の表門にたどり着き、学校の中を忍び眺め歩いて、さまざまに思い出すのである。サロンを抜け、外へ出ると辻馬車がいて乗ると、馬車は雪の坂道をゆっくりと登って行く。その夜の光景は一年にただ一度、歓喜と霊感を伴い訪れるような素敵な夜である。
シュルツのことはさておき、前にも述べたが、カフカ論はたくさん発刊されていて幾冊も読んだ。ここでは省略するが、ただ、オートポイエーシス論を論じた河本英夫のカフカ論があったはずで、寓意など通常の解釈とは異なっていて面白い。簡単に言うと、オートポイエーシス論とは閉鎖した細胞システムが透明な膜を通じて外界から影響を受ける、即ち生物は閉鎖しながら、太陽光など外界からの影響を受けて生きるシステム構造を成立させているという理論である。これを応用して、確か、カフカは銀行のすぐ傍に裁判所や女と出会う寝室など、接触し影響を与える近接したシステム構造を構築していると主張していたはずである。また、ドゥルーズのカフカ論は「マイナー文学」である。マイナー文学の定義については、ドゥルーズ・ガタリの記述したカフカ論を読んでいただきたい。ドゥルーズが書いたにしてはあまり面白みがなかったと記憶している。
さて、ヴィトルド・ゴンブロヴィッチの「コスモス」なる小説への私の感想であり見解である。カフカの全集を持っていてカフカの作品はほぼ読んでいるため、どうしてもカフカと比較してしまう。簡単に述べれば、ゴンブロヴィッチはカフカと異なって、隠されなおかつ表沙汰にされる欲望というより欲情が、出来事を作り出している。どうにも根底にある欲情が唸り響いて幻覚を生み出し、感覚に鋭敏さを加えて、かつ隠された行為を狂暴に作動させる現実があると言える。行為が幻覚であっても、現実に起こっていても一向に差し支えない。これらの境目などなくとも差し支えない。ただ、欲情が満ち溢れて現実にも厳格にも行動を強いている。従って首吊りなどもシーニュがあるのではない、即ち象徴としての意味を持っていない。溢れ返る欲情の波が、すべての意味を押し流しているのである。
歪んだ唇に白い指、矢印に三角形、スズメに小枝に人間の首吊りなどの記述は、コスモスなる宙に意味を吹き込んでいるのではなくて、単に欲情の糸を張り巡らせ、滴る唾液と強迫観念を文章中に流れ込ませていると言える。「コスモス」はシーニュを含んだカフカの小説とはまったく異なった方角にある作品である。色情が現実を幻覚化して善悪に無関係に感覚を鋭敏にさせ、ベルグではない対象を必要とする積極的な行為を強制する、こうした視点から描いた作品である。色情を土台にして現実と幻覚とを混濁させた作品としてはそれなりに優れている。再度述べるが、ゴンブロヴィッチの言うような謎はない、探偵はすぐに犯人を見出すことができる。ただ「コスモス」をすぐさまこのように断定することができるかは、彼の作品をそれほど読んでいないため無理があるかもしれない。
さて、ここからは彼の短編小説に関する記述である。「ヴィトルド・ゴンブロヴィッチ短編集 バカカイ」には十短編が掲載されている。「クライコフスキ弁護士の舞踏手」では、オペラ公演へ切符を買う行列に割り込みを行い、弁護士のライコフスキ氏に咎められたおれは、執拗にクライコフスキ氏を付け狙い、ついに公園でドクトル夫人との不倫現場を発見して大声で叫ぶと、あたりは騒然となる。日々病状は悪化しているが、まだまだ彼を付け狙うつもりである。「ステファン・チャルニエツキの手記」では、ぼくは仲の悪い夫婦の子である。白と黒のネズミの子である。恋人に「ぼくのものにしたい、きみを」と何度も言い続ける。戦争に出兵して戦場にて、世界に露出される裂かれた肉体とその部分を見る。ツバメをいたわるけど蛙を虐める。帰還して恋人に会い「女は謎なのかい」と問い、意味のない呪文を言うように要求する。従わない彼女に「ぼくも謎さ」と言って、蛙を彼女のブラウスの中に押し込める。女は蛙を掴み出せないまま地面をのたうち発狂する。
この二作品だけを読んだが、訳者が同じのせいか文章の威勢の良さは同じである。また、色情と執拗さに謎を含めて、この現実を描いているのは「コスモス」と同じである。ただ、短編のせいかは歯切れが良い、質の高い文章と筋書きの作品である。西成彦の巻末の解説では、ゴンブロヴィッチが構造主義者は文化の中に構造を求めているが、実在の中にこそ彼は構造を求める。人間と人間の間の領域に出現した奇怪な恐るべき形態が、それまで大切にしてきたものを破壊したためである。無論ファッシズム、ヒトラー主義が彼の物の見方に関係している。なるほど、ゴンブロヴィッチが個人を取り扱って、個人が個人との具体的なかつ幻想的な関係性を描くのはこのためなのである。ネズミも蛙もツバメもシーニュではない。彼は彼自身の内側から彼と現実とを把握して文章化する、この文章がこの世界を構築させるのである。幻想であっても現実であっても、歪曲して色を染めても、濃い匂いを発散させる世界そのものを表現し、広大なコスモスとなって広がって行く作品をゴンブロヴィッチは描くことができるのである。
以上
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
