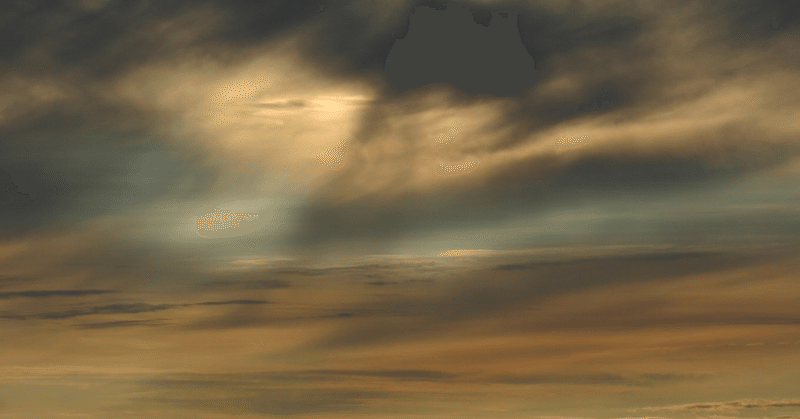
短編小説その20「自転車を押す男」
自転車を押す男
自転車を押している男がいる。自転車がボロくて乗れないのか、坂道が急勾配であるためか。日差しを浴びながら男は額から汗を滴らせている。この夏は暑い。いつもの夏より強く光を注いでいる。太陽が支離滅裂に踊り狂っているためか。爆発する予兆のためなのか。そんなこと男に分かるはずはない。ただ傾斜のきつい坂道をゆっくりと自転車を押しながら登っている。登るからには行先がある。目的も皮算用もある。それは明らかではない。現実はこの動画を見せているだけである。言い換えれば誰もの解釈を拒絶して作動する現実の露出だけを行っている。つまり動きだけである。勝手に言えばどのようにも解釈しても良いということだ。逆に男に使命を与えても良い。使命を与えれば男に目的と皮算用も与えなければならない。誰が与え得るのか。誰でも良いが登場人物を増やして彼らの会話の内に明示しても良い。と言ってどのように可能性が隠されていても、誰もが男の本心を暴くことはできるない。そもそも、ただ自転車の修理に急いでいるだけなのかもしれない。こう言い切れば確かに目的は定めることができる。でも本当なのなのだろうか。本当に男は何をしようとしているのか。そう考える以前に、そもそも坂道を登っていることも暑い日差しを浴びていることも、すべてが確かな現実であると言えるのだろうか。すべての描写が正しいと誰が断言できるのだろうか。頻りに砂埃が舞っている。嘘とも言える、男は砂や土埃が舞い上がる乾燥した道を登っているわけではない。砂利が少し転がっている田舎道とも言える長い坂道を登っているのである。
誰が決めたわけではないけれど田舎道には必ず老婆がいる。腰が曲がってよたよたと歩く老婆が必ず登場する。望んでいるわけではないが、望まなくとも登場させても構わない。勝手気ままに振る舞うわけでもない。男の目的を明らかにする現実のきめ細やかな表現を引き出してきて、老婆は期待に沿う役割を演じてくれるかもしれない。この役割こそが田舎町では重要なのである。華やかさなどない情念を喪失した枯草のようで、生きる屍でもある老婆が場を盛り立ててくれるかもしれない。でも、勇ましい発言をしてくれるわけでもないし、色気豊かに腰を振って踊り出すわけでもない。ぎこちない死人やロボットのように少しばかり徘徊するだけである。老婆自身目的を持っているわけではない。歩くことさえできれば目的などどうでも良くて、歩くことこそが目的とも言える。容貌の描写は要らない。誰もが関心を寄せていない。描写を省くのではなくて容貌を持っていない。決して顔が無いということではなくて、取るに足らないありきたりの老婆と言う概念の内に存在する典型的な老婆なる容貌である。この容貌に何を加えるべきなのか。何もありはしない。美しくも醜くも恐ろしくもない老婆は腰を曲げてゆっくりと歩いている。誰かを殺そうとする殺意を秘めていない。商品を盗もうともしていない。盗みを疑っていても着衣を脱がせて萎びた肌を見せろと言うわけにもいかない。老婆と言う言葉だけが正しくて、老婆であることが誇りであるわけでもない。存在しているそのことのみが正しい。昔、女であったものが今なお女として生き永らえていることだ。無論肉体ばかりではない、魂も持ち女として嫉妬も傲慢も内在させている。むしろ逆に謙虚と言った方が良いかもしれない。どう形容しようとも老婆は心も体も表現される言葉ではすべてを表すことができない、複雑な、でも単純な老婆なる存在としてそこを歩いている。
結び付けなければならない。自転車を押す男と老婆をこの現実にて空間と時間を同時に存在させたい。空間と時間内に隣接する男女がいる。ただ遠目にすれ違っているだけなのだろうか、もしくは既に老婆は自転車の荷台に乗っている。鎮座するように乗っているけれど男は気付いていない。荷台が無理なら、自転車はリヤカーを引いていて、その荷台に老婆は鎮座している。まるで仏様のように微動ともせず褐色の皺だらけの顔の中の目が閉じていて、のっぺりとしている。そもそも老婆とは仏像なのかもしれない。同等の陳述が誰からも開示されて、誰もが納得せずとも陳述は不可分にこの日の午後の夕焼け色に染まっている。文字が色を染めるように、この空を夕焼け色が染めることもあるであろう。いつの日かいつだって空は天から分離して夕焼け色でなくて茜色でもない、薄くも濃くもない何かの清浄な色に染まっていることがある。そして陳述はお寺の鐘が鳴り響くと聞こえなくなる。
自転車に乗っている男は後ろを振り返らない。台座に老婆が座っていることも知らずに坂道を登っている。重くなっていることに気付くべきだ、気付けば変わってしまっているこの現実を確かめることができる。確かめるとは黙視するばかりではない。言葉を発して老婆に尋ね問い掛けることができる。にこりと笑うであろうか、決して笑いなどしない。老婆は地蔵様である。何の言葉も意味をなさない。そうと思われるのは一つの現実が二つの様態を抱えているためである。三つめもきっとあるであろう。老婆とは若くて美しい娘である。娘はきっとにこやかに笑い謎めいて色白の肌が艶めいている。色白の肌やにこやかな笑いが謎めいているのではない、存在そのものが謎めいている。老婆と同等に存在が存在しているそのことが謎めいている。色っぽい流し目は夕焼け色に染まっても誰にも届きはしない。男は汗を滴らせながらゆっくりと自転車を押しているだけである。この坂道はどこにもどの時刻にもあるから、いつも自転車を押して伺い知れない目的地に向かっている。男は台座に娘が住まっていることを知らない。そもそもこの男女は同伴しているのだろうか。もしやハンドルを握る男の手と台座に座っている娘もしくは老婆の肉体とには目に見えないずれがある。一種の空間的なずれとも言えるし、むしろ深い断層としてある種の時空間上の裂け目があるとも言えるのではないだろうか。男が振り返っても老婆も娘も居ずにただ何も乗せていない空の台座が見えるだけである。きっと断層は深くて途方もなく長い時間と距離を隔てている。この暑い日に自転車はリヤカーを引いて姥捨て山に向かっている。あまりの悲しさに現実を認識することを恐れている。男は老婆も娘も捨てる積りはないのである。そもそも乗っていないので捨てることなど思い浮かびもしない。ただ自転車を押して坂道を登っている。いつの日からかずっと坂道はこの地に存在していて、いつも自転車を押している。
日が暮れてくるとカラスが鳴いている。蛙も蛇も鳴いている。畦道には泥鰌が飛び回っている。散水して暑熱を吹き払おうと舗装道路にはおばさんたちが総出である。商店街は誰もがいずに空っぽである。誰がいるのだろう、この時間には赤ん坊がおっぱいを吸いたくて泣いている。少女を虐めたくて少年が待ち伏せをしている。どの女でも女を襲いたくて男が凶器を握って待ち構えている。逃走している泥棒を捕まえたくて誰かが走り続けている。どこを、誰にでも目的はあるはずでそのように行動している。まさに行動とは目的を持ったものである。行動とは自己を断罪するものであっても良い。懺悔されれば司祭は行動の詳細を述べよと迫ってくるであろう。誰しもが知りたいのである、どれだけ感極まったのか活力を浪費してどれだけ命を削いだのか、苦痛と快楽がごちゃまぜになって肉体のどの部位を貫通して行ったのか。電撃的とも言える雷光であったのか、それともふにゃけた豆腐を食べたようなものなのか。決まっているではないか、告発室は密に閉じた部屋で、再び罪を犯すことができる。この罪はもはや神が行うために正当な権利である。女は涙声になっても、懺悔によって罪が消えたとは思っていないし、また新たに罪を重ねたとも思っていない。成り行きでもないし確信犯でもない。女は時間の隙間を埋めただけである。体内に流れ去る自らの時の隙間を差し出しただけである。どのようになってもよいと諦めたわけでもない。時間が経過して私があの部屋に居て司祭さまがあの部屋から出て行かなかっただけである。必然ではなくて偶然だったのである。
ただ自転車を押す男は必然として行動している。必ず成し遂げなければならない。何をと問い掛けられても答えるわけにはいかないが、答えなど持っていない。荷台に乗せるものなどありはせずに空っぽである。リヤカーも引いていない。乗るものなど誰もいないし積んでいるものもない。ただ必然と遠い昔から行動している。行動していると装っているのではない、常に行動しているそのことこそが真実である。別に他意などありはせずに強い意志があるわけでもない。暑い日差しに悩まされながら夕陽に染まりながら夜の闇に溶け込みながら、表情を変えることなく自転車のハンドルを握り押しながら坂道を登っている。結局これらの描写は坂道でも自転車でなくとも良い、筋書きは定められているわけでもない。誰かに所望されているわけでもない、男自らが望んでいるのでもない。けれど筋書きは脚本として廃棄されているわけでもない。あるがままに在って実は脚本がある。この脚本は司祭さまが作ったわけでもない。また女が望んで作らせたわけでもない。男は脚本に従って自転車を押しているのである。舞台上の一場面かもしれず脚本は白紙であっても男の交情と行動を記している。もしや脚本とは記録用紙であるのか、白紙に記されるのは結果であって必然的な予測ではなくとも、記録は必然的な予測としても使用できる。即ち男の自転車を押す行動は未来に向けて果敢に行動しているわけではなくて、記録した鉛筆の線に沿って動いているだけなのかもしれない。誰が何と言おうとも線とは地平線であるに違いない。でも男の行く手に地平線が見えることはない。黙々と自転車を押しているだけである。暑い日差しを浴びて額から汗を滴らせながら坂道を登っている。自転車の荷台はいつも空っぽである。老婆も娘も乗ることがない。懺悔する女がいるわけでもない。男は俯いているのでもしっかりと前を見ているのでもない。夕陽がこの地を照らす夕焼け色の線に沿って、少しずつ坂道を登り動いているのである。
詩や小説に哲学の好きな者です。表現主義、超現実主義など。哲学的には、生の哲学、脱ポスト構造主義など。記紀歌謡や夏目漱石などに、詩人では白石かずこや吉岡実など。フランツ・カフカやサミュエル・ベケットやアンドレ・ブルドンに、哲学者はアンリ・ベルグソンやジル・ドゥルーズなどに傾斜。
