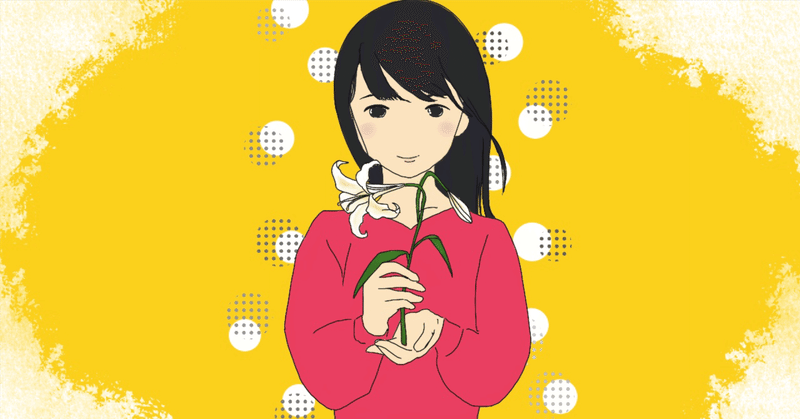
[短編小説]先生と転機 (百合です。)
自由に自分の思いを言葉にしたい。知らぬ間に整備された言葉の制御装置。口から出てこない言葉が煩わしく感じた。カタッと靴を鳴らし黒い漆塗りの正履がきらりと反射した。
「おはよう、今日数学の提出日だよ。」
朝からいきなり長い髪を垂らした佐々木が抱きついて、私が嫌な顔をしても気づいていないみたいだ。席に座る、佐々木以外は席をたたづにまだ黙々と自分の机と向き合っていた。みんな揃って今日提出のはずの数学の問題集を開いていた。ほらよっと佐々木に近づきノートを渡す。佐々木は驚いたように目を見開いた。
「どうしたの、田中が課題を期限内に終わらせてるなんて珍しい。雪でも降るんじゃない。」
冗談には思ない佐々木の驚いた顔に私は少しはにかんで相槌を打った。
「鈴木先生も絶対よろぶって、でも田中以外にとって普通のことなんだけどね。」
「せっかく寝ずにやってきたのに皮肉言わなくてもいいじゃん。」
私は学級委員長の真面目な佐々木とは正反対の不真面目っぷりによく先生達に怒られている。しかし今回の数学の課題は真面目に終わらせた。それには深い訳があるんだが。
五分前のチャイムとともに私たちは席についた。
放課後になりみんなあくびをしながら帰路に着く、今日はみんな寝不足だったらしく一限から先生達に怒鳴られる人が見られた。私もカバンに荷物を詰め校舎を後にする。私はいつもの左手の道を右手へと曲がっていった。
「お邪魔します。」
いつもと違う赤色の鈴がついた鍵を使いドアを開けて中へと進む、ふわっとかおるラベンダーの香りが落ち着かない。柔らかめのソファに腰を下ろして周りを見渡す。時計がカチカチと時を刻む、まだ2時間近くある。私はソファに横になった。
「起きて・・」
光がまぶたから差し込む。
「すいません、待ってたら寝てました。」
私は髪を急いで整えて反射的にソファに正座になった。
「あ、ごめんね今日呼んじゃってしかも待たせて、紅茶どうぞ、」
鈴木先生が紅茶を差し出す。学校と違ってラフなTシャツ、私が寝ていた間に着替えたらしい。
「今日偉いじゃん、ちゃんと数学提出できて私驚いちゃった。」
数学の教科担任そしてクラスの担任である鈴木ゆき。真面目な性格で提出物には厳しい、しかし華奢な容姿と生徒思いなところで人気な教師である。
「私が呼び出すようなことをしてしまったんで。」
笑顔でそう答えると、鈴木は嬉しそうに紅茶を手にし私を見つめた。一気に和んだ雰囲気から真面目な雰囲気と変わったのを感じる。
「家に帰れないのって本当、」
私は紅茶に映る涙に溢れた自分を見つめた。
「本当です。どこにも居場所がなくて、、」
言葉に詰まる。口を開くと嗚咽が止まらなくなりそうだった。とても学校じゃ話せなかった。私の父は若くして学校の校長又は理事長であった。そんな父の所有する空間では見つかる恐れがあった。もう誰も私を守ってくれるものはないんだ。
「父に虐待されて、助けてくれる母は今病気になってもうどうすることもできません。」
私の目は涙で溢れる。父に殴られる光景が脳裏に浮かぶ私はうづくまった。
「ごめんね、気づいてあげられなくて。」
鈴木が私の背中を優しくさすってくれた。その優しさすらも悲しくなるほど私の感情は過敏になっていた。
鈴木が私の状況に気づいたのは最近出会った。数学の授業中、傷つけられたリスカ痕。見つからないようにカーディガンを着ていたが、傷が開いたのか滲んだのを見つけられたのが始まりだ。
「これ、どうしたの」
私は鈴木に連れられ、近くの空き教室に行き傷を鈴木に見せた。
「ただのリスカです。安心してください。」
私は笑顔でそういうことしかできなかった。しかし腕にある青くなった打撲。ただのリスカだと言い訳は通じないだろう。
「すいません、鈴木先生。うちの娘が。今度病院に連れて行くんで。」
するといかついスーツをきた父がいきなりドアを開けて鈴木にいった。私と鈴木がいるのを気になり覗いていたのだろう。私はその時とてつもない恐怖に襲われた。次の授業のチャイムもなりその傷の話はお開きとなった。でも私は授業中今日の夜どんなことをされるか、、恐怖に襲われた。
あっという間に終礼となり私の恐恐る時が近づいていく。鈴木から教卓へと手を振られた。
「何かあったらいつでも相談していいからね。」
ただそれだけ言われただけだった。でもその言葉が私の心を温かくした。
家について、私の体は力が入ったのか震え出した。2階からは母の叫び声が聞こえる、幻覚が見えてるのだろうか。その叫び声が耳に響いて私の恐怖を増幅させた。もうどうすればいいんだろう、頭がぐるぐると考えで巡る。傷が見つかったことを父に怒られる。もう死んだほうがマシなのかもしれない。私は机からロープを取り出して自分の首を絞めた。
ボロボロになった自分の腕を見る。そして足。打撲だらけの体が記憶を蘇らせてくる。きっと誰も助けてくれないんだろう。児童相談所に相談しようと思ったこともある。でも病気の母を置いて私だけ父から逃げることはできなかった。夜中の2時、スマホのライトだけに照れさる。昼から何も食べてなく空腹感で眠ることもできなかった。リビングに行って食料を取ってきてもいいがきっと父がそこで酒片手に寝ているだろう。もう父も顔も見たくなかった。私は久しぶり勉強机に座り数学の課題を開く。涙が溢れる。でももう傷つきたくなかった。
先生、助けてください。父に虐待を受けてます。学校にも家にも居場所がありません。
この短い文章に思いを込めて。私は数学を解き進めた。
終礼後、私は鈴木に教卓に呼び出され、封筒を渡された。その中には、赤い鈴のついた鍵と付箋に書かれた住所だけだった。
私は全てを先生に話した。父のこと、母の病気のこと。誰にもいったことがなく、不安だったが先生は私のことを否定せず黙々と深刻な顔をして話を聞いてくれるだけだった。
「ごめんね、今まで気づいてあげられなくて。頑張ったね。」
泣きじゃくる私の背中を撫でて言った先生の温かい言葉に今までの耐えてきた頑張りはこの時のためにあったとさえ思えた。
しばらく無言の時間が続いた。鈴木は考えることに集中しているのか紅茶を持ったまま一点を見つめている。
「私の家の鍵、渡しとくからいつでも逃げていいよ。夜中でも。」
鈴木は決心したように言った。
「先生は大丈夫ですか。プライベートとか、法律的に。」
「あくまで、緊急処置だよ。だからゆっくり方法を見つけていこう。私も考えるから。だからもうチームだね。」
今までの重みが先生の言葉に取り払われた。
そっからの生活は地獄から抜け出したようだった。父に殴られそうなとき私は家出すると行って私は先生の家に向かった。案外徒歩でも行けて先生は突然のことだったのに温かく迎えてくれた。そのときも紅茶を淹れてくれて私もその紅茶を好きになった。
「結構さっきより落ち着いてきたね。さっきは青ざめてたよ。」
「先生のおかげです。家に来てしまって申し訳ないです。」
「いや、私基本一人だし、今彼氏だっていないから。休みの日とかはたまにいないかもしれないけど、そのときは多分夜までには帰ってくるよ。
でもいつも寂しいから田中さんと話すの好きだし嬉しいな。」
先生の好きっていう言葉に思わず嬉しくなってしまった。
それ以来私は先生の家に気楽に行けるようになった。そして月日が経つことに母の入院が決まったりと私の負担が少しづつだが軽くなっていった。
「先生、私児童相談所に相談することにしました。今までありがとうございました。」
母の入院が決まり、児童相談所に相談することを決心した。先生はそれを応援してくれた。
それを授与してくれて私は父とは離れて暮らすようになった。母方の祖父母の家出暮らしは今までの恐怖から解放されて勉学に集中できるようになり成績も鰻登りでいいことづくしだった。だが一つ悲しいのは鈴木と話す時間が減ってしまった。私はベットに寝転び先生の家の鍵を眺める。すると何故か涙が一滴落ちた。近頃やけに学校でも先生の姿を追っている自分がいる。私は先生とどんな関係になりたいんだ。先生の家にいたときのラベンダーの匂いが忘れられない。私はスマホを手に取り、先生の写真を眺めた。入学式の全体写真、それしか持っていない。私と先生の関係はただの教師と生徒だ。当たり前のことなのに、先生を求めている自分が気持ち悪くてしょうがなかった。
「先生、鍵」
私は先生に鍵を返すことを決心して、終礼後に先生に話しかけた。先生はきょとんとした顔をする。
「ありがとう、またいつでも相談に乗るからね、楽しかったよ。」
先生は私の頭を撫でた。普段はボディータッチをあまりしないのに、身長の高い鈴木の顔を見るため上を向く。すると水滴が落ちる。
「えっ」
涙だった。急いで私は先生に鍵の入った袋を渡した。一瞬のことだったのにその時触れた先生の手の温もりが忘れられない。
「田中どうして目赤いんだよ、泣いたりしたの」
佐々木が私の顔を覗き込む。今は一人にして欲しいのに、佐々木は気を遣えないやつだったなと落胆する。
「アレルギーで痒いんだよ。」
今は冬なのに、私の頭は今は先生のことでいっぱいみたいだった。佐々木の手を握る。全然温もりを感じない冷たい手。先生と佐々木のては何が違うのだろう。
「なんか、変わったね。昔はもっと冷めててお人形みたいだったのに、今はなんか人間だ。恋でもした。」
恋か、、恋ではないはず先生は女性だよ。これは尊敬かな。
「恋と尊敬って違い何」
「急になんだよ、やっぱり恋してんじゃない。恋は尊敬とは違ってずっとその人のことを考えてその人に会いたかったり、触れたいものかな。」
一気に顔に熱が回る。私は先生に恋してるんだ。正解を見つけた気がした。
その時から何度も先生のことを忘れようとした。でも忘れられず思いが強まるばかりだ。もうこんな自分じゃいけない。勉強さえ先生のことばかり考えて身が入らない。もうどうせ振られるんだ。私は先生に告白することを決心した。
「先生、好きなんです。」
その日の夜、2時間ぐらいスマホの電話帳とにらっめこしてようやく告白した。
「私も好き。」
思いがけない、返事。100%諦めた恋愛だったのに。私の恋は実ってしまった。
走って先生の家に向かう。どんなに息切れして死にそうなぐらい苦しくても私の欲求は止まらない。
「先生、好きです。」
改めて対面しているとすごく顔が熱くなって今どんな顔を見られてるのか想像するととても恥ずかしい。
「ごめんね。こんな先生で。」
本当にダメな先生だと思う、私の告白を受けるなんて。嬉しいのにこんなことを考えてしまった。
私たちの恋人としての初めての対面はすごくぎこちなかった。だって私は恋人を一回も作ったことのないし、初めてが担任なんて難易度高すぎる。
「田中さん、私たちの関係は恋人だけど、教師と生徒の関係でもあるのよ。だからこのこともちろん誰にも言ってはいけません。そして体の関係も高校を卒業してから。」
赤くなった顔を隠すためそっぽむく、先生が嬉しそうに私の頭を撫でた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
