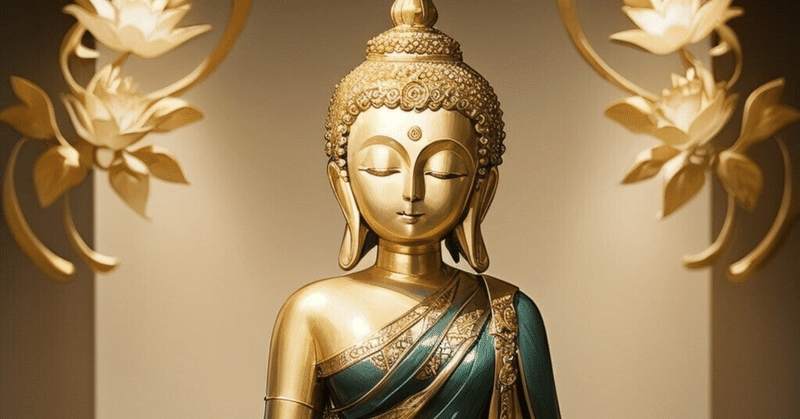
【短編小説】仏に非ず
無邪気な悪が最も恐ろしい。
おぞましい像とそれに魅入られた男。苦労人の店主を添えて。
以前書いた上記の話と同じ世界線の話ですが、読まなくても読めます。
重苦しい空気が店内を覆っている。いつもの喧騒は噓のように遠ざかり、一種の緊張感がぴんと糸を張っていた。皆、それに目をつけられないようにただただ息をひそめているのだ。
店主の口から嘆息が落ちた。ああ、これで本日何度目だろうか。吐く息は埃のように鬱屈を積もらせていく。
原因はわかっているが、どうにもならなかった。もう店主の手には負える代物ではないからだ。
元凶を睨みつけるも、返ってくるのは穏やかな微笑。それがいっそう得体の知れない不気味さを浮き彫りにするのをわかってやっているのだろうか。わかってやっているのだろう。これは昔からそういうモノだからだ。
「本当は貴方を出したくなかったんですけどねえ」
しかしこの店に再び姿を現したということは、彼を見つけてしまったのだろう。
パタパタパタ、と鳩が飛び立つ音がした。カーテン越しに映る小さな影はあっという間に灰色の雲の隙間に消えていく。
一度は逃がしてやることができた。毒牙に引っかかる前に、なんとか外へ返してやることができた。
だが二度目は無理だ。堅牢な鳥籠は獲物が入るのを今か今かと、涎を垂らしながら待ち望んでいる。
はあ、と再度息が落ちる。店主の無駄な足搔きを嘲笑うかのように、それはにこりと笑みを深めた。
何か大事なことを忘れている気がする。そんな考えが頭にこびりついて離れない。
「って、仕事もないのに、なに変なことに囚われているんだか」
首を振って馬鹿げた考えを振り落とそうとしたが、ショーウィンドウに映る男の顔はやつれていた。皺ひとつない白シャツも、腕に輝くロレックスも心なしかくすんでいる。
昔から同じ夢を見ていた。いつ始まったのか覚えていないが、たしか成人した後からだったように思う。
男は霧が立ちこめる森の中に突っ立っていた。目の前には泉があって、何者かが向こう岸に立っている。岸の輪郭すらおぼろげだというのに、男は対岸の向こうに誰かがいるのだと確信していた。その誰かは自分に訴えかける言葉を発していた。霧の向こうから呼ぶ声は、しかしその正体を掴む前に霧に溶けて消えてしまう。
ただそれだけの夢なのだが、不定期とはいえ、全く同じ内容のものを見るというのは何かしら意味があるのではないか、と深読みしてしまうのも無理はあるまい。
だが人に言ったところで解決するわけでもなく、せいぜい話の種になるのがいいところ。よって男はせいぜい場を持たせる雑談に使う程度で、それを放置してきた。
が、今はそうも言っていられない。一度みれば数年は訪れなかった夢がここ最近は連日現れるためだ。己を呼ばう声も日ごとに強くなってくる。
行かなければ。会いに行かなければ。聖母のように清らかな声が己を手招く。焦燥感がくすぶるも、手がかりは何一つない。なにせ夢だ。正確な内容など思い出せるはずもない。
しかしこの夢のせいで意識がもってかれ、ついには仕事すら手につかなくなる始末。見かねた部下に背中を押され、半ば追い出されるように休日をねじこまれたのだった。
「しかし休めと言われてもなあ……」
寝ても焦りが消えることはないし、むしろ高まる一方だ。かと言って闇雲に外に繰り出したところで目的の人物に会えるはずもなく。無計画に雑踏の中に飛びこんだのが、運の尽きだった。かれこれ三時間もあてのない人探しに費やしている。
一番嫌悪している時間の無為な消費を今現在行っているのがなんとも滑稽で、自嘲の笑みが口元に浮かぶ。と、そのときだった。ふいに袖を引かれてつんのめる。
「ったく何だよ」
顔をしかめて振り返れば、そこには誰もいなかった。代わりに目に飛びこんできたのは、煉瓦造りの建物。古ぼけたそれはブランド店や高層ビルが立ち並ぶ街並みには明らかに異質なものだった。だがそれに足を止める者はいない。かくいう自分も、完全に浮いているというのに今の今まで視界にすら入っていなかったのだ。
アンティーク調の扉の両脇には大きな出窓が並んでおり、いかにも洋画のホラー作品に出てきそうな肌がひび割れた人形やら、夜を閉じこめたかのように艶やかに輝く黒数珠やら、無造作に積まれた手のひらサイズの天使像や十字架やらが並んでいた。
癖の強い雑貨屋といったところだろうか。店主の趣味が前面に表れているラインナップは、刺さる人には刺さるのだろうが、己にはあいにく縁のないものだ。男は踵を返そうとした。
が、感情とは裏腹に男は軋む階段を上って扉の前に立っていた。年季の入った木製の扉は見定めるようにこちらを見下ろしている。扉にはめられたダイヤ型の藍が鈍く反射する。思わず喉が鳴った。
「……入れってことか?」
恐る恐る取っ手に手を伸ばした瞬間、ひとりでに戸が開き、真っ暗な口を開けた。生ぬるい風が背中を押す。足はひとりでにその闇の中に一歩を踏み出していた。
一筋の光も差さない暗闇は、男が踏み入れた途端、ぱっと光り輝いてその全貌を明らかにした。見れば天井には大きなシャンデリアがあり、炎が灯っている。なまめかしい蝋の肌に雫が一つ、たらりと垂れた。
周りにはシャンデリアを取り囲むように翼を広げた烏の剝製が一、二羽垂れ下がっていて、夕暮れ特有の物哀しいような、不気味なような、油断すると異世界に引きずりこまれてしまうような妖しさが漂っていた。
だが本来ここにあるべきものはこんな安物ではなく、もっと神秘的で美しいものであったはずだ。
そこまで考えて男は首をひねった。この店に訪れたのは初めてのはずだ。なぜ違和感を覚えるのだろう。
(やはり疲れているのか……)
男は肩を回し、改めて店内を見た。店内は窓に腰かけていた商品たちよりももっと珍妙な品々が並んでいた。
たとえば天井まである大きな棚の最上段にはしゃれこうべや鹿や牛、あるいは検討もつかないような奇妙な骨が並んでいたし、はたまたその下の段にはハーブらしき植物が詰めこまれた瓶がずらりと整列している。他の段には水晶玉やオウムガイのホルマリン漬け、星々の軌道を表す輪っかが幾重にもかけられた天球儀、片目がとれた人形、その他趣味が悪いとしか言いようのない物が陳列してあった。
壁には巨大なタペストリーや少数民族が呪いで使用しそうな木彫りの面が立てかけられている。タペストリーは黒を背景に、中央で大きな円が回っていた。円の内側にひし形が敷き詰められており、さらにその下には一回り小さな円がある。その内側はより複雑な幾何学模様で埋め尽くされていた。しかも驚くべきは、小指の先ほどの模様まで全てにおいて隣り合う色とは違う色の糸で編まれていることである。
赤、青、緑、黄色、橙、黄緑、水色、紫、と無数の色で彩られたその姿はまさに万華鏡。
円が回る。くるり、くるり、と回る。感覚がおぼろげになって、意識が均されていく。自分が足をつけているのは年月を刻んだ古いフローリングではなく、広大な宇宙ではないか。黒地に縫いつけられた無数の点が気まぐれに輝く。いつの間にかラメは星々に変わり、男は茫漠とした闇の中に放り出されていた。
地面がない、先も見えない、方向感覚すらわからない、安心の対極に位置するはずの宇宙空間は、しかし男の中に奇妙な平穏をもたらした。このあまりに広すぎる世界では万事全てが些末なことであり、将来に対する不安だとか、仕事の悩みだとか、そんなものを抱えていること自体馬鹿馬鹿しくなってくる。このまま心地よい闇に身を委ねてしまえばどれほど心地よいことか。男が瞼を下ろしたそのときだった。
しゃん、と錫杖を鳴らす音が聞こえた気がした。空耳だろうか。こんな場所で錫杖の音が聞こえるはずがない。だが金属の輪が叩きつけられる音は、男が無視していることを咎めるようにどんどん大きくなっていく。耳をふさげども収まるどころかより一層激しくなるばかり。
「ああ、もううるさい!」
怒鳴った瞬間、世界が割れた。気づけば男は元通り寂れた雑貨屋に立っていた。大声を出したことさえ久しぶりで、喉に鋭い痛みが走る。同時にこの年になって子どもじみた言動をしてしまったことに頬が熱くなった。
仕切り直すようにわざとらしく咳払いし、男は棚に目を向けた。
「それにしてもこんなものの買い手なんているのか?」
需要があるから成り立っているのだろうが、男の目にはガラクタを無駄におどろおどろしく飾りつけているようにしか見えなかった。
前はこのような雰囲気ではなかったはずだ。グロテスクな物を無秩序に並べたてるのではなく、正体が掴めないものながら魅せられる美しさがあった。と、また妙な感想が浮かんで首をかしげる。やはり疲れているのだろうか。
ここに長居する必要もない。さっさと出てしまおう足を踏み出しそうとしたそのとき、視界の端に何かが動いた気がして思わず動きを止める。
植物やらカラフルな砂やら貝殻やら種類ごとに並ぶ瓶の林に隠されるようにしてそれはあった。すらりと伸びる白い足、薄緑色のスカート、首筋に垂れるひと房の金。
「……妖精か?」
小瓶の中で膝を抱えているのは小さな妖精だった。顔を膝に押しつけているせいで面立ちを知ることはできない。しかし力なく垂れる背中の羽が、その心情を物語っていた。
おいおい、悪趣味にもほどがあるぞ。いくら人形だとしても、わざわざ悲壮感溢れるポーズをとらせなくてもよかったじゃないか。
一度認めてしまうと、囚われの身が哀れでならなくなった。せめて日の当たるところに出してやろうと、瓶をかきわけようとしたそのときだった。
しゃん、と再び金属の輪を叩きつけるような音が響いた。非難の音は男が手を伸ばそうとするたびに激しく打ち鳴らされる。
「ああ、もうだからなんだよ!」
衝動に任せて振り返ったのはごく自然なことだった。が、それこそが相手の思惑だったのである。
目と目が合う。瞬間、電撃が走ったように男は動きを止めた。
二の句が継げぬまま吸い寄せられるようにそれに近づく。手を伸ばしてそれに触れる一連の動きを、男の意識はどこか薄い膜を一枚隔てたところで見ていた。
それは両手で簡単に抱え上げられる程度の小ぶりの像であった。胡坐をかく木彫りの像だ。すらりとしなやかに伸びる背、木の硬さを感じさせぬ全身を包みこむ布は中性的な印象を与える。元は色がついていたのか、ところどころ当時の色合いが垣間見えた。
だが何よりも特筆すべきはその表情だ。慈愛とも可憐ともとれる微笑みは悟りを開いた者特有の超然とした風格と穢れを知らぬ少女のようなあどけなさを両立させていた。
ずっと自分を呼んでいたのはこれだったのだ。男は本能で理解した。
「物音がするから何事かと思えば。やはりたどり着いてしまったのですね、お客様」
振り返ると初老の男がこちらを見つめていた。相変わらず見た目が変わらない。あなたは年をとらないのですね、と軽口を叩きそうになり、慌てて口をつぐむ。
「……あの、変なことをお聞きするようですが、前はシャンデリアではなく何か別のものが飾られていませんでしたか?」
「ああ、前は月が浮かんでいたでしょう。今日は新月なので出てこないのですよ。ですから代用品を出しているのです」
一笑に付される覚悟で尋ねた一言はあっさりと肯定された。
「では私は前にもここに来たことがあるのですか」
「ええ、お客様は覚えていないでしょうが。……まあそのほうが幸せでしたしね」
「はあ?」
男の眉が吊り上がった。
いったい何を言っているんだ、この店主は。覚えていないほうがよかったのなどと。そこである考えに思い至った。
「まさかこれを紹介したくなくて」
腕の中のものを庇うように店主を睨みつけると、彼はなぜか悲しそうにため息をついた。
「ええ、そうです」
「なんてことをしてくれんだ!」
目の前が真っ赤に染まった。これを自分と引き合わせないために避けていたのか。なんて悪党だ。男は掴みかかった。理性など残っていなかった。激しい怒りだけが男を突き動かしていた。極悪人を糾弾する検察官のごとき義憤さえあった。
「話は最後までお聞きください」
店主は男の反論をぴしゃりと遮った。その目はどこまでも静かで冷たい。
「まあ無意味とは思いますが、その像の経緯を説明させていただきます。話を最後まで聞いてから購入を検討なさいませ」
腕を軽くはたかれて男は渋々店主を離した。店主は奥のカウンターまで案内すると億劫そうに腰を下ろした。
「まずはこの店に来るまでの経緯を説明いたしましょう。
これが見つかったのはある山の廃村にある一軒の家からでした。風雨にさらされ、多くのものが朽ちていたのに、それだけが酷い損傷も見受けられず残っていたのです」
「いいことじゃないか」
たしかに色こそ剝げているとはいえ、大きな傷は見当たらない。その微笑みが傷つけられることがなくて本当によかった。
「いえ、話は最後までお聞きください。
これを見つけた人物は、たまたま迷いこんでしまった地元民でしたが、そこにかつて村があったことすら知りませんでした。なにせ地図にも載っていなかったもので。彼はこのまま風雨にさらしておくのは可哀想だとこれを持ち帰りました。それが悲劇の始まりだったのです」
店主は小さく息をついた。
「彼は信心深い男で、床の間の一番よい位置にこれを安置し、毎日欠かさず手を合わせておりました。
彼がこれを家に飾るようになってからひと月後、彼の妻が急逝しました。その次の月には息子が、さらにその次には彼の弟。初めこそ不幸が続く彼を周囲は憐れみましたが、男の身内だけでなく、近所の者にまで犠牲者が及び始めると悠長なことも言ってられなくなりました。
いったい何が原因で厄災がふりまかれるようになったのか。周囲がこの像にたどり着くのはそう遅くはありませんでした。捨てるよう頼みこみましたが、男は生返事を返すばかりで真剣に取り合わない。ついに犠牲者が二桁に達したため、人々は男の家に押し入りました。
そこにいたのは像にすがりついて狂ったように祈りを捧げる男でした。周囲は引きはがそうとしましたが、男は万力のような力ですがりついているので中々はがせない。仕方なく指一本一本を力づくではがすことになりましたが、やはり酷く暴れましてね。爪が剝がれて、血がべっとりとついたそうです。男の血で染まったその姿はまさに法衣をまとっているかのようで、しかもその顔はいっとう嬉しそうに笑っていたと言います。
人々はこの像を焼いてしまおうと考えましたが、決行するその前日、忽然と姿を消しました。その後ふいに現れては持ち主の周囲に災厄を振りまき、持ち主自身も狂わせ、飽いたところで新たな犠牲者を探す旅に出る。それをもう何十年も続けているのです」
「……到底そんな風には見えないが」
像は今も穏やかな笑みを浮かべている。人どころか虫一匹すら殺したことがないような純粋無垢な笑みだ。
店主は力なく首を振った。
「それがこの像の恐ろしいことでございます。花占いをするように手足を引きちぎり、歌うように息の根を止めるのです。これにとって命を奪うのは悪ではありません。遊びであり、娯楽なのです。ただ無邪気に命を握り潰すのが楽しくて楽しくてならないのです。
その証拠に初めて発見されたときはわずかに口角を上げるだけだったのが、ごらんなさい。こんなに満足そうに笑みを浮かべている」
像はこの世の春もかくや、と言わんばかりに幸せな笑みを浮かべている。それがいっそう愛おしさをかきたて、男は滑らかな頬を撫でた。
「ちなみにこの像が発見された廃村は、どうも謎の疫病に侵されて全滅したようでございます。真偽のほどは定かではありませんが、これが関わっている可能性は拭いきれません」
店主は男を真っ直ぐ見つめた。
「私はお客様を害するいわくつきを置いておきたくはありません。しかしこれは捨てても徒労に終わるばかりか、この店の決まりごとに則ってお客様の手に委ねる以外選択肢を与えないのが小賢しいところでございます。いくら趣味に近い気軽な経営とはいえ、この店のルールを店主である私が破るわけにはいきません。これとお客様が出会ってしまった以上、私めはお客様が購入を断念してくれることを祈ることしかできないのでございます」
「大丈夫だ。像の呪いなんて迷信だろう。仏が人を呪うなんてあるまいて」
「これは仏なんてモノではありませんよ。恐ろしいファムファタルだ。こんなモノと一緒にされちゃあ、いくら大陸から来た異国の神だって可哀想です」
店主は吐き捨てた。が、男の耳には店主の言葉の半分も残ってはいなかった。
触れれば像はさらに笑みを深くする。その度に酩酊するような幸福感が胸を満たした。
「前は間一髪のところで私が気づいたので、これがお客様前に現れる前にお客様をお返しすることができましたが、出会ってしまった以上仕方ありません。お客様、どうなさいますか」
「値段は?」
店主は肩を落として男を見上げた。しかし男の心は一つも揺れ動かなかった。
「……百万円でございます」
「わかった。カード払いでいいか?」
さすがに躊躇する価格であったが、この像の笑みに絡めとられてしまえば、むしろ安い買い物だ。値段でひるませようたってそうはいかない。会社が急成長していて、懐に余裕があったのも背を押した。
「どうぞ」
ぼそぼそと呟き、店主は桐の箱に像をしまいこんだ。手に加わる重みが心地よい。
「どうか、約束してください。少しでも異変があればこの店のことを思いだすと。私だけでは力及ばずとも、そういうモノを相手取る人々に連絡をとることはできますので」
「ああ、わかったわかった」
男はぞんざいに手を振って踵を返した。ドアノブに手をかけたとき、突然しわがれた声が脳内に響いた。
『ここにもう足を踏み入れてはなりません。二度目はかばいきれない』
だがそれはすぐに頭を満たす満足感にかき消され、意識の奥底に沈んでしまう。男の胸にはただ夢見心地に近い充足感が残った。
「……またのお越しをお待ちしております。くれぐれも気をつけなさいませ」
扉を開ければ乾いた北風が肌を撫でた。男は振り返りもせず、軽やかに雑踏の中へ消えていった。
像は幸せそうににこにこと笑っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
