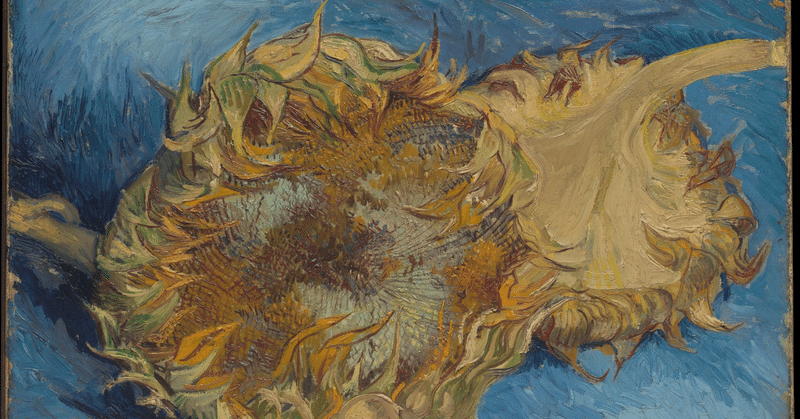
恋と学問 第25夜、浮舟の生き方。
今夜、私たちが読もうとする紫文要領の文章は、第3部「恋愛と物の哀れ」の第2章、「物の哀れは生と死に関わる」(岩波文庫版、123~126頁)に当たります。作品の核心と呼ぶべき箇所です。
たった3頁の分量ですから、ほとんど全文を注釈する形で進めたいと思います。これまで以上にていねいに読み解くことを、あらかじめ御了承ください。
問ひて云はく、然らば此の物語は、好色をいみじき事にして賞美する歟、色にまよふて身をうしなふ人をもよしとする歟、あだあだしきふるまひをもよしとする歟(123頁)
【現代語訳】
ある人が私に次のような質問をしました。「ならば源氏物語は好色を礼賛するのか?色欲に迷って身を滅ぼす人を良しとするのか?不道徳な振る舞いすら、良しとするのか?」と。
これが冒頭の言葉です。前章「なぜ恋が物語の中心なのか」の議論を踏まえた問題設定になっています。恋という、不条理な衝動に駆り立てられて発生する、意識では制御できない心の動きのために、人は時として不道徳を犯すことがあり得るということは、単なる事実の次元に位置する話であって、そこに良いも悪いもありません。事実を指摘することと、その価値を肯定することは別のことです。この質問者には、事実問題と価値問題を峻別する「哲学的センス」が欠けています。たしかに宣長は恋を肯定していますが、それは恋が不道徳を含むからではありません。恋の道が物の哀れを知ることに通じているからです。
質問者の無理解にもめげずに、宣長はこんな例え話をして答えます。
たとへば或人泥水をたくはふるを見て、或人問ふていふやう、真人は濁れる泥水をいみじき物に思ひて賞する歟といふに、かの人答へていふやう。泥水をたくはふる事は蓮をうゑて花を見む料也。泥水を賞するにはあらねど、蓮の花のいみじくいさぎよきを賞するによりて、泥水の濁れる事はすててかかはらずと答へける。此の定也。物の哀れの花をめづる人は、恋の水の澄み濁りにはかかはるべからぬ事也(123頁、承前)
【現代語訳】
あなたが言っていることは、例えて言うならば、泥水を貯めている人を見て、「あなたは泥水のことを素晴らしいものと思っているのですか?」と尋ねるようなものです。彼はこう答えるでしょう。「いえいえ。こうして泥水を貯めているのは、蓮を植えて花を見るための手段ですよ。まさか泥水を善いものと思っているわけではなくて、蓮の花の美しさ、清らかさを愛しているわけでして、蓮を育てるために必要な泥水が濁っていることは、問題にならないのです」と。恋と物の哀れの関係も、これと同じです。物の哀れという花を観賞する人にとって、恋という水の濁りは問題にならないのです
要するに、物の哀れが主で、恋は従だと言いたいのです。物の哀れを知らすという目的(主題)を果たすために、作者紫式部が必要とした手段(題材)が恋でした。この物語の見方を実際に、源氏物語の筋書に当てはめると、どうなるでしょうか?宣長は柏木の話を拾い上げて説明を試みています。
また、柏木衛門の督の好色によりてむなしくなれるも、そのしわざを賞するにはあらず。身をいたづらになすほどの物おもひの深き心のほどをあはれぶ也。又あだあだしきをよしとせぬ事は、巻々にその心見え、前にも弁じたる事也(123頁、承前)
【現代語訳】
柏木が好色によって死んだことについても、作者は彼の行為を礼賛しているのではありません。身を滅ぼすほどの物思いの深かった心のほどを、哀れとするのです。また、不誠実を肯定していないことは、源氏物語の各所の記述から明らかであること、これは前にも述べたとおりです
柏木の悲しい恋の顛末については、第16夜に詳しく述べておきました。光源氏の妻・女三宮を強引に我が物にした柏木を、その行為において肯定することは出来ません。しかし、彼の思いを肯定することは出来ますし、そうすべきです。
柏木は地位も名誉も捨てて、光源氏に冷遇されていた女三宮の心に向かいます。この悲しい女を愛するためなら、いかなる罰が待ち受けていようとも構わない。そう覚悟を決めた時、柏木は、損得と善悪からなる単色の世界線から身を引き剥がします。そこには人間の究極の自己決定、つまり自由があります。
一方、妻を奪われた立場の光源氏は、柏木の死を惜しんで涙を流します。これは、自らが受けた屈辱を離れて、柏木の思いの深さに感動しているのです。このように、物の哀れを知ることは、損得・善悪・自己から身を引き剥がす意志の力を意味します。
恋を肯定することを、不誠実・不道徳を肯定することと取り違えてしまう愚かな質問者に、宣長は答え続けます。
大方物の哀れをしればあだあだしきやうに思ふはひが事也。あだなるは返りて物のあはれしらぬが多き也。其の故は前にもいへるごとく、物のあはれを知り顔つくりて、ここもかしこも物の哀れしる事を知らさむとて、なびきやすにあだなるが多き也。是れは実に知る物にはあらず。うはべの情けといふものにて、実は物の哀れしらぬ也(123頁、承前)
【現代語訳】
だいたい、物の哀れを知る人は不誠実で浮気っぽいと思うのは誤りです。浮気っぽい人はむしろ、物の哀れを知らないことが多いのです。そのわけは前にも述べたように、物の哀れを知っているかのようなふりをして、この人にも、あの人にもと、自分が物の哀れを知ることを知らそうとして、人になびきやすい人に、浮気っぽい人が多いものですが、こういう人は本当は物の哀れを知る人ではありません。俗に言う「うわべの情け」というものに過ぎず、本当は物の哀れを知らないのです
私は物の哀れを知る人だと、各所にアピールするような人が、本当の物の哀れを知るわけがない。人になびきやすく浮気っぽいことが、物の哀れを知ることではない。「物の哀れを知る人」と「人になびきやすい人」は基本的に異なる。そうやって、ひとまず質問者を突き放すわけです。しかし、ここが宣長の話術の面白い所なのですが、とはいえ、「人になびきやすい人」がすべて「物の哀れを知らない人」とも限らない。と、方向を転換して、突然、宇治十帖のヒロイン浮舟の運命に託して、重たい言葉を述べます。
又さにはあらで、ここもかしこも物の哀れしりてなびくもあり。是れも事によるべけれども、まづはそれは一方の物の哀れしりても一方の哀れをしらぬになる也。されば浮舟の君は、それを思ひみだれて身をいたづらになさんとせし也。薫のかたの哀れをしれば、匂の宮の哀れをしらぬ也。匂の宮の哀れをしれば薫のあはれをしらぬ也。故に思ひわびたる也・・・是れいづかたの物の哀れをもすてぬといふ物也。・・・浮舟の君も匂の宮にあひ奉りしとて、あだなる人とはいふべからず。これも一身を失ふて二人の哀れを全く知るなり(124頁)
【現代語訳】
しかしながら、「人になびきやすい人」にも様々な種類があって、真実に物の哀れを知りながら、あちこちになびく人もいます。時と場合にもよりますけれど、こうなると多くの場合、一方の物の哀れを知ると、他方の物の哀れを知らないことになります。だから浮舟は、そのことに思い乱れて、自ら命を絶とうとしたのです。薫の哀れを知れば、匂の宮の哀れを知らないことになる。匂の宮の哀れを知れば、薫の哀れを知らないことになる。故に思いつめる。・・・これはつまり、どちらの物の哀れも捨てたくないという心なのです。薫という恋人がありながら、匂の宮に会ったからといって、そのことをもって浮舟を、不誠実な人間とは言えません。己の一身を失うことで、浮舟は二人の哀れを全く知るのです
いま引用した箇所には、とてつもない思想が籠められています。実のところ、私が紫文要領について文章を書きたいと最初に思ったきっかけは、この難解な文章を理解したかったからでした。・・・ついにここまで来てしまった。ため息が出る思いです。私は今もなお、ここで述べられている思想を、充分に理解できている自信がないからです。
浮舟は、光源氏が亡きあとの世界を描いた「宇治十帖」のヒロインで、宇治八宮の私生児として生まれ、母の再婚相手に伴われて東国に育ち、血縁を頼って京に移り、薫と匂の宮という対照的な性格の貴公子に愛され、悩み、自殺しようとしたが果たせず、発狂して、倒れていた所を横川僧都に拾われ、出家して、俗世との交渉を一切絶ってしまったという、何とも不幸な女です。
彼女のことを、宣長は(ということは紫式部も)、物の哀れを知る人の一人に数えています。彼女の思いを肯定しています。ものすごいことです。彼女の恋は、彼女を幸せにしませんでした。彼女は恋のために死を選び、生き残ってからも、絶えず襲ってくる恋の記憶から逃れるために、念仏にすがらなければならないほど、恋によって人生を狂わされました。この哀れな女の生涯を、宣長は「これでいいのだ」と肯定します。
いかなる価値基準に立てば、彼女の人生を肯定できるのでしょう?合理も道徳も歯が立たないことは分かりきっていますが、かと言って、フロイトのように恋を、無意識にひそむ性衝動の社会的な表現と捉えたところで、彼女の人生の謎を解き明かすことになりません。フロイトは、恋を可能にする「感情転移」の能力が、正しく対象を得て発揮された時点で、その心は健康であると判断を下します。しかし浮舟の場合、感情が転移できることが問題なのです。それが彼女を悩ませる。この恋する能力を自ら封じようとする。制御できるはずがないものを、無理に制御しようとする。
千年来、現代にいたるまで、源氏物語の主題は「浄土思想」にあるという、奇妙な定説がまかり通っています。浮舟を救った横川僧都のモデルが「往生要集」作者の源信であることも根拠になっているのですが、素直に読めば全く的はずれであることが分かります。
浮舟という人間を、作者の紫式部が肯定するのは、過去の恋を否定して極楽往生の祈りに専心したからではありません。彼女が誰よりも自己の心を知ろうとし、他人の心に感じようとした人間だからです。
個人的に、宇治十帖の名場面と思うのが、3箇所あります。
1.匂の宮との不貞行為が発覚して、薫から浮舟のもとへ、不実をなじる内容の手紙が送られてきた時
2.薫の告白によって浮舟の正体を知った横川僧都が書いた、復縁をすすめる旨の手紙を浮舟が受け取った時
3.薫の使者として、浮舟の義弟にあたる常陸守の小君が、小野の里に隠棲する浮舟を訪ねた時
その1。常識は不貞行為をされた側、薫の味方をするでしょう。薫が浮舟を宇治に隠して、たまにしか逢ってやらなかったことや、匂の宮が薫の姿形に扮して、騙し討ちのように浮舟を襲ったことなどを、情状酌量の余地ありと認めても、被害者と加害者の構図は揺るぎません。しかし、手紙を受け取った浮舟は毅然として言い放ちます。「宛先違いではないですか?」と。私は不誠実ではない。断固たる主張です。これは開き直りでしょうか?浮舟はただただ、恋に誠実であろうとしただけでした。
その2。横川僧都は坊主のくせに人間味あふれる人物として描かれています。モデルになった源信と紫式部は面識があったので、この描かれ方には彼女が実際に見て感じた印象が反映されているのでしょう。ともかく、横川僧都の助言を浮舟は聞き入れませんでした。薫と復縁するなんてあり得ない。どうしてこの坊主は分かったような口を利くのか?私の何を知っているのか?
その3。几帳越しに姉の気配を感じつつ、声を震わせて会わせてほしいと懇願する弟を、浮舟は拒絶します。「人違いではないでしょうか」というセリフはあまりにも無情に聞こえますが、言いながら浮舟は泣いているのです。己の恋を完結させるためには死ななければならないと悟った私だ。誇張でも何でもなく、もはや別人と思って欲しい。家族想いな私、恋に生きた私。そんな私は、とっくの昔に捨てて来た。・・・なのに何故、私は泣いているのだろう?心を捨てるのも心だ。心からは誰も逃れられない。
さて、宣長はこの浮舟について、単に物の哀れを知るというのでは飽きたらず、「全く知る」とまで言います。最大級の賛辞と言って良い。なぜでしょうか?以上に見たように、浮舟は恋によって得もしていませんし、幸せにもなっていません。たんに身を滅ぼしただけです。それも、決して褒められたものではない不貞行為によって。しかし、浮舟は誰よりも心について心を砕いた人だったことは確かです。薫の心と匂の宮の心。両者の心を真正直に受け止めようとした結果、浮舟の心は破裂してしまった。
ここで語られているのは浄土思想ではない。ましてや、無意識下にひそむ性衝動が暴発したという話でもない。あるいは、「恋は盲目」のことわざが示すような、判断力の低下が招いた事態でもない。浮舟はむしろ積極的に自ら判断して、己の進路を選んでいる。浄土教が教える専修念仏は、浮舟にとって、恋心を押さえつけるために利用された手段に過ぎません。性衝動が暴発した結果、自殺未遂を起こして発狂したのではなく、ふたりの愛をそのままに受け容れるためには、己をむなしくしなければならないという結論を、熟考の末に得たのです。それは浮舟の「悟り」でした。
・・・何と愚かな。たしかに。賢明であることの意味を、自己利益の最大化に見出だすのならば、浮舟の生き方はきわめて馬鹿げたものです。彼女は薫と匂の宮、どちらを選べば己の利益が最大化するかを、比較考量するだけで良かった。それが彼女にあり得た唯一の、幸せになる道でした。あえてそうせず、「選ばないという選択」をしたのは、彼女の実存に関わる問題だったからです。どちらかの愛を拒絶することに耐えられなかった。ふたりの愛を共に受け容れる方向にしか、進みたくなかった。たとえそのために身を滅ぼそうとも、問題にならなかった。
念のため付け加えますが、紫式部は浮舟を描くことで、このような愚かな恋をするように、読者に勧めているのではありません。濁った水は美しい蓮を育てる手段に過ぎないのです。そう、これは物の哀れを知らすために書かれた物語です。心ある読者は、浮舟の運命に共感できる自分を発見して驚きます。とはいえ、多くの読者は浮舟ほど愚かな人生を歩んでいないでしょう。もっと打算的で、道徳的に非の少ない人生を、それぞれ歩んでいるでしょう。にも関わらず、そんな己の境涯とは程遠い他人の運命にも、共感することが出来るのは、ひとえに人間の不思議というものです。読者は利害と道徳の外部にも人生があることを悟ります。この悟りなしに、いかなる文学経験も意味をなさないのです。
宣長が発見した「物の哀れを知ること/知らすこと」は、単なる源氏物語の主題ではないということです。それは同時に文学の存在意義でもあり、さらに言えば、人間の生の形式の新しい可能性なのでした。
今夜は長くなりました、このへんにしておきましょう。
それではまた。おやすみなさい。
【以下、蛇足】
今回は「物の哀れの思想」の核心に触れたので、どうしても難解な文章になってしまい、少なからず反省しております。
ただ、難解な文章を書きながら、「実人生に照らせば割りと簡単に分かることなのにな」とも考えていました。
恋が入り口になって、利害と道徳の外部にも人生があることを知り、人間の生の形式に新しい可能性が開かれる。・・・こんな小難しく書かなくても、例えば次のような短い言葉を味わうだけでも良かったのです。
「今思えば、結婚して幸せになってやるんだって気持ちが強すぎた。私は結婚に夢を見すぎて、現実に幻滅してしまったんだと思う」
「いや、それは違う。結婚はふたりで幸せになろうと思ってするもんじゃない。この人となら不幸になっても良いって、思えた時に結婚するんだよ」
これは誰の会話かと言うと、意外にも、小倉優子と田原総一郎です。数年前にTVを付けたら、たまたまふたりの対談番組をやっていて、変テコな組み合わせだなと面白がって観ていたら、この今も記憶に残る鮮やかな会話を聞いたのでした。
離婚して間もない小倉は、すでに愛妻を亡くして長い月日を過ごす田原に、「なぜ私の結婚は失敗したか」を説明します。小倉の認識では、自分は結婚によって得られる幸せを過大評価していた。現実的な幸せというものを知れば、次の結婚で失敗することもない。そう思うのだがどうだろうか?
田原は結論どころか前提から否定します。結婚で幸せになろうとすること自体が間違っている。人生を共にすることが、己の幸せよりも優先されるような人が現れた時に、次の結婚を選び取ったらどうか、と。
近くで宣長が聞いていたら、「田原の言うことの方が物の哀れを知っている」と、軍配をあげるでしょう。
さて、次回は紫文要領の順序に従って、「物語は訓戒を主題としない」を扱います。お楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
