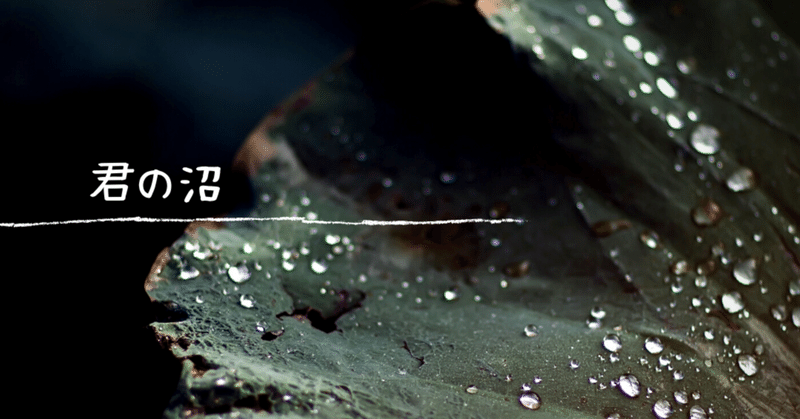
君の沼|短編小説
生まれてこの方、あんなに美しいものをみたのはあれが初めてだった。
月の明かりが反射して、きら、きら、と光る。
ねえ、知ってる?
本当に美しいものを見たとき、人は泣くんだ。
一 蓮の章
僕の住む村のすぐ後ろには大きな沼があって、僕らは農作物を育てて暮らしていた。沼の水は大地を伝って村の田畑を潤し豊かにする。僕らの村では、沼には水神様が住んでいると古くから言い伝えられていた。
「おい、なにボサッとしてんだ。日が暮れちまうぞ。」
はっと我に返ると、真後ろに善治がいた。片膝で僕の背中を小突く。
「ただでさえお前は出来が悪いんだから、人の二倍は働けよ。」
言い捨てると、汗を手ぬぐいで拭いながら善治はまた持ち場に戻っていく。
あいつ、それだけ言いにきたのか。
背中を摩り、僕は去っていく善治を睨んだ。
僕は生まれつき、右足がびっこをひいている。
自分の意思で、うまく力が入れられないのだ。
だから僕は、もう年も二十を過ぎるというのに未だに田畑を一人で耕すことが出来ない。きっとこの先、三十になっても四十になっても、ずっとだ。
ずんずんと自らの足を闊歩して去っていく善治の姿は、僕には輝いてみえた。
両親もよく言っている。
「善治がうちの息子だったら良かったのに。」
そりゃあ、なかなか子どもに恵まれず、それでやっと生まれた一人息子がこんな身体では両親も報われないだろう。
善治がうちの息子だったら良かったのに。
そんなの、僕だって毎日思っていた。
わははははは。
夜になると男達で宴会をするのは村の習慣だ。
畑仕事の終わりには、皆が我が家に集まって酒を呑む。我が家としては田畑の手入れを皆が手伝ってくれることへの僅かばかりの御礼だ。
僕はこれまた酒はからっきし駄目だ。身体が受け付ないのだから仕方ない。酒を配って回るのもそこそこにして、輪からこっそりと抜け出すのも習慣だ。
障子を開けて、軒先から外の空気を浴びる。
土と草の匂いが混じる、生暖かい夏の始まりの風。
僕は深く息を吸う。
気づくとすぐそばに善治が立っていた。
片手に酒の盃を持ち、酔っ払った目元はとろんとして、いつもは上がりっぱなしの太い眉毛が下がっていた。
「おい、明日の天気は?」
首を傾げて僕に聞く。
「晴れだよ。」
僕が答えると満足そうに盃に口をつけて、また宴の中に戻っていった。
月は曇りなく煌々と輝いている。
いい夜だ。
僕はそのまま、軒下の下駄に足をつっかける。
いい夜には、沼に行きたくなる。
「蓮。どこ行くんだよ。」
「こんな夜に危ないぞ。」
後ろから男達の声がする。
「ほっとけよ。いつものことなんだから。」
たしなめる善治の声が聞こえ、やがて小さくなった。
僕の足で小1時間。
夜の沼は月の光でぼうっと白く浮かび上がっていた。
風が背の高い草木を揺らす。
虫たちの鳴き声がしている。
僕は沼の側に着くと、尻を地面につく。
ゆっくりゆっくり、ずる、ずる。
水面がぎりぎり触れない程の距離。僕と沼とのお決まりの距離感だ。胡座をかいて、腰元の袋からビー玉を取り出す。
腕を伸ばして月にかざすと、ビー玉は滑らかに光った。
赤、黄色、青、紫。
ビー玉に塗られた色は、まるで水の中に絵の具を落としたようである。
僕は次々と袋からビー玉を取り出した。
ビー玉をくれたのは、祖父だった。
足が悪くて、他の子供達と同じように外を駆け回る遊びが出来なかった幼い僕は、いつも家の軒先で、外を見ていた。
外を見て、風を感じて、生き物の声を聞いて、天気の移り変わりを眺めていた。
そんな僕に、祖父が与えてくれたのがビー玉だった。
それから僕は、軒先でビー玉をぶつけ合ったり、ビー玉越しに外を見て過ごすようになった。
成長してからはビー玉遊びに興じることはなくなったが、それでもお守りのようにいつも腰袋に入れて、ふとした時に、こうやって眺めるのが好きだった。
沼は、風でゆったりと揺れていた。
音はなく、ただ暗闇の中ずうんと大きくそこにある。
このままここに落ちたら、どんなかな。
僕は目を閉じて想像してみる。
子どもの頃、皆は沼でよく泳いでいた。でも僕はそれが叶わなくて、やっぱり今のように畔で座ってビー玉を眺めていたのだった。
思い出してふふっと笑う。
僕はまるで成長していないらしい。
そろそろ帰ろう。
僕は立ち上がった。すると
ぽちゃん。
沼に何かが落ちる音がした。
「あ、ビー玉。」
僕の膝にでも乗っていたのだろう。
立ち上がった拍子に、片付け漏れたビー玉の一つが沼に落ちてしまったらしい。
揺れる沼の水面が僕を挑発するかのようにみつめている。
たかが一つ、されど一つ。
落ちたのは何色だったのだろう。
しかし僕に沼を泳いで拾うことは出来ないのだった。
とその時、沼の水面がぼうっと光った。
何事かと思い目を擦る。
水面の光はやがて大きく広がって、中から何かが浮かんできた。
驚くべきことに、それは人の形をしていた。それの頭に髪はなく、けれども顔や手足は人間そのものである。
服を着ておらず、皮膚は艶やかに湿っていて背には魚のような鱗がついている。鱗は一つ一つが赤や黄色、青色、紫色とさまざまな色を帯びていた。鱗に月の光が当たって落ちて、沼の水面は七色に輝いて見えた。
その生き物は、沼から上がると僕の元にやってきた。
手を差し出されて見ると、そこには僕の落としたビー玉が一つ。ビー玉は七色に光っていた。
「ありがとう。」
生き物は、僕の声を聞いて少し笑ったようにみえた。一瞬触れたその手は、驚くほど温かかった。
生き物が再び沼に沈むと、光は小さくなり、やがて辺りは暗闇に戻った。
僕は呆然としていた。
あの温かさが、あの七色の光が体中に残って消えない。
気づくと僕の目からは涙が溢れていた。
本当に美しいものを見たとき、人は泣くんだな。
僕はそんなことを思った。
涙はいつまでも止まらない。
僕はずっとずっとそこにいた。
手に握っているビー玉をみると、それは無色透明だった。
また、涙が溢れてしまった。
次の日の夜も、その翌日も、翌々日も、沼へ行くとまたその生き物は現れた。
初めこそ声が震えたものの、今では全く怖くない。二人並んで沼辺に座り、ビー玉遊びや虫や風の観察をするのが、僕には何よりの楽しみとなっていた。
その生き物に性別があるのかは判らなかったが仕草や笑い方は女性的であり、なんだか恋人でも出来たような気分だ。
今日は随分と蛙が激しく鳴いていた。風もいつも以上に生っぽい。
「雨でも降るかな。」
僕が言うと、彼女は驚いた顔をし、やがて嬉しそうに微笑んで空を指さした。
彼女は指で、くるくると空をかき回すような仕草をする。すると、だんだんと雲が厚くなり、やがて雨が降り出した。
「すごい。雨を降らせることが出来るんだ。」
僕は興奮して飛び跳ねて大いに転び、泥まみれで帰宅することとなった。
翌日と、翌々日は雨だった。
僕はこの足で雨の日には出かけられない。
仕方なしに、軒先に出て、ざあざあと降る雨の音を聞いていた。
彼女のことを、考えた。
「それはあれだ、河童だな。」
「いやいや、ただの妄想でしょう。」
田んぼの脇で善治達と握り飯を食べながら彼女のことを話すと、彼らは馬鹿にしたように笑った。
季節は梅雨で、雨が降ったらたちまち畑仕事は出来なくなる。だからこうして晴れている日は、皆総出で仕事だ。
「水神様かもしれないなぁ。だとしたら、蓮。粗相をするなよ。怒らせでもしたら俺たち食いっぱぐれちまう。」
善治が僕の肩を乱暴に叩いた。
「確かに、あれは神様というくらいに神々しかった。」
僕は相槌を打ちながら最初の夜を思い出そうと目を瞑る。
暖かい手や、艶めいた鱗、七色のビー玉。
ふうっと息を吐いて目を開けると、鳥たちが高く飛んでいた。
「おい、蓮。このあとの天気は?」
善治がいつもの調子で尋ねる。
「今日も晴れだよ。」
僕は七色の余韻の中で答えた。
早く彼女に、会いたい。
二 善治の章
今年の天候はどうもおかしい。
梅雨真っ只中だというのに、この1ヶ月、とんと雨が降らないのだ。
俺の住むこの村は、田畑と沼に囲まれていて、全員残らず農家だ。
雨が降らないと作物は育たない。
当然、商売あがったりの食いっぱぐれ。
それでも俺達に出来ることは何もない。
仲間の家に集まって、酒を飲み、酔っ払いながら雨乞いをするくらいだ。
けれども、皆本当は不安になっている。
このままでは、冬が越せない。
不安を忘れたくて、また酒を飲む。
わははははは。
宴もたけなわ。不安を忘れて完全にただの酔っ払いと化した男達を横目でみながら縁側で呑んでいると、ふと蓮が外に出ていくのが見えた。右足は相も変わらずびっこを引いて、それでも迷わず沼の方へ向かっていく。
蓮はこの家の一人息子だ。
昔から足が悪いくせに外が好きで、夜もよく出かけてはいたが、少し前に沼で水神ならぬ河童ならぬ不思議な生き物に出会ったらしい。それからというものの、夜毎沼に出かけていく。
まるで人目を忍んで恋人に会いに行く間男のようだ。
うとうとして、いつのまにか眠ってしまったようだ。
気づくと、そばに蓮が立っていた。
「善治、今日はもう帰りなよ。みんなも帰ったから。」
蓮の細い黒髪が月明かりの下で風に揺れている。
「明日こそ、雨降るか?」
伸びをしながら聞くと蓮は首を振った。
「明日も、晴れだよ。」
蓮の瞳は少し赤く潤んでいて、何故だか泣いた後のように見えて俺は驚く。
蓮も、不安なのかもしれない。
翌日も、翌々日も雨は降らなかった。
そして今日も。
流石に村中がまずいと思ったのか、今日は宴会が蓮の家で行われることはなかった。
男達は全員、俺の家に集まって頭を付け合わせて話し合っている。とはいえ、横にはしっかりと酒もある。なんだかんだ場所を変えただけで真面目になった気になっているようにも思えて滑稽だ。
「沼から引いている水だけでは、流石にもたないぞ。」
「作物が売れないとなると、どうする。若い者だけで出稼ぎにでも行くか。」
「そもそも、こんなことは初めてだ。一体どうして雨が降らないんだ。」
男達は口々に言い合った。
俺は部屋の隅に座って、ちびちびと酒を飲む。集まったからと言ってなんの解決策もないだろう。それでも何かしていないと不安な気持ちも良く分かっていた。
すると、それまで黙っていた村の長ー俺の爺ちゃんが口を開いた。
「こんな時、水神様がおったらのう。」
昔々、その昔。
人々は自然と共に暮らしていた。
人々は風を感じ鳥や虫達の声を聴いた。中には精霊の声までも聴くことが出来る者もいた。
村の沼には精霊の長である水神様が住んでいて、日照り続きの時は雨を降らせ、雨続きの時には晴れを呼んでくださった。
人々は収穫した作物や藁で編んだ道具なんかを水神様にお供えして、持ちつ持たれつ、そうして人と自然は共に生きてきたのだ。
爺ちゃんの言葉に、年老いた男達がうんうんと頷いた。
「人そのものをお供えするなどした時代もあった。"生贄"ってやつさ。」
そんな声も聞こえた。
「どうして人は自然と一緒に暮らさなくなったの。」
俺は尋ねる。
「文明がどんどん発達して、人の生き方は変わった。電気も水も整備され、我々は豊かになり、別次元の豊かさを求めるようになった。けれども自然は変わらない。ただ、じっとそこにある。生きる速さも求めるものも、人と自然は異なっていったのだよ。」
そう言って爺ちゃんは皺だらけの手を擦った。
わははははは。
結局最後は、話し合いの場はいつもの宴会と化していた。
皆、楽しげに酒を呑んでいる。
辛くても笑って酒が呑める内は大丈夫だ。
これは親父の受け売りだ。
酔いを醒ますために、外に出る。柱に凭れていると風に吹かれていると、酔いが回ったのか眠気が急に襲ってきた。そんなに呑んでいない筈なのに。
すると俺は夢をみた。
沼の水に足をつけ、蓮がぼうっと立っている。
「僕が生贄になるよ。」
蓮はこちらを振り返りながらそう言った。
俺は少し離れた畔から大声で叫ぶ。
「馬鹿なこと言うな、蓮。いいから早く、戻って来い。」
けれど蓮は首を振った。
「善治だってよく言っているじゃないか。僕は“出来損ない”だって。生贄になることで村の役に立てるなら、僕は本望だよ。」
俺は蓮の元へ行こうとするが、何故だか足はちっとも動かない。
「蓮!」
蓮は今まで見た中で一番の笑顔をしていた。穏やかに笑っている。
「善治、ありがとな。」
蓮はそのまま沼にゆっくりと沈んでいった。
夢はそこで終わった。
気づくと俺は廊下の柱に寄りかかって居眠りをしていただけだった。嫌な汗が背中を伝う。外をみると、蓮がちょうどが軒先から沼の方へと歩いていくのがみえた。
あいつ、また行くのか。
俺は蓮がいることにほっとしながらも呆れる。この一ヶ月、晴れている日は欠かさず沼に行っているのだ。全く何が楽しいんだか。
その時、ぱちんと頭の中で何かがはまるような音がした。
俺は慌てて立ち上がり、無我夢中で蓮の後を追った。
最後に雨が降ったのはいつだった?
蓮が沼の生き物に出会ったのは?
数日だけ、蓮が沼に行かなった事があった。雨が降っていて、足が悪い蓮は外に出ることが出来ないからだ。
あれから、雨は一度も降っていない。
「蓮!」
俺は沼に向かって叫んだ。
はっ、はっと走る自分の息遣いが夜の静けさに強く響いていた。
蓮は沼の畔に立っていた。
足首は水に浸り、手にはいつも腰にぶら下げているビー玉袋を握っている。
普段は煩いほどの蛙の声が、何故だか今日はしんと静まり返っていた。
「蓮。」
俺はゆっくりと蓮に近づいた。夢とは違う。今度は歩ける。今度こそ。
「俺はお前のことを出来損ないだなんて思っていない。」
走ったばかりで切れ切れになる息を継ぎ、俺は続ける。
「お前は足こそ悪いが、天気の変わり目を誰より先に気づけるじゃないか。」
俺は蓮の腕を強く握った。
「お前の両親がなんて言ったって、村の奴らがどう思っていたって、俺はお前を尊敬しているんだぞ。だからー。」
最後の言葉は息が詰まって声にならなかった。
それにしても、今日はなんと月の明るいことだろう。家の明かりも届かないこの場所で、蓮と俺は互いの顔をはっきりと見ることができた。
沼の水面も心なしか光って見える。
蓮は、ふっと目を細めた。青白い首が少しだけ傾く。
「知ってるよ。」
そしてゆっくりと俺の腕を解く。
「見てて。」
蓮が俺に背を向ける。腰元の袋からビー玉を一つ取り出すと、沼に放った。
沼はキャッチするかのように、飛沫を上げてビー玉を包むと、そのままビー玉は沼の底に沈んで見えなくなった。
蓮は次から次へ、ビー玉を投げる。
ぽちゃん、ぽちゃん。
水音と共に、少しずつ外の音が戻ってきた。
風が草木を揺らす音、蛙の鳴き声、虫達の羽の擦れる音。
いつの間にか、大合唱だ。
自然の音が、まるで波のように押し寄せてくるのだ。
これは一体どういうことだ。
ビー玉の力なのか、酔っぱらっているのか、それとも今まで俺が聞こうなかっただけなのか。
蓮は楽しそうに身体を小さく揺らしていた。
袋の中のビー玉が最後の一つになった頃、蓮は言った。
「帰ろっか。」
気づくと音はいつも通りで、蛙が煩く鳴いていた。
帰り道、俺は残った一つのビー玉を月に向かってかざしてみる。
蓮が昔からよくやっていた遊びだ。
無色透明のビー玉に月明かりが通過してそれは何とも言い難い色だった。
「変な色。」
そう言うと、蓮はふふっと笑った。
翌日は、雨だった。
お読み頂きありがとうございます⸜(๑’ᵕ’๑)⸝ これからも楽しい話を描いていけるようにトロトロもちもち頑張ります。 サポートして頂いたお金は、執筆時のカフェインに利用させて頂きます(˙꒳˙ᐢ )♡ し、しあわせ…!
