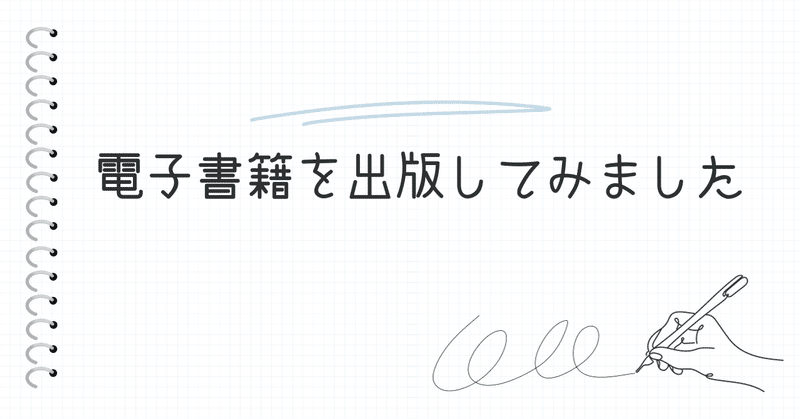
Amazon Kindleで電子書籍を出版してみました【半透明な世界の向こう側】
Amazon Kindleで、電子書籍を出版しました。
文学フリマ東京で出店したものと同作品です。価格も文学フリマと同じ200円。
ただし、もしKindle Unlimited(Amazonの電子書籍定額読み放題サービス)に加入している方は無料で読めちゃいます!
あらすじ
引きこもり気味の女子高生 麻美は、とあるきっかけで、近所に住む小学生 萌と、中学生の頃担任だった高原と再会する。
高原は、受け持つクラスの生徒と思われる人物からSNSの嫌がらせを受けており、萌は母親からのネグレクトを疑われていた。
3人それぞれが抱えている苦しみから救い出してくれたのは、「海からの贈り物」。シーグラスを拾い集める中で、それぞれの人生の光を見つけ出す、ちょっぴりビターな青春小説。
人と関わり合う中で傷つけられることもあるけれど、同じように人に救われる時だってある。
お互いの傷を少しずつ癒していく3人の物語です。45,000字と小説にしては短いので、良かったら読んでみてください!!
試し読みはこちらから
将来が漠然と不案です。
柳 麻美は、自分が書いた文章の不自然さに目を凝らした。あ、と口が自然と開く。「不案」じゃなくて「不安」。小学生でも中々間違えないようなミスを、高校生の自分がしたことに笑ってしまう。
「不案」でも、完全な間違いってわけじゃないけど。
麻美は「案」だけを消しゴムで消した後、自分の字を再度じっくりと眺め、その全てを丹念に消していった。このプリントを見るであろう第三者が、消しゴムをかけた跡から自分が何を書いたのか、推測できないようにと願いながら。
心の相談室。そんな捻りのないネーミングのプレートが掲げられた部屋
で、麻美はA4サイズのプリント一枚と向き合っていた。
書き終わった頃にまた来るわね。そう言い残して、カウンセラーのカワタ先生はどこかへ行ってしまった。カワタ先生は月二回だけこの部屋を訪れる。麻美のような生徒と、この狭い部屋で向き合い、それぞれの相談を聞いているに違いない。
麻美がその顔を思い浮かべる度に「カワタ」と片仮名でしか認識できないのは、相談室を一歩出ると、先生の顔も名前も、あっという間に霧散し、朧気なものとなってしまうからだ。
麻美はプリントの問をもう一度目で追いかける。設問は三題だけ。
「あなたが今抱えている不安や悩みはありますか? 自由に書いてみましょう」
「それを誰かに相談できていますか? (できない理由があれば教えてください)」
「先生や保護者の方に知ってほしいこと、伝えたいことはありますか?」
プリントの裏をめくると、紙のサイズぎりぎりまで引き延ばされた長方形が印字されている。これを目にする人間を受け止めてやるという度量を、これでもかという程過剰にアピールしているかのようだった。
「その他、今のあなたの気持ちを自由に書いてみましょう」。
自由に書いていい。今の気持ち。お腹が空いた。そんな風に書いたら不真面目な生徒、って思われるんだろうな。麻美は他人事のように思う。この部屋にいる限り、ちょっとぐらい繊細な生徒を演じないといけないような気持ちに襲われた。こういう設問に真面目に答える生徒はどのくらいいるんだろう。言葉にできないから、この部屋に通されたんじゃないか。
その推測を確かめる術はないのに、麻美はそう確信する。
グラウンドから響く、野球部の声出しが時間を知らせている。麻美のような帰宅部の生徒はもうとっくに下校している時間だ。急に苛々が募り、麻美は目の前の忌々しい設問を片付けるべく、もう一度シャーペンを動かした。
相談室は、必要最低限のもので構成されている。少し年季の入った木目の存在感が際立った机。カワタ先生がいつも座っているソファ。麻美も同じものに腰かけ、高さが低い机に自分の腰を折り曲げながらプリントに向かった。クリーム色のカーテンは教室と同じものだ。換気のために開けられた窓から入ってくる風に、夕焼けに照らされたカーテンがゆっくりとはためく。今日も、一日が終わってしまった。
はあ、と麻美は何度目か分からないため息を漏らす。この部屋は嫌いだ。この部屋を訪れるように、担任から遠まわしに提案される自分は、もっと嫌いだ。
「ただいま」
「お帰りぃ」
キッチンから漂ってくる油の匂いに麻美は鼻をひくつかせた。夕食に揚げ
物は珍しい。
「食べたくなっちゃって。春巻きにしてみたの」
麻美が何か言う前に、麻美の母は少しはしゃいだような声でそう説明した。何か言いたげな顔をしている。言いたいけれど、それを懸命に隠そうとしているのを麻美は当然のように感じ取った。春巻きは麻美の好物だということを母は当然のように知っている。
「やった。楽しみ。着替えてくるね」
麻美の発言に、母はほっとした顔をした。その表情の変化に、麻美は自分の部屋へと向かっていた足を思わず止めた。
「お母さん、私ね」
ぱちぱち、と油が跳ねる音が響く。母が緊張した面持ちで、うん、と短く返事をした。
「別に、いじめられているとか、そんなんじゃないから。ただちょっと…学校、たまに嫌になるだけだから」
油が大きく跳ねる音がした。母は、麻美が続けて何か言う前に「危ない、危ない」と天ぷら鍋に向き直り、麻美に背を向けたまま返事をした。
「ご飯食べながら話そう。今日、どんなこと話したか、教えて」
「……うん」
二階の自分の部屋へと上がる。小学生の頃から使っている自分の部屋はほっとする。少なくとも、心の相談室よりかはずっと。自分の部屋というものが与えられ、勉強机が来ただけで大騒ぎしていた頃から十年以上経った。その勉強机には高校で使っている教科書が乱雑に並べられている。明日の課題を思い出して、時間割を貼ったコルクボートに目が自然と引き寄せられた。中学の頃の自分が書いた張り紙も一緒に飛び込んでくる。
清ヶ丘高校 絶対合格。
あの時の自分に、今の自分は到底会わせられそうにもなかった。
春巻きの熱さに格闘しながら、麻美はぽつりぽつりと相談室での話をした。カワノ先生と簡単に面談したあと、プリントを渡されたこと。また二週間後にお話ししましょう、と締めくくられたこと。
「麻美は、行って良かったと思った?」
母は相変わらず、遠慮がちに麻美に投げかける。箸を動かしているはずなのに、母のお茶碗の中身も、取り分けられた春巻きも、少しも減っていない。麻美はそれに気付かないふりをしながら、どうかな、と答えた。そんな答えは期待していないと分かっているのに。
「何だろう。あんまり、皆が思っているより深刻じゃないっていうか」
「そんなに心配しなくていいってこと?」
「そう。さっきも言ったけど、いじめとかトラブルとか、そういうんじゃないから」
「だったら」
母が言いかける。言いかけた後に交わされた母の視線に、さっきまでとは違う苛立ちが滲んでいた。麻美は思わず肩に力が入る。
「――何でもない。また行ってみたら? 無料でプロの人に話聞いてもらえるんだから、お得と思えばいいんじゃない」
今日、何のドラマやってるんだっけ。母はあからさまに声のトーンを変えながら、テレビのリモコンを手に取った。麻美は早くこの場を立ち去りたくて、春巻きにかぶりつく。揚げたてよりかは幾分食べやすくなっていたけれど、油を吸いすぎた皮と、具が詰まり過ぎた餡の圧迫感に負けないように咀嚼する。胸が詰まるような感覚には気づかないふりをした。ごくりと、押しこむようにしてそれを飲み込む。
麻美の家は三人家族だ。単身赴任中の父と、パートで県庁に勤めている母。そして、高校二年になる麻美。麻美が生まれる前に購入したというこの家は、それなりにまだ綺麗なままだ。キッチンからはリビングでくつろぐ家族の姿が見えるようになっている。幼かった麻美が床や壁に落書きをしないよう、両親は常に目を光らせていたらしい。
テレビの音をBGMにしながら、しばらく食事を続けていると、母が思い出したようにそういえば、と切り出した。
「ねえ、麻美は最近、萌ちゃんを見かけたりした?」
「萌ちゃん?」
誰だっけ、と麻美が首をかしげると、母が「ほら、緑谷さんのところの」と情報を付け加えた。
「ああ……可愛かったよね。今、何年生かな」
麻美が過去形で思わず話してしまうのは、近所に住んでいるというのに、母が口にした萌ちゃん、という女の子をもう何年も見かけていないからだ。最後にあったのは確か、萌ちゃんが小学校入学の時だった。入学式だったのか、少し派手な装いのお母さんに手をひかれ、真新しい、そしてやや大きすぎるようにも見えるランドセルを背負った萌ちゃんと家の前ですれ違った。
可愛いなあ。そう素直に思ったことを、麻美はまだ覚えていた。
「そうそう。もう高学年じゃないかしら。萌ちゃん、最近、夜遅くまで一人で公園にいたりするらしいのよ」
「ええ? 何で?」
「うーん理由は分からないけど……元々、萌ちゃんのお母さん、夜のお仕事してるような感じだったけどね」
夜のお仕事をしている母親。夜遅くまで公園で遊んでいる萠ちゃん。
麻美たちが住む家から数百メートル程のところに住んでいる緑谷さんのお家に、何か異変が起きているのだろうか。
「あなたが今抱えている不安や悩みはありますか? 自由に書いてみましょう」
「それを誰かに相談できていますか? (できない理由があれば教えてください)」
「先生や保護者の方に知ってほしいこと、伝えたいことはありますか?」
ふと、自分が数時間前に向き合っていたプリントが頭に浮かぶ。萌ちゃんは、何て答えるだろう。
「心配だね」
自分の口からついて出た言葉に、麻美ははっとした。母には「心配しないで」と言っておきながら、断片的に伝え聞いただけの家庭については、さらりと言ってのけている。
その感覚の気持ち悪さを誤魔化すように、麻美もテレビに目を移した。麻美の気分など知る由もない人々が、手を叩いて笑い、あらかじめ作成していたVTRに真剣に聞き入るフリをしている。
羨ましいと思うと同時に、麻美はその雑多なやり取りに救われたような気持ちになった。
ありとあらゆるSNSを巡回しなければ、眠りにつくことができない。
そんな生活になったのはいつだったか。高原 恭介はしばし逡巡したが、答えは出なかった。明確な日付は覚えていない。ただ、確かそうだ。中間テストの結果を返したぐらいの時期。半袖で過ごすのが当たり前の気候となり、体育や放課後の部活指導でかく汗が嫌になった頃のことだ。
恭介自身は元々、学生の頃からSNSを定期的に見る習慣は持ち合わせていなかった。全世界に発信したいこともなかったし、集めたい情報もさほどなかった。友達のアカウントを見たいとも思わない。大学の頃は、毎週末のテニスとバイトと授業、その当時付き合っていた彼女と過ごす時間で埋め尽くされており、顔も名前も知らない他人の日常が恭介の生活に入り込む余地はなかったのである。
それが、中学校の教師として四年目を迎えた今、恭介は恐らく受け持っているクラスの教室の誰よりも、必死にSNSの海を潜り、その中に自分が登場していないかを随時確認しなければ気が済まない。
絶えず親指を動かす。時々その動きを止め、性急に画面をタップし、いつの間にか止めていた息をふっと吐きだす。その繰り返しだ。生徒たちのSNSアカウントは、全てとはいかないが目ぼしいものは大体把握している。ネットリテラシーの緩さに教師の一人として心配になるが、恭介にとっては好都合だった。フォローしていないアカウントからは見れない設定になっているものもあるが、そのアカウントと会話しているアカウントを覗き見すれば、どんな投稿をしているのかはある程度推測することができた。
『タカキョってまじ偉そう。うざ』
そんな投稿を見かけたときがあった。タカキョ。恭介が生徒からつけられたあだ名だ。なんて捻りのない、と初めて聞いたときには鼻白んだような気持ちになったが、テキストとしてスマホで見た瞬間、胸の奥がみるみる内にぎゅう、としぼりとられるような圧迫感を感じた。
投稿していた生徒のアカウントを確認する。間違いなく、自分が勤務している学校の生徒だ。投稿している体育祭終わりの写真や写り込んでいる制服が間違えるはずもなかった。
その登校につけられた、「イイね」だか「スキ」だかは二桁に近い数字がついていた。どういう意味だ。他の生徒も同じように思っているのか。ただの悪ふざけか。
学校という特異な空間の中で、教師が自分の悪口を言っている生徒と遭遇する回数はそう少ないわけではない。顧問をしているテニス部でも、あまりよく思われていないことを知っている。それでも慕ってくる生徒はいるし、保護者から「高原先生が担任で良かった」と言ってもらえるときもある。全ての生徒に好かれる必要はない。あまりにも脆くて、輪郭がはっきりとしない、思春期真っ只中の中学生を四十人も相手にしなければならない職業なら尚更だ。
それが、スマホの中に綴られた、生徒からの本音であろう言葉。恭介はただただ、呆然としてしまった。
それから、恭介は中学生が好んで使いそうなSNSのアプリをスマホにダウンロードした。同じように自分のアカウントも作った。全ては、自分のプライドを少しでも守りたい一心で。
恭介は一通り巡回し終えると、一番見たくないページにもう一度飛んだ。アカウント名は「@tsukumuku1123」。男か女かも分からず、誰が投稿しているものなのか見当もつかない。ただ、フォローしている人間を見る限り、恭介が勤務している中学校の生徒もしくは関係者であることは間違いなさそうだった。
『現社のテスト、採点ミスあった。最悪』
『声出しの時、まじでうざい。テニス部の男子、よく耐えてるなって思う』
主語がないから、恭介のことだと断定はできない。ただ、身に覚えがあることばかりだった。日付も一致する。
その日から、恭介の日課が一つ増えた。そうしてその日課は、とんでもない重さと圧力をもって恭介の生活を支配しつつある。
Amazon購入ページはこちらから
どうぞよろしくお願いします!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
